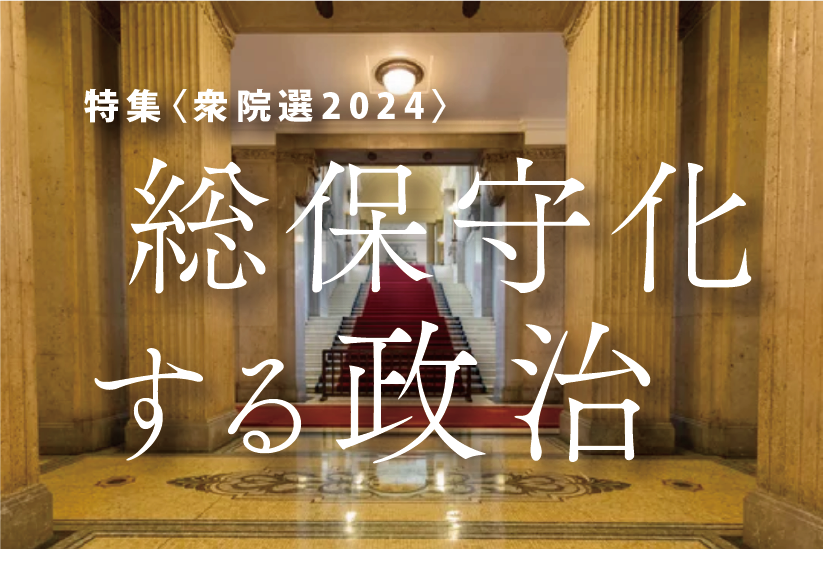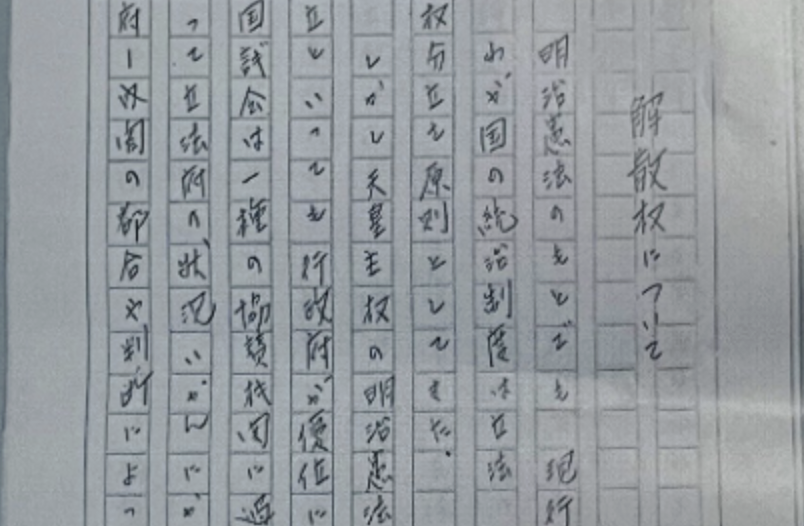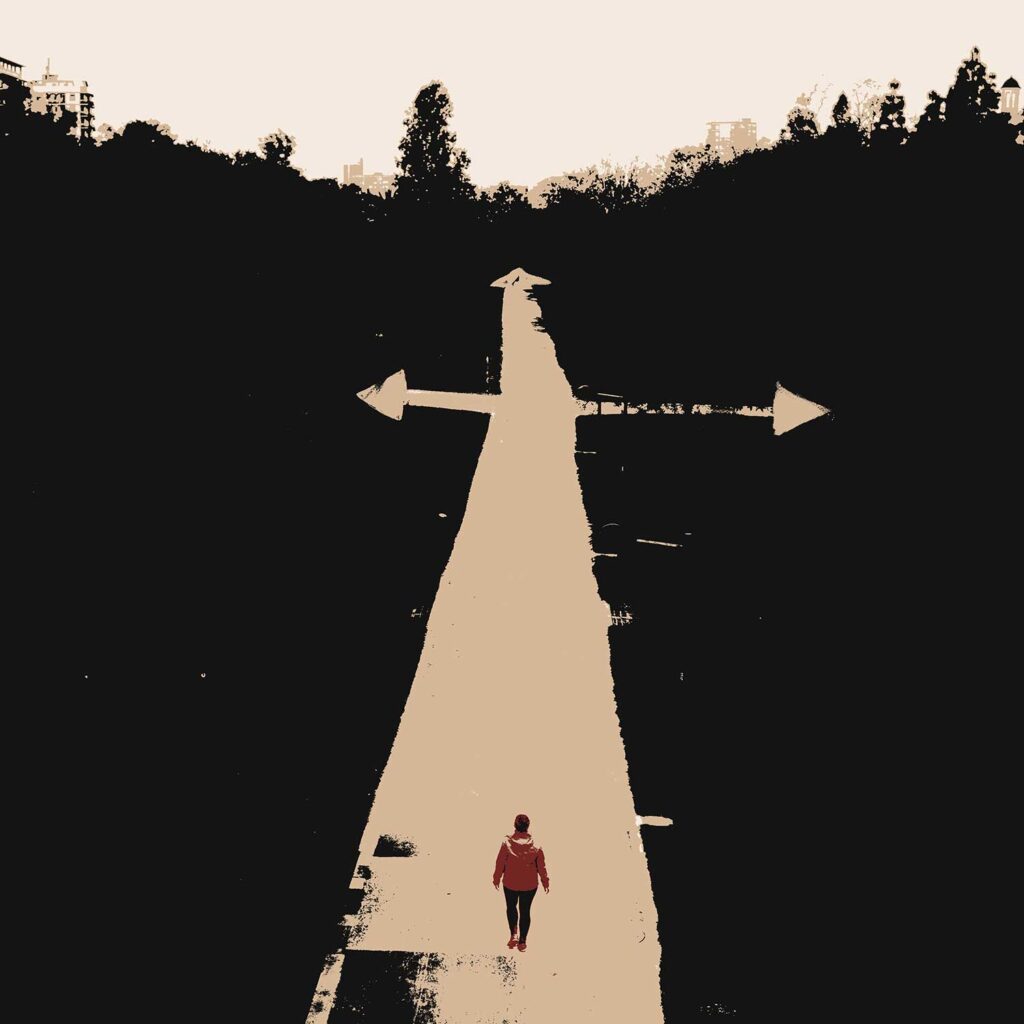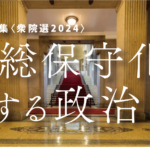他の特集記事はこちら(特集:総保守化する政治)
路上から生まれた野党共闘
2015年夏の安保法制成立後、「野党は共闘!」のコールが国会前にこだました。それは、国会という多数決の場で安保法制を廃止するには、野党の側も束になっていかなければならないというシンプルな発想であった。シンプルであるがゆえに多くの人々の賛同を得た。冷ややかに見れば、国会の外で声を上げたところで、国会内の議席配分は変わらない。でも、2015年は「そういう問題」ではなかったのだ。わたしも一人で「安保関連法案に反対するママの会(ママの会)」を立ち上げ、全国に仲間を広げていた。
このコールを誰が考案したのか、わたしは知らない。しかし、このコールで重要なことは、路上から生まれたということだと思う。政治家同士の密室のやり取りではなく、野党が共闘する以外に安保法制を廃止することができないという、誰にでもわかる事実から支持され、人々の口から口へと広まっていった。「野党は共闘!」はわたしたちの絶望から生まれた希望であった。
「ママの会」では「だれの子どももころさせない」を合言葉に、デモや集会を行なった。「だれの子どもも」という部分には二重の意味がある。まず、安保法制で最も危険にさらされるのは、現行憲法遵守を誓って入隊した自衛隊員だということ。次に、仮想敵国(とその人々)を作り出していくようなやり方では、平和は生まれないということ。このメッセージの普遍性を握りしめるようにして、わたしたちは活動した。
来年2025年は、安保法制10周年を迎える。10年というと短いかもしれないが、当時国会にも連れて行き、1歳であったわたしの子どもが、小学校高学年になるまでの時間が経った。この10年を振り返りつつ、野党共闘とはなんであったのか考えてみたい。
市民連合の立ち回り
野党共闘の具体的な調整を担った政治団体が「市民連合(安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合)」である。発足の記者会見が2015年12月に開かれ、わたしも駆けつけた。「安保関連法案に反対するママの会」の有志としてである。それまでは単なる叫びであった「野党は共闘!」がこれから現実化してくると思うと、素直にワクワクした。安保法制が成立して終わりではなく、次のアクションにつなげていくことが、切実に必要だと考えたからである。国会前に集まった何万人という人々を離散させてしまったら、どれだけの損失であっただろうか。甘いと言われるかもしれないが「日本の政治が変わるかもしれない、いや変えなければならない」という使命感を抱いた。
市民連合は、主に民進党(当時)と共産党が合意できる、最大公約数的な項目を挙げ、それを野党に提示した。それに対して野党はサインをした。この時期はSEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)のメンバーも市民連合内で活躍しており、記者会見の物理的なセッティングなどイメージ戦略でも大いに力を発揮してくれた。前出の写真は今でもわたしの好きな写真である。政治家は偉い「センセイ」なのではなく、市民の声を聞きに来るべき、対等な存在なのだということを写真が示している。
実際の選挙では、一人しか当選者が出ない「一人区」を中心に候補者調整を進め、多くの選挙区で成果を上げた(その一方で共産党などが候補者を降ろさざるをえなかったことは明記しなければならない)。これは自民党と野党が、改憲の発議に必要な3分の2の議席数を争うときには、必要不可欠な戦術である。しかしながら次第に、野党共闘には次に記すような問題が浮上してきた。
野党共闘のジレンマ
振り返ると、自民党から民主党への(歴史的な!)政権交代があったとき、わたしはどの政党に投票したのか記憶していない。しかし自分の信条として棄権はしていない。つまりわたしは政党政治に関しては、その程度の有権者であった。そのわたしは、野党共闘の一員となりつつも、政党政治のジレンマに直面することになる。