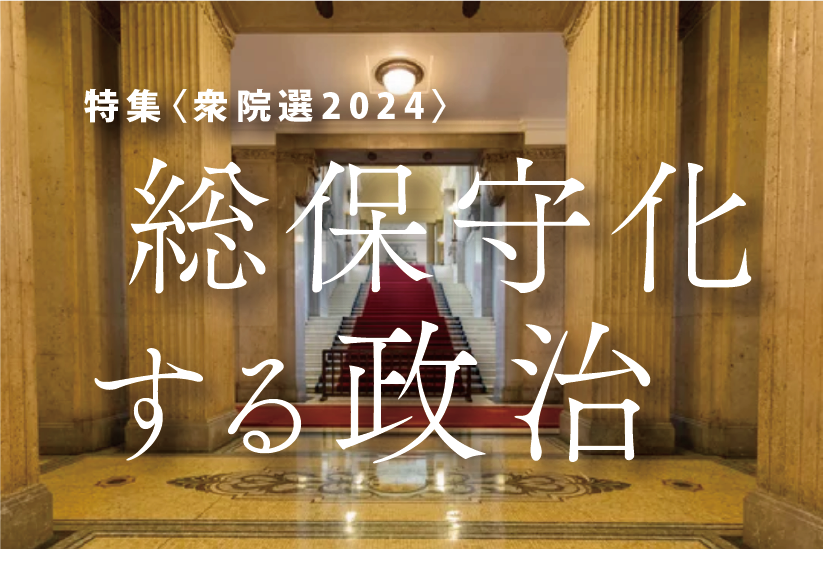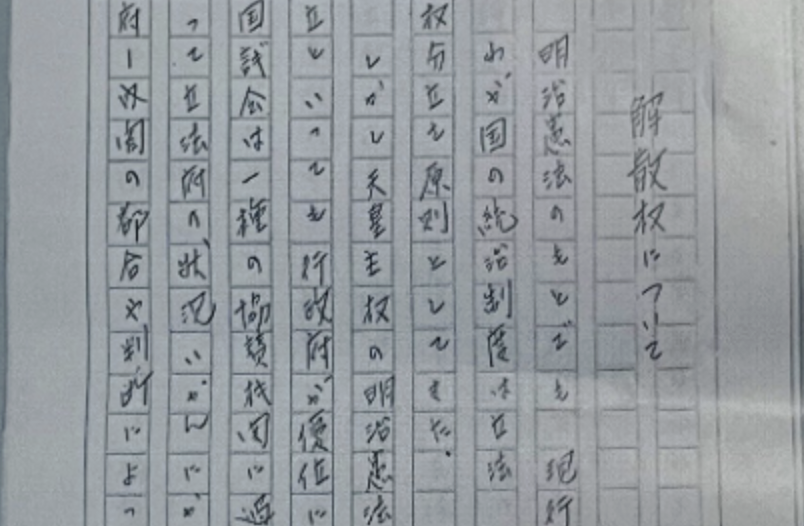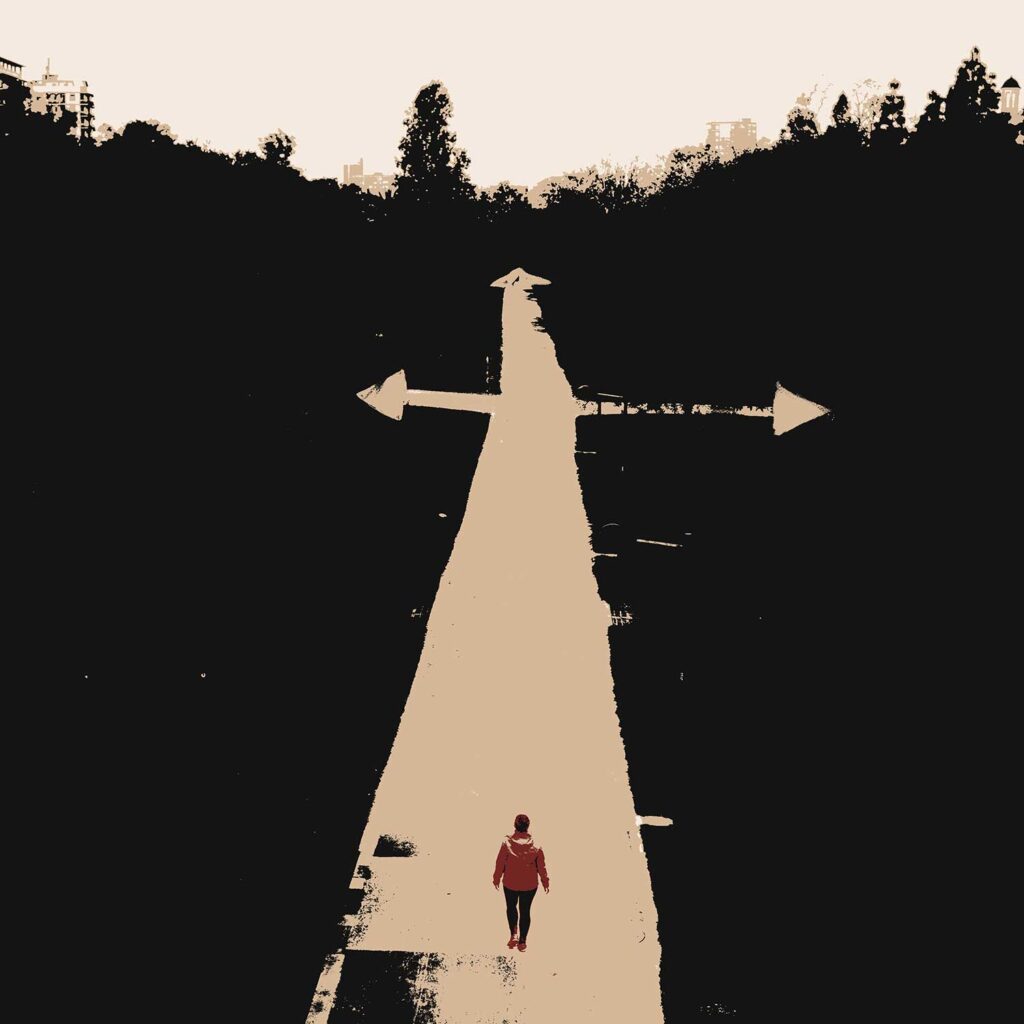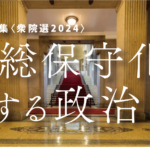他の特集記事はこちら(特集:総保守化する政治)
急増する中小零細企業の倒産
企業の倒産が急増している。昨年の倒産件数は8497件で、前年比33・3%増と、近年にない大幅増加となったことが、帝国データバンクの倒産情報で報じられた1。今年上半期の倒産件数は、すでに小泉氷河期不況の頃のピークを超え、「アベノミクス」前の不況期のレベルに達しつつある2。その倒産の7割を占めるのが、資本金規模別で「個人+1000万円未満」という小規模事業者である。
奇妙なことは、これが、目下の株高に見られるような、景気回復期とされている時期に起こっている点で、通例見られない現象だということである。この原因には、輸入物価高騰や人手不足ももちろん効いていよう。しかし、政策によって直接もたらされている面も大きい。
たとえば、2023年のゼロゼロ融資後倒産、つまり、無利子無担保のコロナ支援融資を受けた事業者の倒産は、前年の1・7倍に激増したとされている3。
元来、未曾有の厄災による営業困難への公的支援なのだから、融資ではなくて給付になってしかるべきだった。融資だとしても、返済はコロナ禍が終わったら正常な経済に戻ることを前提に企画されていたはずだ。それが当初想定になかったウクライナ戦争などによる輸入物価上昇のコスト高に見舞われて、みんなさらなる経営困難に陥ったわけだから、一律に返済を繰延するか免除するのが筋である。
ところがそうする代わりに、かえって返済時期にまさに合わせて日銀が金利を引き上げたのである。金利が上がれば、小規模事業者がコロナ融資の借換えをしようとしても、利子がかかるので困難になる。原材料高で、これまでと同じことをするにも仕入れ金額が膨らんでいるので、金利が上がると日々の運転資金を借りるのも困難になる。これを機会に廃業や倒産に追い込まれた事業者は多いだろう。
さらに、中小零細企業によってギリギリの判断で計画されていた設備投資は、ちょっとの金利上昇で断念される。住宅建設も数多く断念されるだろう。それがいくつも集まれば地域経済への打撃は大きい。
もう一つ、中小零細企業の倒産増に影響していると思われるのが消費税である。「公租公課滞納倒産」、つまり、税金や社会保険料を払えないための倒産が勢いを増している。上記倒産情報の8月報4では、1~8月の同倒産の累計は113件で、すでに去年1年間の総数123件に迫っていると報告されている。
コロナ禍で一時、納税猶予の措置がとられたが、まだ十分にコロナ禍が明けないうちに解除された。本来なら「免除」になってしかるべきところなのに、「猶予」でしかなかったので、コロナ禍が明けて、コスト高がかさむ中で、猶予期間の分も合わせて納税が迫られてしまった。
そこに昨年10月からのインボイス導入である。コスト高の中、過半の企業はコスト上昇の半分以下しか価格に転嫁できていない5。免税業者だった零細事業者に、消費税の転嫁などできるはずはない。ところが消費税は法人税と違い、赤字を出していても納税しなければならない。払えずに廃業・倒産に追い込まれる業者が続出するのは当然に予想された事態である。