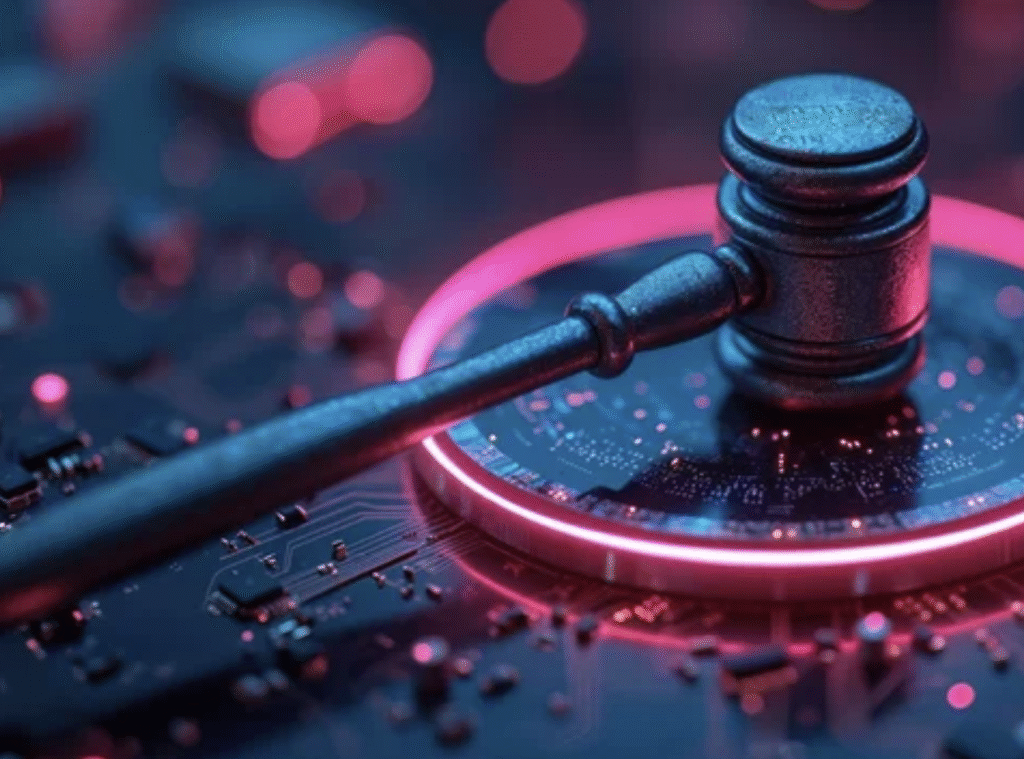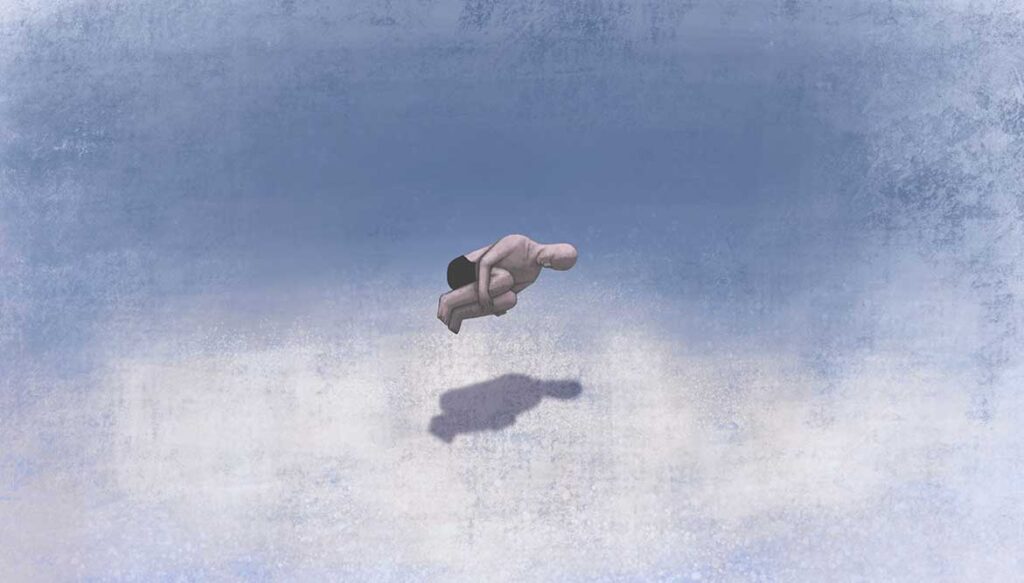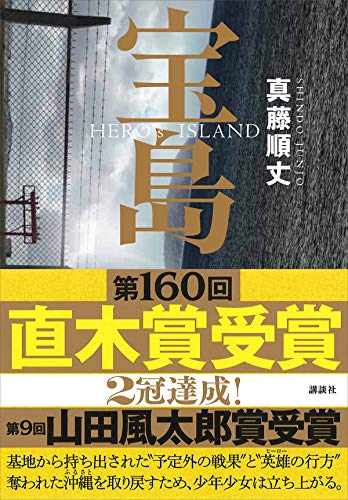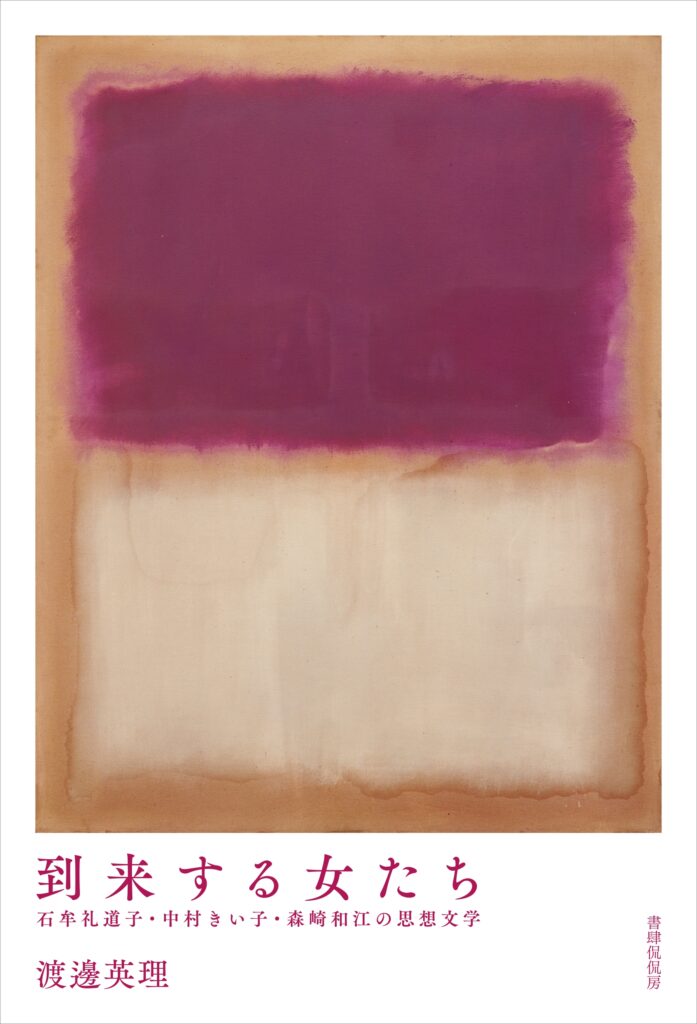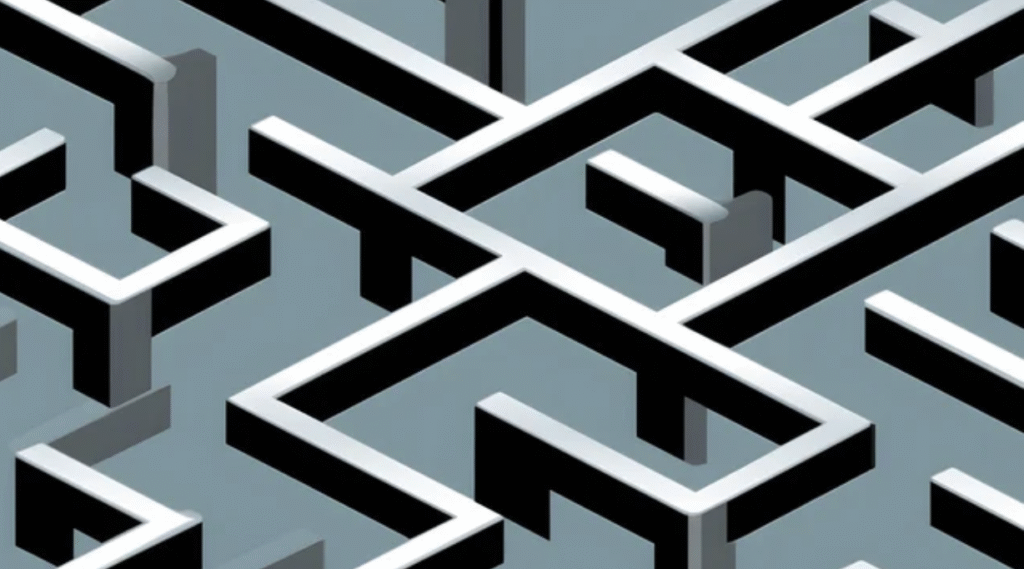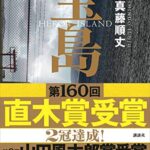【関連】イスラエル極右とガザ〝戦争〟(上)蘇るカハネ主義の脅威
【関連】イスラエル極右とガザ〝戦争〟(中)「カハネ国家」への道
10・7の衝撃とネタニヤフの失策
2023年10月7日のハマスによる奇襲(以後、10・7)は、イスラエルにとって青天の霹靂だった。しかし、これを未然に防げなかった背景に、ネタニヤフ政権の過信と欺瞞に基づく重大な失策があったことは疑いない。
陸・海・空のすべてを封鎖されたガザからの将来の攻撃に備え、ネタニヤフ政権は、アイアンドーム、地上のフェンス、地下の壁、そして24時間体制の監視網といったテクノロジーに全面的に依存していた。その一方で、ガザ周辺に展開する部隊を強化する代わりに、入植地拡大の布石として、軍の精鋭部隊をヨルダン川西岸地域に重点的に配置する政策を採った(註1)。とはいえ、最大の失態は、パレスチナ自治政府を冷遇する一方で、ハマスの財政基盤を事実上支えてきたことにあるだろう。
1 B. Atzili, “Dereliction of Duty,” War on the Rocks, 2025/4/3.
現財務相のベツァレル・スモートリッチは、2015年に国会に初当選した折、「ハマスは資産であり、パレスチナ自治政府は重荷である」と述べた。その理由として彼は、ハマスは「テロ組織なのだから誰も認めないし、誰も(国際刑事裁判所での)地位を与えないし、国連安全保障理事会での決議案の提出を誰も許さないだろう」ことを挙げた(註2)。やがてこの方針を採用したネタニヤフは、2018年にカタールからガザへの送金を許可し、翌19年のリクード総会議で「パレスチナ国家に反対する者はガザへの送金を支持すべきだ」と発言したと伝えられている(註3)。その後、ハマスの実効支配以来禁止されていたガザからイスラエル領内への出稼ぎ労働も許可され、労働許可証の発行数は2021年の数千人規模から23年には約2万人まで拡大された。
2 A. Speri, “Before They Vowed to Annihilate Hamas, Israeli Officials Considered It an Asset,” The Intercept, 2024/10/14.
3 Y. Yisrael, “Netaniyahu al ha’avarat hakesef ha’katari lekhamas,” Reshet 13, 2023/11/29.
イスラエル政府による一連の緩和措置により、ハマスは安定した資金源を得ることができた。その資金をもとに、地下トンネル網の構築や軍備の増強に注力し、イスラエルの情報機関はトンネルを利用したハマスの連絡網を傍受することができなかった(註4)。一方、イスラエルを逆占領するというメシア主義的な構想さえ抱いていたハマスの最高指導者ヤヒヤ・シンワルは、「大いなる事業」に向けた準備を着々と進めていた(註5)。にもかかわらず、ネタニヤフは、情報機関からの再三にわたる警告や、シンワルの暗殺を求める提言を無視しつづけた(註6)。
4 L. Shoval, “Failure in Handling Intelligence,” Israel Hayom, 2025/3/4.
5 Sh. Eldar, “Hamas Actually Believed It Would Conquer Israel,” Haaretz, 2024/4/5.
6 L. Berman, “Netanyahu Ignored Warnings over Hamas Threat for Years,” The Times of Israel, 2024/11/23.
10・7以降、こうした一連の失策が明るみになると、最高裁のリベラルな基盤を骨抜きにしようとする「司法改革」に反発していた人びとだけでなく、「我が家イスラエル」党首アヴィグドル・リーベルマンのような極右議員からもネタニヤフの責任を問う声が上がった。しかし、ハマス掃討作戦の開始とともに、現政権の打倒よりもハマスに対する「勝利」を優先すべきだというコンセンサスが国民の間で形成され、ネタニヤフの辞任を求める声は次第に下火となった。
人質という障壁
ネタニヤフ政権は、今回の軍事作戦の目的として「ハマスの殲滅」と「人質の救出」の2つを掲げた。しかし、人質の生殺与奪の権をハマスが握っている以上、2つの目的は本質的に両立し得なかったと言わざるをえない。
イスラエルには、人質や捕虜の救出のために破格の交換に応じてきた過去がある。第2次ネタニヤフ政権下の2011年、シャリート軍曹ただ1人の救出と引き換えに1027名のパレスチナ囚人が釈放された。その中には後に10・7の首謀者となるシンワルが含まれていた。この苦い経験を経て、囚人の解放に対する慎重な世論が形成され、戦時下を通じてこの問題をめぐる見解は大きく二分された。
イスラエル民主主義研究所の世論調査によると、2023年10月時点で、イスラエルのユダヤ人のうち45・9%が人質の交換のためにハマスと交渉することを支持し、42・2%が反対した。約半年後の2024年5月には、56.3%が人質救出を最優先すべきだと答えた一方、36.8%は軍事作戦の継続を優先させるべきだと答えた。
こうした中、人質の救出に最も冷淡な態度を見せてきたのが、イタマール・ベン=グヴィルとスモートリッチを筆頭とする極右閣僚たちである。2025年1月、イスラエル政府がハマスとの3段階の停戦に合意すると、ベン=グヴィルは大臣を辞任して連立から離脱した(その後、停戦が失効した同年3月に政権に復帰)。彼は、停戦は「ハマスへの降伏」に等しく、「戦争の成果を消し去るものだ」と糾弾し、「この1年間、我々は政治的な力を使ってこの取引が進められるのを繰り返し阻止してきた」と誇らし気に語った(註7)。一方、スモートリッチは、人質の救出はイスラエルにとって「最も重要なことではない」、政府の第1の焦点はハマスの殲滅であるべきだと発言し、人質の家族らを激高させた(註8)。
7 E. Breuer, “Ben-Gvir Boasts of Blocking Gaza Hostage Deal,” The Jerusalem Post, 2025/1/14.
8 S. Sokol, “Smotrich Says Returning Hostages ‘Not the Most Important Thing,” The Times of Israel, 2025/4/21.
「人質/捕虜の贖い」という戒律は、ディアスポラのユダヤ社会では常に最優先されてきたが、このような規範は、イスラエル社会にもある程度共有されてきたと考えられる。しかし、戦時下の極右閣僚たち――その多くは信仰者でもある――の発言や、イスラエル国防軍による無差別攻撃の実態からは、10・7以降、少なくとも政界や戦場では、人質の命よりも敵の殲滅を優先すべきだとする規範が優勢になったことが見て取れる。
戦闘の長期化に伴い人質救出を求める世論が高まるなか、停戦交渉を妨げる極右閣僚の発言からは、人質問題が、彼らがもはや隠そうともしなくなったガザ再征服という野望の障壁となっていることが、次第に明らかになっていった。
「神権化」するイスラエル国防軍
シオニズムは、その発生当初から反宗教的とさえ言える世俗ナショナリズム運動であり、ユダヤ教とシオニズムの融合を目指した「宗教シオニズム」は長らく傍流に過ぎなかった。だが、1967年の「6日戦争」(第3次中東戦争)でイスラエルが電撃的勝利を収めて領土を大幅に拡大すると、そこに神の介在を見出した人びとの間で占領地への入植運動が活発化した。入植者を中核とする極右勢力は、ネタニヤフの長期政権を経て、ついには政治的ヘゲモニーを握るまでになった。その影響が政界以外で最も顕著に表れているのが、イスラエル国防軍(IDF)の構成である。