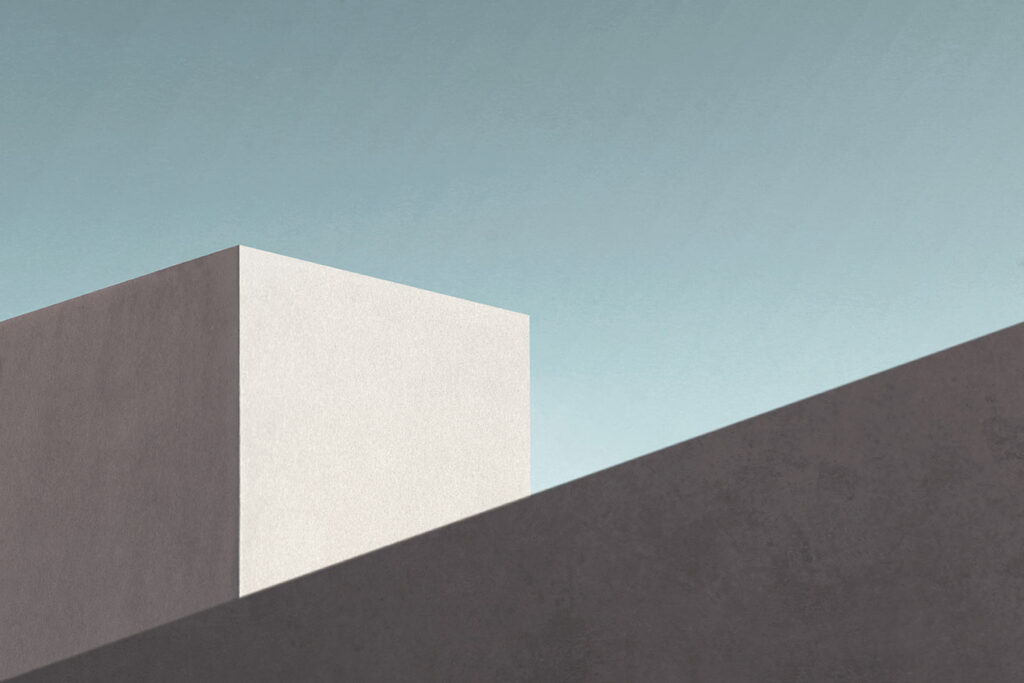【関連】統一教会の行方――公共の福祉の侵害と信教の自由(藤田庄市)
【関連】奪われた人生と尊厳を取り戻す――統一教会2世による提訴(藤田庄市)
ある政治家が2022年の夏の駅前で血祭にあげられたとき、私はランデュジャンという村で寝入っていた。天の川は土地の言葉で「白き道」という。夜ふけに目がさえて庭に出たとき、星々が痛ましいほどに輝いているのに息を吞んだ。そのときになって七夕祭という故郷の風習を思いだしたことをいまも覚えている。本当はすれちがうこともなかった2つの星の邂逅を祝う祭だ。
特定の団体とつながりがあると思いこんで犯行におよんだ。故郷ではそんな思いこみ好きの報道がなされていた。報道の自由の低い国柄ゆえなのか、国家ぐるみの無邪気な思いこみの甲斐あってこそ、統一教会による組織犯罪がこれほどまでに見すごされてきたのかもしれない。
絶対に許されぬ民主主義への凶行だと評する者たちもいた。では、それまで権力に居直ってきた者の血が流されることではじめて居住まいを正すそぶりをみせ、束の間のその場しのぎをしてみせた社会、咎を受けるべき政界の関係者たちがいまも揃ってけろりとした顔でいる社会の民主主義とは、そもそも何なのだろう。殺人罪の被告として法廷に立つことでしか声を聞き届けられることのなかった者がいるということ、それが国家ぐるみの組織犯罪の被害者でもあるという事態を、どう受けとめたらいいのだろう。
事件を呼び水にしてはじめて、宗教2世の被る宗教虐待というものが語られるようになった。それでも、言葉は充分に尽くされたとはいえない。そこには構造的な理由もある。
第1に、被害を受けていることと被害をそれとして自覚することのあいだには隔たりがある。加害行為のなかには、それが巧妙であればあるほど、あるいは被害者の立場が弱ければ弱いほど、それとして気づかれにくいものがある。支配というものがその典型である。人の内面にまで支配が及ぶと、被害者は自発的な服従や忖度へと誘導される。
第2に、当事者が被害を語ることにはさまざまな障壁が伴う。政治・社会・心理的な困難に加え、文化の壁も立ちはだかる。宗教2世はいわば異文化の環境に置かれている。被害の実態をわかりやすく伝えるためには、文化の違いを踏まえた上でのある種の翻訳作業が求められるため、それだけの説明コストがかかる。
しかし、なににもまして私たちの言葉を貧しく浅はかなものにしているのは、宗教という限定的な切り口による問題設定の仕方にある。そのために私たち自身の加害性が棚上げされ、ともすると他人行儀な善意の言葉を並べるだけで終わってしまう。
事件の加害者は統一教会のような集団の存在する社会を「人類の恥」と呼んでいた。日本社会が恥ずべきものであること、ひいては日本社会を生きる私たち自身が恥知らずの存在であることを認めることは、生やさしいことではない。しかし、手がかりは日々のいたるところに転がっている。
統一教会がそのひとつである。それは恨の文化を持つとされる異国からやってきたのではなく、日本社会そのものの醜さの粋を集めたものとして、日本社会のうつし鏡としてある。それを悪魔祓いするようにして解散に追いこんでみたところで、みずからの醜悪な影から逃れることはできない。
ここではそこに従来とはまったく異なる角度から光をあてる。宗教ではなくレイシズムをめぐる歴史の観点から、統一教会の2世問題を論じたい。
レイシズム、ナチス、日本
レイシズムとは人種に基づく差別のことである。具体的な実践として、人種というそれ自体では恣意的な区別に、なんらかの裏付けを与えるために優生学というものが試みられたことがあった。そこにレイシズムという呼称を与え、その本質主義的な性格を批判したのは、ユダヤ系ドイツ人のマグヌス・ヒルシュフェルトだった。亡命先のニースで客死する前年にあたる1934年に『Rassismus』が出版され、日独防共協定の結ばれた1936年に英訳された。ナチスの掲げたアーリア至上主義=反ユダヤ主義を批判するためのものだった。それが日本の占領政策にも関与したルース・ベネディクトの目にとまり、1942年には日本の民族主義を批判の射程に含めた『Race』が出版されたことで、英語圏でもレイシズムという語が普及した。
このレイシズムに関して、日本は屈折した歴史を辿ってきた。ルース・ベネディクトの指摘するとおり、日本人はナチスによる人種差別を免除されていた。ヒトラーに言わせれば、日本人はアーリア人である。無論、それは建前にすぎない。現実には列強諸国による差別のまなざしが存在していた。そもそも国連憲章への人種的差別撤廃の明記を求め「黄色人種に対する人種的偏見」の解消を目指したのは日本だった。その反面、植民地の拡大をとおしてアジアという人種差別の対象を見出してきたのも日本だった。戦後にはそれらの差別対象を失った反動により、単一民族の島国としての歪んだ自己像にとらわれた。
現代の日本のレイシズムは、そこを出発点にしている。1947年5月に施行された憲法においては、日本国民以外に基本的人権を保障しない姿勢が打ちだされた。憲法施行の前日、大日本帝国憲法に基づいて出された外国人登録によって「外国人」という存在が規定され、戸籍や住民登録のない者たちが密入国者として違法化された。さらに、朝鮮半島で大量の戦争難民が生まれているのを背景に1951年7月に難民条約が国連で採択されると、10月に入国管理法が定められ、難民の厳しい取り締まりが始まった。
このとき、そもそもだれが日本人でだれが外国人であるかの法的な線引をしたのが、1899年以来の国籍法である。国籍の定め方に関しては、出生地主義と血統主義という2つの考え方がある。前者は文字どおり出生地を国籍取得の要件とするのに対し、後者は生みの親との血縁を要件とする。日本では後者が採用されてきた。つまり、自分たちと同じ血を引く者のみが同じ日本国民であるとされてきた。その法的な裏付けとなるのが全日本国民の血縁関係を網羅した戸籍簿であり、象徴となるのが万世一系とされる天皇の皇統譜である。
日本国民としての同一性はもっぱら血縁によって支えられている。憲法の言葉をわがものとして結束する市民社会とは異質な共同体、一種の部族社会と考えてもいい。このような血統主義の社会にあっては、血統を乱すような存在が脅威とみなされる。とりわけ同じ人種の顔をしていながら日本人としては認められない他者、自分たちの同一性を内側から乱すような他者が、日常的な排斥の対象になった。部落差別や在日朝鮮人差別がその典型である。
このような血統主義に基づく差別の問題は、統一教会とは無関係のように思われるかもしれない。しかし、そうではない。統一教会の教義の核心には、むしろそれしかない。