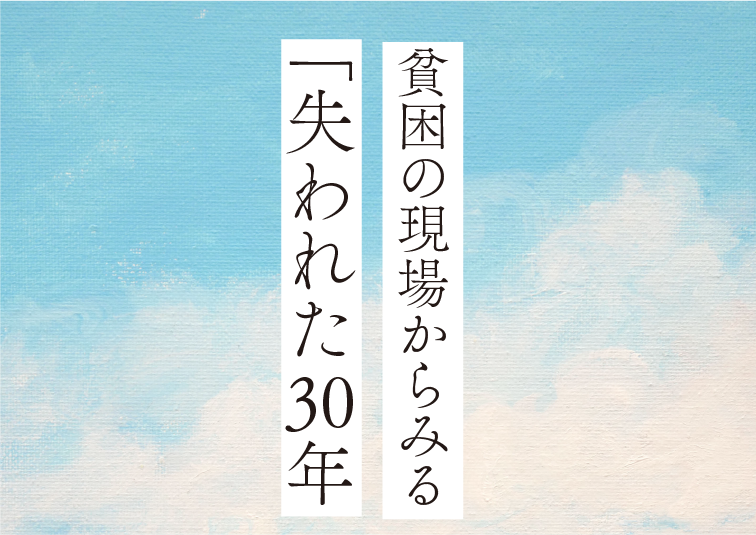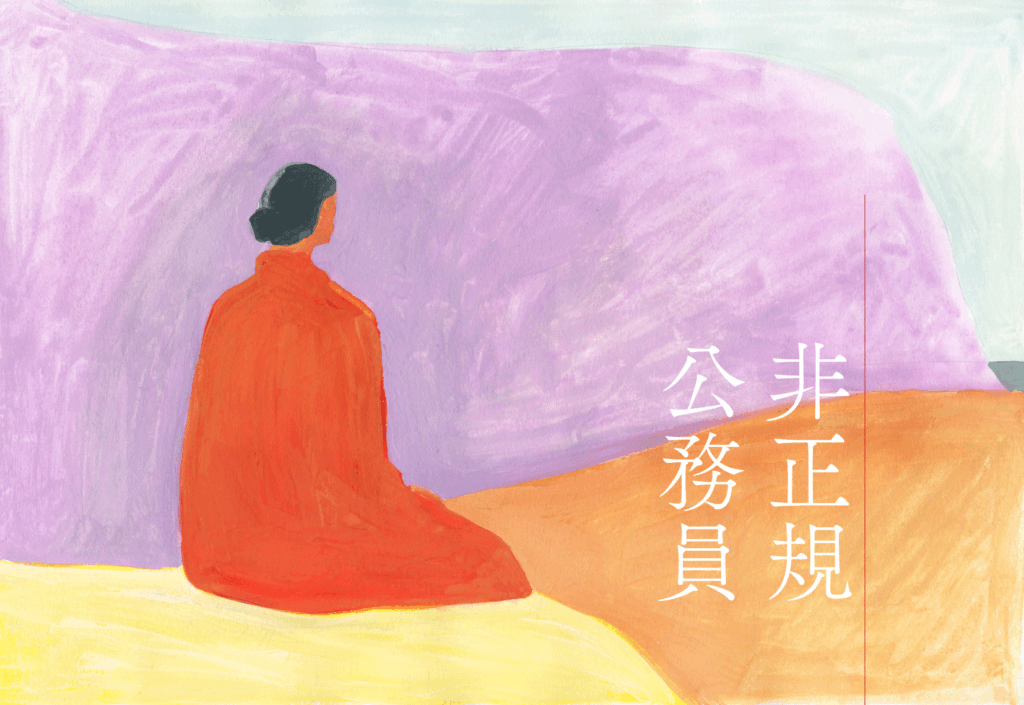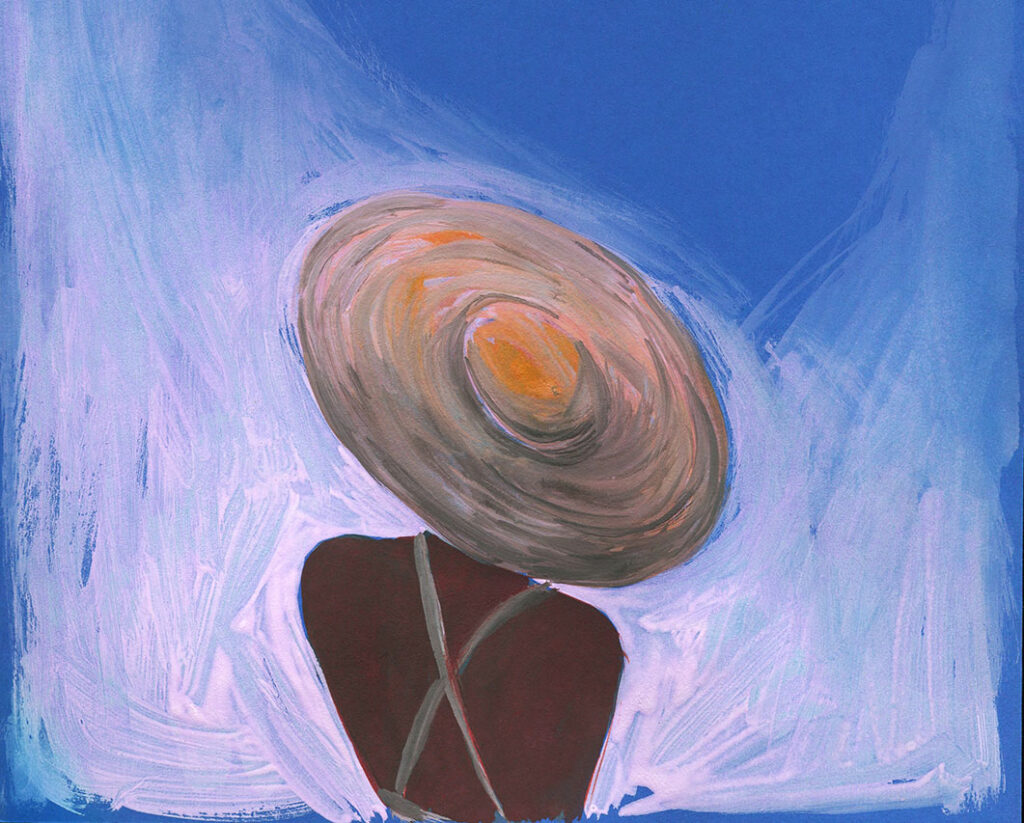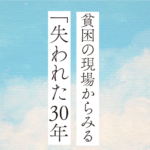皆川宏之:1971年生まれ。千葉大学大学院社会科学研究院教授。専攻は労働法。関連する論文に「ドイツにおける非典型労働と低賃金労働」(『労働者像の多様化と労働法・社会保障法』所収,有斐閣)など。
三宅芳夫:1969年生まれ。千葉大学大学院社会科学研究院教授。専攻は哲学・思想史・批判理論/国際関係史。著書に『ファシズムと冷戦のはざまで』(東京大学出版会)、『世界史の中の戦後思想』(地平社)など。
新自由主義グローバリズムの展開
三宅 今年は1995年の日経連のいわゆる「新時代の日本的経営」から30年ということで、新自由主義グローバリズムによる世界空間の再編という大きな文脈を念頭に置きながら、主にここ30年の日本における雇用、格差、貧困の変化を考えていきたいと思います。
振り返ると、1990年代には日本社会ではすでに格差は拡大しはじめていたにもかかわらず、2000年くらいまではまだ「不平等は広がっていない」と強弁する言説が階層研究などの領域でも力を持っていたわけですね。しかしそれから四半世紀、いま日本で不平等と貧困が拡大していることを否定する人はまずいないと思います。この不平等と貧困を急速に拡大させる1つの要因になったのが、非正規労働の解禁・拡大です。現在は日本の全労働の4割が非正規、女性では5割を超え、若年女性だとそれを上回る。最近は年金受給額の実質低下もあり、65歳以上の高齢者の非正規の割合も急上昇しています。
格差ということで言うと、1980年代には日本は米国、英国はもちろん、大陸欧州より格差が小さい社会でしたが、今や大陸欧州、英国をとっくに抜き去り、相対的貧困率は米国を上回りました。日経連の例の報告に関わってまだ存命中の人が「ここまで不平等が広がることは想定していなかった」と証言する時代になっています。当人の弁によれば、「正社員の給与をもっと下げたかったんだけど、それは抵抗が強く、摩擦を避けるために非正規の導入・拡大を選択した」と妙な言い訳をしていましたけれども。
しかし、「新時代の日本的経営」の労働者の3分類では、はっきりと「雇止め」ありの年俸制導入が明記されている。つまり、最上位には今まで通りの終身雇用・年功序列型の、いわば企業にとことん忠誠を尽くす「産業士官」的なグループを想定するが、中間には年俸制・雇止めありの「専門職」、最下位にはパート・アルバイトなどの非正規雇用という三層モデル。これが21世紀に入って全面化していった。この報告書を出した日経連は元来、財界側の労務担当組織だったわけだけれども、ある意味で「役割」を終えて、2002年には経団連と統合。これは日本の労使の極端な非対称的な力関係、つまり資本側・経営側が圧倒的に強すぎるということの反映でもあると思います。
関連:特集 新自由主義の30年
皆川 この30年ほどの社会的な動きや流れということでは、三宅さんの言われる通りだと私も思いますね。
三宅 ここで少し視点を広げて新自由主義的グローバリズムによる世界空間の再編の背景を簡単に整理しておきたい。「新自由主義」という言葉は現在いろいろな使われ方をしていますが、私の見方は、国際的には新自由主義的再編は1973年にはすでに開始されていた、というものです。
第一に、ラテンアメリカでは合法的に選挙で選ばれたチリのアジェンデ政権が米政府に支援された軍部のピノチェトによってクーデターで倒され、その後の経済政策は「シカゴ・ボーイズ」と呼ばれるM・フリードマンの弟子達によって運営される。ここで社会保障削減・緊縮財政を軸にした劇的な新自由主義政策を、IMFと連携しながら強行。これは、その時点でのいわゆる「北側」諸国ではまだ政治的に実行不可能だった政策パッケージだと言えます。いわば「反共」を盾にした軍事独裁政権だからこそ可能だった。このモデルが、漸進的に80年代以降北側にも導入されてくる。これはナオミ・クラインが『ショック・ドクトリン』で描く現代史像でもあります。
同時に1973年は第四次中東戦争=オイル・ショックの年でもある。WWII後の北側の高度経済成長の条件の1つである「ただ同然」のエネルギー資源の確保、これが不可能になる。となると、「成長の果実」の資本と労働の間の分配が再検討されざるを得ない。紆余曲折を経ますが、基本的には資本側は労働側への「妥協」としての分配のレベルを下げていく選択を採る。これはD・ハーヴェイが強調するポイントです。つまりWWII後、ソ連の存在を前提として、西側でも社会民主主義政党を媒介に、労働者側の「忠誠」を確保するために、一定の妥協のメカニズムが構築された。これはドイツを典型とした欧州では「ネオ・コーポラティズム」と呼ばれるシステムです。実際、経済成長していれば、非対称であれ、「富の分配」という妥協はしやすかった。これが不可能になったわけです。その後、政策決定は資本と国家、さらに政党と組合という複数のアクターの選択の重畳を経るわけですが、おおむね一貫して階級妥協の廃棄、福祉国家の縮小の道をどの地域でも辿ります。オイル・ショック後の失業率の上昇を背景にして、仏のJ=P・ルペンをはじめとする欧州極右が抬頭しはじめるのはまさにこの時期。21世紀現在は、全欧州で極右の政権奪取の可能性が生まれていますが、これは新自由主義的再編が極限まで進んだ結果とも言えましょう。
さて、世界システムの覇権国家である米国はといえば、WWII以降インドシナで「反共パラダイム」に依拠して仏帝国主義に巨大な資金援助、1965年からは直接軍事介入に踏み切りますが、勝利の見通しのないまま膨大な軍事費負担が引き金になり、1971年にはついにニクソンは金ドル兌換停止を選択、ここにいわゆるブレトン・ウッズ体制は終焉する。いわば、第一次「アメリカ・ファースト」事件と言えます。