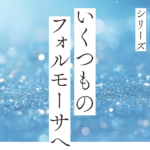これまでの記事はこちら
今年の7月初め、東アジアの南の海域で発生した大型の颱風「ダナス」。その例外的な進路は、台湾の島を南西部から襲って嘉義県布袋鎮から台南市の北門區にかけての海岸に7月6日の夜半に上陸し、最大瞬間風速50メートルを超える猛威を振るってあたりに大きな被害をもたらした。通常、台湾への颱風はほとんど例外なく太平洋に面した島の東海岸から来襲する。そのため台中や嘉義、あるいは台南といった西海岸の都市は中央山脈の高峰が壁となって守られているといわれてきた。今回は、猛烈な颱風の歴史的にきわめて稀な経路が、自然にも、また都市にも、思いもかけない災厄をもたらしたことになる。
「ダナス」とはフィリピンのタガログ語で「遭遇する」とか「経験する」とかいった意味をもつ言葉である。東アジアの颱風の名称は、この海域に接する国々の言語による140種の固有名のセットを順番に採用してゆくシステムがとられており、一番のカンボジア語「ダムレイ」(象)にはじまり140番のベトナム語「サオビエン」(海星)までが、5~6年ごとに一巡するようになっている。日本語の「カジキ」やマレー語の「ターファー」(鯰)、中国語の「バイルー」(白鹿)や韓国語の「チェービー」(燕)など、魚や動物にちなむ名が多いが、タガログ語名の颱風にかぎっては「ラガサ」(速い動き)とか「ルピート」(冷酷さ)とか「タラス」(鋭さ)など、颱風のエネルギーを形容する言葉が採用されていて特異な命名の感性を見せている。今回の颱風「ダナス」(遭遇/経験)も、とても暗示的な名前であったといえるかもしれない。
というのも、私の台湾南部への旅が今回このダナスの襲来の日に偶然重なり、颱風という気象現象の驚くべき「野生」の力に、台南の地でまさに「遭遇」することになったからである。私が台北から乗車予定だった台南往きの急行列車が、早朝、運行休止となった。颱風は島の南に上陸して北上し、私は島の北部から西海岸に沿って南下する予定であったため、両者の動きはまさに途中で衝突することになったわけである。
午前中いっぱい待たされ、颱風が通り過ぎたのちに運転再開された高速鉄道に乗って台南の街に着いたのは、颱風襲来から一夜明けた7月7日の午後遅くであった。中心市街にも颱風の爪痕はまだあちこちで残っていた。建物や塀の一部は破壊され、看板が吹き飛んだまま道路に転がっている。ほとんどの店はシャッターを下ろし、住民は瓦礫の整理に精を出していた。疲れた表情の人々に聞くと、台南の北門區にある台湾全土の王爺(オンヤァ)信仰の総本山の廟「南鯤鯓代天府)」のランドマークである巨大な牌楼(山門)が、強風により倒壊したのだという。人々のショックは大きかった。この門は台湾最大の木造建築物といわれ、12本の丹塗りの太いヒノキの柱で支えられた豪壮な姿で知られる。台南の民衆にとって、王爺は大陸福建の泉州から海を渡って来た人々が信仰してきた疫病を鎮める神で、港に特有の、海を媒介にした疫病の蔓延を歴史的に何度も体験してきた人々によって手厚く祀られてきた。その廟の象徴である山門が倒壊することは、台南民衆にとって自分たちの大切な信仰心のよりどころを失うことに等しいのであろう。身体の一部をもぎ取られるような痛み、といえばいいだろうか。


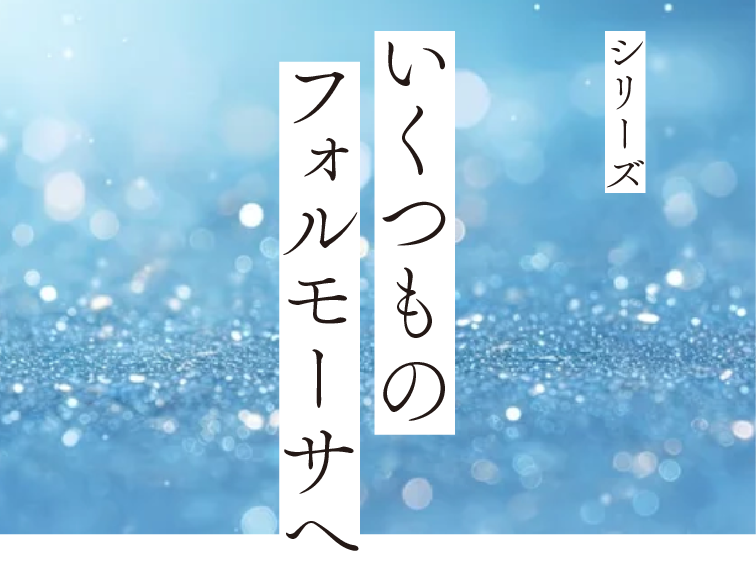






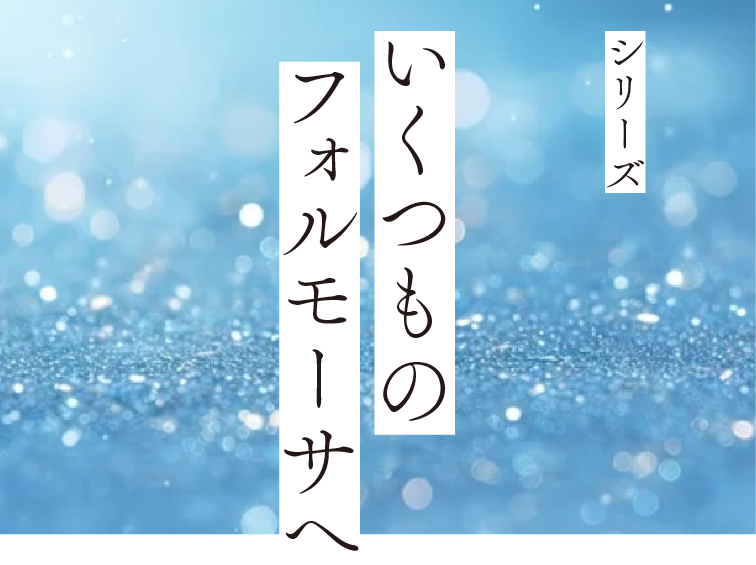
.jpg)

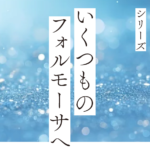
-150x150.jpg)