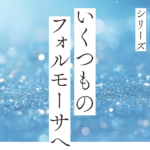これまでの記事はこちら
伝承、継承にある奇蹟
2年半ほど前、台湾の古い民衆叙事歌謡「唸歌(ニェンガー)」の驚くべき歌い手・楊秀卿(ヤン・シュウチン)が89歳で亡くなったのを知ったとき、私は大いなる落胆とともに、かろうじて伝承されてきた民衆芸能としての唸歌とその伴奏楽器である月琴をあらたに学ぼうという希望をなかば諦めかけた。彼女の代わりは他にいないように思えたからである。その演奏と歌唱の奔放と独創は、いかなる制度的な教育の場も再生産することが不可能な、奇蹟のような単独性、唯一無二の野生の輝きを放っていた。だが今回、神の恩寵のようにして目の前に現れた楊秀卿の教え子・楊咩咩(ヤン・メイメイ)と語り合い、月琴で音合わせをするうちに、私の気持ちは変わっていった。
2本の弦が、楊咩咩の親指と人差指に挟まれた、水牛の黒い角を自ら削った不定形のピックで弾かれる。するとそこに、あきらかに演奏者個人によって出された音とはちがう、アウラに満ちた「伝承の音」が響きだす。それはまさに「月琴」という楽器そのものが体現する、民衆の集合的記憶によって充填されてきた凝集体、いわば「うた」の集合体が、月琴みずからの声として語りはじめるからである。しかも楊咩咩が弦を弾くと、その音には、あの楊秀郷のものとしか思えない音響的陰翳とノイズが、たしかに聞こえてくるのだった。月琴という民俗楽器に宿る「手」というものの身体的伝承は、音符や音階をただ正確になぞるだけではない。それは、西欧的な意味での「音楽」を形成するメロディやリズムといった要素の外部にある秘密の領域、フィリピンの作曲家・音楽理論家ホセ・マセダならば「ドローン」と呼ぶような、記譜不可能な唸り、ノイジーな群音のざわめきの影を、たしかに随えているのである。月琴が決して西欧的な意味での「平均律」楽器ではなく、いくつもの不協音、すなわち均等に分けられた通常の十二音階から外れる揺らぎの音を、楽器の構造としても秘め隠しているという事実が、それを雄弁に語っている。
楊咩咩が歌いだす。代表的な唸歌のひとつ「江湖調(カンホーティアウ)」の一節。歌うなかで声色が変わり、台湾語による歌詞に踏まれた韻と旋律の上下運動とが、微細に重なり合ってゆく。不意に歌をやめて説話の場面になると、一世紀も前の民衆の日常の一幕かとおもわれる情景が、大道の即興劇のようにして目の前に迫ってくる。


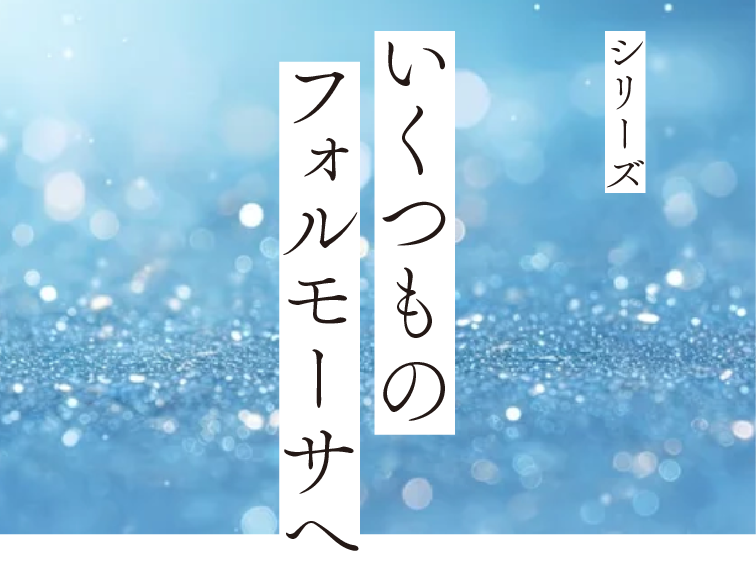









.jpg)

-150x150.jpg)