半世紀前、私とフォルモーサの島との決定的な「邂逅」をもたらした原風景の一つが、写真家・東松照明の鮮烈な写真集『太陽の鉛筆』(1975)であった。沖縄「復帰」直前の1969年から1970年代前半にかけて、沖縄・宮古・八重山諸島において撮影された異色のドキュメンタリーともいうべき150枚の白黒写真を前半に、沖縄から台湾、フィリピン、インドネシア、マレーシア等の東南アジア島嶼域を移動しながらカラーで撮られた民衆の生き生きとした日常風景80枚を後半に置いて、東アジアの群島地帯が共有する、国家や文化の枠組みを超えた「風景の連続性」を示唆した、それはきわめて刺激的な写真集であった。
この写真集に横溢する「海」の遍在と、すべての写真が一つになって示す清々しいほどの「越境的=脱国境的」視線に誘われた大学生の私は、1978年春、いまだドルが流通し車輌が右側を走る那覇から船を乗りついで、日本列島の最西端の島、与那国島へとたどり着いた。日本領土が果てる島の西の外れの岬「西崎(いりざち)」の断崖に立ち、そこから遠くはるかな水平線上にかすむ台湾の島影を見て心が騒いだ。東京という中心からの視線を解除し、「日本」の最果てに赴いて国家領土なるものの幻想の「自明性」を批判的に問い直し、周縁から中央を「眼差し返す」ことが私のひそかな目的であったが、それ以上に、海を隔てて隣り合うフォルモーサの島の雄大な影を発見したことが、私に「国境」なる制度の恣意的な虚構性をはっきりと教えた。日焼けした皺深い顔と手をもつ与那国の老漁師に話を聞くと、古くから島の漁民たちは対岸の花蓮や宜蘭からやってくる台湾漁民たちとまったく同じ海域で日々操業し、お互いに深い信頼関係を築きつつ、国境線の存在など気にもかけずに同じ海を「共有」していたという。互いの漁船のあいだで、足りなくなった漁具などの貸し借りさえしばしば行なわれていたのだという。分断ではなく、繋がりを生み出す海。有機体として、すべてを共生の関係に導く群島の連なり。こうして台湾は、人間や事物のそのような脱国家的な連続性を示す特別の場所として、私の前にくっきりと立ち現れたのである。



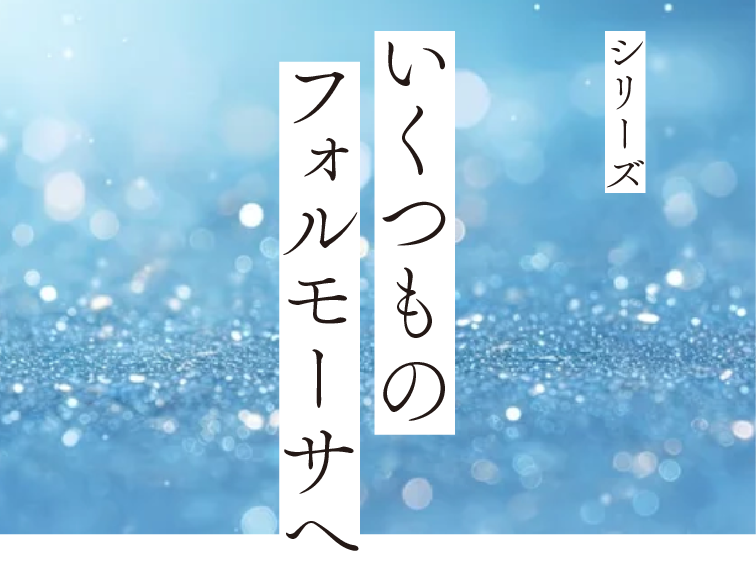




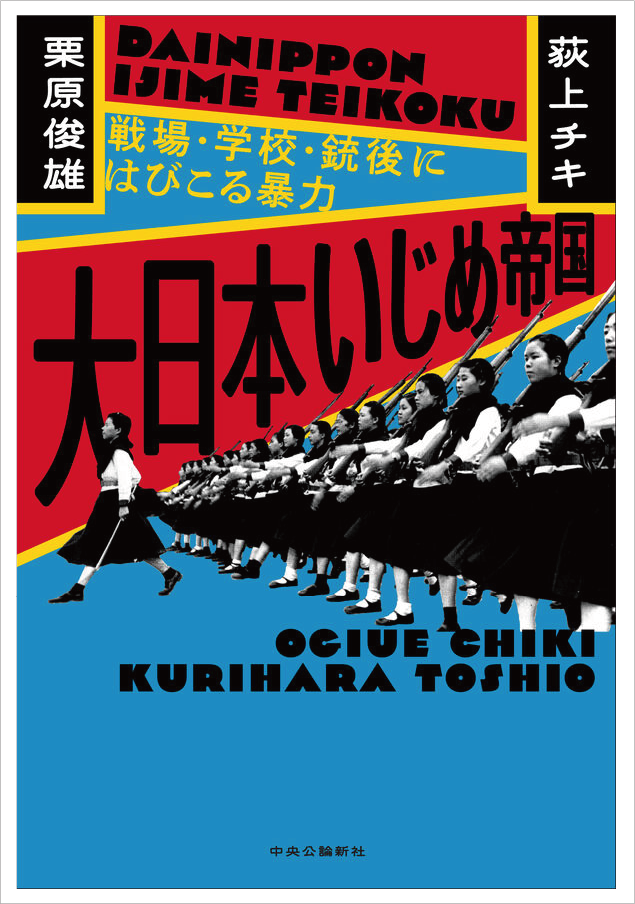

.jpg)

-150x150.jpg)

