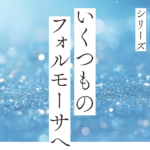これまでの記事はこちら
広東語とポルトガル語が飛び交う風景
マカオに短い旅をした。1999年に中国へ返還されて四半世紀が経つ、旧ポルトガル領植民地都市。私はマカオ旧市街の一角に古いコロニアル建築を改修した安価な宿をとり、ひたすらかつてのポルトガルの記憶を求めて時間の襞(ひだ)をたぐるように街を彷徨った。16世紀初めから東アジアと南アメリカとに同時に進出し、一時は世界の海をほしいままに支配した一つの海洋帝国の屈折と変転にみちた一つの帰結を、私はアジアの一角において身近に感じてみたいと思ったのである。16世紀なかば、ポルトガル人がこの半島にはじめて上陸して布教と交易の拠点をつくってから約500年がすぎ、長くポルトガルの施政権のもとにポルトガル人と土着の広東人と他のアジア地域から流れてきた人々とのあいだの混淆文化が花開き、マカオは世界でも稀にみる多民族・多文化・多言語混在の街として近現代の歴史を生きてきた。
台湾からわずか1時間半のフライトで、中国大陸の一角にやってきた私の第一印象は、この街のサウンドスケープ、すなわち音風景の大部分をつくりだす、土地ことばとしての広東語の遍在だった。「中国」の一部であるにもかかわらず、いわゆる中国の国語としての「中国語(マンダリン)」の片鱗すら感じられないことの驚き。むしろ大陸中国とのあいだに複雑な関係性を抱える台湾の方が、日常の表面的なサウンドスケープとしては、はるかに「中国語」(それをベースとする台湾華語)的なるものに浸されている。土着民衆的な「台語=福佬語」も広く生きのびている台湾だとしても、マカオと比較したときの日常台湾における逆説的な言語状況を、近代の東アジアの歴史の複雑性の帰結として私は感じることにもなった。
それほどにマカオの日々の民衆的風景は広東語の響きに充たされていた。一方で、音ではなく視覚的にいえば、この街は完全なる二言語併用状態、すなわち広東語とポルトガル語の文字の二重表記によって特徴づけられている。ポルトガル語を日常的に話す人をほとんど見かけないにもかかわらず、公共空間の文字使用における徹底したバイリンガル性は印象的だ。下町の賑わしい屋台街にある生鮮市場「下環市場 Mercado de S.Lourenço」。この地区がかつてはカトリックの小教区として聖人名サン・ロウレンソを冠して呼ばれていたことに由来する名が、この市場の建物の正面に漢字とともにはっきりと記されている。大きな漁港をもつマカオらしく、市場の魚や海老は生きたまま平たいバットに海水とともに並べられ、横になって勢いよく泳ぎ、翔び跳ねている。野性的な広東語の叫び。買い求める民衆のエネルギーも逞しい。


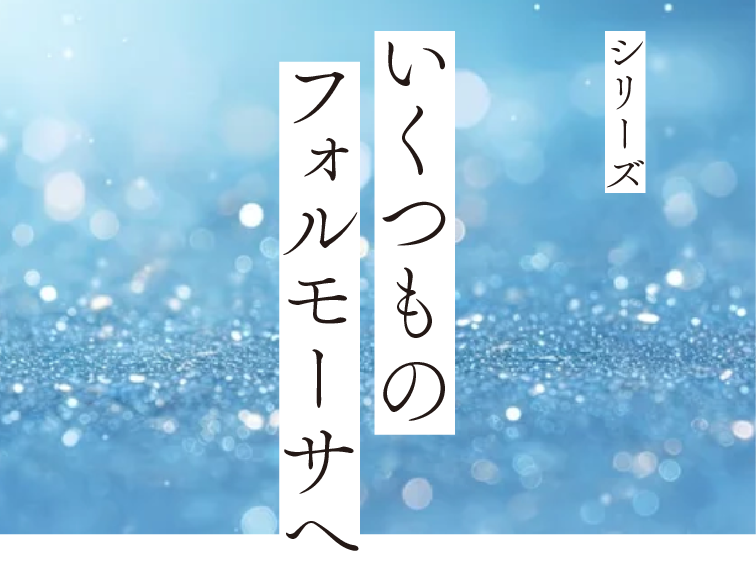







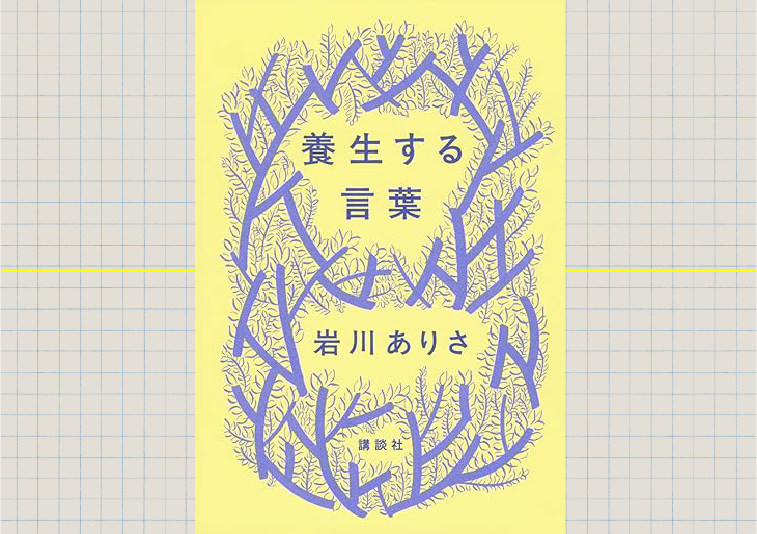

.jpg)

-150x150.jpg)