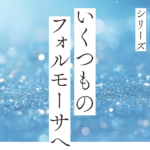これまでの記事はこちら
泥土的滋味に目を覚ます
5月から6月にかけて開催された国立台湾大学の総合図書館での特別展示「黄春明文學季」に合わせて企画されたイベントで、「黄春明文学と島々の声」(「黄春明文學與島嶼之聲」)と題して講演・パフォーマンスを行なった。会場となったのは台湾大学校史館の大理石の優美な正面階段を上った2階の中央展廳と呼ばれる開放的なスペース。100余年の時を刻む歴史ある建物の開け放たれたクラシックな格子窓からは外気が流れ込み、堅固な石造りの高い天井は美しく音を反響させる。舞台は小さな半円形の広場のようなかたちをしていて、講演と、私自身の脚本・演出による説話・歌・音楽の複合的な舞台(私はこの形式を「吟遊オペラ」と名づけている)を行なうにはうってつけの、遊戯的で親密さ溢れる空間だった。当日は、大学の台湾文学研究所で学ぶ学生や大学院生たちを中心に、研究者やアーティストや作家や一般市民など、学外からも多くの参加者が雨模様の一日にもかかわらず参集してくれた。
今年90歳になる、台湾文学の至宝とも言うべき作家・黄春明(フワン・チュンミン)。私は、彼の郷里、宜蘭(イーラン)での幼少年時代の経験が色濃く反映された素朴かつ潤いある小説世界を出発点にしながら、「人間」と「郷土」とのあいだの豊饒かつ複雑で屈折した関係性の歴史を日本の文学や詩へと架橋しながら省察し、その主題を即興的な物語と歌で変奏してゆく舞台を何人かの若い共演者に呼びかけて創った。イベント当日、思いがけないことに黄春明先生自身も高齢をおして夫人とともに来場してくれ、私にとっては最前列に座った作家本人を前にしての語りという、特別に気持ちの昂ぶる公演となった。
黄春明は日本統治時代の1935年、台湾北東部宜蘭県の町・羅東(ルオトン)に生まれている。8歳で母を亡くし、貧しいなか、学校で問題を起こすなどして中学を退学処分となり、台北の電気屋で徒弟として働いたりしたこともあったが、やがて台北・台南・屏東などの師範学校で学んで小学校の先生となり、郷里の人々や出来事をモチーフにした小説を書き始める。軍役を終えたあとは宜蘭のラジオ局で記者・編集者・司会者として精力的に仕事しながら、雑誌に多くの小説を発表。「郷土文学」の旗手として、リアリズムを基調としつつ風刺やユーモアの精神にもあふれたその作品は多くの人々に愛され、翻訳を通じて海外にも広く紹介されてきた。


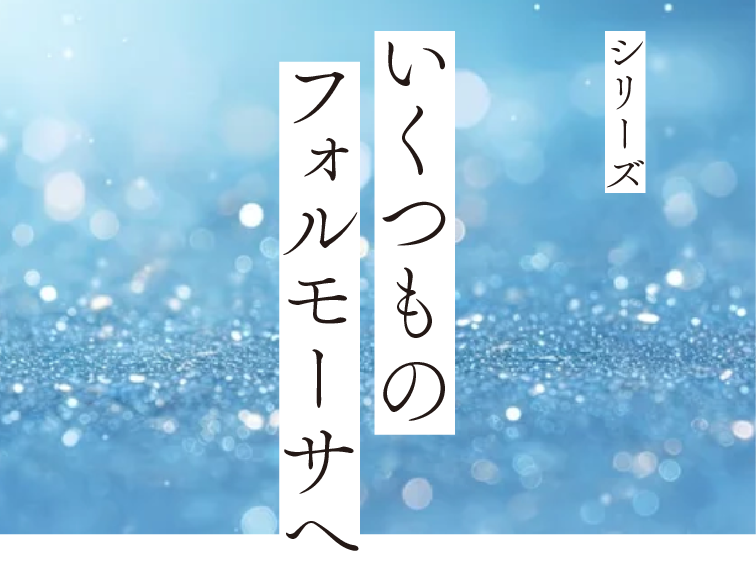







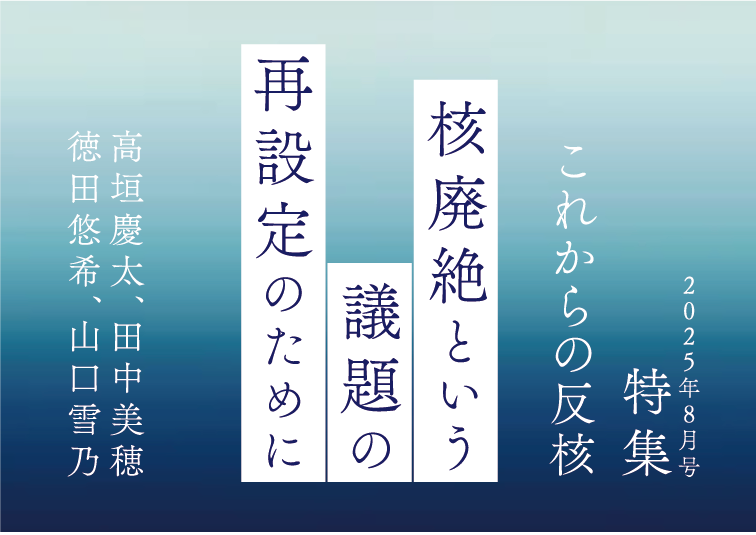
.jpg)

-150x150.jpg)