「フォルモーサ」の無数の反響
16世紀なかば頃、アジアの未知の海域を航行していたポルトガル船の航海士が台湾の島を見て発したという感嘆の声が、私に隠された歴史と記憶と想像力の見えざる糸を喚起する。その船乗りの声は、海上からはじめて望む緑豊かな島の姿に感嘆し、「フォルモーサ!」Formosa!(なんと美しい!) と叫んでいる。この「フォルモーサ」という言葉のなかには、東アジアに(そしてポルトガルやスペイン、さらにオランダやイギリスを介して世界全体に)到来した大航海時代、そして布教と植民地主義の時代から現在に至るまでの、複雑で回帰的ですらある関係性について思考するための、特別の寓意の力があるように思われる。
それはたしかに西欧による近代世界の「発見」をうながす叫びであり、植民地主義的「領有」の前触れとなる符牒である。美しかったはずの島々は、それゆえに奪取され支配された。その意味で、フォルモーサは、一つの大いなる幻想でもあった。だが同時に、それはどこかでその後の歴史の顛末を超えてゆく、原初の、いまだ整序されない混沌とした響きをも宿している。フォルモーサが一つではなく、画一的な意味にも回収されない、群島論的な想像力を開く未知の可能性をはらんでいることが予感されてくる。
振り返ってみると、私はこれまで、ポルトガルやスペインの植民地としてはじまったラテンアメリカやカリブ海への旅や滞在を通じて、このポルトガル語の「フォルモーサ」(スペイン語では「エルモーサ」)の無数の反響をどこかでつねに聞きながら旅し、「世界」について考えてきたようにも思う。台湾に来る前に、すでに私はさまざまなフォルモーサと出遭って いたのかもしれない。そしていま、私は台湾の生活者の日常感覚にできるだけ近づきつつ「住む」ことを、このフォルモーサの島で試みようとしている。
狭義においても「フォルモーサ」は、いまやポルトガルによる台湾島の別称としての過去の歴史的な意味論を抜け出し、中華民国、台湾といった政治的な文脈で使用される名辞をより文化的な文脈に開き、そこに、漢民族を中心とした旧来の台湾人のアイデンティティを超える、この数十年のあいだに生まれつつある脱規範的でかつ混淆的な国民意識をあらたに語ろうとするときに言及される言葉となりはじめた。そして私のさらなる閃きは、「フォルモーサ」という言葉が一種の「呪音」として、世界を既存の地政学や言語地理から解放し、思いがけない接続的な関係性や詩的な飛躍の可能性を発見するための、手がかりともなる概念なのではないか、という直観である。「いくつものフォルモーサ」とは、そんな未知の関係性にみちた世界地図をあらたに見出すためのヴィジョンとなりうる。


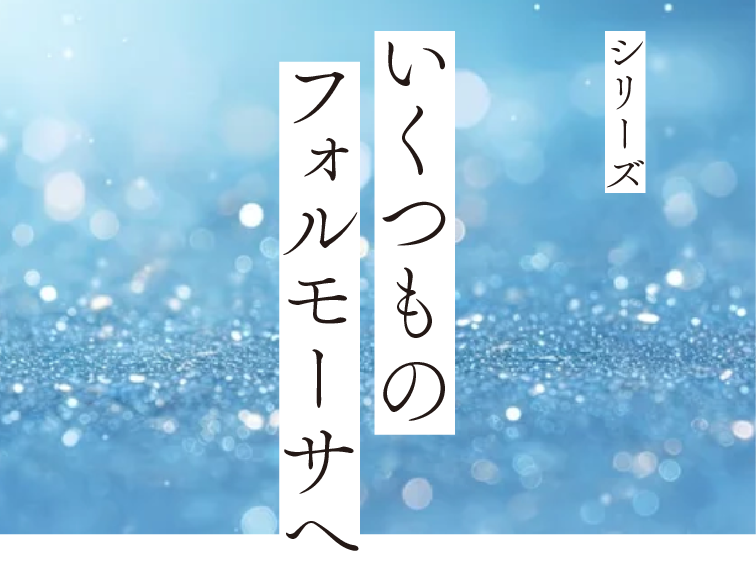






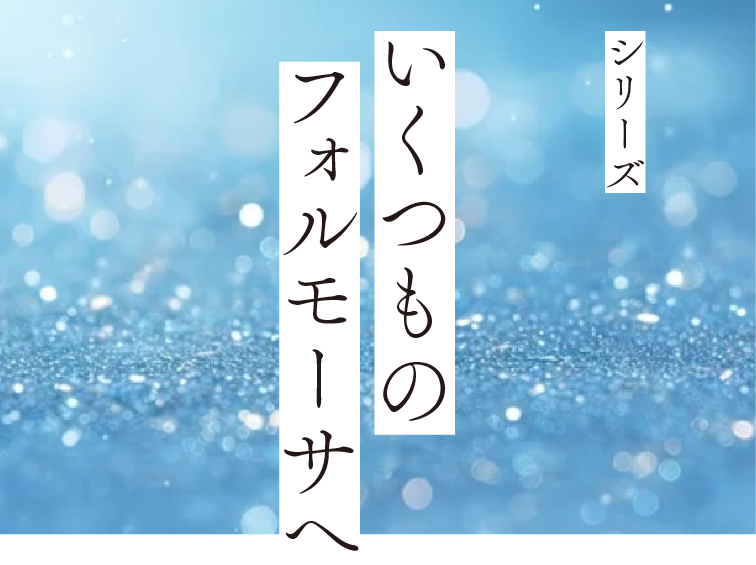
.jpg)

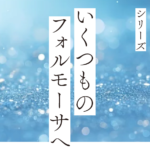

-150x150.jpg)