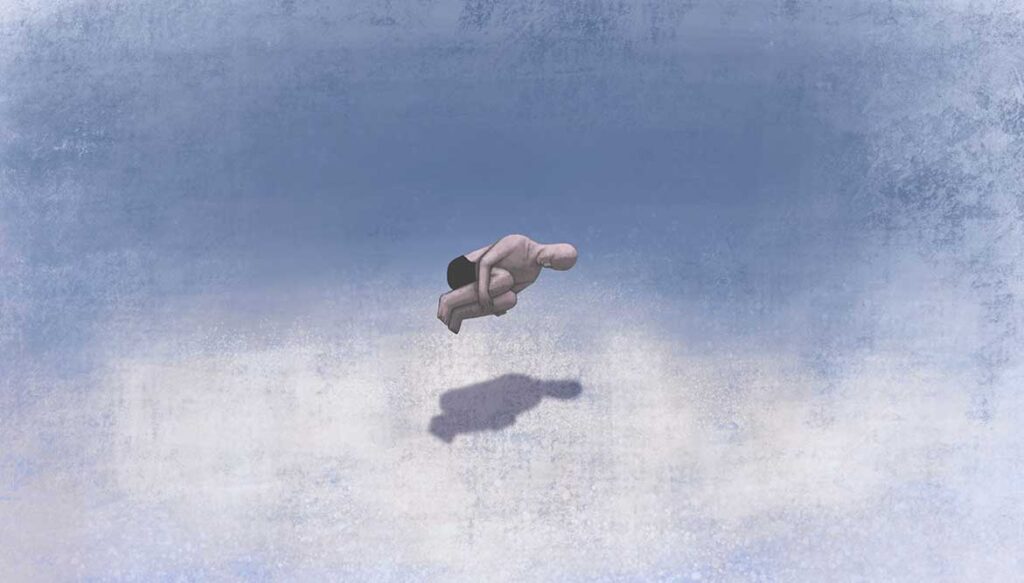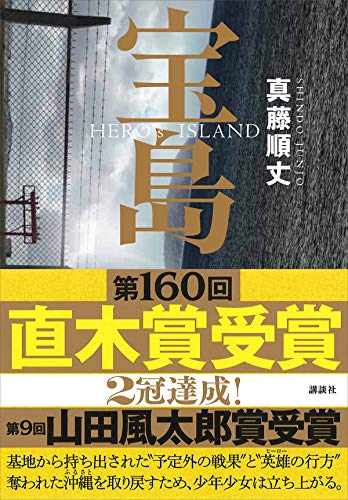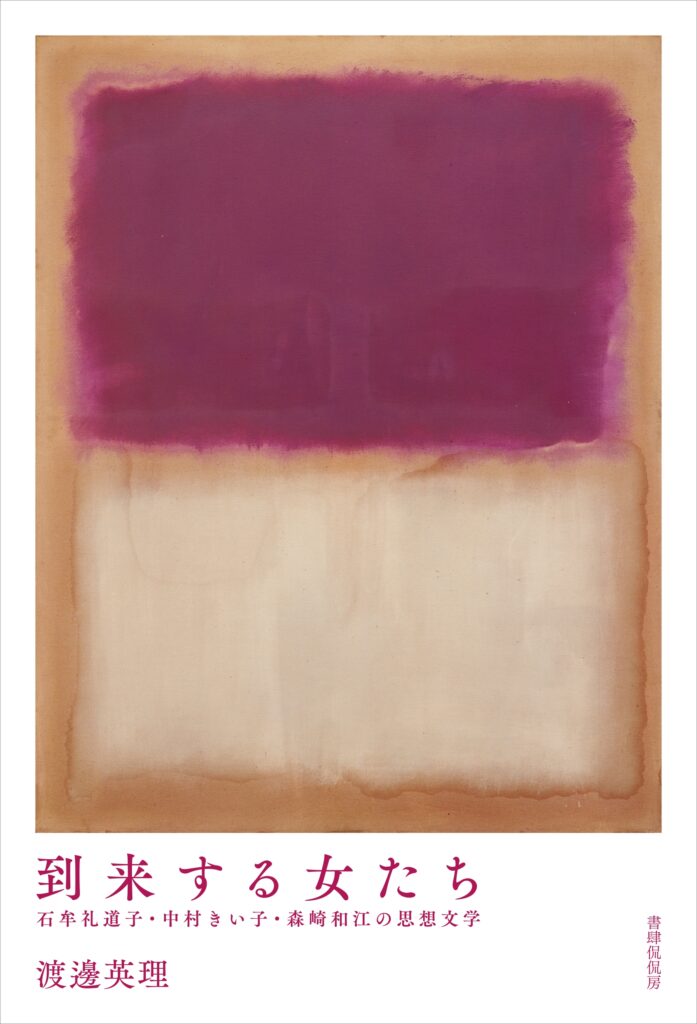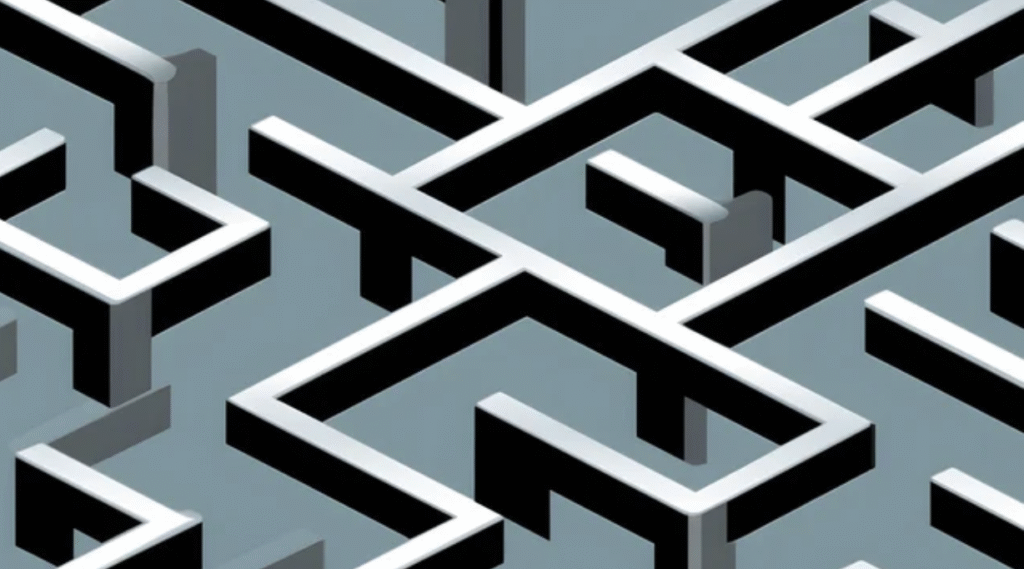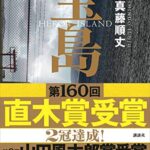ことの始まりは、7月24日発売の『週刊新潮』7月31日号。「創氏改名2・0」と題された高山正之の連載コラム「変見自在」が掲載された。
とりわけ問題なのがコラムの後段。高山は外国にルーツを持つ3人の名前をあげ、日本風の名前で日本の批判をするな、と主張した。8月4日、高山のコラムで名指しされたひとり、作家の深沢潮さんが抗議の記者会見をしたことで事件は広く知られることになった。
作家を裏切った出版社
高山の主張は奇妙だ。なぜ、外国にルーツを持つ人が日本風の名前で日本を批判してはいけないのか。小泉八雲のように褒めるならいいってことか? 批判を「悪口」と捉えて好悪に矮小化したり、ルーツ云々で「日本を批判していい人/いけない人」に分けたり、なんと幼稚で薄っぺらなこと! だが、こんな低劣なコラムも凶器になる。この3人を攻撃せよと煽動している。名指された3人の当惑や怒り、不安、悲しみ、恐怖はいかばかりか。高山は元産経新聞の記者だそうだ。犬笛を吹くことの影響を知らないはずがない。3人の名をあげたのは、彼らの人権を踏みにじるためだ。
犬笛を吹いたのは高山だが、それを響かせたのは『週刊新潮』である。高山も悪質だが、『週刊新潮』編集部と新潮社はもっと悪質だ。
深沢さんは2012年に新潮社の「女による女のためのR ─18文学賞」で大賞を受賞してデビューした。受賞作「金江のおばさん」は短編集『縁を結うひと』(新潮文庫)に収録されている。ここで出版、とりわけ文芸出版における著者と編集者、著者と出版社の特別な関係について留意する必要がある。
作家は編集者や出版社を信頼して作品を書く。創作に向かう作家は孤独なものだが、編集者は作家をサポートし、ときにそれは二人三脚にたとえられる。作家エージェントが発達した英米ではエージェントが作家のために動くが、日本では出版社と編集者がその役割を果たす。信頼していた出版社に裏切られたらどんな気持ちがするか。ましてやデビューのきっかけとなった出版社なのだからなおさら。多くの作家が新潮社に抗議したのも当然だ。深沢さんも所属する日本ペンクラブの女性作家委員会、そして言論表現委員会は8月5日、排外的言論の横行を懸念するという声明を発表した。