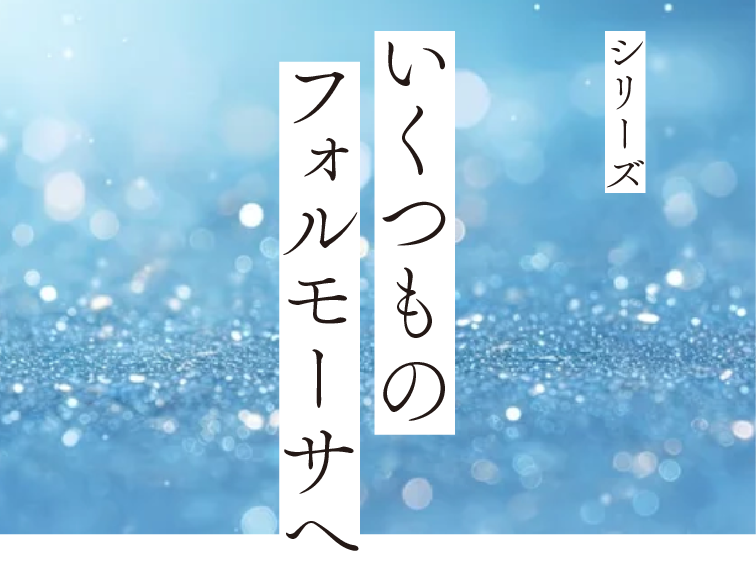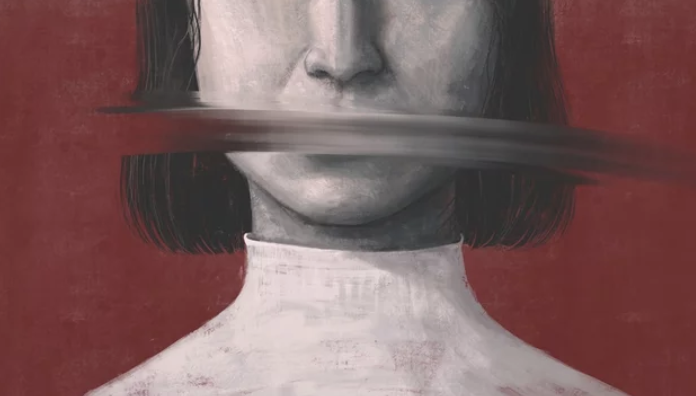「浦添(うらそえ)西海岸」――この海のことを、読者はご存知だろうか。
沖縄の空の玄関口、那覇空港から北へ、車で20分。青く澄んだ3キロも続く海岸線が訪れる人を迎えてくれる。潮が引いた浜におりると、どこからともなく「パチパチ」という賑やかな音が聞こえてくる。それは小さなエビをはじめとする生き物たちが奏でている音だ。そして、空からは海鳥たちがやってきて、海の中ではカラフルな熱帯魚たちが泳ぎまわる。水平線で海と空が出会い、地球の丸さを感じる、これぞ沖縄という景色を求めて、多くの人々もこの海にやってくる。
2018年、西海岸道路が開通するまで、この海へのアクセスは米軍施設キャンプ・キンザーのフェンスに阻まれてきた。
6年ほど前、道路の開通とともに大型商業施設もオープンし、手つかずの自然の海が多くの人の目に触れることになった。夕方になると水平線にあたたかなオレンジ色をした夕日が沈む、美しいサンセットを楽しめる場所でもある。聞けば、若者たちにとって浦添西海岸は初デートの場所だったり、友と語りあったり、カラフルな想い出の詰まった大切な場所になっているという。
だが、今その海に持ち上がっている米軍那覇港湾施設(那覇軍港)の代替施設を建設する計画について、若者たちにはあまり知られていない。沖縄の若者たちだけではない。本土から来る観光客も、あるいは本土で辺野古の基地に反対の声をあげてくれている人々にさえも、あまり知られていない。それが25年にわたって沖縄を拠点に報道マンとして取材を続けてきた私の実感だ。
これからの沖縄を生きていく若者たちの声を抜きに、この海の埋立計画が進められていいのか……。考え抜いた末、私は地元のテレビ局を辞め、短編ドキュメンタリー「この海は誰のもの 沖縄うらそえ西海岸物語」の製作にとりかかった。
辺野古と同じ構図
まず、埋立計画の概要についてお伝えしたい。
那覇軍港の移設にともなって、防衛省によると、49ヘクタールを埋め立てる計画だという。新たに建設される施設には、事務所や倉庫など合わせて、17の建物が配置される予定となっている。2024年7月には、環境影響評価(アセスメント)の第一段階となる配慮書の公告縦覧が始まった。時期を同じくして沖縄防衛局は設計のためのボーリング調査の掘削を開始している。外務省の「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」によれば、海を埋め立てて代替施設が完成するまでに16年の歳月を必要とするという。
沖縄の本土復帰から2年後の1974年、日米両政府は、「県内移設」の条件付きで那覇軍港の全面返還に合意した。
しかし、移設の条件がネックとなって実現せずにきたのだが、1995年、3人の米海兵隊員による女子小学生暴行事件が発生。それをきっかけに、沖縄県内にある米軍基地の整理縮小を求める世論が高まり、対応を迫られた日米両政府が日米特別行動委員会(SACO)を設置した。翌年の最終報告で、普天間飛行場をはじめとする県内11の施設の返還が決まった。その中で、浦添ふ頭地区への移設を条件として、那覇軍港の返還が約束されたのだった。
移設には海の埋立をともなうことから、地元では反発の声も根強く、移設計画は停滞していたが、2001年、当時の浦添市の儀間光男市長が受け入れを表明。2013年の市長選で松本哲治市長が移設反対を掲げて当選するも、2017年、公約を撤回して移設容認に転じ、那覇軍港の移設計画が動き出したのだった。
問題を複雑にしているのは、返還が予定される那覇軍港が経済的に一等地とされており、その跡地利用に地元の経済界から大きな期待が寄せられていることだ。
那覇港湾の開発の長期計画では、今後、取り扱い貨物の増大が見込まれるとして、浦添に軍港だけでなく新たに埋立をしてふ頭を整備することも併せて構想されている。その民港部分の埋立は「物流空間」と「交流・賑わい空間」に分けられ、面積はそれぞれ77ヘクタールと32ヘクタール。「賑わい空間」は世界水準のリゾート敷地とも言われるが、軍港に隣接する高級リゾートなどあり得るのだろうか。
軍港部分と民港部分の埋め立てを合わせると、109ヘクタールにもなる。あまりピンと来ないかもしれないが、東京ドーム30個分に匹敵する面積となる。