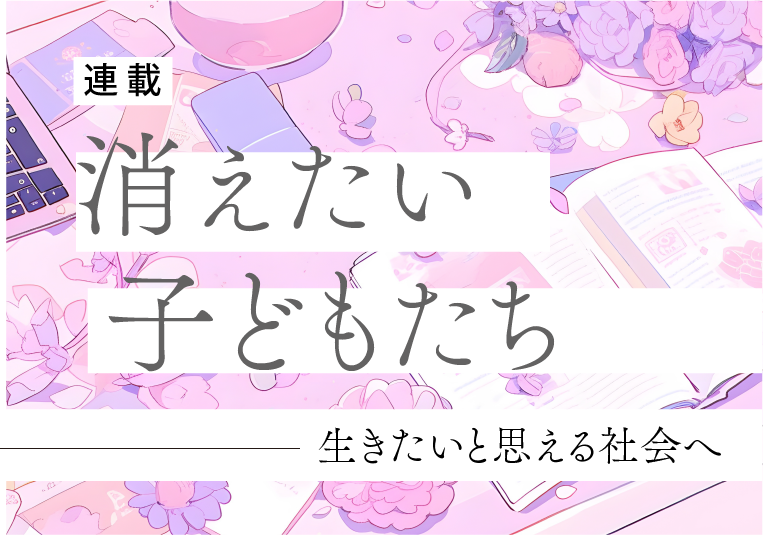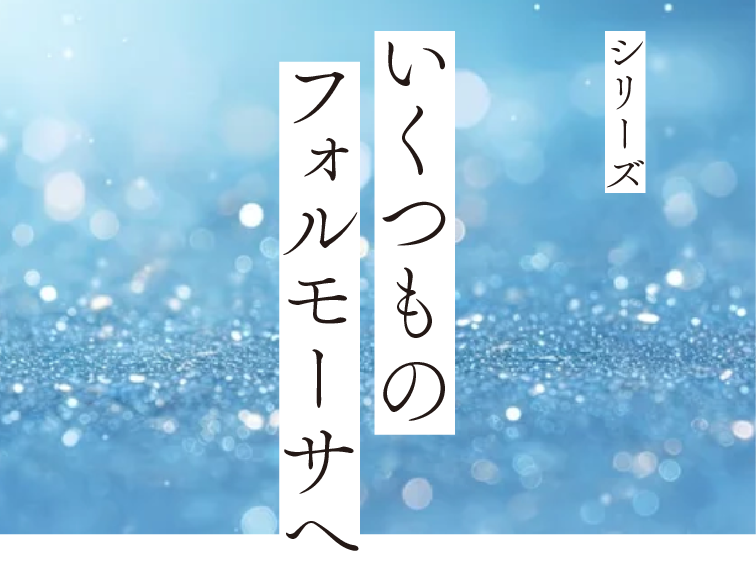これまでの記事はこちら(ルポ 消えたい子どもたち)
「注意力が要らない職場があったら教えてください。そんな企業ないですよね――」
独立行政法人・日本学生支援機構の「大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書(2023年度)」によると、障害のある学生は全国で5万8141人。疾患の認知度が上がった影響か、2006年度から10倍超に増えている。
障害種の内訳は「精神障害」「病弱・虚弱」に次いで「発達障害」が全体の20.1%を占める。発達障害は脳機能の発達に関係する障害で、大きく「ASD(自閉症スペクトラム障害)」「ADHD(注意欠如・多動性障害)」「SLD(限局性学習障害)」に分けられる。
冒頭の発言をしたのは、都市交通学を研究する修士課程2年の大学院生、山本哲也さん(仮名、23歳)で、ASD、ADHD、SLDのほか感覚過敏の発達特性を自認し、医師の診断も受けている。障害者手帳を所有してはいないが、発行が認められる障害の程度だという。
山本さんは、大学卒業前の就活中、200社にエントリーシートを送り、採用過程が進んだのは52社。しかし内定は1社も得られなかった。就活中は相手企業に対し、障害があることはオープンにしていない。それなのに、なぜ内定が取れなかったのだろうか。
「SLDと注意力の欠如が原因で最終の適性検査で落とされました。問題量が膨大で、スピードを求められ、ひっかけ問題では注意力や緻密さも要求されたのです。私の特性ではだめだったみたいです」
ある企業の人事担当者から不合格の連絡があった際に、その理由を聞いてみた。「適性検査の結果が悪すぎた」という返答だったので、その時に初めて発達障害だと伝えた。
「今は情報化時代。実務に就いて、メールを送り間違える、会社の携帯電話をなくすなどの事案があった時には、コンプライアンス違反にもなり、取引先にも多大な迷惑をかけてしまうので、雇用には慎重にならざるをえません」
「今回は障害を理由に落としたわけではない」と納得しつつも、就職のハードルの高さを山本さんは感じた。
発達障害は、身体障害と違って外からはその困難に気づきにくい。それゆえ生きづらさや「困り感」を抱えこんで生活している。山本さんのように障害を併せ持っている場合も多く、それぞれ独特な行動や思考、感じ方があって、対処の仕方も一律ではない。
筆者は山本さんにオンラインで取材したが、穏やかで丁寧な物言い、理路整然とした話し方に好感が持てた。
「障害があっても特性を感じさせなければ、ひょっとしたら障害ではないのかもしれませんが、なかなかそうはいかず。私のように字が書けない、文章が理解できない、注意力に欠けるというのは生きるうえで重大な問題なのです」
自分の字が読めない
特性を自認したのは、小5のとき。字がきれいに書けなかった。小学校に入学したてのころは、字がきれいな子もそうでない子もいたが、学年が上がるにつれて他人にも読める程度になっていく。しかし山本さんの字は、本人ですら、何が書いてあるのかがわからなかった。文章を読む速度も速くなっていく傾向にあるのに、いつまでたってもたどたどしい読み方のままだった。読むのも書くのも徐々に周囲との差を自覚するようになった。そして新たにもう一つ、注意力の欠如に気づいたという。