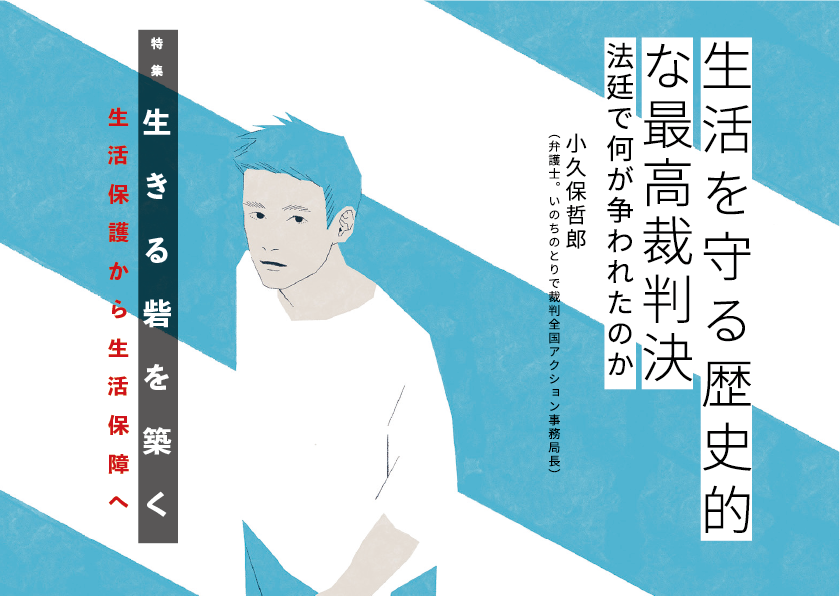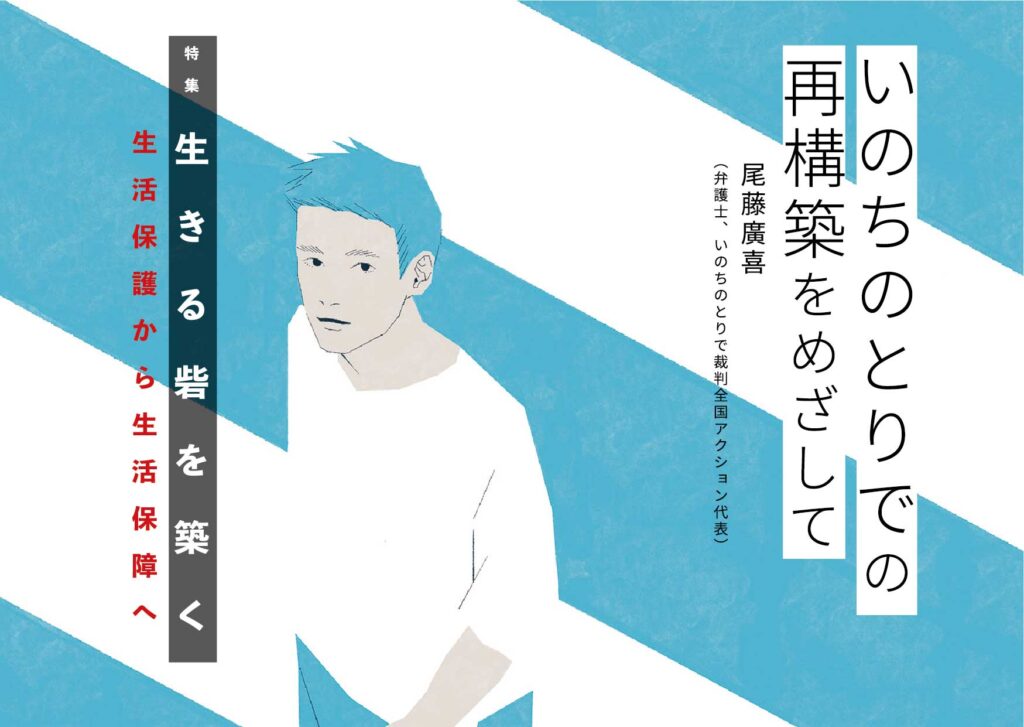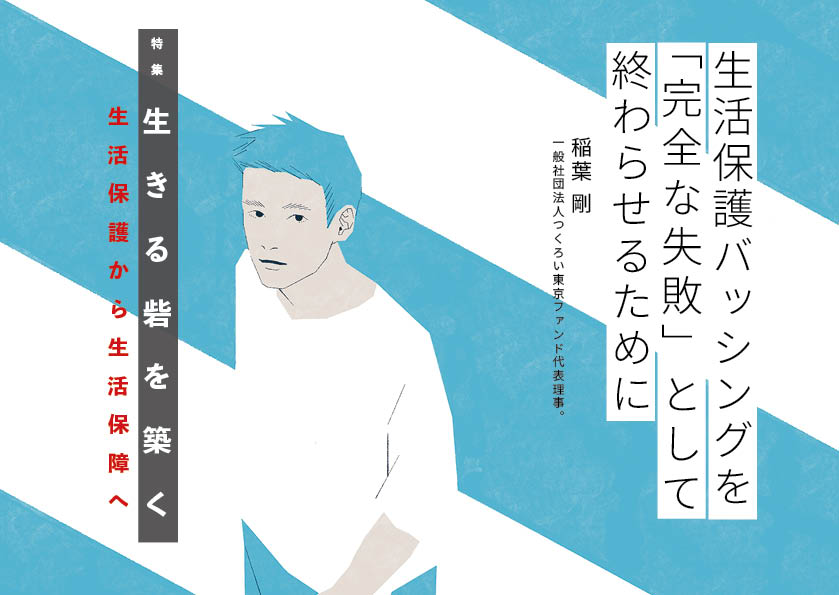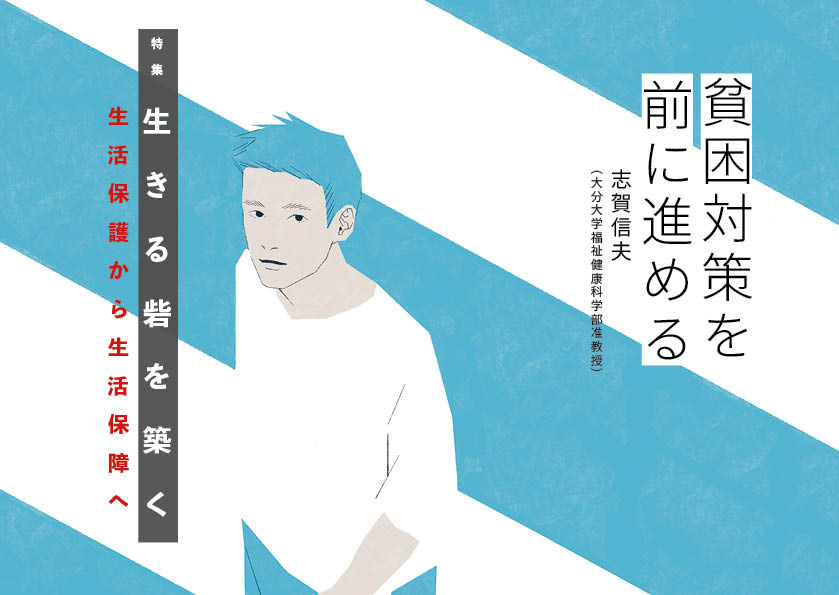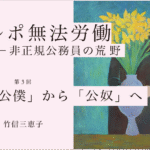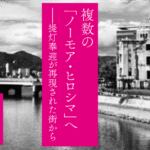2025年6月27日午後3時、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、歴史に残るであろう画期的な判決を言い渡した。
2013年からの史上最大の生活保護基準引下げ(以下、「本件引下げ」という)の違法性を問う「いのちのとりで裁判」で、本件引下げの違法性を認め、保護費減額処分の取消しを命じたのだ。
本件引下げは、基準生活費とも言われる生活扶助基準(生活費部分)について、平均6.5%、最大10%引き下げるもので、削減総額は670億円に及んだ。
本件引下げに先立つ2012年春、人気お笑いタレントの母親の生活保護利用をめぐり“生活保護バッシング”が吹き荒れた。バッシングを煽動したのは、当時、自民党に設置された「生活保護プロジェクトチーム」の座長だった世耕弘成議員や片山さつき議員だ。そして、2012年12月の総選挙で当時野党であった自民党は、「生活保護の給付水準10%引下げ」を公約に掲げて大勝し、政権に復帰した。第二次安倍政権が発足するや、選挙公約に合わせるかのように本件引下げが決められた。
これに対して、全国29地域で1000人を超える原告が立ち上がり、31の訴訟を闘っている集団訴訟が「いのちのとりで裁判」である。
本稿では、「いのちのとりで裁判」の法廷で何が争われ、下級審裁判所がどのような判断を示してきたのか、そして歴史的な最高裁判決の内容と意義について記したい(本稿でも紹介する主要な判決の判決全文や評価については、「いのちのとりで裁判」ホームページに逐次掲載されているので、興味をお持ちの方はご覧いただきたい)。
引き下げの問題点――「デフレ調整」による物価偽装
本件引下げの9割近くの580億円は、「デフレ調整」といって物価を考慮した削減である。デフレ(物価下落)で生活保護世帯の実質的な可処分所得が4.78%増えたので、その分、生活扶助費を削減したというのだ。
しかし、1984年から現在に至るまで用いられている「水準均衡方式」という生活扶助基準の改定方式は、一般世帯の消費水準と生活扶助基準のつり合い(均衡)を維持しようとするものであって、物価を直接考慮したのは後にも先にもこのときだけである。
しかも、2008年から2011年にかけての一般の物価下落率(総務省CPI)は2.35%なのに、厚生労働省が創出した「生活扶助相当CPI(消費者物価指数)」の下落率は倍以上の4.78%に及んだ。その理由は、その期間に大きく物価が下落していたテレビやパソコンなど、生活保護世帯がほとんど買えない教養娯楽財を一般世帯以上に購入しているという、あり得ない消費構造を前提とすることで、物価下落率が増幅されたことにある。まさしく「物価偽装」というべき統計偽装である。
生活保護基準の改定については、生活保護法の制定当初から専門家による審議会の検証をふまえてなされるべきものとされ、現にそうされてきた。ところが、厚生労働省は、本件引下げ当時、基準見直しに向けた検証を行なっていた社会保障審議会の生活保護基準部会(以下、「基準部会」という)に諮問することなく独断で「デフレ調整」を行なった。基準部会に諮問して委員に反対されるのを避けようとしたとしか考えられない。