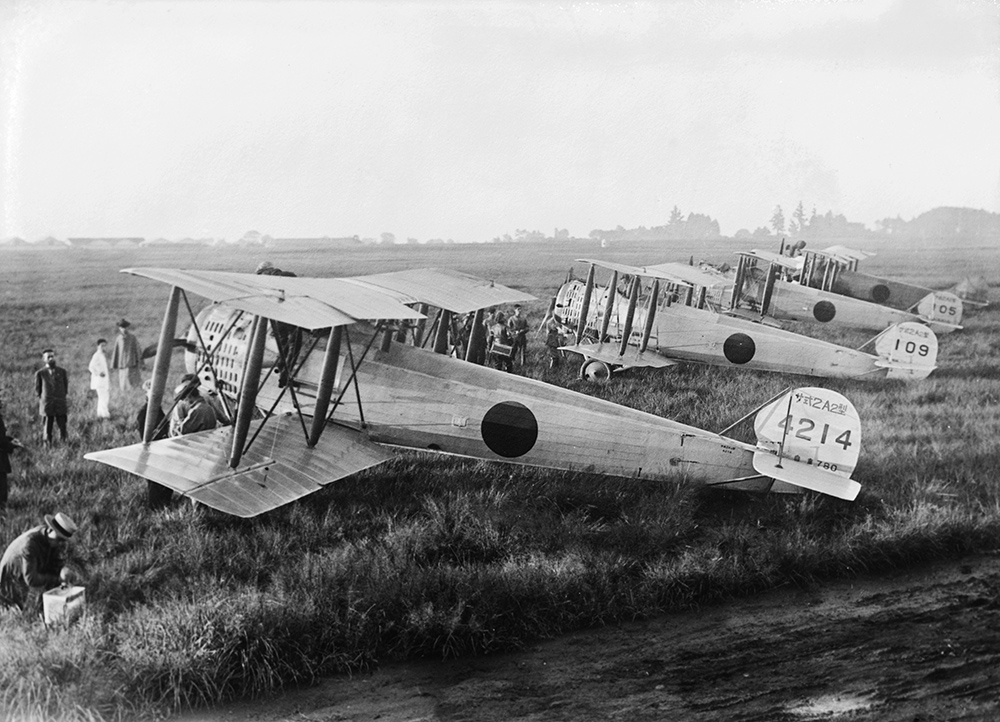ポツダム宣言と日本国憲法
本稿がとりあげるのは、国家の税財政権(国家が租税を賦課徴収する租税権力と、国家が財政を支出する財政権力の総体)である。平和主義との関係から、どのような制約と統制がそこに課せられるかを考えよう。
ポツダム宣言(以下、ポ宣言)6項は、「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」と、軍国主義者らの永久の追放に言及した。とくに1947年1月の公職追放令施行命令改正は、戦争犯罪人・国家主義団体の指導者らとならび、植民地経営や戦争遂行に関わった企業・金融機関・その他の経済団体の幹部をのきなみ追放の対象にした。
そして、ポ宣言の9項は、日本軍の完全な武装解除を規定し、11項で「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ」と、再軍備につながる産業の維持を禁じた。
GHQは、これらの方針にもとづき、戦時経済の中心にいた財閥の解体をおしすすめた。1946年、三井・三菱・住友・安田の四大財閥の持ち株は政府機関に移管され、それぞれの財閥は解散させられた。
占領期における経済の脱軍事化は、同時進行で制定された憲法の全体構造にも反映する。第一に、軍国主義者に公務就任の面で不利益を課すことは、国民に自由や権利を保障することと矛盾しない。むしろ、自由や権利の保障に必要な条件整備である。日本国憲法(以下、憲法とする)の文民条項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」(66条2項)は、軍国主義者の公務就任を制限することで、経済政策の脱軍事化を担保している。
第二に、経済の脱軍事化は無条件・無期限に実施される。これは日本国憲法9条2項「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」との関係で理解する必要がある。ポ宣言は日本政府が主体的に受諾し、対内・対外的に表明した法的文書の一つで、そこに書かれたことは、サンフランシスコ講和条約によって自動的に抹消されてしまったわけではない。もちろん軍事産業を支援する経済政策、兵器輸出を奨励する経済政策、いずれも否定される。
したがって第三に、軍需産業の禁止は、ポ宣言を追いかける形で憲法に取り入れられたとみるべきである。そのことは経済的自由権、すなわち職業選択の自由(22条1項)および財産権(29条2項)にともなう制約の一つとなる。経済的自由権は「公共の福祉」に反しない限りで認められるが、「軍需産業を維持してはならない」ことは「公共の福祉」の一つに当たる。この2箇条は、「何人も、軍需産業の禁止に反しない限り、職業選択の自由を有する」し、「財産権の内容は、軍需産業の禁止に適合するように、法律でこれを定める」と読み替えることができる。
経済の脱軍事化を目的とした制約、すなわち軍国主義者の追放、軍需産業の禁止と戦力不保持、経済的自由に対する平和主義からの制約は、憲法に内在化する。公権力はこの制約に反して行使されてはならず、制約に反した公権力の行使は無効とされる(98条1項)。公務員にはその制約を尊重し擁護する義務がある(99条)。もちろん税財政権の行使においても、この制約が貫徹されなければならない。
中華人民共和国の成立、朝鮮戦争など、東アジアにおける冷戦体制の形成とともに、税財政を含む統治の現実は、脱軍事化という理念から後退していった。そしていま、東アジアは、世界で最も熾烈な軍拡競争が展開している地域の一つである。私たちの課題は、そういう現実を矯正し、平和・非核の東アジアを実現することである。そのためには、9条平和主義が税財政権に対して何を求めたのかを知る必要がある。
このように戦争と税財政の緊密な関係を意識するとき、軍事の面から進行する「戦争をする国づくり」だけでなく、税財政の面から進行する「戦争をする国づくり」も克服しなければならないことがわかる。だから税財政(経済)と戦争を峻別して、前者を相対的に放免する思考枠組――その例が〈経済をつかった軍事的優位〉と〈軍事をつかった経済的権益〉の二本柱を追求する経済安全保障論であり、それを法制化した経済安保法体制である――も再考を迫られる。