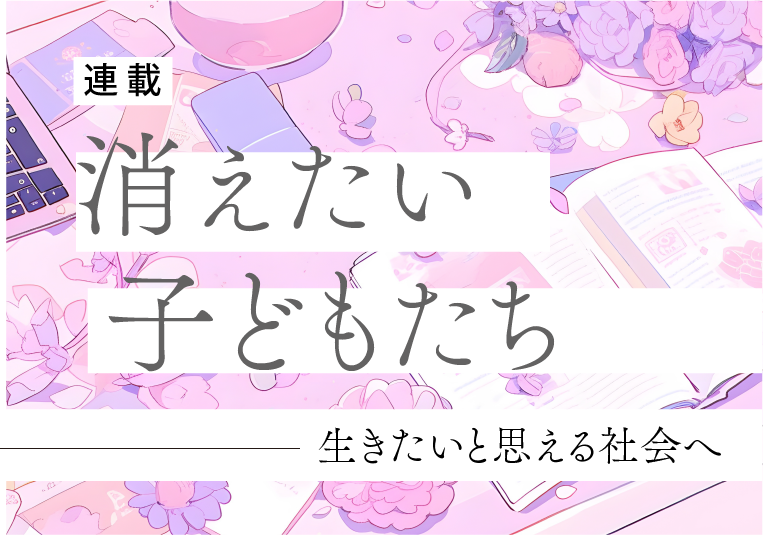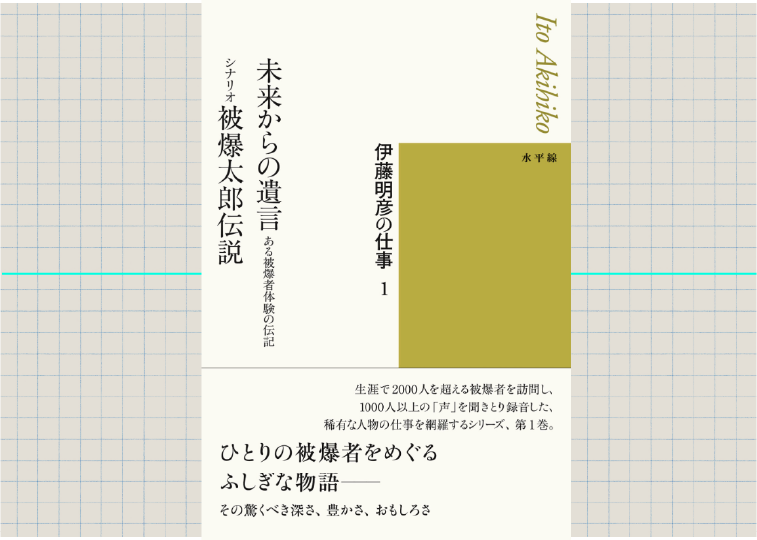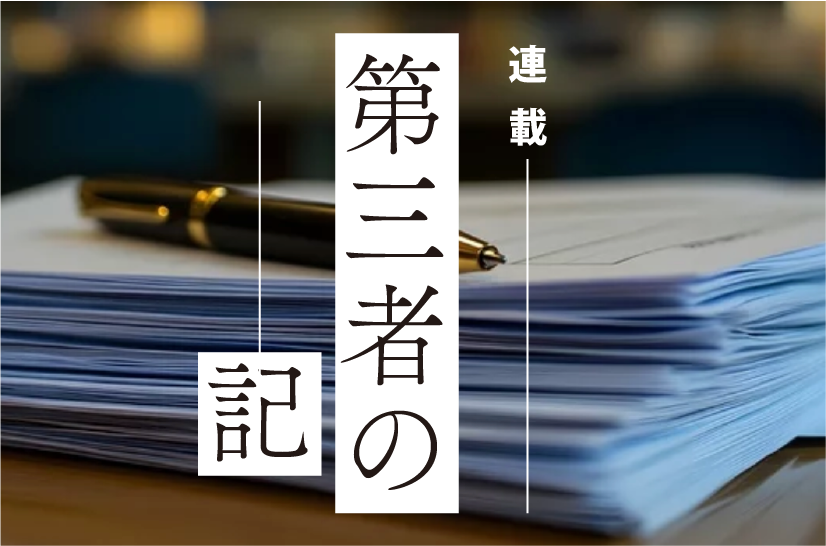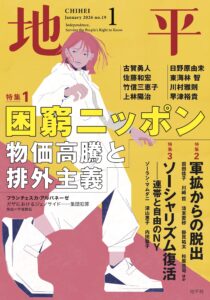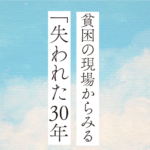これまでの記事はこちら(ルポ 消えたい子どもたち)
2025年3月7日、愛知・名古屋高等裁判所は、現行の結婚制度が同性婚を認めていないことは合憲か違憲かを争う、いわゆる同性婚訴訟で、法律婚制度を利用できないのは性的指向による法的な差別で、民法と戸籍法の規定は憲法違反だとの判決を示した。2019年から始まった一連の裁判は、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の全国5カ所で提起、高裁での判決は4件すべて憲法違反となった。
「同性婚は、当然の権利です。同性婚する、しないが選べる法制度をきちんとつくって、LGBTQ(性的少数者)の人権を守ってほしいと思っています」
そう話すのは、渋谷区議会議員のやがさきさやかさん(38歳、矢ヶ崎清花)だ。自らがLGBTQ当事者であることを公言し、2023年の渋谷区議選で当選した。
街宣で当事者だと告げると、「気持ち悪いんだよ」と心ない野次が飛び、アンチがいるのを肌で感じた。当事者どうしでも、考えの差で偏りが生じ、連帯できない一抹の寂しさもあった。日本でいち早く2015年に、パートナーシップ制度(同性カップルが法律婚と同程度の実質を備えた関係であることを証明する制度)を導入した渋谷区なのに、である。
「さまざまな考えの人がいるのはわかっているので、カミングアウト(性的指向や性自認などの自分の秘密を打明けること)は不安でした。しかしそれも私のアイデンティティです。LGBTQの人々はカミングアウトの難しさを抱え、さらに日常的なストレスにもさらされている。だからこそ私がカミングアウトすることで、そうした生きづらさを抱える人たちの後押しをしたいと考えました」
各種調査によるとLGBTQの人は、日本の人口の約3~10%を占めているとされながら、自分の性自認や性的指向を家族、なかでももっとも理解してほしい相手である自分の親に対してカミングアウトできないでいるという。
「性転換手術を海外で済ませてきたことを両親に告げると、母には号泣され、父は怒ったあと押し黙ったままでした。結婚予定もあり後戻りはできず、トランスジェンダー当事者でも受け入れてくれる企業に転職し、公言できたことで気持ちが楽になりました」(35歳、IT企業勤務のAさん)
しかし、比較的順調に進んだAさんのようなケースばかりではない。認定NPO法人ReBitが実施したアンケート調査「LGBTQ子ども・若者調査2022」によれば、10代のLGBTQの91.6%が保護者にセクシュアリティに関して安心して話せない状況だと回答している。
また過去1年に48.1%が自殺念慮、14.0%が自殺未遂、38.1%が自傷行為を経験したという。日本財団の「第4回自殺意識調査」(2021年)と比較すると自殺念慮はおよそ3.8倍、自殺未遂は4.1倍になっている。孤独感が「しばしばある・常にある」とした10代は内閣府の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」(2022年)より8.6倍高い状況にある。さらに、就職・転職でハラスメントを体験したのはLGB等の35.7%、トランスジェンダーの75.6%に。性的マイノリティというだけでハラスメントの被害に遭いやすく、生活困窮にもつながっている実態を見ると、生きづらさは深刻だ。