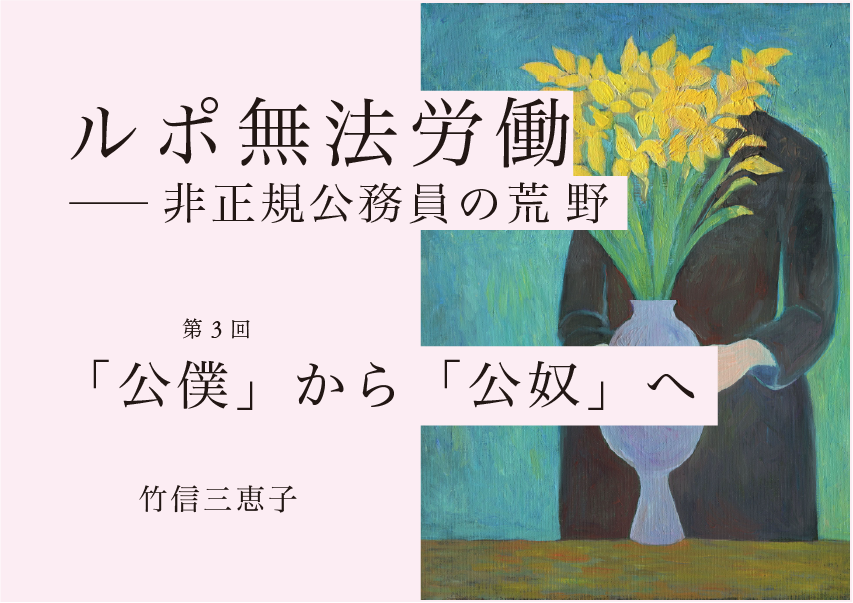【連載第1回】歌舞伎町で。(1)差別と排除のなかで置き去りにされる少女たち
【連載第2回】歌舞伎町で。(2)「少女を守る」と胸を張るおじさんたちが守りたいもの
「家にいられないとき、声をかけてくるのは体目的の男の人だけだった。そういう人しか自分に関心を持たないと思っていたし、頼れるのはそういう人だけだった」。そう話したのは、中学2年生の少女だ。
また別の17歳の少女は、「まわりの大人に助けを求めても、誰も助けてくれないし、知らない男の人に声をかけられて、嘘でも同情してもらえるほうが気持ちが楽になるから。知らない人について行って、殺されるかもしれないけど、他に行けるところがなかった」と、泣きながら話した。
彼女たちは家で虐待され、学校や児童相談所、警察などに助けを求めたものの、家に戻される経験を繰り返し、大人を頼ることを諦めた先で、「泊めてあげる」と声をかけてきた男たちに性を買われ、性搾取の被害に遭っていた。
家族神話――価値観の押し付け
日本では、家族は一緒にいることが幸せであるとか、それが本来の形であるといった価値観が福祉の分野にも浸透している。児童相談所でも職員が、保護された子どもをいかに「家庭復帰」させるかに重きを置いて対応したり、「家族は一緒にいたほうがいいと思う」「あなたのためだ」と子どもを説得しようとしたりすることがよくある。
家に帰りたくないと訴える子どもに対して、その背景にある問題に介入して状況を改善させたり、家以外の場所で生活できるように選択肢を用意したりすることもなく、「家に帰らなかったら、どうやって生活していくつもりなの?」と子どもに責任を押し付けるように話をし、諦めさせようとする場面を目撃したことも何度もある。もちろん、私たちColaboは、そのような対応を目にしたときには、その場ですぐ抗議し、対応と方針を改めるよう申し入れる。すると、「家族を壊すようなことはしてはいけない」と言われたことがある。この社会には、親子は一緒にいるほうが幸せだろうと思い込んでいる人が多くいる。