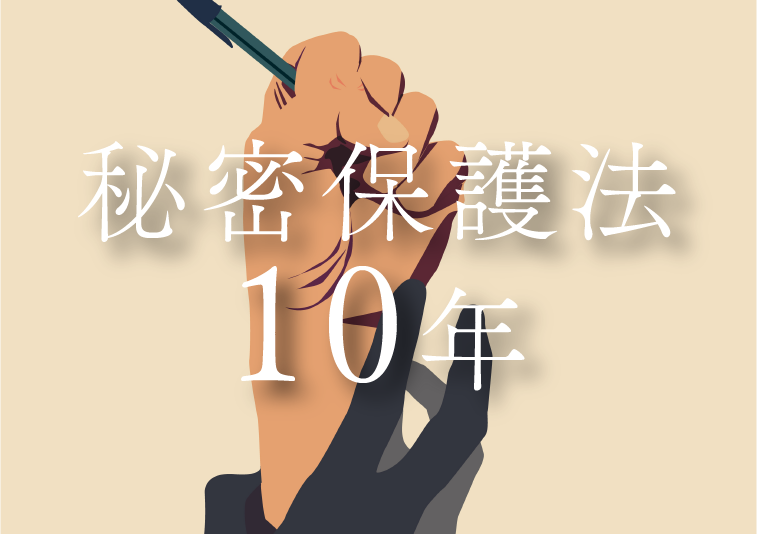秘密保護法の施行から10年の節目を迎え、秘密保護法が実際にどう運用されているのかを検証したい。
秘密保護法は、①国の安全保障に関する情報について、「特定秘密」に指定すること、②特定秘密を取り扱う者を制限するために、「適性評価制度」を導入すること、③特定秘密を漏えいした者や特定秘密を取得した者を、厳しく処罰することという3本柱によって構成されている。そこで、この3本柱に沿って、運用の実態を見ていく。
特定秘密の指定
秘密保護法は、行政機関の長は、①防衛、②外交、③特定有害活動の防止、④テロリズムの防止という、4分野に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを「特定秘密」として指定すると定めている。
なお、秘密保護法案の審議段階で、このテロリズムを含め、定義が恣意的に拡大解釈されるおそれが指摘されていたなか、石破茂・自民党幹事長(当時)は、ブログで、秘密保護法案に反対する市民団体らのデモについて「単なる絶叫戦術は、テロ行為とその本質においてあまり変わらない」と書いて、批判を呼んだ。本年、石破茂氏は首相となったが、この発言は忘れてはならないだろう。
秘密保護法では、特定秘密の指定・解除と適性評価の実施についての運用基準が定められている。
この運用基準では、特定秘密の指定の要件は、特定秘密保護法の「別表」に掲げる事項に関する情報であること(別表該当性)、公になっていない情報であること(非公知性)、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要である情報であること(特段の秘匿の必要性)の3つであることが確認されている。
運用基準の策定に際してのパブコメを経て、特に遵守すべき事項の中に、「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の事実を指定し、又はその隠蔽を目的として、指定してはならないこと」と追加されたことが重要である。
■年次報告書を読み解く
秘密保護法の運用は、基本的に秘密のベールに包まれているが、以下の年次報告書を読み解くことで、運用の実態を垣間見ることができる。
まず、政府の年次報告書(以下、「政府報告書」という)であり、特定秘密の指定・解除および適性評価の実施の状況について、国会に報告するものである。次に、内閣府独立公文書管理監の年次報告書(以下、「独立公文書管理監報告書」という)であり、特定秘密の指定・解除および特定行政文書ファイル等の管理の適正を確保するため独立公文書管理監および行政機関の長がとった措置の概要を、内閣総理大臣に報告するものである。そして、衆参それぞれに設置された情報監視審査会の年次報告書(以下、「衆院審査会報告書」、「参院審査会報告書」という)があり、調査・審査の経過および結果を記載した報告書である。