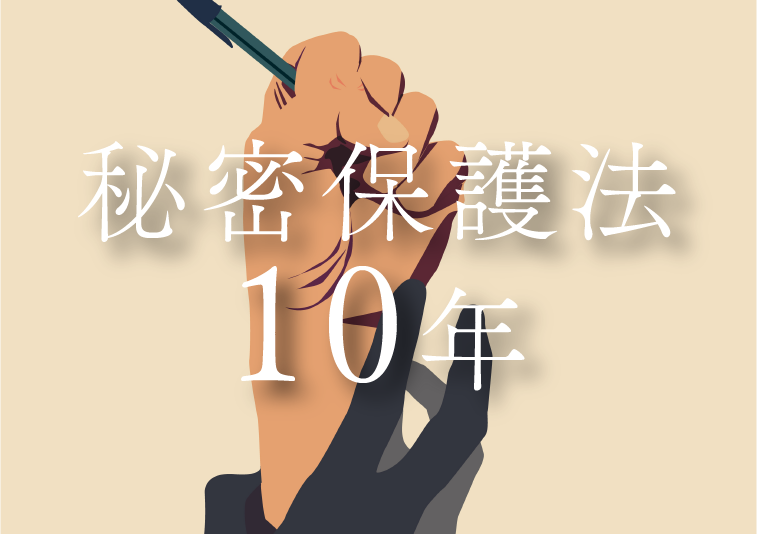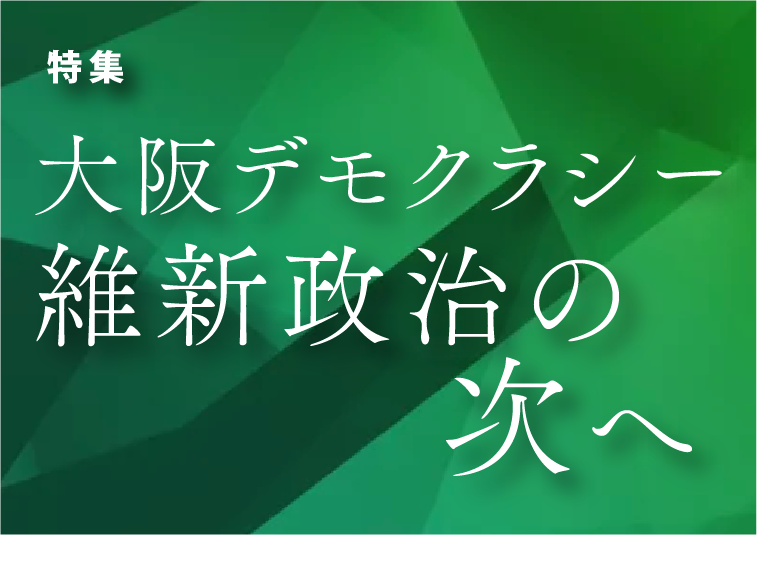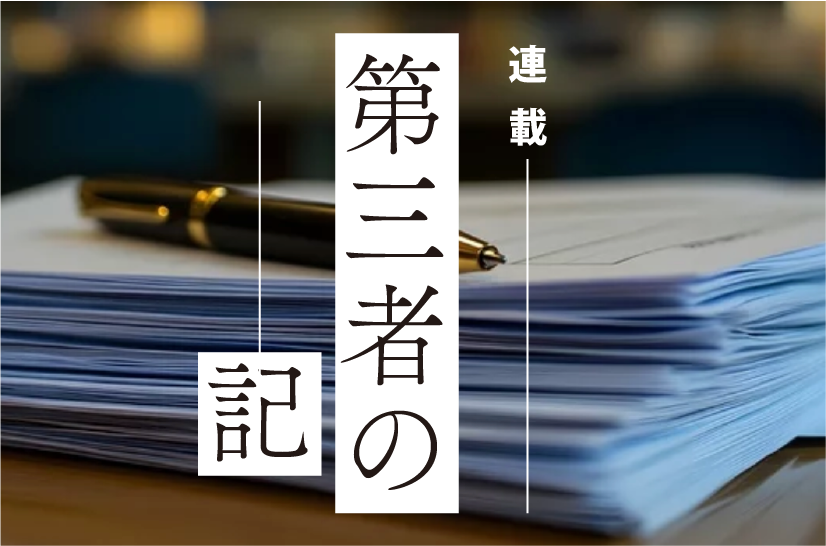防衛省取材30年
――2014年12月に特定秘密保護法が施行されてから10年が経過しました。その前年、安倍政権が法案を国会にかけた際には大きな反対運動が起き、多くの問題点が指摘されました。施行から10年、私たちの知る権利にどのような影響が出ているのか、実際の運用がどうなっているのか、検証したいと思います。石井暁さんは共同通信の防衛省担当記者として、長きにわたって防衛省・自衛隊をめぐる取材を続け、数多くのスクープ記事を出してきました。そのスクープには防衛機密・特定秘密に関わる内容が少なくありません。まず、自己紹介も兼ねて防衛省取材をされてきた経過をお聞かせください。(聞き手:熊谷伸一郎)
石井 1985年に共同通信に入社したので、新聞記者になって今年〔2024年〕でちょうど40年が経つことになります。1994年から、防衛省の――当時は防衛庁でしたが――担当になりました。それ以来30年間、防衛省・自衛隊の取材をしてきたことになります。
高校や大学の時代から憲法問題、とくに第9条については関心があり、自衛隊について本を読んだり、友人らと議論をしたりしていました。記者になってからも、防衛省の担当になりたいと自ら希望して担当になりました。
――30年、ある特定の省庁を担当して取材しつづけるというのは、非常に珍しいのではないでしょうか。
石井 あまり例はないかもしれませんね。共同通信の中でも、例えば厚生労働省や財務省の担当だけ30年、という記者はいません。編集委員として特定の分野について専門的に取材を深めて、連載記事などを書いていく記者はいますが、担当として現場での取材を長期間にわたって続けるケースは、あまりないと思います。レアケースではありますが、防衛省や自衛隊にこだわって取材していきたいということは会社に訴えてきました。
日米共同作戦計画案をスクープ
――石井さんは独自取材で数多くのスクープを出してきたわけですが、近年では、自衛隊と米軍が「台湾有事」を想定して共同作戦計画を作成していることを記事にしています。
石井 「台湾有事」の際、沖縄や鹿児島の南西諸島に米軍が臨時拠点を設けることを日米共同作戦計画の原案に盛り込んだという記事ですね。2021年12月24日、クリスマスイブの各紙朝刊に掲載されました。特に沖縄の地方紙2紙、鹿児島の南日本新聞には1面トップで掲載され、大きな反響がありました。
この計画の中には、「有事」の初動段階で、アメリカの海兵隊が南西諸島に分散して臨時の軍事拠点を置き、そこに対艦、対空ミサイル部隊を展開して、洋上の中国軍艦艇、航空機の排除にあたる、といったことが記されています。そして自衛隊は米軍の後方支援に当たることになっています。
この計画内容によれば、当然、それらの島の地域住民が巻き込まれる危険性はとても高いわけです。南西諸島には約200の島があるとされていますが、その中で米軍の臨時拠点とされる可能性があるのは、水道のある40の島とされています。基本的に、米軍と自衛隊は軍事組織なので、それらの拠点とされる島に住民が住んでいる、生活しているということはまったく眼中にありません。
住民にとってみれば自分たちの生命と生活に関わる重大な問題ですから、自衛隊がどのような計画を持っているのか、それがたとえ軍事的な秘密であるとしても、住民や自治体には当然、知る権利があります。
沖縄県や鹿児島県などは記事にすぐ反応し、特に沖縄県の玉城デニー知事は政府と防衛省に説明を求めるというコメントを出しました。県民の間でも、これは自分たちにとって大問題だということで「ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会」という市民団体が結成され、幅広い人たちが参加して今も活発に活動しています。
特定秘密と「知る権利」
――こうした内容は、政府・防衛省にとっては表に出したくない性質のものと思います。それでも報道していく意味はどういった点にあるのでしょうか。