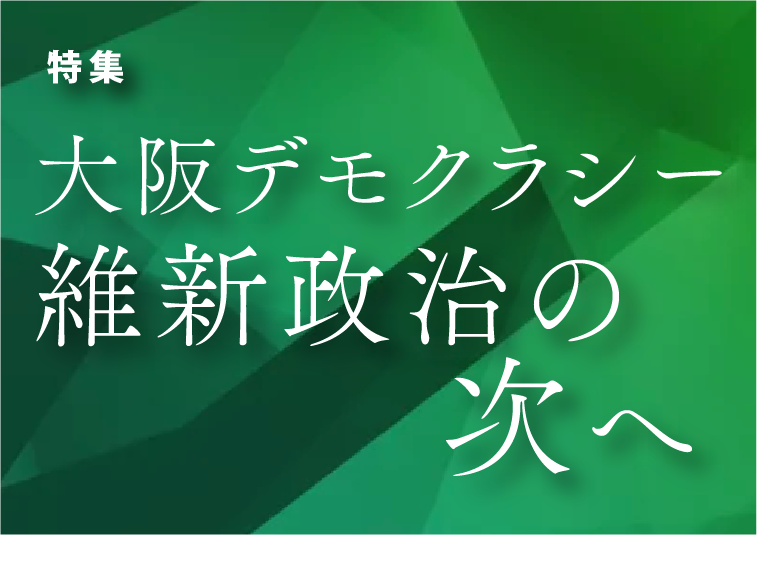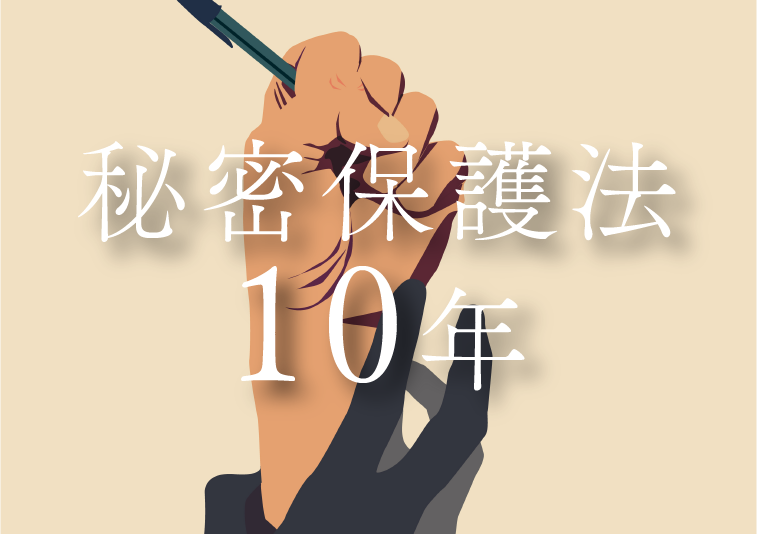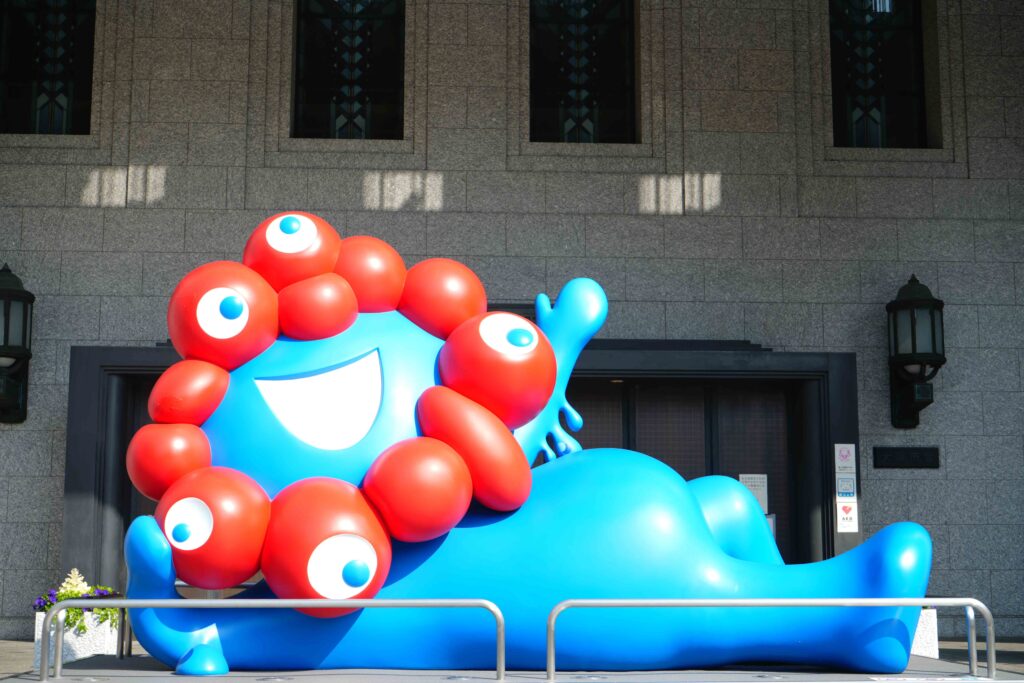特集「大阪デモクラシー 維新政治の先へ」
維新の退潮と私たちの停滞
過日の総選挙での日本維新の会(以下、大阪維新の会を含めて維新と略す)に対する評価は、当初、全国的には微減に終わったが、拠点の大阪では19小選挙区を独占する底力を示した、というものだった。しかし、徐々に近畿や大阪においても退潮が顕著であったとの評価が広まってきた。維新の比例票は近畿において約110万票減少しており、獲得議席も10議席から7議席へと減らしている。大阪においても約56万票減らした。
もっとも、自民党も逆風の中、大阪で比例票を20万票弱減らし、立憲民主党の比例票は微増にとどまった。維新が議席数、得票数において他の政党を凌駕していることは揺らいでいない。大阪の比例票の得票比率で見れば、維新は前回の42.5%から30.7%に落としたが、これを埋めたのは国民民主党、参政党、保守党などである。
一方で、13年に及ぶ維新政治に対抗してきた大阪の社会運動は、いまだ維新政治に代わる新しい運動を創出できていない。総選挙における維新の退潮は、維新政治に代わる新しい運動の台頭によるものとは言えない。
しかし、運動は選挙だけではない。もちろん民主主義社会において選挙結果がもたらす影響は極めて大きい。それだけに社会を変えたいと願うものは選挙に注目し、注力する。最後は選挙に勝たなければならない。
しかし、選挙がすべてではない。選挙に勝った者がトップダウンで強権を行使できるというのは、健全な民主主義とは言えない。参政権は選挙権に限定されるものではない。住民参加、市民協働、当事者の参加・参画なども大切な参政権であり、それは「既得権益」と排除されてよいものではない。本稿では、できる限り自治の現場に寄り添って維新政治の次に来る大阪の民主主義について考えてみたい。
「財政ポピュリズム」が破壊したもの
維新政治を「財政ポピュリズム」という視点から分析することを、桃山学院大学の吉弘憲介教授が提起している(1)。いわゆる既得権益層に投入されていた財源を引きはがし、頭割りの普遍主義にもとづく給付に転換するのがそのポイントである。
橋下徹市長時代の大阪市財政をもっとも特徴づけるのは、人件費の大幅削減と公債費(借金の返済)の急増だという。新たな給付は所得制限を設けないものを優先した。こうした維新政策が支持されたわけだが、吉弘教授の分析が興味深いのは、この政策が支持されたのと同じ理屈で、維新が掲げる政策、すなわち都構想や万博、IRなどが支持されない、との指摘だ。