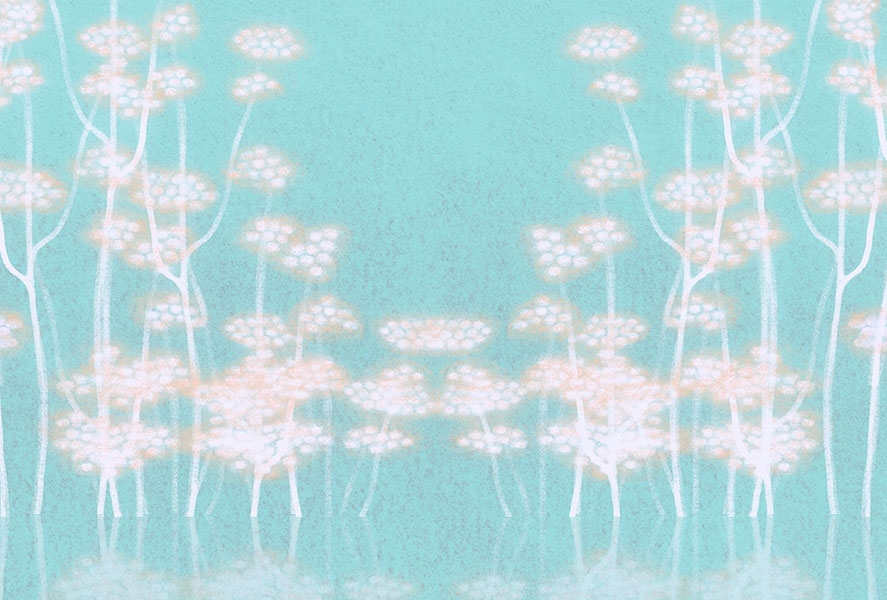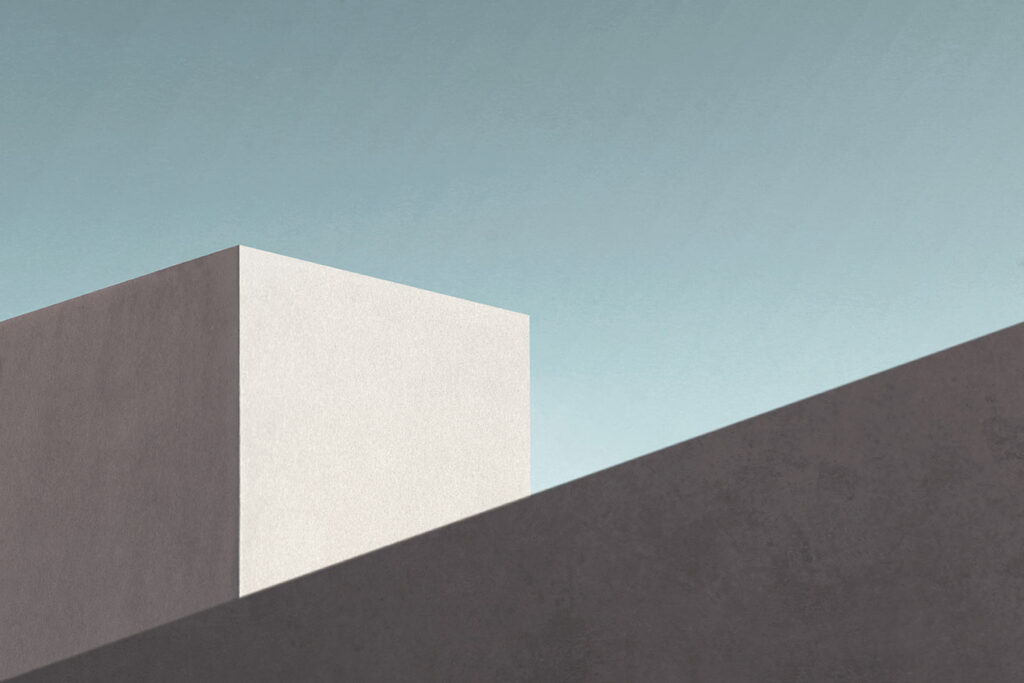入管施設に1300日以上収容された2人の外国人男性が、日本の入管収容制度と入管法は恣意的な(思うがままの)拘禁を禁じた国際法(「自由権規約」)に違反するとして国を訴えた裁判は、東京高裁に舞台が移った。経過は、本誌の「入管と国際法(上)法廷からの報告」(2024年11月号)、「入管と国際法(下)原告本人尋問──収容はどれほど人を傷つけるか」(2025年1月号)を参照してほしい。
今年6月の東京地裁判決(本多智子裁判長)は、原告2人の収容の一部について「自由権規約」の判断基準を適用して違法と認め損害賠償を命じたものの、入管収容制度と入管法自体が国際法違反の訴えは退けた。原告と国の双方が控訴し、12月に控訴審が始まる。何が問われているのか。
「自分たちのための裁判ではない」
6月17日、地裁判決の傍聴は抽選となり、関心の高さを示した。傍聴券の当選を確認し法廷に向かう。原告と弁護団の表情がうかがえる、やや前寄りの席に座った。
「主文、被告は原告に対し……60万円……支払え」
損害賠償を認めている。原告が勝ったと言えるのか。
「入管法52条等は『自由権規約』9条1項、4項に違反しない」
いや、原告側の大事な主張が退けられている。ならば、どういう理屈で損害賠償を認めたのか。法廷で聞いただけでは整理がつかず、報告会へと急いだ。
「残念ながら(収容の)違法性を認めていない。心から喜べない、笑えない。いまでも(多くの収容者が)中にいるわけだから、同じ繰り返しになる。私たちは自分たちのために裁判をしたわけではない」
原告でイラン国籍のサファリ・ディマン・ヘイダーさんが複雑な思いを口にした。表情は終始、晴れなかった。
ハンスト、「2週間仮放免」、うつ病、自殺未遂
原告は2人とも退去強制処分となり、入管施設に収容された経験を持つ。
サファリさんは1991年に来日、祖国で不当に自由を奪われるなど迫害を受けたとして3回、難民申請しているが認められていない。裁判で対象となった入管収容は4回、1357日にのぼった。
もう1人の原告、デニスさんは2007年に来日、トルコ政府による少数民族クルド人への迫害を理由に4回、難民申請しているが認められず、裁判では3回、1384日に及んだ収容が問われた。
かつて入管当局は、外国人が非正規滞在となっても拘束を一時的に解く「仮放免」を弾力的に運用していた。しかし東京五輪を控えた2018年、「送還の見込みが立たない者であっても、収容に耐え難い傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める」とする「仮放免運用方針」を定め収容を強化した。これによって「仮放免」が認められず、長期間にわたって入管施設に収容される人が増えた。「迫害されて命の危険がある母国には帰れない」と難民認定を訴えるサファリさんとデニスさんも収容された。
2019年、先の見えない収容に絶望した人たちが、抗議の意思を示すハンガーストライキを起こし全国に広がる。同年6月には長崎県の大村入国管理センターでナイジェリア人の男性が餓死する事態も起きた。
入管当局はハンストで体調を崩した人を2週間だけ仮放免して、再び収容する対応を始めた。これが多くの人を苦しめ、「水中で溺れている人に一瞬だけ空気を吸わせて、また水に沈ませる」と批判された。
サファリさんは長期収容と「2週間仮放免」の繰り返しで、食べても吐くようになり、頬はこけ、うつ病を発症した。医師は診断書に「繰り返す収容によるストレスが、症状の圧迫に影響している可能性が高い」と記述、デニスさんも複数回、自殺を図るなど心身を害した。