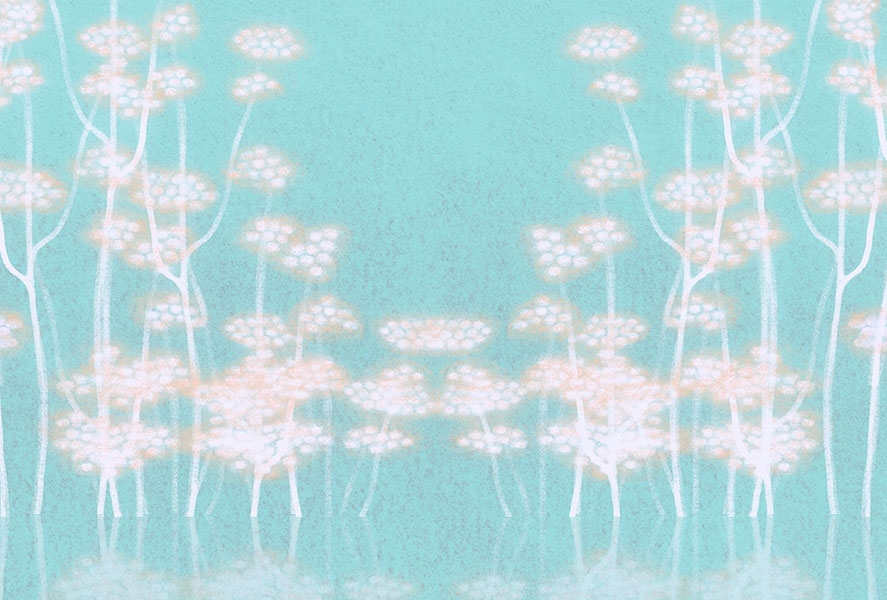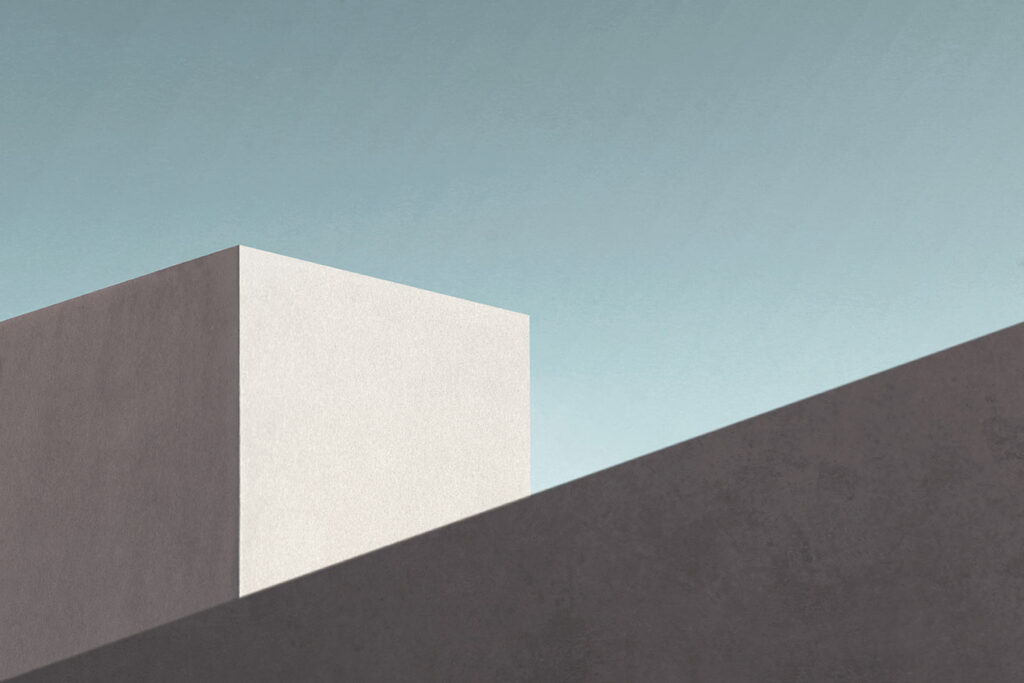昨年の『地平』8月号では、米国の大学に広がるパレスチナ支援運動について報告した(「立ち上がるアメリカの学生たち」)。2023年10月のハマスによる越境攻撃以降、米国では圧倒的なイスラエル支持がつづいた。そんな中で、イスラエルによるパレスチナへの歴史的・構造的差別や搾取、支配の体系に異議を唱え、ガザ戦争を「虐殺」と批判し、パレスチナの自由を早くから訴えたのは、米国の大学生たちだった。彼らは、米国政府に対してイスラエルへの軍事支援の停止を、大学にはイスラエル政府や企業、軍との関係断絶を求めた。
開戦後、イスラエル政府への批判や反戦の声は「反ユダヤ=差別主義」とみなされた。しかし、多くの学生や教員は、逮捕や退学、解雇のリスクを負っても、沈黙を拒んだ。
米国の大学は、ベトナム反戦運動以来とも評される熱気に包まれ、反戦運動のうねりはハーバード大やコロンビア大などから全米各地、世界のキャンパスへ広がった。
一方、立場の弱い留学生や外国人教員の中には、この問題を語ること自体を恐れる人も少なくなかった。外国人教員のひとりである私は、昨年の寄稿でこう記した。「この原稿を書きながら、まったく不安がないといえば噓になる。(中略)しかし、教員の端くれとして、大学とは社会で最も『自由な場所』であるべきだと思う。処罰を恐れず、誰もが言いたいことを言い、異なる意見の人と膝を突き合わせて徹底的に議論する。まして、ガザ侵攻という圧倒的な暴力と不正義に対して何も言えない高等教育など、どんな価値があるのだろうか」。
あれから1年3カ月が過ぎた。「すべてが改善した」と報告できれば、どれほど幸いだろうか。残念ながら、状況は急速に悪化してしまった。
私はワシントンDCやニューヨーク在住の日本人特派員ではない。カリフォルニア州中央部の都市フレズノに住み、地方の公立大学で学生にジャーナリズムを教えつつ、ドキュメンタリー制作や取材をつづけている。周囲には一面の農地が広がり、住民の多くは共和党支持者だ。リベラルの牙城とされるカリフォルニア州の中でも、ここは歴史的に保守的な土地である。
しかし、私が日々接するトランプ支持者たちは、テレビで見かけるような過激な「MAGA(メイク・アメリカ・グレート・アゲインの略)」ばかりではない。ごく普通の家庭の父親、懸命に働く農民、私の学生とその家族でもある。
2018年、第1次トランプ政権時、私はフルブライト奨学金でカリフォルニア大学バークレー校の研究員となり、リベラルの象徴とされる地域・ベイエリアで暮らした。ある日、同僚に「州内でおすすめの街」を尋ねると、「州中央部には行かないほうがいい。Those people(あの人たち=共和党支持者)の地域だから」と言われた。その言葉にむしろ背中を押され、翌年、フレズノへ移り住んだ。「あの人たち」の隣人となり、やがて教師になって見えたのは、トランプ支持者たち、生活苦を抱えた移民、非正規移民の子どもたち、将来に不安を抱える若者たち――ベイエリアからは見えなかった米国社会の現実だった。
昨年の大統領選挙では、フレズノを含む州中央部の多くがトランプ氏を支持した。民主党の票田とされるカリフォルニアも一枚岩ではない。州全体ではハリス氏が20ポイント差で大勝したものの、選挙結果を赤(共和党)青(民主党)で色分けした地図を見てみると、青に染まったのはサンフランシスコやロサンゼルスなどの大都市がある太平洋沿岸で、州中央部は赤に染まった。
同様の傾向は全米各地でも見られる。都市と地方。学歴と所得。ブルーカラーとホワイトカラー。社会構造の分断は、支持政党と直接的に結びついていた。
米国の「地方」に積もりつづけてきた静かな怒りや絶望、アカデミアやエリート層への不満が、深刻なインフレを受けて爆発し、トランプ再選を可能としたように私は思う。噓と扇動とヘイトを撒き散らすデマゴーグの再選を許したのは、果たして「あの人たち」だけなのか。分断を生み出した責任の一端は、むしろ「あの人たち」と嘲笑い、地方を蔑んできた側にもあるのではないか。そう感じている。
大学という知の現場で今、何が起きているのか。カリフォルニアの片隅で、教室という小さな窓から見つめてきたトランプ第2次政権発足からの一年を時系列で振り返っていきたい。
アカデミアへの攻撃と自己規制
今年1月20日、トランプ氏が再び大統領に就任。この日、議会承認を経ない「大統領令」を立てつづけに発令した。内容は、米墨国境の国家非常事態宣言、難民受け入れの一時停止、連邦職員の原則フル出勤を指示する覚書、世界保健機関(WHO)とパリ協定からの離脱手続き開始、連邦政府として性別を男女二性に限定する方針など多岐にわたった。その数は計26件。就任初日からこれほど多くの大統領令が発令されたケースはなかった。