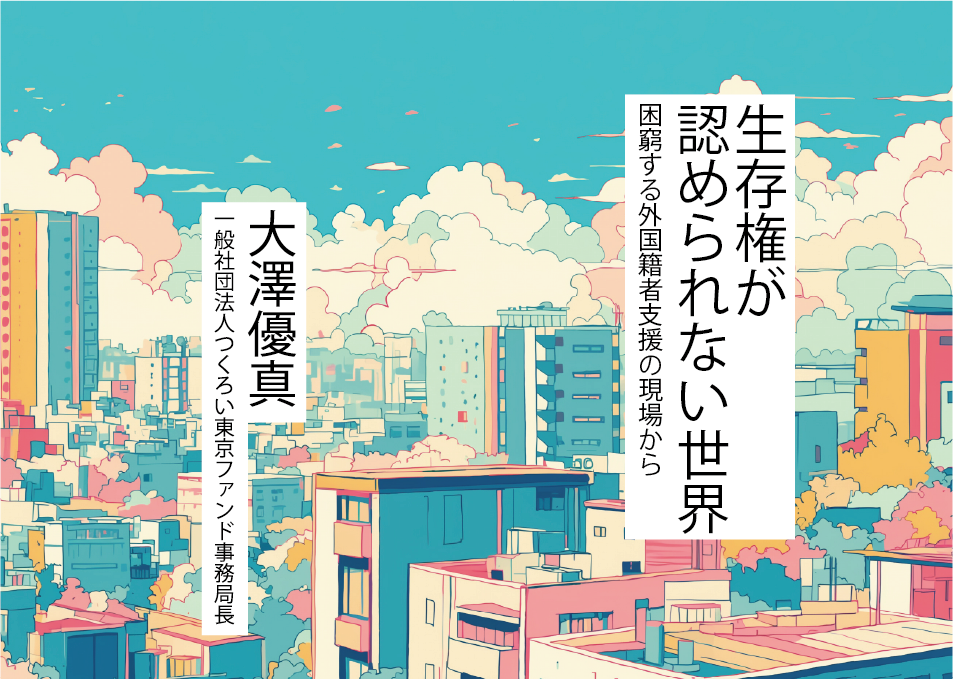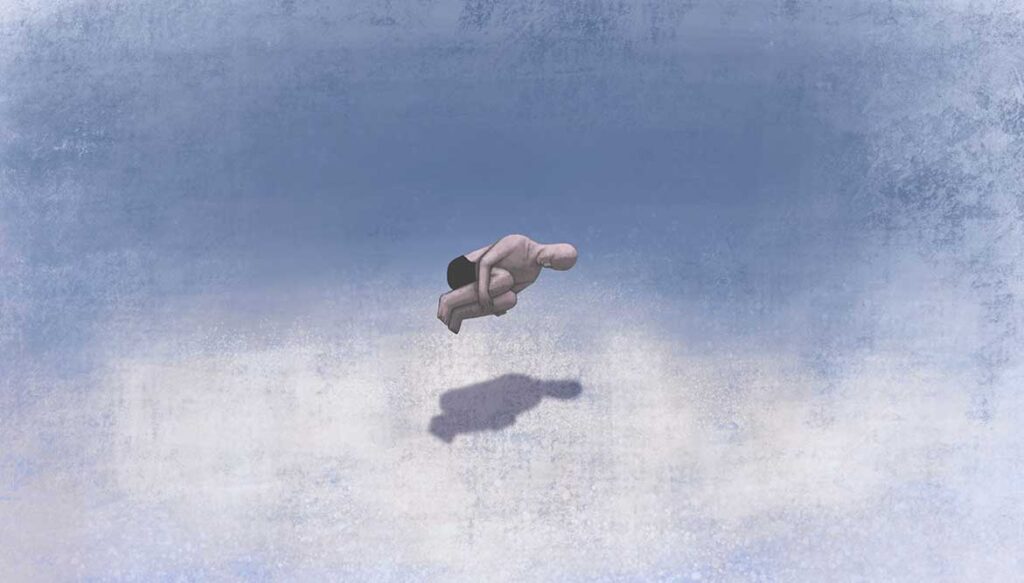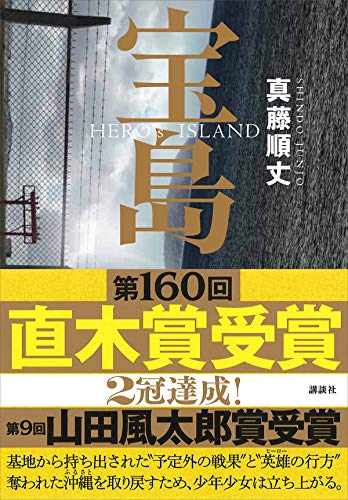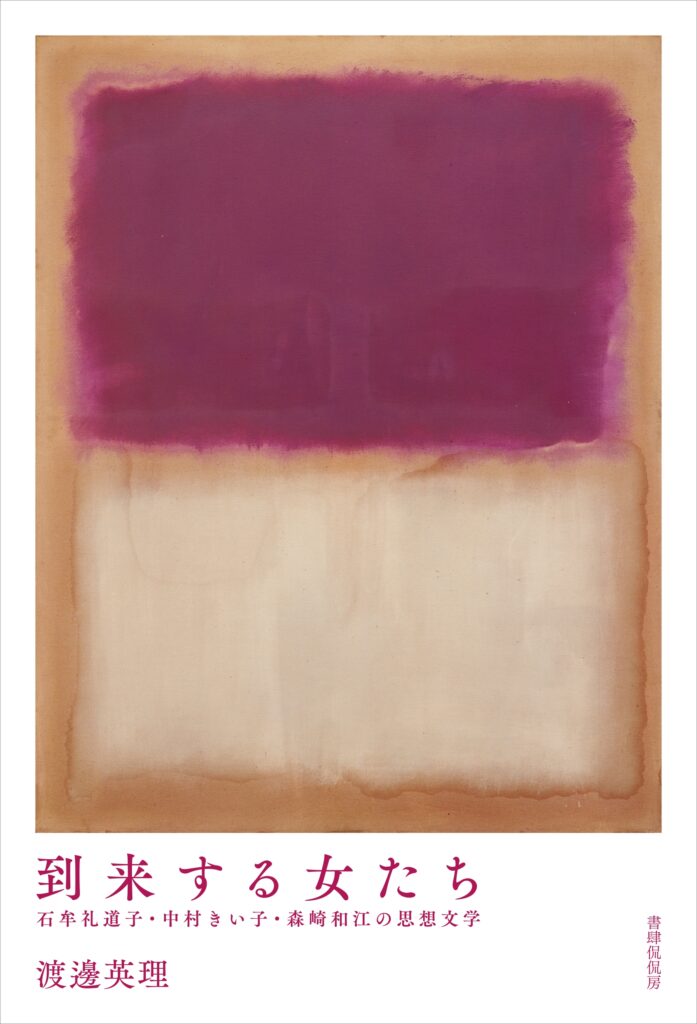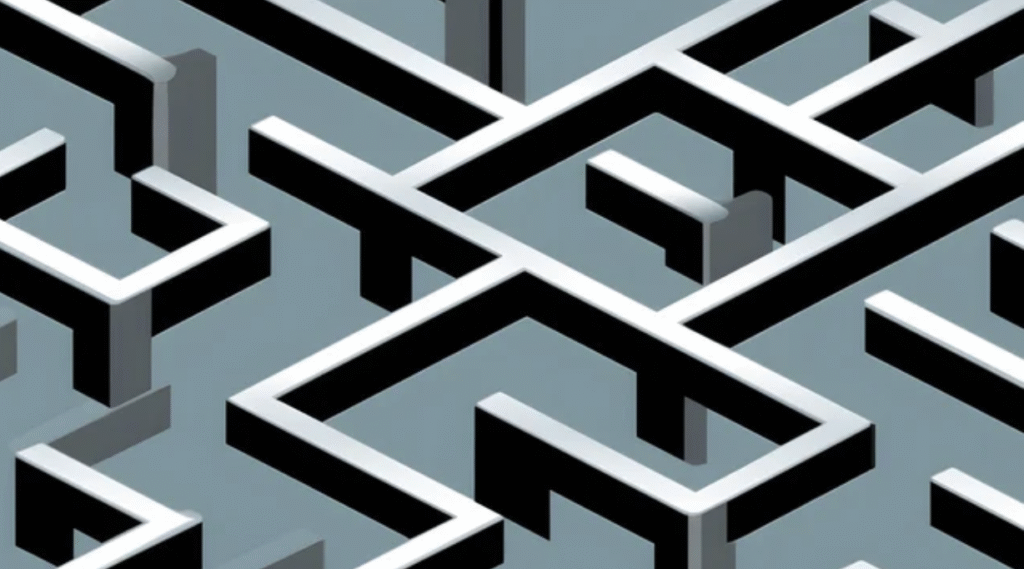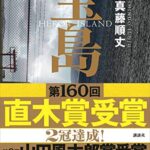【関連】特集:隣人である移民(2025年11月号)
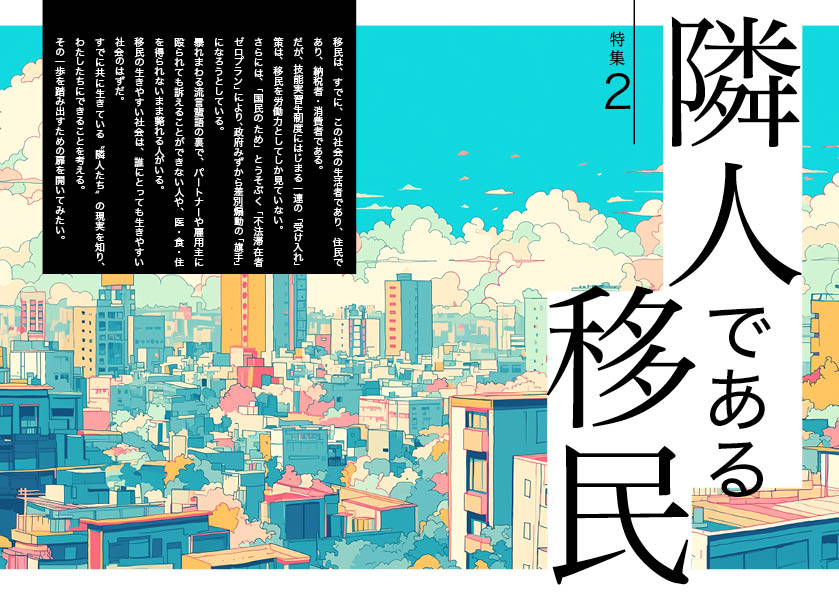
はじめに――「移民・外国人問題」の政治化
今年7月の参議院議員選挙において、「日本人ファースト」を掲げた参政党によるアジェンダ設定をきっかけとして、「移民・外国人問題」がにわかに政治化している。そのなかで、数年前から顕著になっていたクルド人にたいする排外主義や、医療・社会保障や税制度における「外国人ただ乗り」言説も勢いづいているようにみえる。また、8月末に公表された、法務大臣の私的懇談会報告書「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理~活力ある強い日本の実現/国民の安全・安心の死守~」が、選挙での外国人問題の争点化を受けて、「『政府方針』に近い文書に変わっていった」と報道されているように(注1)、「移民・外国人問題」の政治化は今後、政策形成にも一定の影響を及ぼす可能性がある。
註1 『朝日新聞』(2025年8月30日)。
たしかに、日本に暮らす移民(外国籍者)の数は増加し、2024年末には約377万人、人口の3.0%と過去最高となった(出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。統計はないものの、日本籍をもつ移民ルーツの人も加えれば、さらに数は多くなる。欧米の移民受け入れ国と比較すると、人口に占める移民の割合は低いが、2022年以降、前年より30万人以上の増加が続いているため、肌感覚で移民の増加を実感する機会も増えているかもしれない。くわえて、「移民・外国人」への不満を表明する議論では、しばしば――意図的かどうかわからないが――日本に暮らす移民と、外国人観光客が混同されている。その外国人観光客の増加はより顕著であり、2024年に3687万人に達した(日本政府観光局「訪日外客統計」)。
高齢化や少子化、人びとの生活スタイルの変容などの背景を考えると、今後も移民の数は増加するだろう。とするならば、移民の人たちとともにこの社会を形成していくという視点が不可欠だが、そのためにもかれらの社会統合を支えることが必要である。しかし現実には、その統合を阻むさまざまな障壁が存在する。本稿では、日本に暮らす移民の社会統合についての議論と現状を確認しつつ、特に近年の移民が直面している障壁について論じたい。
1.日本に暮らす移民の人たち
前述のように、昨年末には日本に暮らす外国籍人口は過去最高になった。国籍別でみると、最も多いのが中国籍者の約87万人で、ベトナム63万人、韓国41万人、フィリピン34万人と続く。まだ全体の人数は多くないが、コロナ明けからは、ミャンマー、インドネシア、ネパール籍者の増加幅が大きくなっている。
本稿で論じるように、日本における移民の生活は、かれらの法的地位である在留資格によっても大きく規定されている。そのため在留資格別の割合も確認しておこう。最も多いのが「永住者」で92万人、その後、「技能実習」46万人、「技術・人文知識・国際業務(以下、「技人国」)」42万人、「留学」40万人、「家族滞在」31万人、「特定技能」28万人と続く。
近年の日本の移民の特徴として、日本人との家族的つながりで定住する移民よりも、労働や就学目的で滞在する移民が増加していることがある。この点は在留資格の変化にも表れている。日本の在留資格は30種類あり、「身分に基づく在留資格」と「活動に基づく在留資格」の2種類に大きく区分される。「身分に基づく在留資格」には、「特別永住資格」「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の5つがあり、前二者を除けば、原則として日本人もしくは永住者との家族関係によって与えられる在留資格である。なおこれら5つの資格保持者は、就労などに制限がない。一方、「活動に基づく在留資格」は、日本での仕事や就学と紐づいた在留資格である。
註2 特別永住資格は、厳密には在留資格ではないが、本稿ではそれを「身分に基づく在留資格」に含めている。
このうち近年増加の幅が著しいのが「活動に基づく在留資格」保持者の割合で、2012年には外国籍人口全体の33.3%だったが、2024年には57.0%にまで増加した(図1参照)。この背景には、日系人や日本人との結婚移民など、1980年代から2000年代半ばにかけて移民人口の一定の割合を占めていた日本人との家族的つながりをもつ移民の数が停滞する一方で、日本の移民労働者の受け入れが徐々に緩和されてきたことがある。そこで次節で、移民労働者受け入れ政策の流れについて確認しておこう。