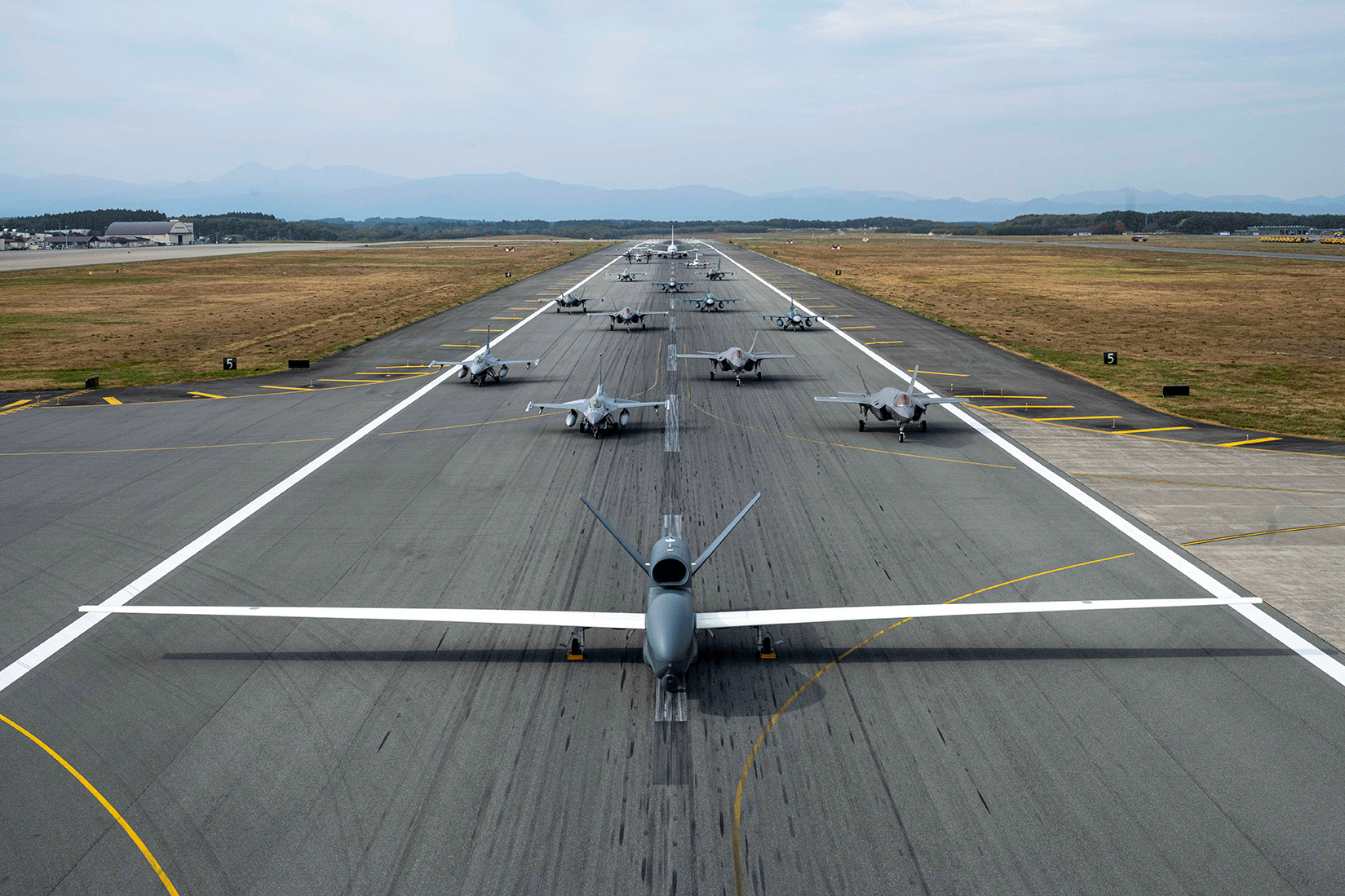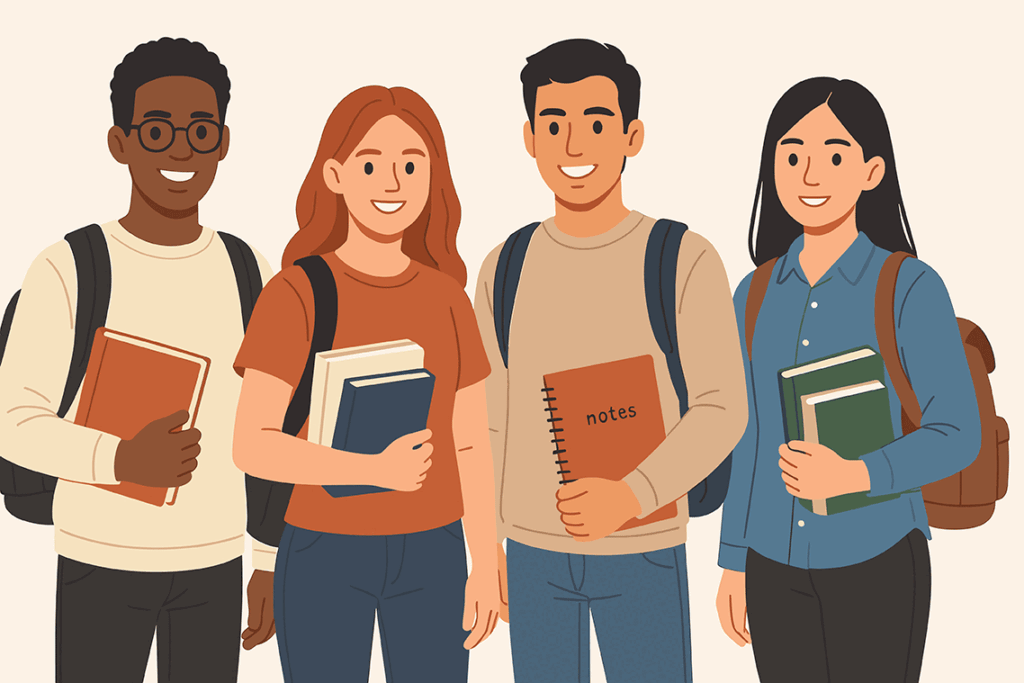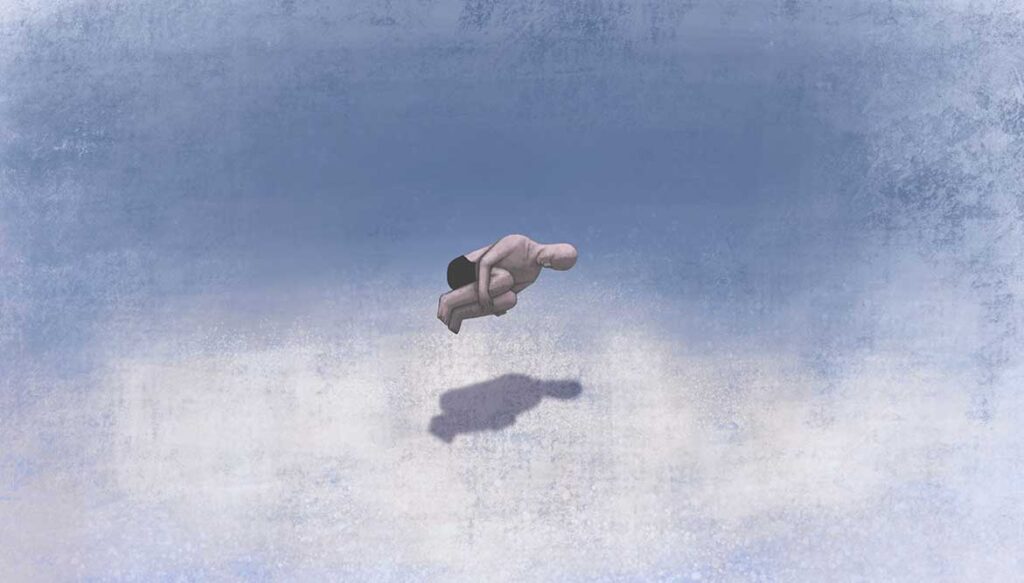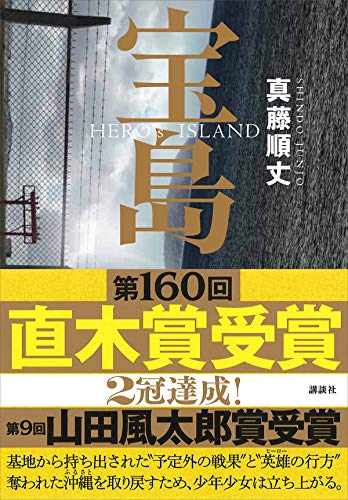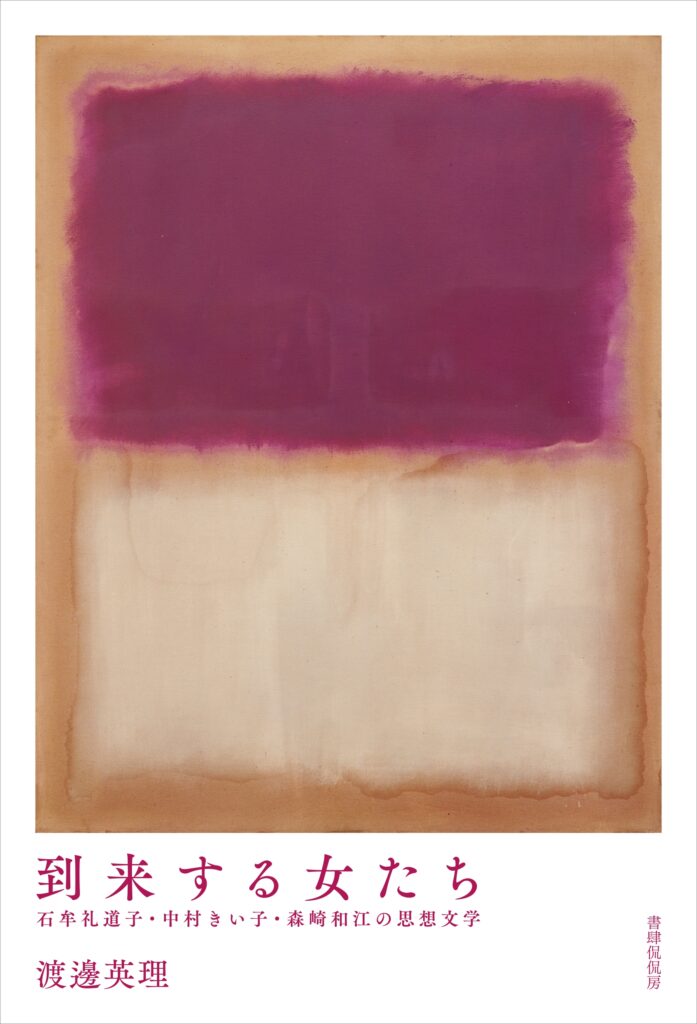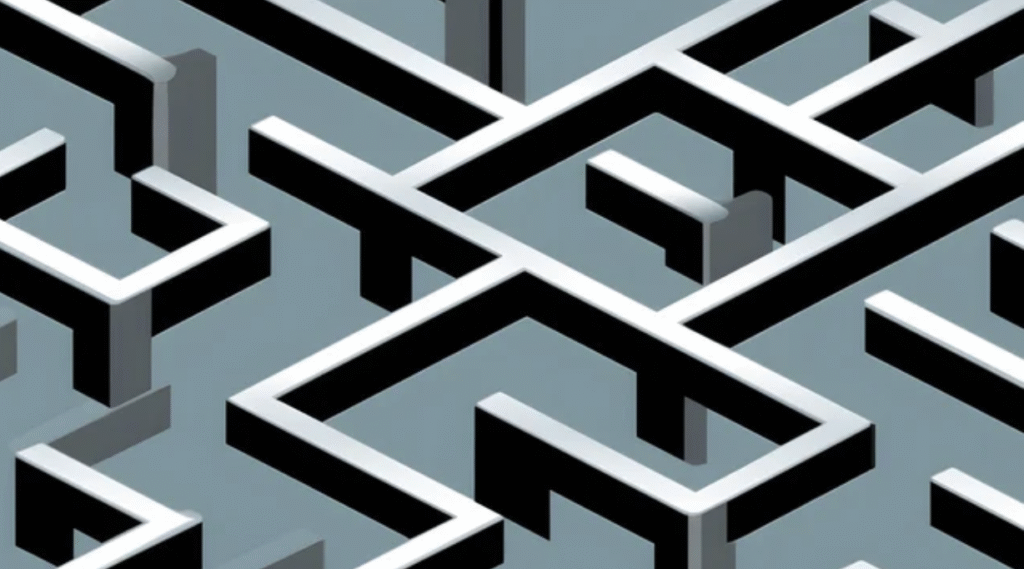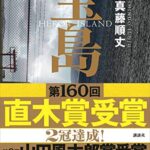【関連】安保五条と憲法九条――未完の安保法制と改憲(古関彰一 獨協大学名誉教授)
【関連】特集:安保法制10年
日米の「口約束」は「当たり前」
トランプ大統領の相互関税問題が今年4月初めに出された時点で、石破首相は「日本は特別扱い」と、極めて楽観的であった。多くの国民もこの首相発言に、日頃聴き慣れた「日米同盟の固い絆」が脳裏をかすめたに違いない。ところが早くも4月末には雲行きが怪しくなってきた。米国側から「特別扱いはできない」と言われてしまったのだ。
その後、日米合意が成立したと報じられた。交渉を担当した赤沢大臣からは、合意は文書ではなく「口約束」であったと伝えられた。その「口約束」の合意内容は、しかし、トランプが7月31日に署名した大統領命令にも、8月6日付の米連邦官報にも盛り込まれていなかった。その後、米国側は「口約束」を撤回し、最終合意に至る9月9日まで10回の会合が持たれた。結果的に5カ月近い「マラソン交渉」になった。
そして、合意成立は同時に首相の辞任表明となったが、4月はじめの首相の「日本は特別扱い」との落差の大きさに戸惑いを感じた読者も多かったに違いない。
当然ながら、EUなどは当初から合意文書を取り交わしていた。今回の関税問題は、諸外国と同時に起きた問題であったため、これまでの日米両政府だけの「安保協議」のような議事録非公表で秘密同然の協議とは違っていたため、他の諸外国と比較可能となり、違う意味での日本の「特別扱い」が露呈してしまった、ということではないか。
本稿の「日米同盟」が誕生した経緯と手続きを振り返ると、私たちが政府から知らされず、メディアも報じないという今回の経過と相似形の構図が浮き彫りになり、「さもありなん」と思えてくるのである。
舞台は「安保共同宣言」
「日米同盟」が、両国の首脳間で明確な形で政治の舞台に登場したのは、1996年の橋本龍太郎首相とクリントン米大統領との間の「日米安全保障共同宣言」(以下、「共同宣言」)であった。
日米両首脳によって発されるのは多くの場合、「声明(コミュニケ)」だが、ここでは「宣言(デクラレーション)」であった。「宣言」といえば、私たちは「ポツダム宣言」を連想する。同宣言によって連合国に敗北を迫られた日本は、昭和天皇が「詔書」を出して敗戦を受け入れたが、詔書は「国の大事」の際に天皇が出す最上位の命令だ。日本国憲法のもとで「詔書」は廃止された。
橋本・クリントン両首脳が「宣言」と銘打ったことは、日米首脳が出してきた従来の「声明」より重要な地位にあるものと見ていいだろう。確かに、内容的に考えても日米安保にとって歴史の画期を示すものであった。
その重要性は、日本政府がこの共同宣言について日米安保条約を「再定義した」ものと説明してきたことにも現れている。現行安保条約の4条は、「日本国の安全又は極東における国際の平和と安全に対する脅威」が生じた際に日米が協議する、としているが、同宣言は、日米安保条約について「アジア太平洋地域において安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎」と変化させた。すなわち、その防衛地域について「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全」から「アジア太平洋地域」へと変化させたのである。これを「再定義」と位置付けた。
冷戦終結後の日本の防衛地域が「アジア太平洋地域」へと拡大されたことにより、海外派兵とそれにともなう有事法制の整備が必然的に要求されることになる。そのため、1978年の「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の改正、そして「同盟(国)」や「同盟関係」という概念が生まれることになったと見ることができよう。
「同盟国」とは
日米共同宣言のなかで、「同盟」や「同盟関係」がどう定められているかを紹介しよう。
4 (両首脳は)日本と米国との間の同盟関係が持つ重要な価値を再確認した。両者は、(中略)21世紀に向けてアジア太平洋地域において安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎であり続けることを再確認した。
5 (a)両国政府は、両国間の緊密な防衛協力が日米同盟関係の中心的要素であることを認識した上で、緊密な協議を継続することが不可欠であることで意見が一致した。
(b)(両首脳は)1978年の「日米防衛協力のための指針」の見直しを開始する。
日米共同宣言で「同盟関係」という言葉が出てくるのは、この部分のみである。その主語が「両首脳は」あるいは「両国政府は」であることに注目していただきたい。
同盟関係と言えば、一般的に国家間の関係と考えられている。政治学事典を見ても「同盟国」の項では「同盟の最も重要な機能は、国家間の安全保障協力、わけても共同防衛である」(猪口孝編『政治学事典』弘文堂、2000年刊、土山實男執筆)とあり、『広辞苑』では「互いに同盟関係にある国家、すなわち同盟条約の当事者」とある。
いずれも、「同盟」関係とは「国家間」の関係であること、そのために「条約」に基づくものだと説明されている。日本の場合も「同盟」はすでに経験済みだ。日露戦争を前にして「日英同盟」を結び、「日英同盟協約」(1902年)を締結している。さらに太平洋戦争開戦の直前にナチス党のドイツ、ファシスト党のイタリアと「日独伊三国同盟条約」(1940年)を締結し、国家と国家の関係を構築していた。
ところが「日米同盟」は、そもそも首脳同士の「宣言」のなかの一節の中にあるに過ぎない。そして「宣言」は、憲法が定める「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」(41条)である国会の承認を経ていない。したがって、「条約」などと異なり、首脳同士が交わした政府文書に過ぎないのだ。