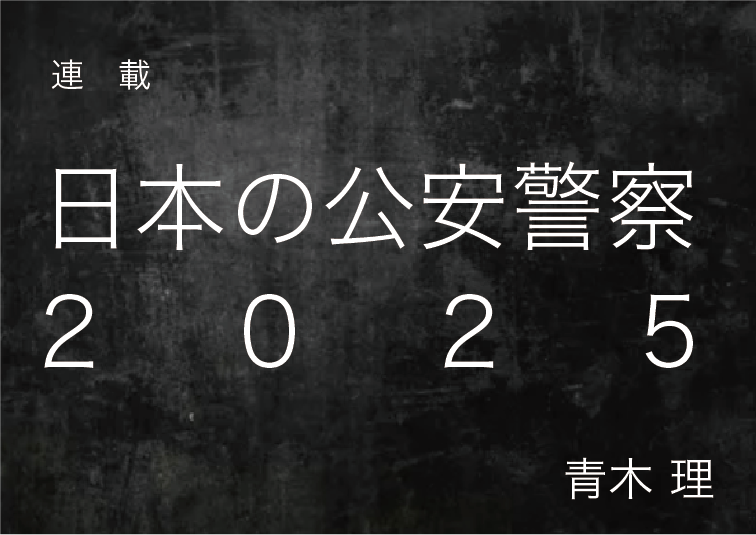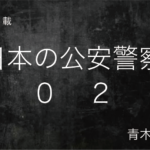これまでの記事はこちら
本来「公安」のあるべき姿とは
前回記したとおり、背後に特定の政治思想が横たわる事件の捜査を担い、それを起こす恐れが強いとみなした団体や個人を監視する公安警察とは、煎じ詰めれば政治警察であり、思想警察でもある。
しかし一方、公安警察も警察組織の一部門である以上、その活動にはおのずから制約が加えられ、少なくとも時の政権とは一定の距離を保つ必要がある。マックス・ウェーバーが指摘したように、警察もまた軍事組織と並ぶ国家の「暴力装置」であり、民主主義政体下ではそれをどう民主的に制御するかが重要課題。たとえば時の政権が警察に容喙して誰を逮捕しろとかするなとか、どこを強制捜査しろとかするなとか、強大な権限と物理的な力を有する警察=「暴力装置」を恣意的に動かすことがあってはならず、逆に警察が政権に容喙してそれを動かしはじめれば警察国家になってしまいかねない。
そのために戦後日本は、極度に中央集権的な警察組織がファッショの尖兵と化した戦前・戦中の反省の上にも立ち、公安委員会制度を創設した。すなわち、全国各都道府県の警察組織は都道府県公安委員会の「管理」に服し、国家機関である警察庁は国家公安委員会の「管理」に服する、と警察法は定める。
その公安委員会のメンバーは、国家公安委員長には国務大臣が充てられるものの、その他の国家公安委員や各都道府県の公安委員は民間有識者が選ばれる。それも警察や検察、特定政党との関係性を可能な限り排することも警察法は求めている。
時おり耳にする誤解だが、同じ「公安」の二文字を冠していても、公安委員会と公安警察はまったくの別物で、むしろ公安委員会制度は警察という「暴力装置」を民主的に制御し、政治と警察が直結することを避けるための〝クッション〟も果たす大切な装置である。なのに現状では国家公安委員会も、各都道府県の公安委員会も、その事務局機能を警察が担い、委員の人選も警察が事実上差配し、さしてその役割を果たさない〝お飾り〟と化してしまっている。
とはいえ、公安委員会が果たすべき機能と制度自体の重要性に変わりはなく、本来は制度を有効に機能させるための改革こそ必要だと私は思う。にもかかわらず、この制度や装置に埋めこまれた大切な理念や原理原則を蹴散らし、政治と警察の一体化を異様なほど進めたのが故・安倍晋三氏が率いた「一強」政権であった。
「一強」政権下の公安警察
特に2012年から20年までの8年弱に及んだ第2次政権ではそれが露骨で、事務担当の官房副長官には警察官僚出身の杉田和博氏が一貫して起用されつづけた。事務担当の官房副長官は官僚出身者が就いて霞ヶ関全体を睥睨し、各省庁の総合調整などにあたるが、戦後の歴史を振り返れば、過去には故・後藤田正晴氏のように戦前・戦中に内務省にいた警察出身者が就いた例もある。ただ、戦後発足した警察庁の出身者が就いたのは麻生太郎政権の漆間巌氏が初で、在任期間は1年に満たなかった。
しかし、同じく警察庁出身の杉田氏は菅義偉政権でも引き続き官房副長官を務め、戦後最長となる9年近くも君臨した。このような人事は極めて異例。また、霞ヶ関官僚の幹部人事を牛耳る内閣人事局が2014年に発足すると、杉田氏は17年からの4年余にわたってそのトップの局長も兼務し、霞ヶ関には不健全な忖度の風潮が蔓延した。
その杉田氏は、1966年にキャリア官僚として警察庁に入庁後、警備局の外事課長や公安一課長、さらには公安警察組織の〝総元締め〟といえる警備局長などを歴任し、まさに生粋の公安部門出身の警察官僚であった。
加えて、「一強」政権下で官邸に深々と突き刺さった公安部門出身の警察官僚は杉田氏にとどまらない。もう一人の〝主役〟が北村滋氏である。