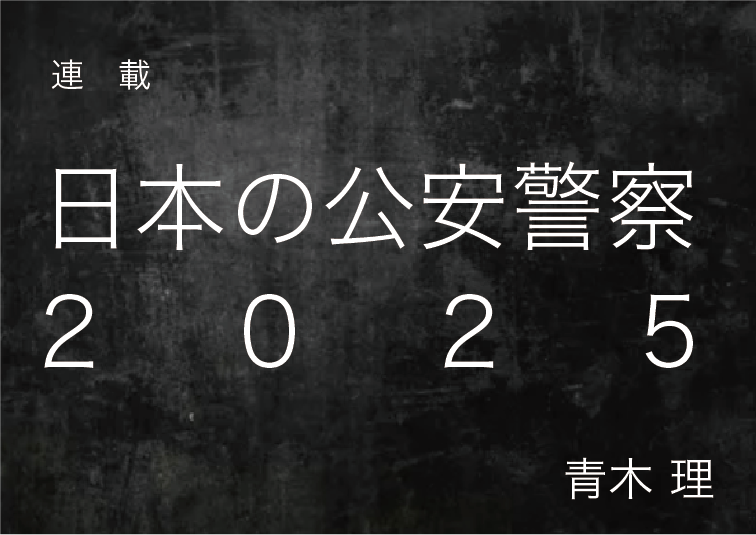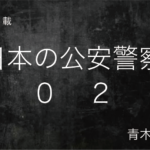これまでの記事はこちら
戦後警察のありようの大転換
本誌の前々号(2025年10月号)に掲載された私と石井暁・共同通信編集委員の対談は、かねてから抱いていた疑問を解いて状況認識をアップデートする、私自身にとっても新たな知見を得る貴重な機会になった。
お読みいただいた方ならば承前のように、主なテーマとしたのは先の国会で成立した、いわゆる「能動的サイバー防御(アクティブ・サイバー・ディフェンス=ACD)」関連法である。日々膨大な量が行き交うサイバー空間=ネット空間上の各種通信情報を監視し、サイバー攻撃の“兆候“を掴んだなら、攻撃元と目したサーバーに侵入するなどして“無害化措置”をとる――そうした行為を可能とするACD関連法が孕む数々の問題点にも対談で言及した。
その枢要で最大のもののひとつが、まずはこの“無害化措置”なる行為にある。仮にサイバー攻撃の“兆候”を掴んだとして、ほぼ間違いなく外国にあるだろうサーバーに侵入して一方的かつ強制的な“措置”をとれば、当該国からみればこれは事実上の“先制攻撃”と受け止められかねない。いかにサイバー空間上の行為とはいえ、これは「専守防衛」を矜持としてきた戦後日本の防衛政策を根本から転換するもの、と捉えるべきではないのか。
また、いかにサイバー攻撃の“兆候”を掴むためとはいえ、サイバー空間=ネット空間上に日々行き交う膨大な通信情報を広範に監視するのは、これは憲法が保障する「通信の秘密」の重要価値と真っ向から衝突する。しかも情報通信環境の激変に伴い、あらゆる団体にせよ個人にせよ、情報通信の主要手段がネットに移行した現在、ACD関連法はその広範な「常時監視」に道を開き、一般市民を含む機微なプライバシー情報を当局に根こそぎ把握されることになってしまわないか――。
記者として防衛省・自衛隊を四半世紀以上にわたってウオッチしつづけてきた石井氏も同じ懸念を共有しつつ、概略次のように重要な事実を指摘した。
すなわち、ACD関連法とは「基本的に安全保障分野の法律だと理解されていることが多い」けれども「実態はかなり異なる」と。「この対談に先立って複数の関係者に取材したところ、たとえばある防衛省幹部は、これは警察の権限を強くするために警察主導でつくられた法律だと言い切っていました」と。だから「実態としては警察による警察のための法律」なのだと。つまり、法制定の過程では防衛省・自衛隊と警察庁が水面下で綱引きを繰り広げたにしても、最終的には警察庁がACD関連法に基づく諸活動の主導権を握り、「しかも、かなり警察は周到に準備していた」とも石井氏は指摘した。
現実に警察庁は関連法成立より3年も前の2022年4月、庁内に「サイバー警察局」を新設し、その実働部隊として関東管区警察局に「サイバー特別捜査隊」を設置している。さらにはACD関連法成立の1年前となる2024年4月にはこれを「サイバー特別捜査部」へと格上げした。
まさに準備周到なこうした動きを、単に“新規部門の創設”とのみ捉えては物事の本質を見誤る。成立したACD関連法による諸活動の主導権を警察が握り、同時に組織態勢も整えられたことは、これもこの国の戦後警察のありようを根本から大転換させる出来事であったからである。本連載でも以前記したとは思うが、非常に重要なことなのであらためて確認しておきたい。
1945年の敗戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指示によって旧内務省は解体され、戦後の警察組織は基本的に分権型の自治体警察組織として再出発した。内務省を頂点として極度に中央集権的だった戦前・戦中の警察組織が――特に特高警察などが軍部ファッショの尖兵と化した反省と教訓に基づくものであり、だから現在のように北は北海道から南は沖縄まで、それぞれの都道府県警本部――首都・東京は警視庁――がそれぞれの都道府県公安委員会の管理に服する態勢が整えられた。
他方でGHQの占領政策は朝鮮戦争の勃発や冷戦の激化によっていわゆる“逆コース“をたどり、旧内務官僚らも中央集権的な警察機構への回帰を目論み、独立回復後間もない1954年には警察行政の中央機関として警察庁が設置されている。
以後、キャリア官僚が差配する人事や予算などを梃子として警察機構は徐々に中央集権的な色彩を強め、特に警察庁警備局を頂点とする公安部門ではそれがことさら顕著だった。公安警察組織が監視対象と目した団体の内部や周辺に「協力者」と呼ばれる情報提供者=スパイを獲得して運営する隠微な作業も、あるいは1986年に発覚した神奈川県警の公安部門による共産党国際部長宅への電話盗聴のような明々白々たる違法行為も、すべての指示や承認等は警察庁警備局から各都道府県警の公安部門へと直接発せられ、公安警察組織に関しては早くから相当に中央集権的な態勢が築かれていた。逆にいうなら中央集権的な警察機構は、一種の政治警察でもある公安警察にとっては宿願であり、必須不可欠な態勢とも位置づけられてきたことになる。