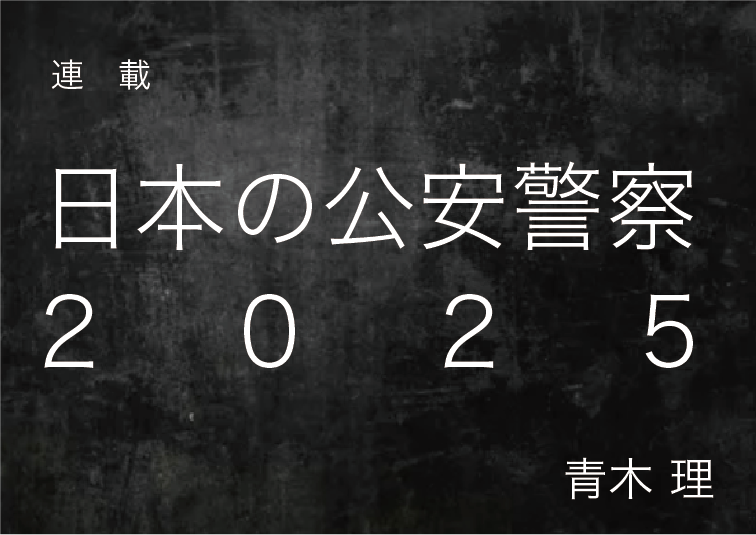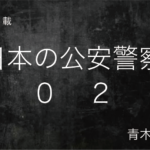これまでの記事はこちら
公安警察の権限はどう変容したか
公安警察の現状を考察するこの連載では、ここまで大きく2つのことを記してきた。
まず、戦後長く「反共」を最大のレゾンデートルとしてきた公安警察組織が冷戦体制の終焉以降、「テロ対策」やら「経済安保」やらを呼号する政治の意向や国際情勢などを梃子とし、「外事」などを新たなレゾンデートルに位置づけてきたこと。
実際、この国の公安警察組織において現場の最大部隊である警視庁公安部では近年、外事部門が着実に増強・拡充されてきている。その公安部の外事部門が暴走し、生物兵器の製造にも転用可能な化学機器を中国などに不正輸出したと捜査の刃を振りかざし、なのに初公判直前に検察が起訴を取り消すという異様な経過を辿った冤罪事件=大川原化工機事件は、新たなレゾンデートルを内外に誇示したい公安警察組織の歪んだ欲望も背景には横たわっていた、と指摘した。
と同時に、特に「一強」長期政権下、本来は時の政権と一定の距離を保つべき警察組織が――就中、公安部門に出自を持つ警察官僚や出身者たちが政権中枢に幾人も深々と突き刺さり、戦後例がないほど政権と警察が一体化してきたこと。
そうした警察官僚やその出身者たちが政権の“守護者”として“政敵潰し”などに暗躍する一方、かねて公安警察組織が渇望していた数々の治安法を手に入れてきたことも概観した。
かつては世論や野党などの猛烈な反発で頓挫してきたスパイ防止法と相似形の貌を持つ特定秘密保護法はその代表格であり、他にも共謀罪法、重要土地利用規制法、経済安保情報保護法、あるいは通信傍受法=盗聴法の大幅強化等々、ろくな歯止めが設けられていない、極めて杜撰で、しかしだからこそ極めて危うい治安法の数々は、いずれもこの10年と少々の間に続々と成立、施行されてきている。
では、こうした治安法を手に入れたことで、公安警察組織の権限や活動内容、活動範囲等はどう変化してきたのか、どう変化しうるのか――それらを考察するのが今回の主なるテーマである。