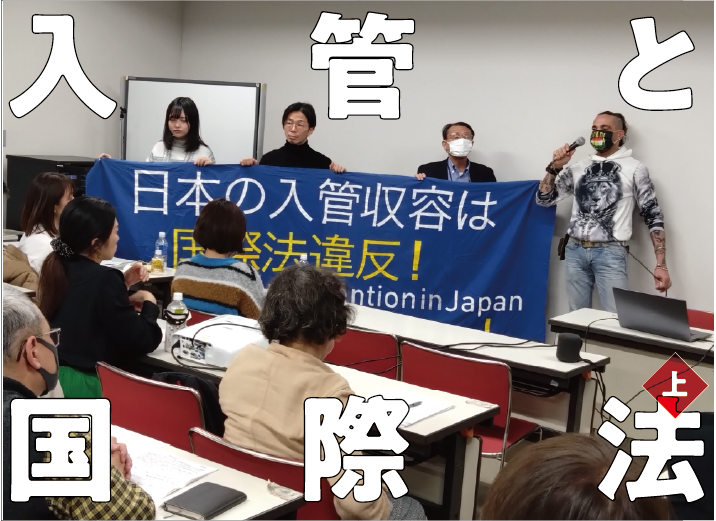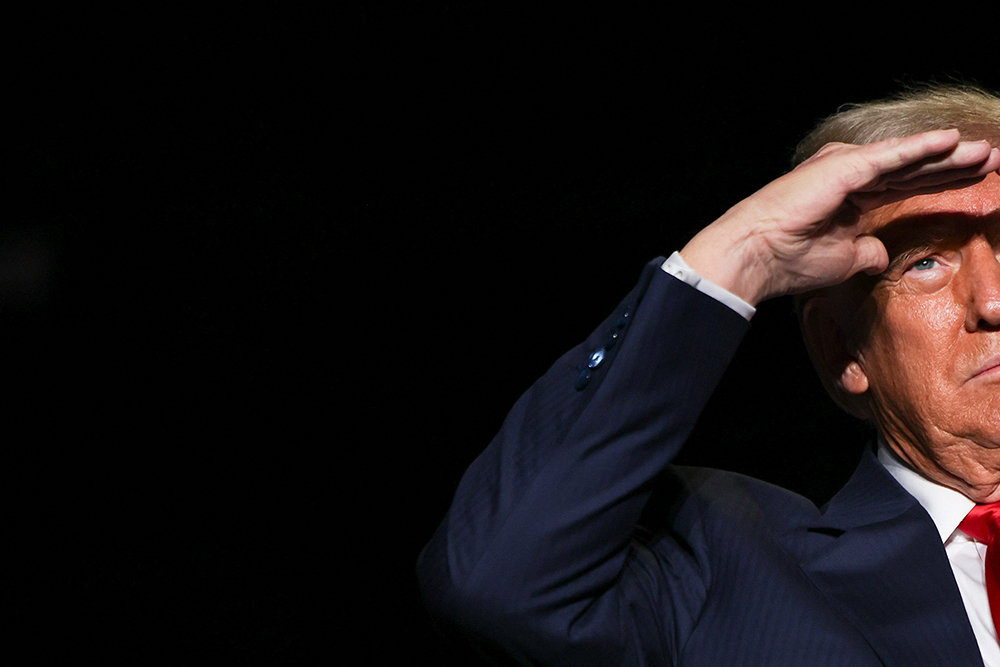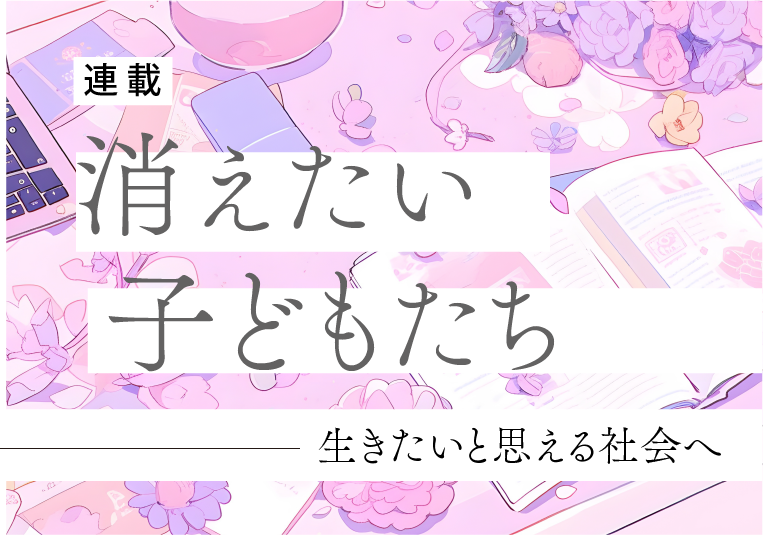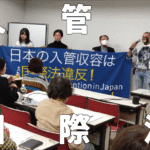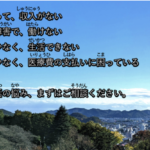女性差別撤廃条約とは
――今年は女性差別撤廃条約の採択から45年、国連女性差別撤廃委員会による日本の取り組み状況についての審査もあります。まず、この条約の制定の経過や、どのような内容、仕組みを持った条約なのか、お教えください。
山下 1979年、国連で生まれた女性差別撤廃条約は、「世界女性の権利章典」とも呼ばれ、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃を目的とする条約です。戦前の「男は仕事、女は家庭」、その後の「男は仕事、女は家庭と仕事」といった機能平等論から脱して、「女も男も家庭と仕事」という男女平等論ヘの転換をはかった条約です。
それまでの固定化された男女の役割分担概念を変革することが基本理念です。法の上の差別だけではなく、実際の生活に中にある慣習・慣行における差別も撤廃し、公的セクターばかりでなく、個人・団体・企業による差別も撤廃することを求めていること、さらに、直接差別ばかりでなく、間接差別も撤廃することを求めているのが、この条約の大きな特徴ですね。
1946年に、国連経済社会理事会のもとの機能委員会のひとつとして「女性の地位委員会」が設置され、女性の地位向上に取り組みました。委員会が最初に手がけたのは法体系の整備で、1967年に「女性差別撤廃宣言」が採択されましたが、さらに法的拘束力のある国際文書を作る必要性から条約化が始まったのです。まず国連事務総長の呼びかけで各国から新文書についての案が出され、1974年、76年に女性の地位委員会作業部会で審議され、女性の地位委員会案が作られました。その後、77年、78年、79年に総会第三委員会作業部会で審議され、1979年12月18日に、第34回国連総会で採択されました。
国連は、1975年の国際女性年を起点に、その後の76年から85年までを「国連女性の10年」としました。その間、三度、世界女性会議を開催し、世界中で女性の地位向上に向けた大きなうねりが起きました。女性差別撤廃条約は、そのような世界的な盛り上がりを背景に生まれたといえます。日本は、1985年6月に女性差別撤廃条約を批准し、7月25日に効力発生を迎えました。
現在189カ国が批准しており、名実ともに「世界女性の権利章典」です。国連加盟国で条約を批准していないのは、イラン、スーダン、ソマリア、トンガ、パラオ、そしてアメリカだけです。
――アメリカが批准していないというのは、驚くべきことですね。
山下 女性差別撤廃条約よりもさらに締約国の多い子どもの権利条約も、アメリカは批准していません。これは困ったことで、実際、日本にも悪い影響があるのです。
女性差別撤廃条約から20年を経た1999年、条約の実効性を強化するために女性差別撤廃条約の「選択議定書」――個人通報制度と調査制度を規定しています――が第54回国連総会で採択されました。この選択議定書の批准国もすでに115カ国に達しているのですが、日本はまだ批准していません。そこで私たちは選択議定書の批准を求めて政府や各政党へのロビイングも行なっています。2009年、当時の内閣官房長官にお会いしたとき、「アメリカも条約を批准していないんでしょう」のひと言で話が終わってしまったのです。そういう悪影響があるんですね。アメリカでは民主党政権になるたびに批准の動きがあるのですが、結局、いまだに批准されていません。今度の大統領選挙のあとにどうなるか、注目しています。
締約国の3つの義務
――条約の批准国はどのような義務を負うのですか。
山下 締約国は、3つの義務を負います。
1つ目は尊重義務です。国は、女性に対する差別となる法律、規則、行政、手続き、慣習、慣行を維持してはならず、間接差別も撤廃しなければなりません。
2つ目は保護義務です。国は、個人、団体、企業による差別から女性を保護し、ステレオタイプな慣習、慣行を撤廃する措置をとらなければなりません。措置をとらないと「相当な注意」義務違反とされます。
3つ目は充足義務です。事実上の平等を促進するため、暫定的特別措置をとって、女性の権利を充足しなければなりません。不作為は条約違反です。
条約の実行を推進するのが女性差別撤廃委員会、略称CEDAWです。CEDAWはこれまでに39の「一般勧告」を出し、締約国に対する評価と勧告を含む「総括所見」も出して、条約を精緻化してきました。選択議定書による個人通報事例や調査事例の集積もあります。女性差別撤廃条約は、45年前に採択された規定から、現実に即して進化し、内容も豊富になってきているのです。そのため「生ける法/Living Instrument」と呼ばれています。
CEDAWでは締約国で条約がきちんと実施されているかどうかをモニターするため、締約国と定期的に「建設的対話」を行なっています。近代国家は法治国家ですから、女性差別撤廃条約という人権条約を批准したら、締約国は実効性を高めるための措置をとっていく義務を負います。そのために、多くの国々は先ほど触れた選択議定書も批准して、しっかりその義務を受け入れ、性差別のない社会に向けて改革を進めているのです。
この45年の間、女性差別撤廃条約は、女性の権利の国際基準としての役割を果たしてきました。国際的にも、この間、各国のジェンダー平等は、飛躍的に前進しました。女性差別撤廃条約をもとに、各国が法制度を変えてきたからです。たとえば、担い手が男性に偏ってきた政治分野で女性の進出を進めるためのクオータ制をとる国は130以上と言われています。経済分野でも、EUの国々では、取締役の女性比率を40パーセント以上に設定しています。
皆さんもすでにご存知のように、日本は、その流れから大きくおくれを取っています。私は、こうなってしまっている原因のひとつとして、日本政府が女性差別撤廃条約で求められている内容に誠実に向き合おうとしてこなかったことがあると思います。『地平』(10月号)で国際人権の専門家である馬橋憲男さんが、日本政府にとって人権条約とは何なのか、と本質的な問いかけをされていますが、CEDAWの「総括所見」も「法的拘束力がない」として、そのアドバイスを受け入れようとせず、選択議定書もいまだ批准していません。これでは、ダメですよね。
なぜ日本は停滞しているのか
――世界経済フォーラムが発表しているジェンダー・ギャップ指数で日本は、2024年度、146ヵ国中118位です。G7の中では最下位です。どうしたらこの状態から脱出できるのでしょうか。