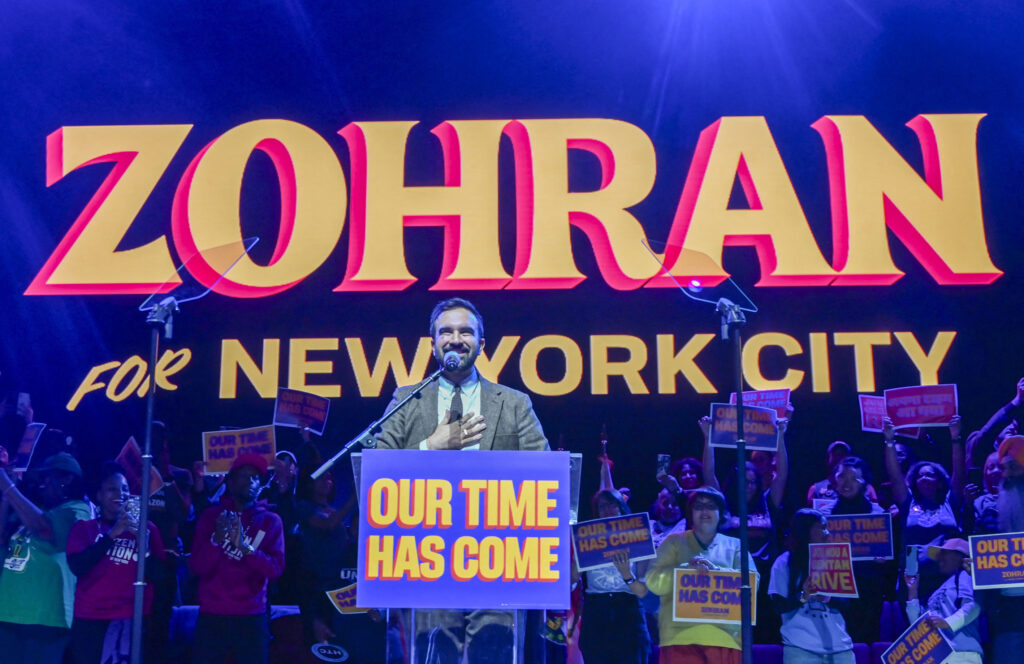ある朝、不穏な夢から目を覚ますと
今年2月12日、ニューヨーク・タイムズに「ある朝、不穏な夢から目を覚ますと自分がベッドの中で一匹の巨大なゴキブリに変身していることに気づいた」というカフカの有名な一文で始まる、苦渋と皮肉に満ちた切実なエッセーが掲載された。
寄稿したのは作家で米国PEN会長のバーナード大教授ジェニファー・フィニー・ボイランだ。タイトルは「I’m a Transgender Woman. This Is Not the Metamorphosis I Was Expecting(私はトランス女性だ。これは予期していた変身ではない)」
トランプ政権の反DEI政策による象徴的な「変身」の強制。「DEI」とは多様性(Diversity)、公正性(Equity)、包摂性(Inclusion)の頭文字。「反DEI」とは、とどのつまり、「世の中にはいろんな人がいて、みんな公正に扱われる権利があるし、みんな一緒に仲間でいこうよ」というスローガンの破棄、放逐である。
ボイランは2000年に女性へと性別移行した。しかしトランプは、再度大統領に就任した初日の2025年1月20日当日に「性別は生物学的な男女のみ」と定義する大統領令に署名した。性的にもジェンダー的にも「いろんな人はいない。男女だけだ」ということだ。
結果、トランスジェンダーやノンバイナリー(男女二元の定義では収まらないジェンダーのありかた)の存在が即座に否定されることになった。ボイランは「男」に変身させられた。
連邦機関のウエブサイトでは「LGBTQIA+(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クイア、インターセックス、アセクシュアル……)」などの表記が「LGB」だけとなり、バイデン政権で認められた男女以外の性別表記「X」は旅券など政府発行の公的書類の性別記載では無効となった。トランスジェンダーのスポーツ参加は禁止され、米軍へのトランス男女の新規採用は排除され、すでに従軍しているトランス兵士も退役を迫られている。未成年の性別適合治療は現時点で計26州で違法で、連邦政府や民間企業での多様性研修やLGBTQ+保護プログラムも軒並み廃止・縮小、学校における各種マイノリティの生徒支援プログラムも撤廃されるばかりか、それらを推進してきた教育省そのものすら廃止されようとしている。
トランスジェンダーあるいはノンバイナリーの若者たちの疎外感、喪失感はいかほどのものか。
現在66歳のボイランですらこの予期せぬ「変身」に「私の驚きは想像できるだろう」と続ける。
彼女のその「驚き」は変身の強制についてだけではない。トランプ政権による「固定的かつ不変的な性別」の独自定義の珍妙さについてもだ──「女性とは、受精時に大きな生殖細胞を生み出す性別に属する人を指す。男性とは、受精時に小さな生殖細胞を生み出す性別に属する人を指す」
しかし「受精時」には性別は表現型的には男女に分かれてはいない。「雄」を決定する因子であるY染色体が「小さな生殖細胞」(精子)を生み出す精巣の発達を引き起こすには7週間ほどかかる。つまりそれまでは誰も「男性」ではない。
したがって、「この大統領令が発令された後、インターネット上ではアメリカのジェンダーは実際には男女二つではなく一つにリセットされたのだという意見が飛び交った──つまり女性に、だ」。続けてボイランは皮肉まじりに「Welcome to my world!(私の世界へようこそ!)」と綴るが、問題はその種の生物学的、遺伝子的解釈にはないことを彼女は知っている。問題の核心は彼らの標榜する「ジェンダーイデオロギーの過激主義から女性を守る」ことでも「連邦政府に生物学的真実を取り戻す」ことでもなく、実際には「トランスジェンダーの人々の生活を可能な限り困難にすることが目的」なのだと。
事実、大統領令に反して、トランス女性の女性スポーツ参加を禁止しないと宣言していたメイン州に対し、トランプ政権は4月2日、同州の学校、保育施設、放課後活動の給食助成金を打ち切る通告を行なった。この決定は「単なる始まりだ」と脅しつつも「連邦法に従って女性と女子を保護するなら(助成は)いつでも再開する」として。
遡ること2月、同州では州校長会が早くも同大統領令への反対を公式に表明していた。これに対してトランプが連邦助成金の停止で脅すと、同州のジャネット・ミルズ知事(民主)と州法務長官は「大統領は自分の政治課題を推進するために子どもたちを人質にしている」と非難、「助成金と学問的機会を守るために全ての適正な法的手段を講じる」と徹底抗戦を宣言していたのだ。
そして大いなる伏線は2月21日、ホワイトハウスで行なわれた大統領と全米州知事との恒例の初会合の席だ。ミルズは他州の知事の前でトランプからひとり直々に名指しされ、「私の大統領令に従うつもりはないか?」と念押しされた。彼女は「メイン州は、州法と連邦法に従う」とのみ応じ、取材メディアのカメラの前で大統領の気分を害した。なおも「私に従ったほうがいい」と繰り返す彼に、ミルズは「法廷でお会いしましょう」と言い放っていたのだ。
メイン州は、「女性を守る」という大義名分からも「生物学的真実」からも遠く離れ、大統領令と無関係な人々をも犠牲にするこの助成金カットを、学校における性差別を禁ずる公民権法と合衆国憲法の平等保護条項に違反するとして提訴している。
大統領令はまさに「トランスジェンダーの人々の生活を可能な限り困難にすることが目的」なのだろう。
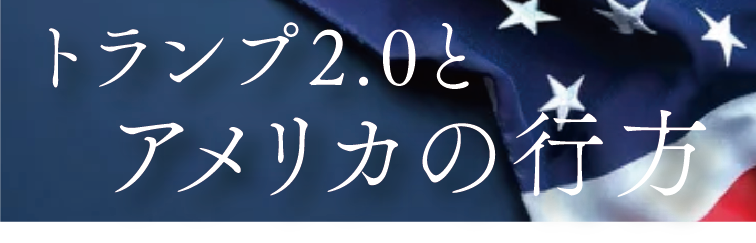


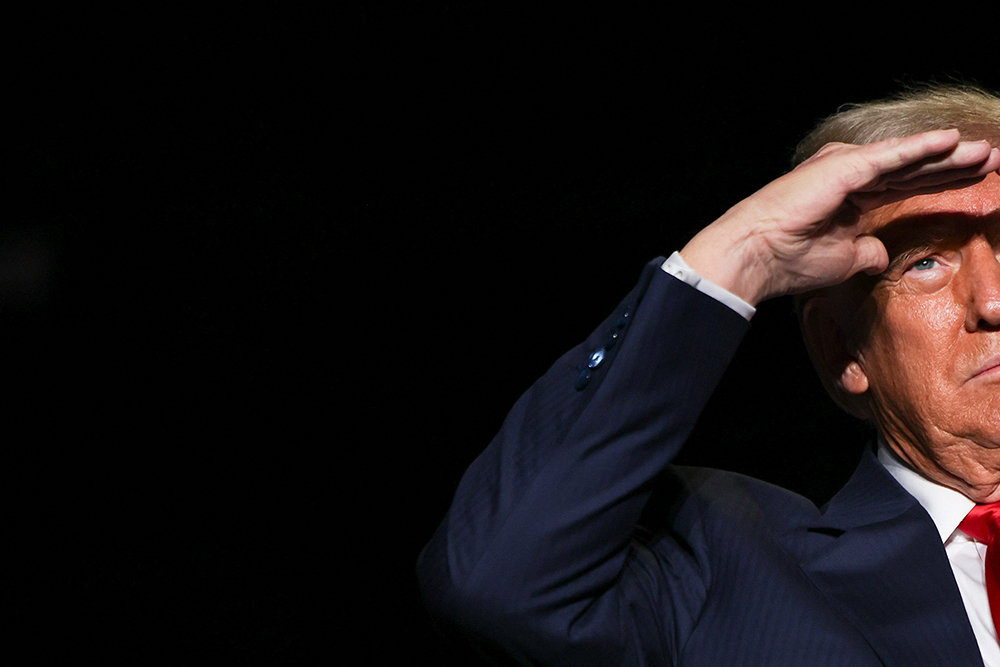










-768x1024.jpeg)