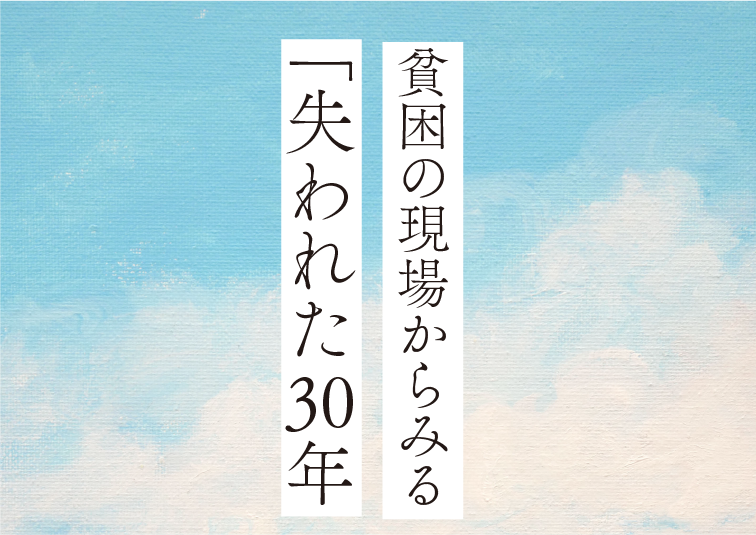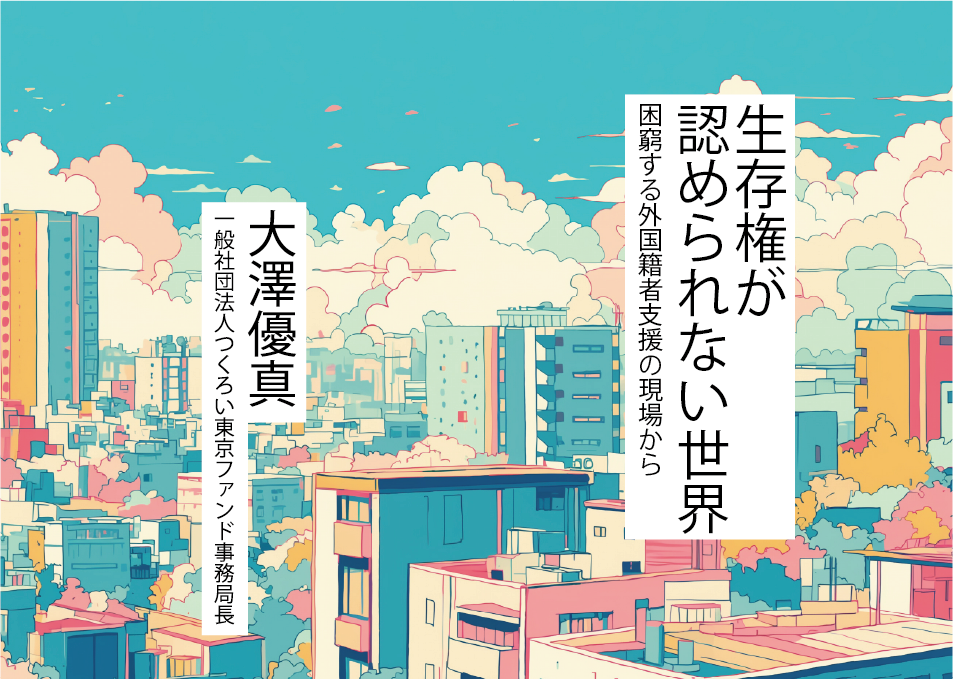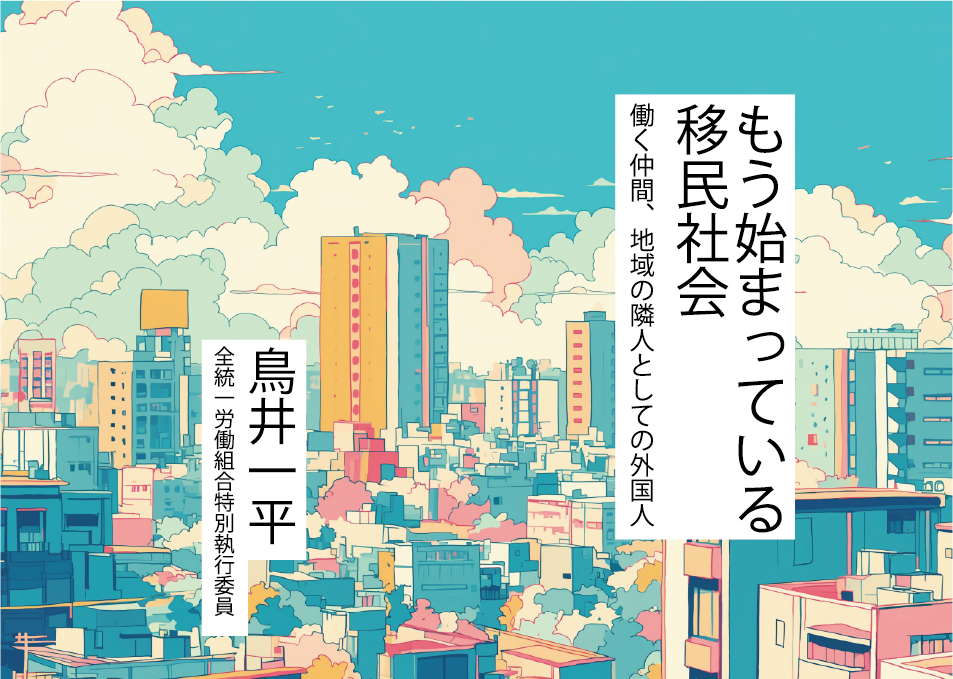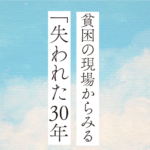誰もが尊重される町へ 国立市福祉事務所の挑戦
昨年11月、「公的扶助研究会(注1)」が主催したシンポジウムに、東京都国立市の生活福祉担当課長、左川倫乙(ともつぐ)氏と、小田原市生活援護課査察指導員の秋澤和典氏とご一緒した。
小田原市は「保護なめんな」ジャンパー事件で一躍有名になってしまった自治体で、一方の国立市は2013年度~17度の5年間にわたり、保護費の返還処理漏れや支給漏れなどの大規模な事務処理遅延があることが2018年度に発覚した。
国立市も小田原市も、問題が発覚した際に、まずは公的に謝罪をするところから始まり、被害を受けた当事者へ謝罪と説明をし、設立された検証委員会に洗いざらい情報を提供した。また、外部の有識者や支援者とともに事件が起きた原因を探り、その上で働き方を見直し、職員の意識改革を重ね、再発防止を図った点で共通している。とりわけ、国立市は当事者や支援団体の声に耳を傾けるという点を強調していた。市内や近隣の民間支援団体と密接に協働することが相談者にとっては最善であり、双方が対立することは誰にも、特に相談者に、利益をもたらさないのだと。
民間の支援団体に属する私は、常々、行政とは一線を画すべきと考えている。なぜなら、行政と親密になった活動家や民間支援団体が権力への批判をしなくなる姿をこれまで見てきたからだ。庇護されることによって安定を担保されれば、行政と「うまくやる」ことに力点は移り、支援対象よりも行政側に配慮するようになる。声を上げるべき場面で声を上げにくくなるし、仮に上げてもトーンは変わる。
私は、当事者の側に立ちつづけるために、行政とは必要最低限の関係を築きつつ、相談者や利用者が行政に不当な目に遭わされていれば、冷静に、しかし遠慮せずに抗議したい。その程度の対等性を手放したくない。
支援団体と行政の関わり方について、国立市の左川課長と私は意見が真っ向から対立した。帰宅後も引っかかるものがあった。というのも私は国立市にこれまで足を踏み入れたことすらなく、国立市も福祉事務所も知らない。私は持論で遮断したものの、大事なものを見失っていないだろうか。そこで調べてみることにした。国立市の生活保護行政がどんなものかを。
「すべての人に安心して幸せに暮らす権利があります」
まず、市のウェブサイトをチェックして、私は目を丸くした。一般的に自治体ウェブサイトに掲載される生活保護の説明は、市民の権利性を謳いながらも、非常に厳格で固く、憲法や生活保護法の解説、要件に関する事務的な言葉が並ぶのが常だ。要件や義務ばかりを強調して、説教されているような気持ちになるものや、制度を使わせたくない本音が匂い立つようなものも多い中、国立市はかなり独特だった。「すべての人に安心して幸せに暮らす権利があります」と題された文章は、生身の人間が、誰にも分かる言葉で優しく語りかけていた。
関連
・「人権」が忌避される世の中で──ある自治体の市民と市長の取り組みからの考察(小林美穂子)
・【全文公開】桐生市事件——生活保護が半減した市で何が起きていたか(小林美穂子)