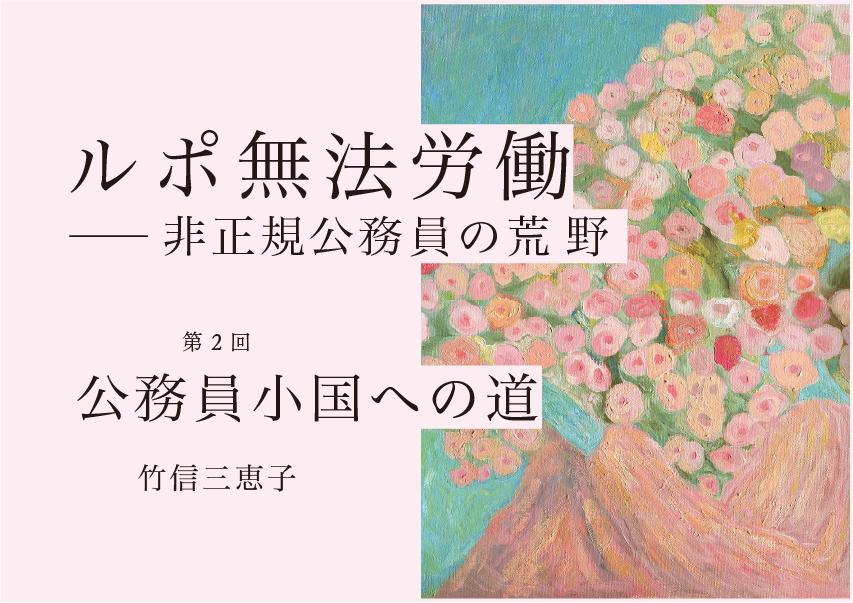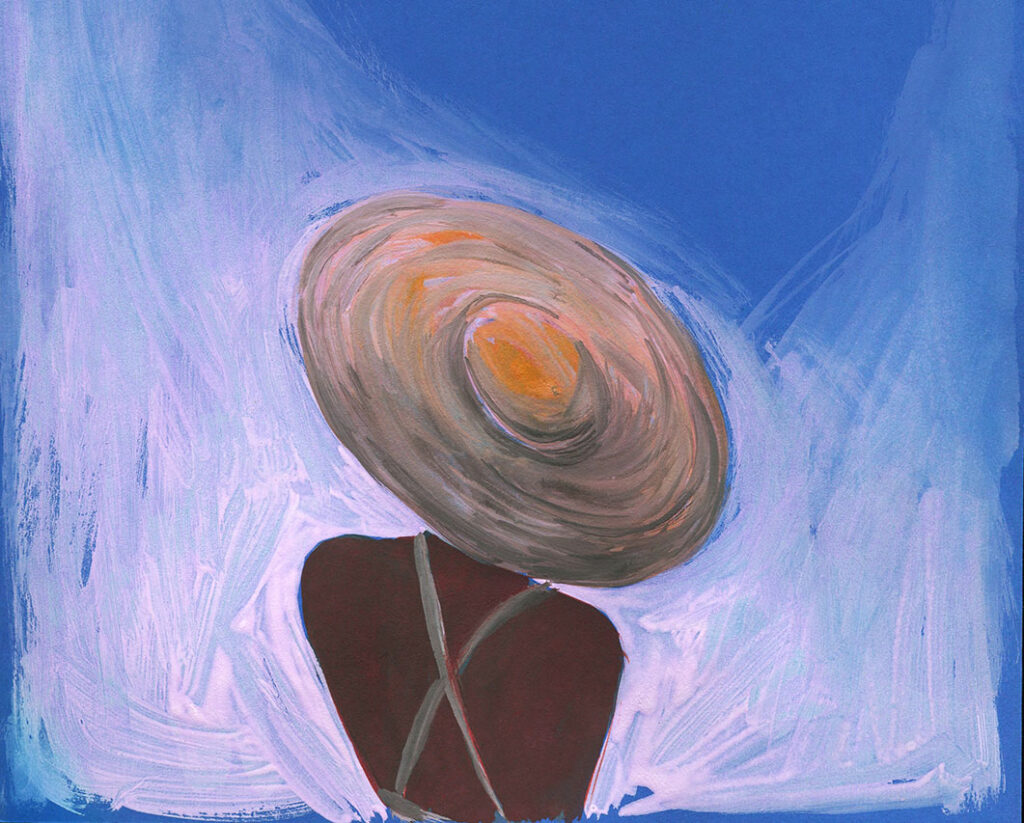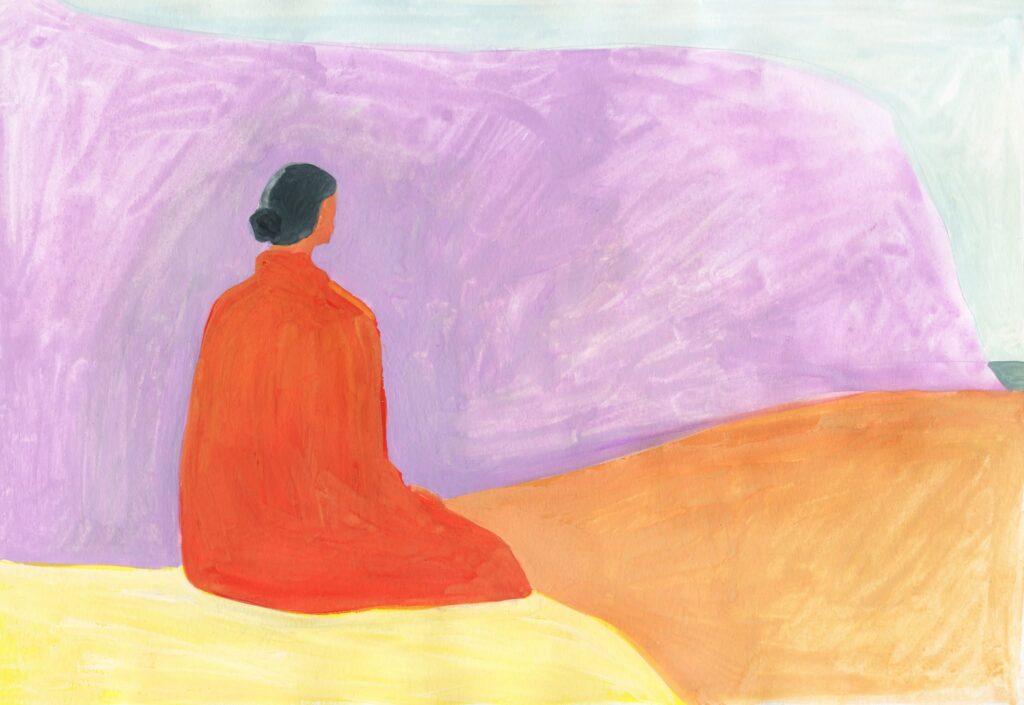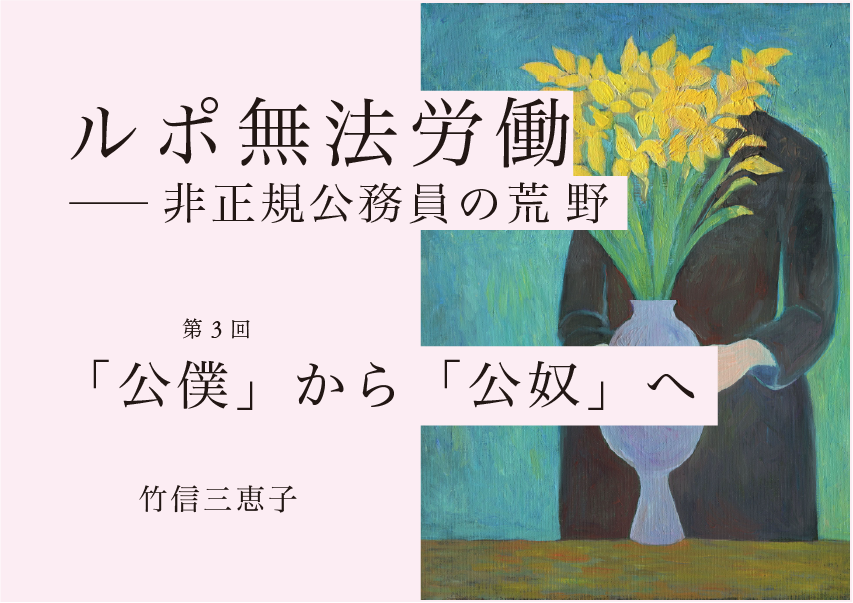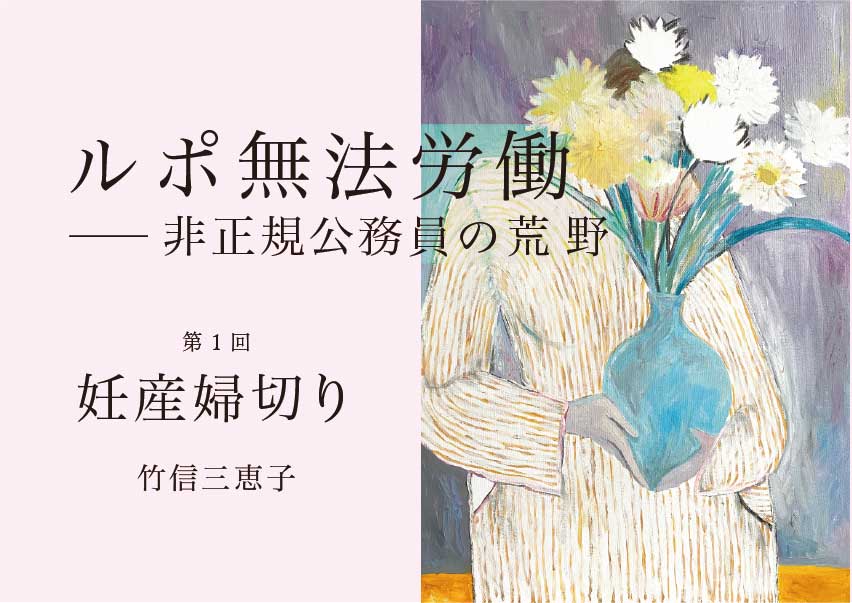前回の「妊産婦切り」に見られたように、労働者の権利という点では、非正規公務員は無法状態ともいえる状態に置かれている。背景にあるのが1980年代以来営々とつづけられてきた公務員減らしと非正規化と労働権の抑え込みだ。こうして生まれたのが、人口当たりの正規公務員がきわめて少ない「公務員小国」だ。
【関連】ルポ 無法労働――非正規公務員の荒野(1)妊産婦切り
「土光臨調」と「小泉改革」
「まさか、こんなことが」。1981年、福島大学の助教授だった晴山一穂は東京の公務員組合から日々伝えられる「第2次臨時行政調査会」の動きに、衝撃を受けていた。
公務員労働運動など現場に関わりつづけた行政法学者として知られる晴山は、1948年岩手県に生まれ、京都大学で学んだ。京都時代は、1960年代から始まる革新自治体の先駆けともいわれる蜷川虎三・京都府知事の選挙運動にも学生仲間と参加している。社会福祉などの民生重視の政策が、市民を巻き込んで自治体から広がるのを目の当たりにし、晴山は「公共と言えばお上、という意識が強かった日本に、公共を自分ごととする市民自治の機運がようやく生まれ始めた」と希望を抱いていた。
だが1979年の第2次オイルショックによる経済危機の中、財政赤字の立て直しを旗印に1981年、「第2臨調」が始まる。「ミスター合理化」と呼ばれた土光敏夫経団連会長をトップの、通称「土光臨調」が始まり、晴山の知る公務の世界は異次元の展開を遂げていく。
当時の大平正芳首相は「一般消費税」の導入を目指すが、税といえば戦費調達という記憶が根強かった日本社会で増税への不信感は強かった。与党は大敗して税収増という選択肢が失われ、「土光臨調」では、児童手当の所得制限の引き下げ、教員の人員抑制など生活者や公務職へのしわ寄せによる「解決」や、公的機関の民営化・規制緩和による民間資金の導入が答申されていった。
そんな「民営化」の中でも、1982年から87年までの中曽根政権下で推進された国鉄民営化はひときわ過酷だった。組合員を狙い撃ちにした大量解雇に加え、「人材活用センター」という部署に多くの労組員が隔離され職場から切り離された。90年代以降、民間企業でパワハラとして問題化する「追い出し部屋」のはしりと言えそうな労務管理だ。
中曽根は2005年11月20日のNHKのインタビューで、「国労(国鉄労働組合)は総評(当時の労組のナショナルセンターだった日本労働組合総評議会)の中心だから、いずれこれを崩壊させなくてはならない。それで総理大臣になったときに国鉄の民有化を真剣にやった。皆さんのおかげでこれができた」「そしたら総評が崩壊し、社会党が崩壊した」と述べた。「民営化」のこうした暗部は、土地の規制緩和政策によるバブル景気の狂騒の中でかき消された。