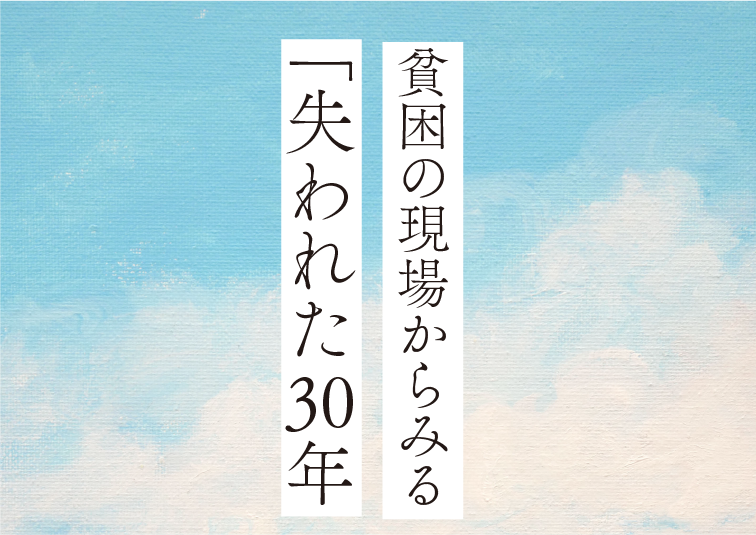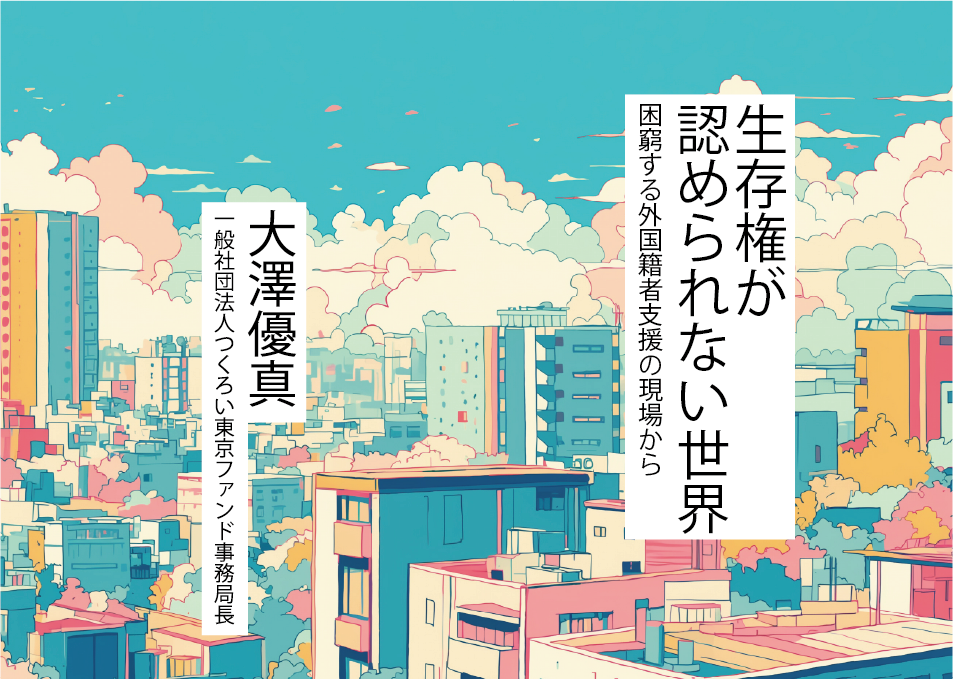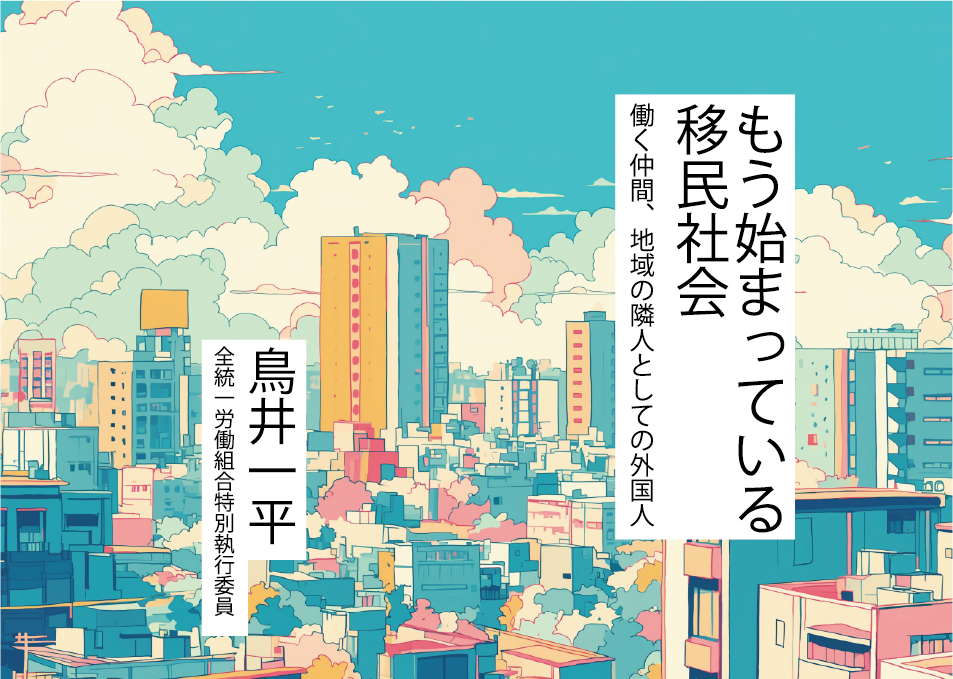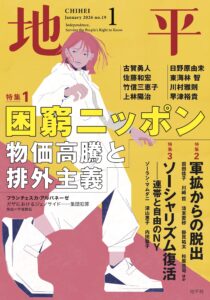「工場のラインが止まり、寮にはいられるものの所持金も食料も尽き、1週間水だけで過ごしている」(40代男性)
「派遣の寮を追い出され、1ヶ月前からネットカフェ生活。残金は数円」(30代男性)
「コロナで派遣切りに遭い、シェアハウスを追い出されそうで困っている」(40代女性)
これらの言葉は、コロナ禍、困窮者支援団体に寄せられたものである。
コロナ禍を受け、「反貧困ネットワーク」の呼びかけでホームレス支援に関わる40ほどの団体によって「新型コロナ災害緊急アクション」(以下、緊急アクション)が結成されたのは2020年3月。
以降、緊急アクションには2500件以上の相談が寄せられている。新型コロナが5類に移行して2年近く経つ現在も、メールフォームには「家賃が払えない」「食べるものがない」といったSOSの声が届きつづけている。
メールをくれる人の7割ほどがすでに住まいを失い、4割ほどが携帯も止まっている状態。世代として目立つのは、バブル崩壊後の1993〜2004年頃社会に出た就職氷河期世代=ロスジェネ。ざっくりというと今の40代前半から50代前半だ。また、全体の相談者に占める女性の割合は2〜3割ほど。
ちなみに、リーマンショックがあった2008年末から09年の年明けにかけて開催された「年越し派遣村」には6日間で505人が訪れたが、そのほとんどが中高年男性で女性はわずか5人。
しかし、コロナ禍1年目の年末年始(2020年から21年にかけて)に3日間開催された「コロナ被害相談村」(派遣村有志によって開催)を訪れた344人のうち、女性は62人で18%。その翌年の年末年始には2日間で418人が訪れ、うち女性は89人と21%を占めた。1年目に訪れた女性62人のうち、29%がすでに住まいがなく、42%が収入ゼロ、そして21%が所持金1000円以下。
そんな現場には女性だけでなく、派遣村の時にはほとんどいなかった20代30代の姿も目立つ。
こうして振り返ると、この十数年で困窮者支援の現場を訪れる人は若年化し、女性が増えていることがわかる。若者や女性を守る「余力」がこの社会から失われたのだろう。
雇用破壊のはじまり
さて、この号の特集は「新自由主義の30年」。
今年の1月、50歳となった私は、20歳から50歳までがきっちり「失われた30年」とかぶった1人だ。
多くの人は20代からの30年間で就職したり結婚したり出産したりローンを組んで家を買ったりすると思うが(実際、ロスジェネの親世代はそれが「普通」だった)、私の周りにはそのすべてを経験していないという人も少なくない。私もその一人だ。
社会に出る際、「時代ガチャ」に外れたロスジェネ。
そんな「失われた30年」の戦犯と言われるのが、日経連の「新時代の日本的経営」という報告書だ。1995年、私が20歳の頃に発表されたこの報告書は、労働者派遣法と並んで、この国の雇用破壊の元凶と言われている。
内容はと言うと、これからは働く人を3つに分けましょう、という提言だ。ひとつ目は正社員にあたる「長期蓄積能力活用型」。幹部候補生みたいなもの。次は、高度な専門職である「高度専門能力活用型」。むっちゃスキルを持ったスペシャリストというイメージ。そして最後が「雇用柔軟型」。聞こえはいいが、当初から「死なない程度の低賃金の使い捨て労働力を増やすつもりか」と批判されてきた。
バブル崩壊から数年後に出されたこの報告書により、不安定雇用はどんどん拡大。95年には1001万人、雇用者の20.9%だった非正規は、24年には2100万人以上と倍増。非正規雇用率は今や4割に迫る勢いだ。
そんな中でも大きかったのが、2004年の製造業派遣の解禁である。
コロナ禍、私がショックを受けたのは、相談会などで「同世代ホームレス」と複数出会ったことだったが、その多くは製造業派遣解禁を受け、十数年、全国の工場を転々としてきた人たちだった。
半年契約などで愛知や静岡、埼玉などの工場を転々とする生活。住まいは寮なので、派遣の契約が切れると同時に住まいも失う。仕事がない期間はネットカフェでしのぎ、次の工場に行くという綱渡りのような日々。
製造業派遣の解禁は、このように、職も住まいも人間関係も流動的ゆえ家族形成にも前向きになれず、またどこに行こうとも地域社会の一員としてカウントされず、住民票と実際の居住地が一致しない「広義のホームレス状態」の人々を膨大に生み出した。だが、この層の総数や実態は、おそらく誰も把握していない。
そんな中、派遣の仕事をつないで生き延びてきたこの層が、雪崩を打つようにして路上に放り出されたのがコロナ禍だった。
コロナ禍における生活危機
2020年秋に会った40代のA男さんもその一人だ。
長らく製造業派遣の仕事で全国を渡り歩いてきたという彼がコロナ禍初期に働いていたのは警備会社。仕事を選ぶにあたっての最優先事項が「寮付き・日払い」だったことから、いつからか工場か警備の仕事しか選択肢がなくなっていたという。ちなみに「日払い」という条件は、次の職場に辿り着く頃にはたいてい所持金が底をついていたから。
しかし、雇うほうはそんな人たちの事情を知っているので足元を見る。全国を転々とする生活を始めるようになってから、現場の労働条件や待遇はどんどん劣悪になっていったという。
そうして20年、建築や工事の現場が止まったことにより、警備の仕事は激減。寮にもいられなくなった彼はそこから1カ月ほど、都内の公園で初めての野宿生活を経験。季節は夏。日中はエアコンが効いているパチンコ屋の休憩室で過ごし、銀行にある最後の数千円を極力減らさぬよう、1週間500円の生活をした。そんな中、困窮者支援のNPOから宮城県で仕事があると教えてもらう。
交通費は出るということで宮城に行き、寮に入ったA男さん。やっと一息つけたわけだが、出勤初日、検温したところ微熱があることが発覚。当時、37度以上の人は工場に入れず、48時間待機となってしまったのだ。
この時点で所持金はゼロ円。1日働けばその日に日給から2000円もらえると聞いていたものの、計算が狂った瞬間だった。しかも派遣会社から「3日後、確実に働けるかわからない人を寮にいさせるわけにはいかない」と言われて追い出されてしまう。
微熱があり、コロナを発症しているかもしれず、所持金もない人間を寮から追い出す――。これが製造業派遣の実態である。そうしてA男さんは縁もゆかりもなく、知り合いもいない宮城県でホームレス状態になった。
結局、支援団体の助けで東京に戻り、生活保護申請。そこで私は彼と出会うのだが、果たして支援団体と出会えていなかったら、宮城でどうなっていたのだろう?
コロナ禍、このようなSOSはある種、「典型的」と言えるものだった。
一方、驚いたのは「年越し派遣村の時もお世話になった」というロスジェネ男性と会ったこと。
リーマンショック後の不況で住まいを失った彼は派遣村に来たことで支援とつながったものの、以来十数年、派遣と生活保護を繰り返すような日々だったという。そうしてコロナ禍で再び職と住まいを失い、ホームレス状態に。そこで相談会を訪れたのだ。
また、コロナ禍は女性に大きな打撃を与えたわけだが、風俗や水商売で働く女性たちからの相談も急増。中でも目立ったのが、「風俗の寮を追い出される」という相談。客が激減し、寮費を払えず明日にも追い出されるという話を聞くうち、その女性が東日本大震災の時も同じような目に遭っていたことがわかったケースもあった。被災地ではなかったものの、自粛ムードの中、客が激減し、その際も同じ状況に陥ったのだという。
これらのことからわかるのは、この国には、経済危機や災害、感染症流行という「何か」があった際、生活が根こそぎ破壊される層が存在するということだ。そしてその数は、確実に増えつづけている。「新時代の日本的経営」によって、社会は確実に脆弱さを増している。
緊急一時保護される若年層
もうひとつ、紹介したい数字がある。それは2023年7月発行の『区政会館だより』(東京23区が共同して行なう事務に関する広報誌)に掲載された「路上生活者対策事業の紹介(令和四年度実績報告)」。23区には「緊急一時保護事業」があり、ホームレス状態の人を一時的に自立支援センターという施設で保護するのだが、2022年度、この「緊急一時保護」を利用したのは630人。
驚いたのは年代別の数字で、そのうちの18%が20代以下。路上生活と言えば中高年以上の男性というイメージを多くの人が持つと思うが、緊急一時保護が必要なまでに若い世代が路上に放置されているという事実に愕然としたのだった。
また、全体を見ると、40代以下が60%を占める。では、これまではどうだったのかといえば、リーマンショックのあった2008年では20代以下はわずか4%。40代以下は42%で、もっとも多いのが50代の34%。60代以上は23%。しかし、それが2014年になると20代は15%となり、40代以下は66%にまで達する。以降、20代以下は増えつづけている。
「闇バイト」の背景にある貧困
貧困が深刻化する中、困窮ゆえの事件も相次いでいる。
2024年2月には東京・高円寺のコンビニで強盗未遂で46歳の男が逮捕。男は「2〜3日食事がとれておらず、金を手に入れて食事がしたかった」と供述している。
同年10月には、久留米市で47歳の男がコンビニでおにぎりを盗んで逮捕。「全財産を使いきって5日間何も食べていなかった」と語る男は、「おにぎりが食べたくなってはじめから強盗するつもりでコンビニに入った」と容疑を認めているという。
貧困問題に関わりはじめてから、私はずっと「これを放置するとゆくゆくは治安の問題として社会が多大なツケを払わなければならなくなる」と警鐘を鳴らしてきた。
そうして2024年、困窮を背景にした犯罪は「空腹で万引き」から、「闇バイト」強盗という形で新たなフェーズに入った。メディアや警察は「安易に闇バイトに手を出さないように」と呼びかけている。が、闇バイトに応募するのは困窮しているからだ。「即日」「高収入」などに惹かれて手を出してしまうのはそれほど逼迫しているからである。
「金に困っていた」
「税金の滞納が数十万円あり、短期間で稼げるアルバイトを探していた」
逮捕された実行役の言葉である。
石破総理は2025年1月の施政方針演説で、闇バイト問題について、「匿名・流動型犯罪グループ」に対する「仮装身分捜査等」による検挙の徹底などと述べている。また、自民党は闇バイト強盗対策として、防犯カメラ設置の補助などを打ち出している。だが、本気で闇バイトをなくしたいのであれば、もっとも手っ取り早いのはマトモな「貧困対策」をすることだ。
しかし、自民党政権はこの30年、根本的な対策には決して手をつけず、小手先のことばかり繰り返してきた。その結果、日本は「30年間、賃金が上がらなかった唯一の先進国」となり、韓国に平均賃金を抜かれ、GDPを中国、ドイツに抜かれた。
それだけではない。「第三次ベビーブームの担い手」と期待されていたロスジェネを放置した結果、少子化は加速し、未婚率は上昇。
「若者は家も車も買わない」と言われはじめた頃の若者も今や50代。雇用を安定させる方向に舵を切れば多くの問題は改善に向かったと誰もがわかっているのに、そこには決して手をつけなかった。その30年の無策のツケを、多くの人が時に人生を台無しにしながら支払わされているというのが実態だ。
すでにいろいろなことが手遅れだ。しかし、誤りを認めて今からでも方向転換すれば、被害は減らせる。
どうか「失われた30年」を「40年」にしないでほしい。
今、祈るように思っている。
関連:消費されない言葉を!――貧困の現場からの模索(雨宮処凛)