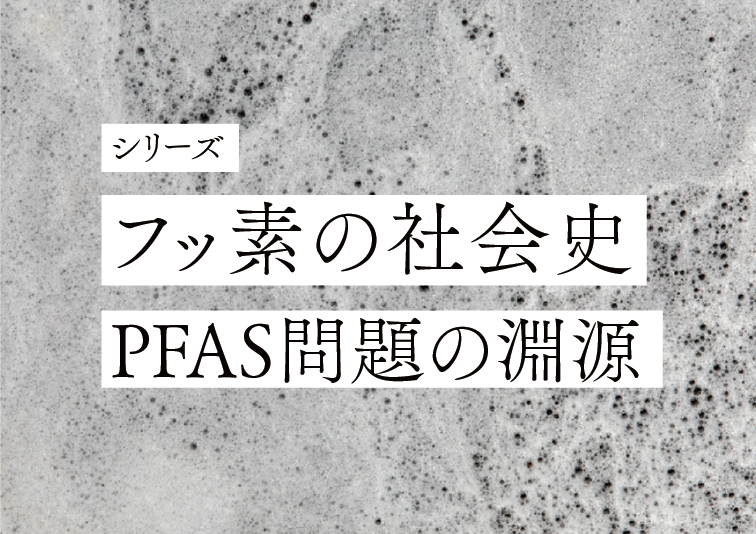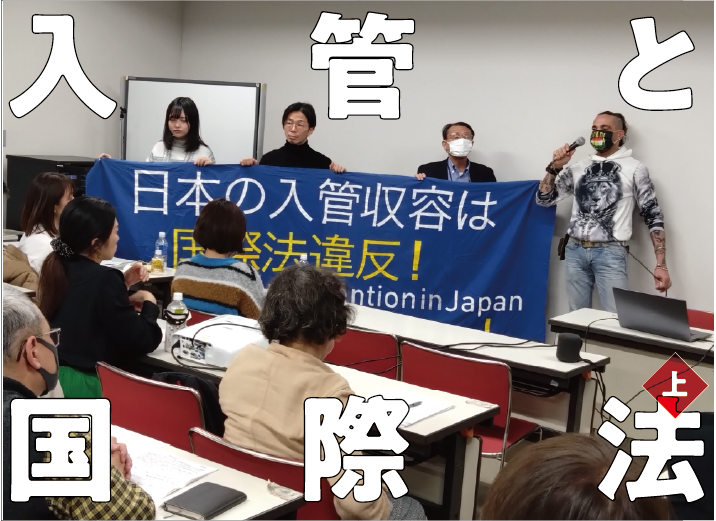二つの相反する流れ
近年、出入国管理および難民認定法に関し、大きな改正が相次いでいる。
まず2020年、特定技能制度が導入された。非熟練労働者については、古くは非正規滞在者、最近では国際貢献が目的のはずの「技能実習」や、勉学を目的に滞在するはずの「留学」の在留資格で在留する外国人の労働に頼る、「バックドア」や「サイドドア」からの受入れが続いてきた。それが特定技能制度の導入により、「フロントドア」からの受入れがついになされるようになったと評された。
昨年には激しい議論の末、難民と収容について大きな改正がなされた。この改正入管法により、一定の難民申請者を申請中でも送還できる制度が導入され、在留資格を持たない者が収容所外で生活するには、原則として、条件違反をしていないかを監視する民間人(監理人)の設置が必須とされた。
さらに今年、人権が保護されないなどとして長く批判されてきた技能実習制度に代わり、「育成就労制度」がついに導入されることとなった。その内実は看板の架け替えに過ぎないという批判がなされているが、それだけでなく、政府はこの制度の導入を口実として、新たに、永住資格の取消制度を導入しようとしている。
これらの動きは一見すれば、外国籍者の受入れ拡大の方向(特定技能や育成就労制度の導入)と、締め出す方向(難民や収容をめぐる改正や永住資格取消制度の導入)という、二つの相反する流れがあるように見える。これらの動きに共通項はあるのだろうか。
日本に移民はいない?
日本では、日本国籍を持たない者については、「外国人」という呼び方が長く使われてきた。しかしながら、外国人、という呼び方は、旅行者も永住者も在日三世四世もすべてひとくくりにする。また、あくまでも、日本の外の人という排外的なニュアンスもある。そのため、単なる旅行者でなく日本に住んでいる外国籍者を指すには、「移民」という言葉が使われるべきではないかと言われるようになっている。
他方、政治の世界ではまったくそれとは別の考え方がとられている。2016年、自由民主党政務調査会労働力確保に関する特命委員会は、「『移民』とは、入国の時点でいわゆる永住権を有する者であり、就労目的の在留資格による受入れは『移民』に当たらない」とした。しかし、入管法7条1項2号では、上陸の際に申請できる在留資格から、永住者が明文で除外されている。つまり、入国時点で永住権を有する者というのは入管法上、存在しない。この定義にしたがえば、現在、日本には300万人を超える外国籍者がいるにもかかわらず、結局、日本には移民はいないということになる。
「移民」(immigrants)という言葉には、国際的に統一した定義はないものの、国連では、「少なくとも1年(12カ月)の間、通常居住する国以外の国に移住し、目的地が事実上その人の新たな通常居住国となる人」との定義が用いられることが多い。このことからすれば、日本政府によるその定義は異常というほかない。
今年5月2日、米バイデン大統領は、中国やインドと並んで、日本は外国人嫌いで移民を望んでいない、と発言した。外国籍者が多く住むにもかかわらず、日本に移民はいない、と言い張る日本の姿勢を考えれば、バイデン氏の指摘が誤りだとはとうてい言えないだろう。