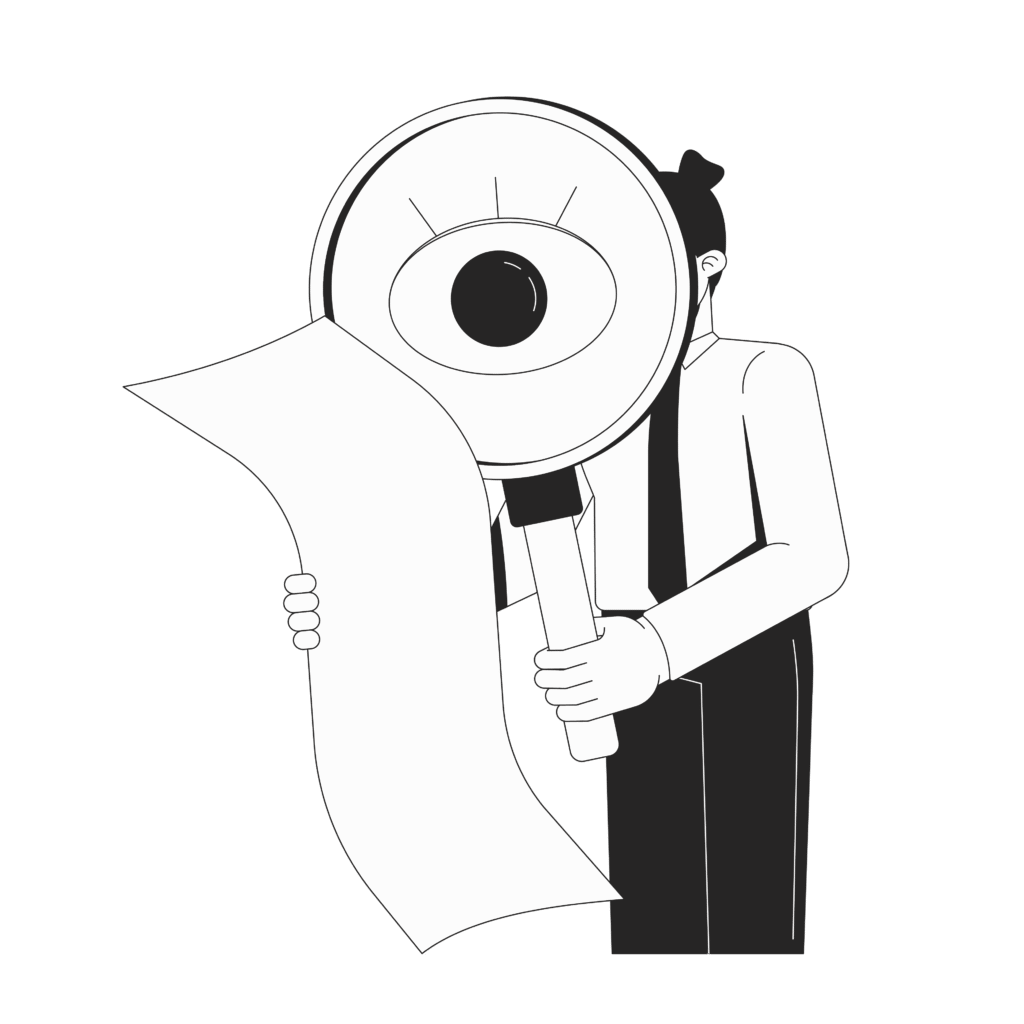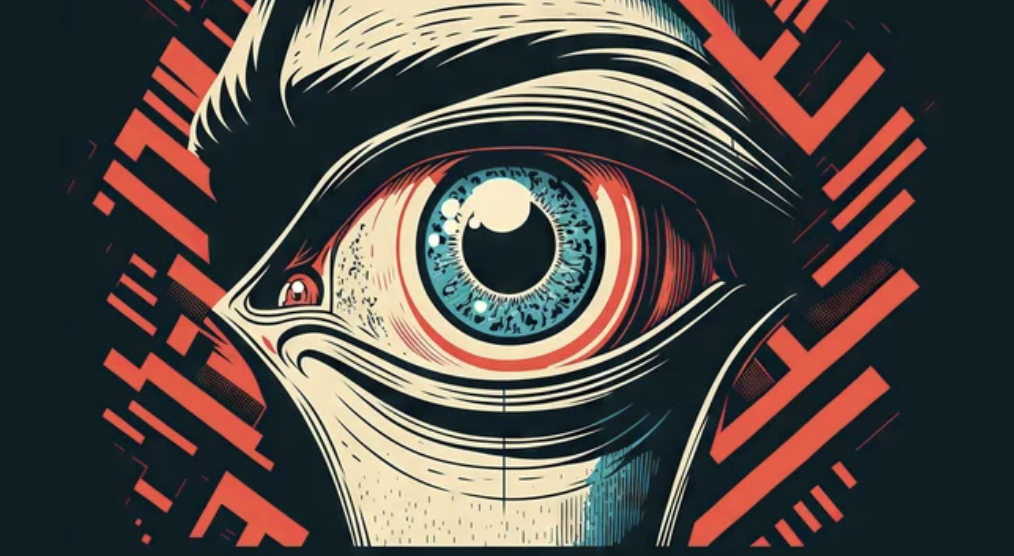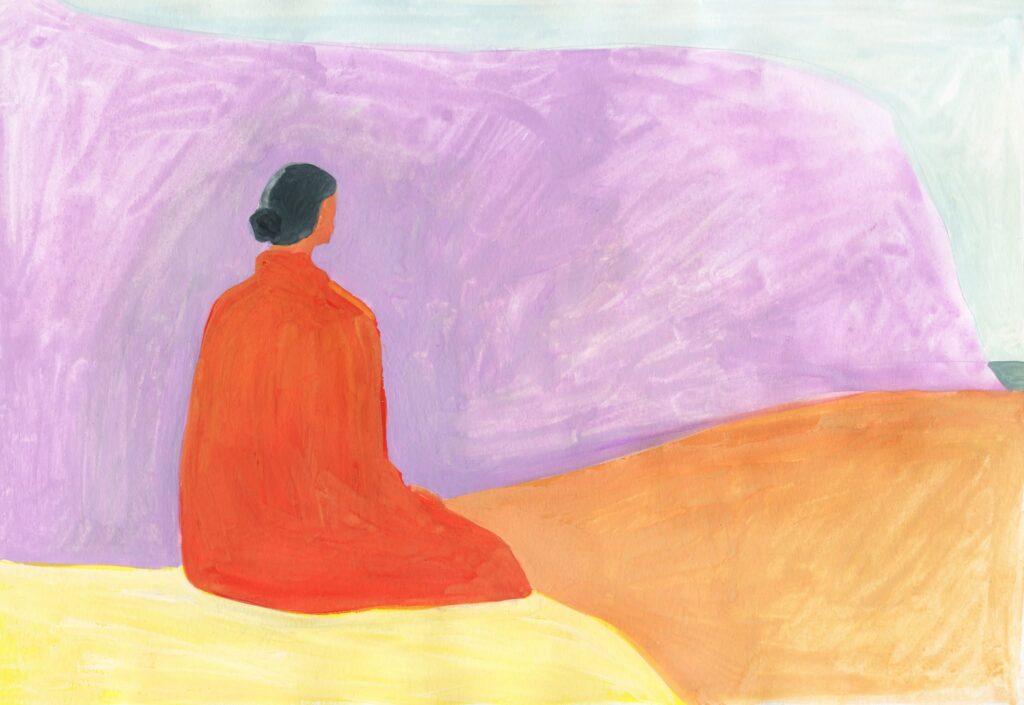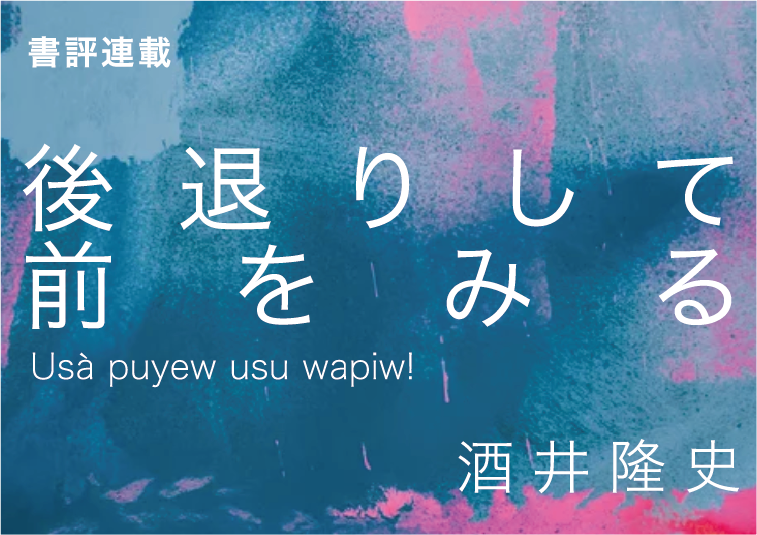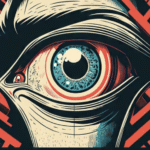青木 理(あおき・おさむ)
フリージャーナリスト。1966年長野県生まれ。1990年共同通信社に入社。公安担当記者としてオウム真理教事件などを取材。著書に『日本の公安警察』(講談社現代新書)、『時代の反逆者たち』(河出書房新社)など。
石井 暁(いしい・ぎょう)
ジャーナリスト。1961年8月15日生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。1985年共同通信社入社。現在、編集委員。立命館大学客員教授。1994年から防衛庁(防衛省)を担当。主な著書に『防衛省追及』(地平社)、『自衛隊の闇組織――秘密情報部隊「別班」の正体』(講談社現代新書)。
警察の権力を肥大させる法律
――今年5月に能動的サイバー防御法が国会を通過しました。外国からのサイバー攻撃について、事前にその兆候を察知し、排除するための措置を講じるという内容です。通信の秘密に関わる懸念などから反対の声も出ましたが、野党の多くも賛成して成立してしまいました。今日は、自衛隊と公安警察の動向に詳しいお二人から、こうした動きをめぐってお話をうかがいたいと思います。
石井 能動的サイバー防御法、横文字で〈アクティブ・サイバー・ディフェンス法〉、その頭文字でACD法と呼ばれていますが、この法律をめぐっては、外国からのサイバー攻撃に対して、まずは警察が、そこで手に負えなければ自衛隊も加わって積極的に防御する、と説明されてきましたし、多くのメディアもそう報じています。警察は平時からサイバー空間をパトロールし、おかしな兆候を見つけたら先手を打ってその攻撃元に侵入して「無害化措置」をとる。そして武力攻撃事態ということになれば、自衛隊が前面に出て無害化するということで、サイバー空間ではあるけれども、基本的には安全保障分野の法律だと理解されていることが多いと思います。
しかし、実態はかなり異なるようです。この対談に先立って複数の関係者に取材したところ、たとえばある防衛省幹部は、これは警察の権限を強くするために警察主導でつくられた法律だと言い切っていました。自衛隊は、平時は自分たち(防衛省・自衛隊)を守る。グレーゾーンになったら警察のお手伝いに入る。自衛隊にはその程度の計画しかなく、実態としては警察による警察のための法律だ、と。
青木 今回の能動的サイバー防御法の作成過程や国会審議などで僕が注目していたのは、防衛省・自衛隊と警察のどちらが主導権を握るか、という点でした。結局のところ警察が主導権を握る形になったわけですね。
石井 そのようです。しかも、かなり警察は周到に準備していたといえます。2022年4月には警察庁にサイバー警察局を新設して、その実動部隊として警察庁の関東管区警察局にサイバー特別捜査隊を設置しました。ACD法の成立前の2024年4月にはサイバー特別捜査部に格上げしています。警察庁が皇宮警察本部以外で直接、捜査権とそれを行使する部隊を持つことに道を開いたわけです。すなわち、FBI(米連邦調査局)のような捜査を警察庁ができるようになった。このことの意味は決して小さくありません。
警察の権限には司法警察権と行政警察権という二つがありますが、通常の捜査というのは司法警察権にもとづいて行なわれるので、当然、警察は検察の指揮を受けなくてはなりません。しかし今回のACD法は法的には行政警察権の扱いとされています。つまり、警察が検察の指揮を受けずに強制権を持つということにほかなりません。
青木 同感ですし、さらに危うい面を孕んでいるとさえ言えるでしょう。司法警察権と行政警察権の違いを簡単に補足しておけば、警察の諸活動のうち、犯罪の捜査や被疑者の逮捕といった刑事司法手続きに関する各種権限が司法警察権に属します。当然ながら、被疑者の逮捕にせよ家宅捜索などにせよ、検察の指揮を受けるばかりか、権限の行使にあたっては裁判所の令状が必須です。
一方の行政警察権は、犯罪の予防や公共の安全、治安や秩序の維持などを目的とする諸活動の権限で、たとえば職務質問や泥酔者保護などは典型ですが、裁判所の令状も必要とされない。この両者の違いは、今回の能動的サイバー防御法において最大の問題点になります。
後ほども触れると思いますが、言うまでもなく能動的サイバー防御法は、憲法が保障する「通信の秘密」と真っ向から対立します。石井さんが指摘されたとおり、警察が「平時からサイバー空間をパトロール」し、サイバー攻撃の「兆候」を探知して「先手を打つ」なら、ネット上を行き交う膨大な通信情報を常に監視しておく必要がある。実際、関連法もそれを可能にしています。
一方、「通信の秘密」と対立するという意味では、いわゆる通信傍受法=盗聴法がすでにあって、猛反対を押し切って1999年に成立して以来、対象事件なども大幅に拡大されてきました。この治安法も数々の問題点を孕みますが、それでも司法警察権の範囲にかろうじて収まっています。一応は犯罪捜査のために通信傍受は行なわれ、その際は裁判所の令状も必要なわけですから。
しかし、能動的サイバー防御法は違います。犯罪捜査のためなどではなく、「サイバー攻撃を防御する」という目的のためにネット上の膨大な通信情報を警察が監視・収集し、しかも「常時傍受」までを可能にする。これはとてつもなく大きな転換であり、戦後は比較的抑制されてきた行政警察権を恐ろしく肥大化させるものです。
もう一点、これも石井さんが言及されましたが、おそらくは今回の法成立も睨み、警察庁はすでに独自の捜査権を持った。これも極めて重大な転換です。
日本の警察組織は戦後、全国各地の都道府県警がそれぞれ独立した自治体警察として再出発しました。これは戦前・戦中の極度に中央集権的な警察組織がファッショ体制の尖兵と化した反省や教訓に基づくもので、戦後間もない1954年に警察行政の中央機関として警察庁が発足したものの、基本的にその役割は各都道府県警の指導や調整などにとどめられてきました。
とはいえ、現実には人事や予算などを通じて警察庁を頂点とした中央集権的な色彩は強まり、公安部門は特にそれが顕著ではありましたが、それでも各地の都道府県警はそれぞれの都道府県公安委員会の管理に服し、自治体警察の体裁はかろうじて保たれてきたわけです。
ところが今回、「サイバー防御」という御旗を掲げて警察庁が戦後初めて直接の捜査権を手にした。ある意味では“国家警察の復活”です。と同時に、ネット上を行き交う膨大な通信情報の「常時傍受」まで可能となったわけですから、警察組織の権限と活動範囲がこれだけ大規模に改編・拡大されるのは戦後史に特筆される事態と評しても過言ではないでしょう。
【関連】
【連載】日本の公安警察2025 青木 理(ジャーナリスト)
サイバー防御法案の何が危険なのか 井原 聰(東北大学名誉教授)
ネット監視・サイバー先制攻撃法の危険性 海渡雄一(弁護士)