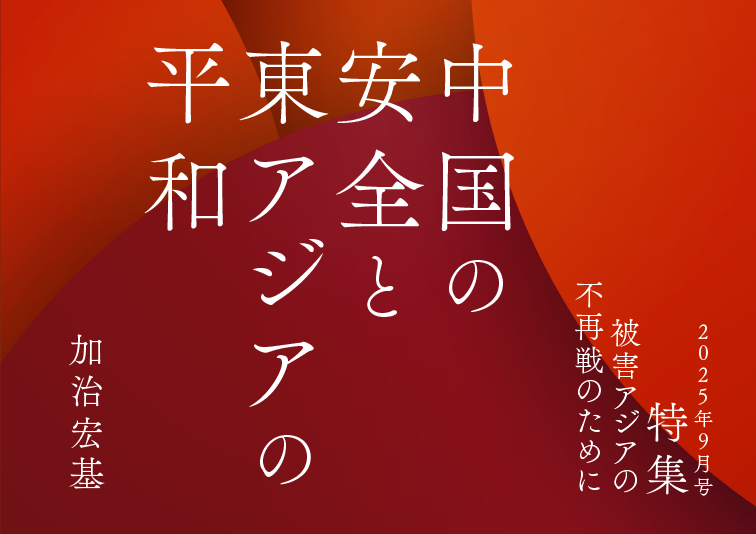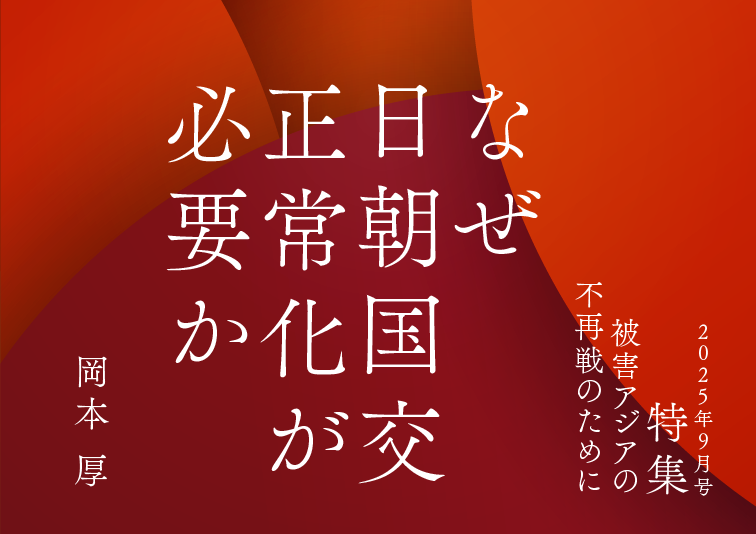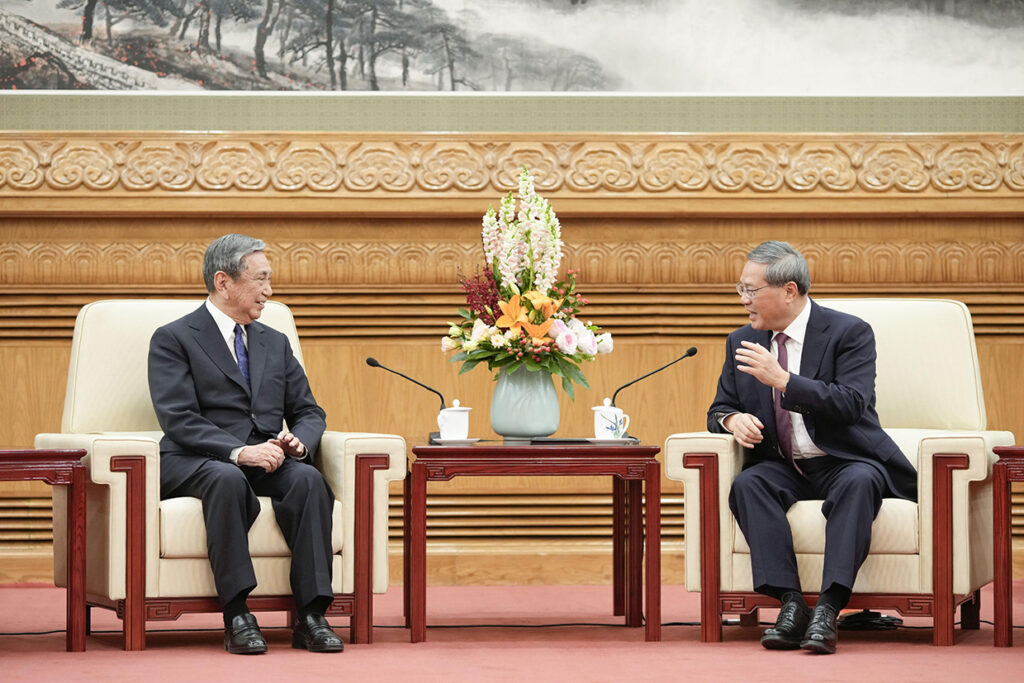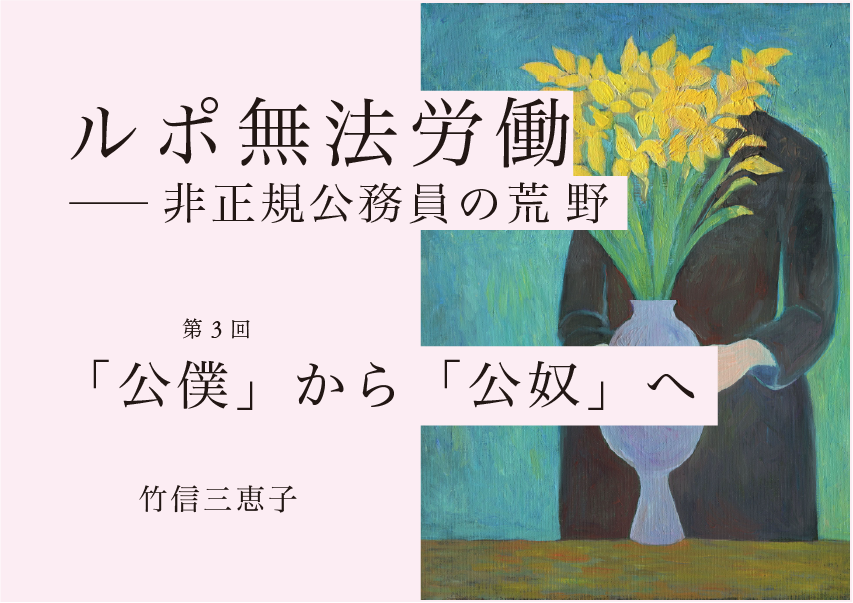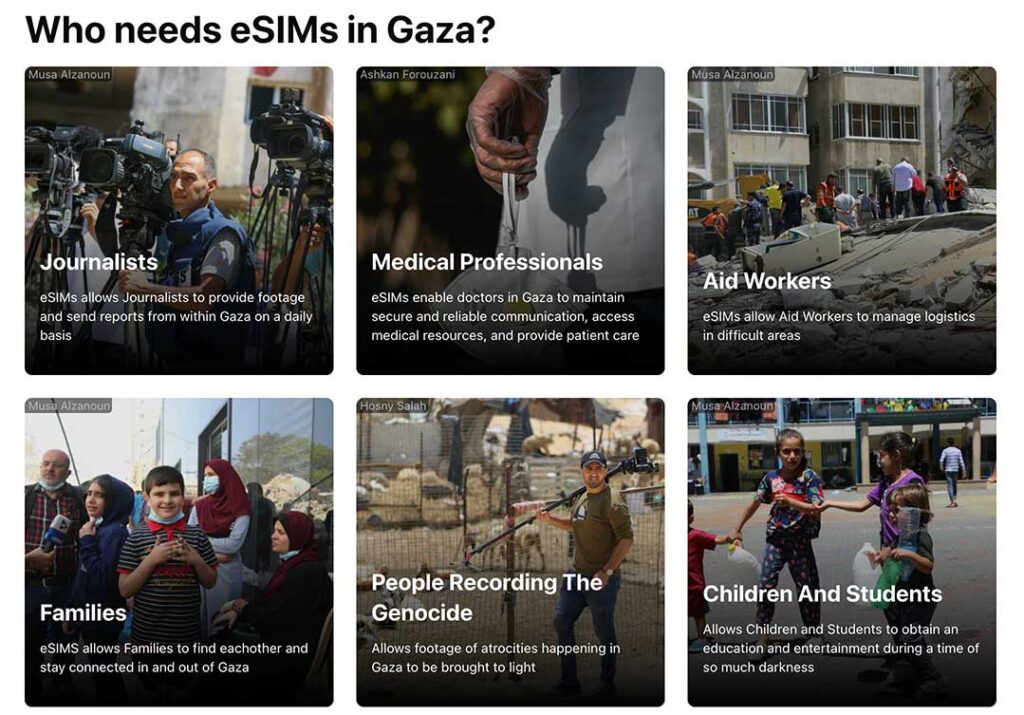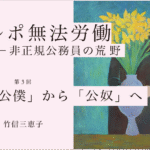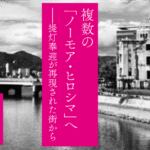特集:東アジアの不再戦のために
国連は、「国際の平和及び安全」を維持することを目的として(憲章第1章第1条)、80年前に創設された。ヴェルサイユ体制の破綻を教訓に構想されたその集団安全保障体制は、米国、ロシア、英国、フランス、そして中国からなる五大国の協調を要諦としてきた。つまり、安保理常任理事国は、自らの権威を維持すべく拒否権の乱発に歯止めをかける自己拘束を同機構の「正義」としたハズである。しかしその実、五大国は国益を優先し、絶対的権能をもって国連の目的と規範を歪曲する政治的恣意性が看取される。
その一角に坐す「中国」は、1971年の第26回国連総会で中華民国から中華人民共和国(以下、特に指定のない限り中国と表記)へと代表権が変更された(国連総会決議A/RES/2758(XXVI))。そして今日、中国が特に東アジアの平和にとって決定的影響を有すことは贅言を俟たない。日本など関係国・地域の私たちにとって、中国の安全保障(中国語で「安全」)観とその政策背景を可能な限り的確に捕捉することが、この地域の平和のあり方を考察し、そのための方策を検討する上で肝要である。
安保理常任理事国の恣意的政治性
2022年2月、ロシアがウクライナへの侵攻を開始するや、安保理は速やかに対ロ制裁について審議を始めた。また同年9月にも、親ロシア派が多数を占めるウクライナ東部地域での「住民投票」は不当かつ無効だとして、ロシアに即時撤退を要求する決議案が安保理に提出、審議された。しかし、両決議案は同国の拒否権により否決された。
安保理常任理事国が国連加盟国を侵攻したことを理由に、あるいは安保理が対ロ制裁を結実し得なかったからといって、「安保理、ひいては国連は制度疲労を来し機能不全に陥った」と結論づけるのは性急に過ぎよう。なぜなら、ロシアに限らず五大国は、幾度となく恣意的政治力によって国連の安全保障体制を翻弄してきたからである。
1999年3月から6月にかけて、セルビア共和国のコソヴォ・メトヒヤ自治州でセルビア人を中心とする連邦軍や民兵組織などの武装勢力による非人道行為を阻止するためとの大義を掲げ、北大西洋条約機構(NATO)は安保理の授権を経ぬまま空爆を強行した。NATOを主導する米英等がロシアと中国の拒否権を懸念し、安保理での審議を回避した結果、国連の枠外で「平和執行」が断行されたのだ。だが安保理は、同作戦が「憲章第7条に明記される軍事的強制措置だった」と事後承認し、コソヴォに関する独立国際委員会による調査報告書「コソヴォ・リポート」(2000年)も、爆撃は平和実現にむけた「違法だが正当」(illegal, yet legitimate)な行為だったと結論づけた。