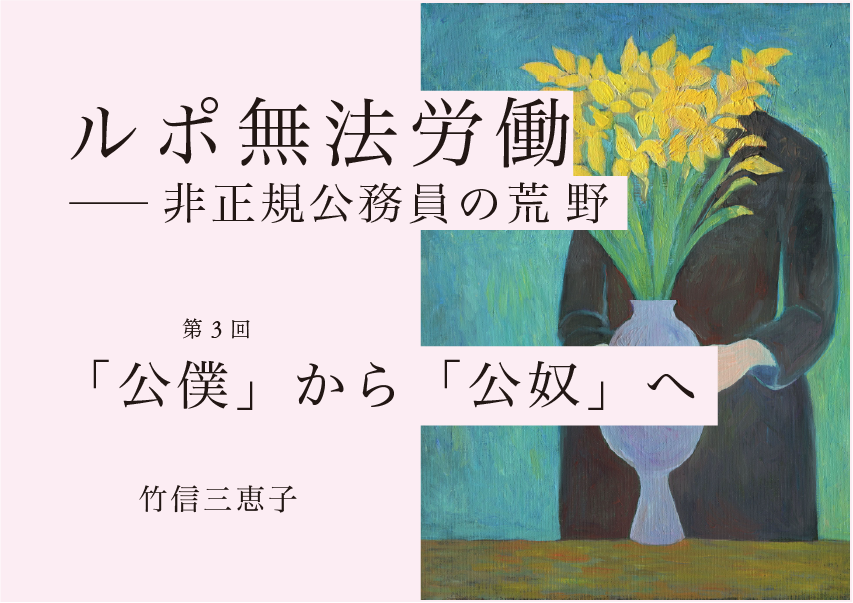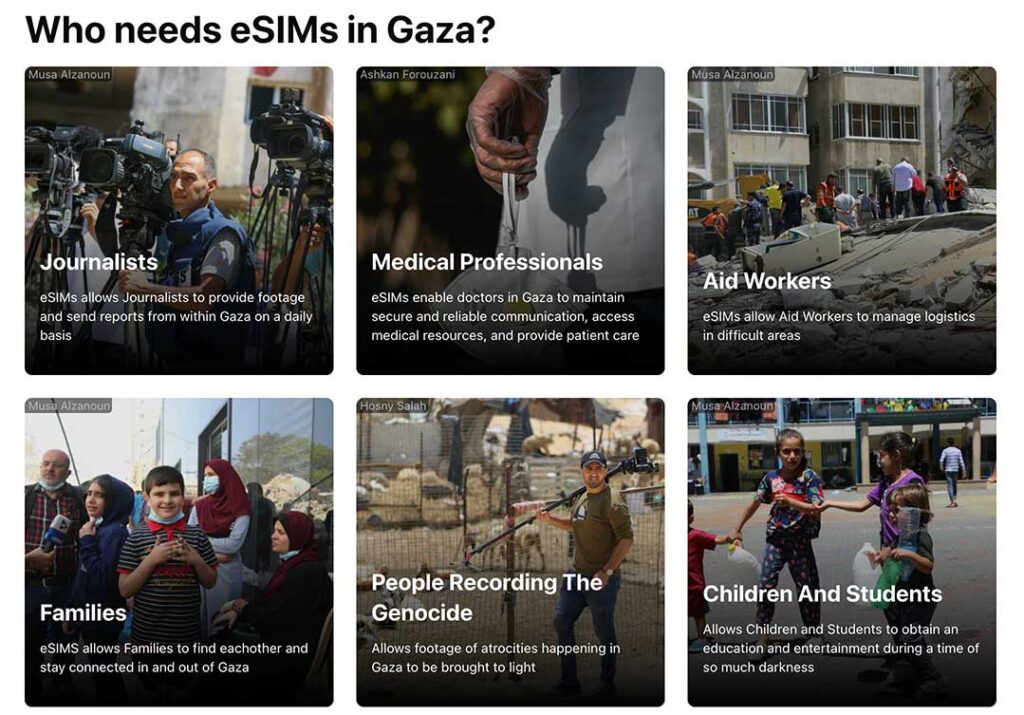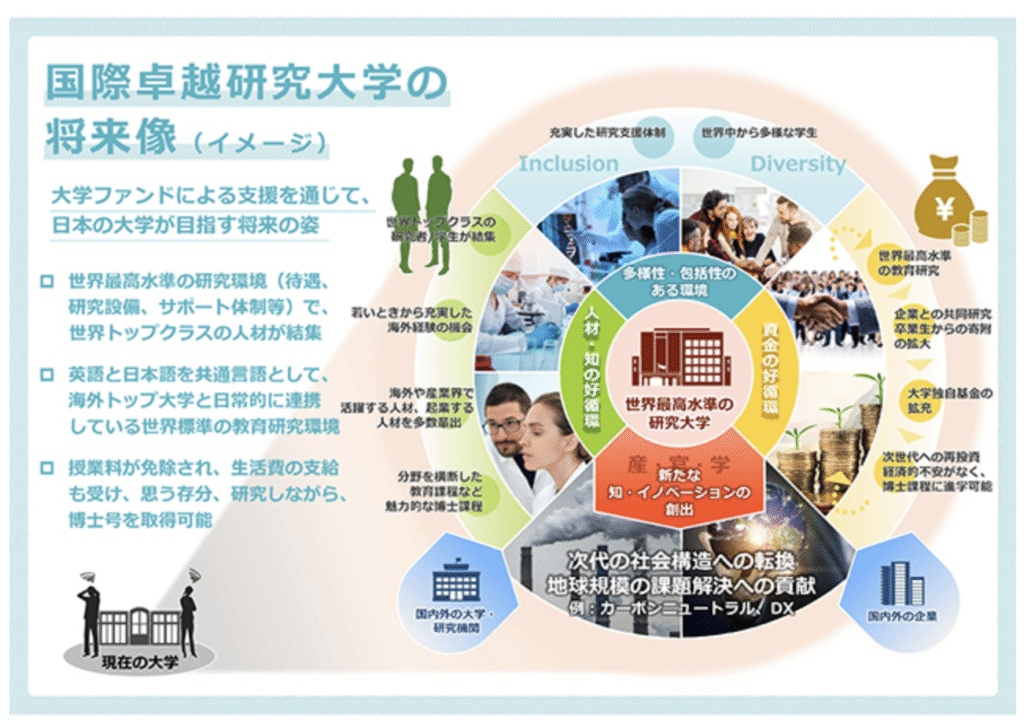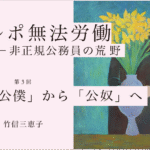再現された「軍都の夜」
広島平和記念資料館には、直視するのがつらい写真や現物が多く展示されている。被爆の実相を表すそれらの展示物。しかし、それとは別の意味で、目を背けたくなるような写真も展示されている。その一つが、1937年12月に広島市内で行なわれたときの写真である。
「南京陥落を祝う提灯行列」と題されたそのパネルには、次のようなキャプションが付いている。
1937年(昭和12年)12月、日本軍は当時の中国の首都南京を占領した。この過程で多数の市民が虐殺され、南京事件や南京大虐殺などと呼ばれている。犠牲者数には様々な推計があり、中国では30万人余りとしている。広島では南京陥落を祝う提灯行列が行われた。
日本軍兵士が南京で、その近郊で、殺戮・略奪・放火・強姦などの暴虐行為を繰り返したことを、当時の広島市民は知らなかっただろう。そのことを含み置いてもなお、他国の首都に侵攻し、武力で占領、つまり暴力で奪い取ったことを臆面もなく祝う広島市民の姿を直視するのはつらい。なぜなら、この日に戦勝を祝っている人の多くが、1945年の原爆による大量殺戮で殺されたに違いないから。
寒い冬の夜、わざわざ提灯を手に持ち外出し、「皇軍」の戦勝を祝っている大勢の市民たちは、日本軍によって踏みにじられた人々のことを想像できていただろうか。そして、その7年8カ月後に、今度は自分たちが無残に殺されることを予想していただろうか。
『軍都廣島 「廣島」と「ヒロシマ」を考える』(清水章宏・橋本和正著、一粒の麦社)によると、広島における戦勝祝賀行事は日清戦争のときに始まったという。「大本営が広島に設置されたことにより、戦争の情報は広島にすぐ伝えられます。戦勝の報道が届くたびに、広島県や広島市は市民に国旗・提灯などの掲揚を指示し、祝賀行事に市民を動員しました」。戦前に全国各地で行なわれた戦勝祝賀行事は、まず広島市で始まり、「お手本」として波及したのである。
そのような苦々しい「提灯行列」の歴史を経験したはずの広島で、しかも原爆ドームに近いひろしまゲートパークで、今年6月19日、天皇・皇后の来訪を歓迎する「提灯奉迎」が行なわれた。約5000人が集まり、天皇・皇后は、宿泊するホテルの窓越しに手を振った。
どうしてそんなことを思いつけるのだろう。
今回の提灯奉迎の計画が報道されたとき、最初に抱いた疑問だ。この人たちは「提灯行列」にともなう苦々しい気持ちを共有していないのか。そもそも広島における「提灯行列」の歴史すら知らないのか。それとも知ったうえで、それを愚かしい歴史とは感じていないのか。
これが、「平和都市・広島」の現在の到達点なのか。
この提灯奉迎を企画した日本会議など極右勢力を、まず批判する必要がある。しかしそれで充分だろうか。このような行事が大きな反対運動も起こらず実施できてしまう土壌が、「平和都市・広島」にあるのではないか。
だとするならば、今からでも「平和都市・広島」の土壌を耕しなおさなければならない。戦勝を祝う提灯行列の歴史をはじめ、「8月5日までの広島」の歴史を深く共有し、「提灯奉迎」という発想を拒む歴史意識と共通理解が広島の内外で形成されなければならないはずだ。