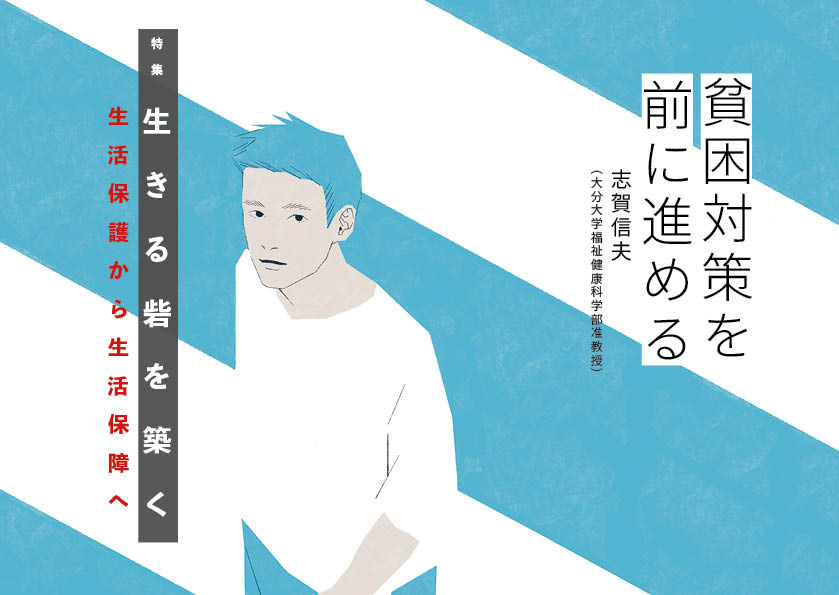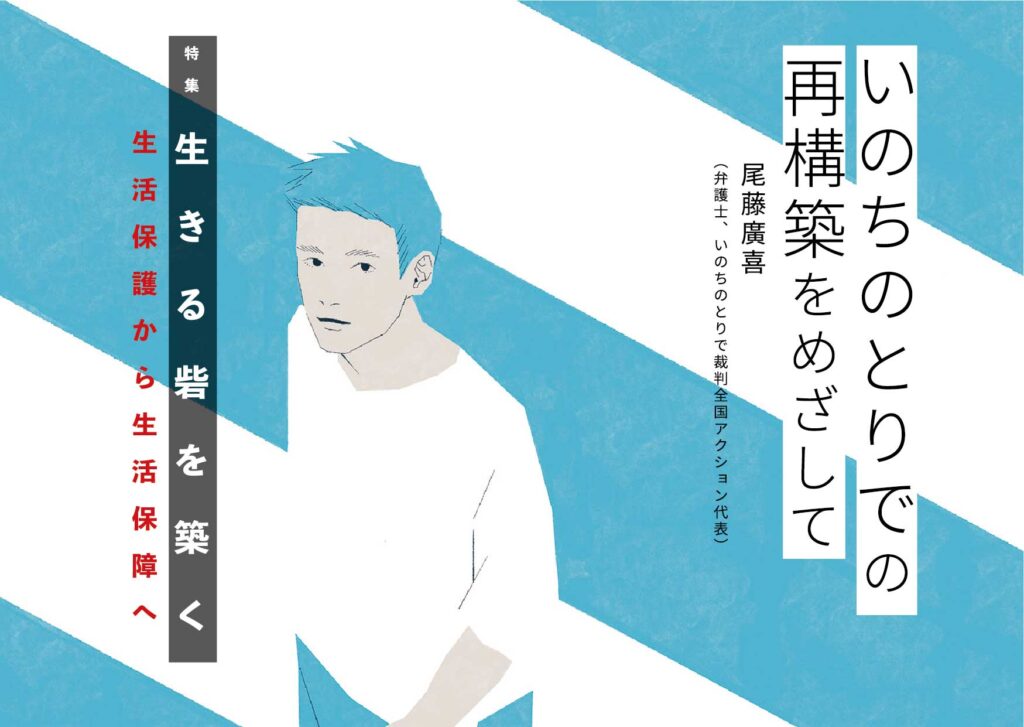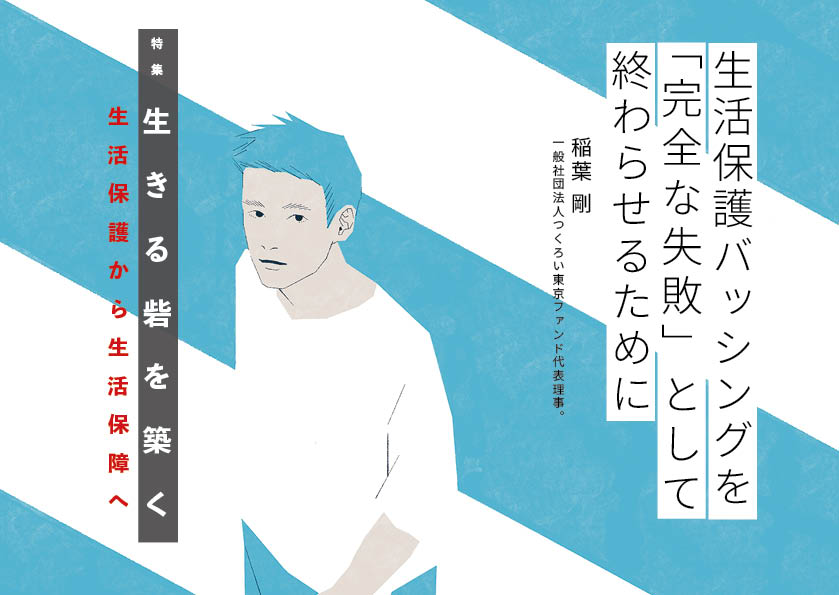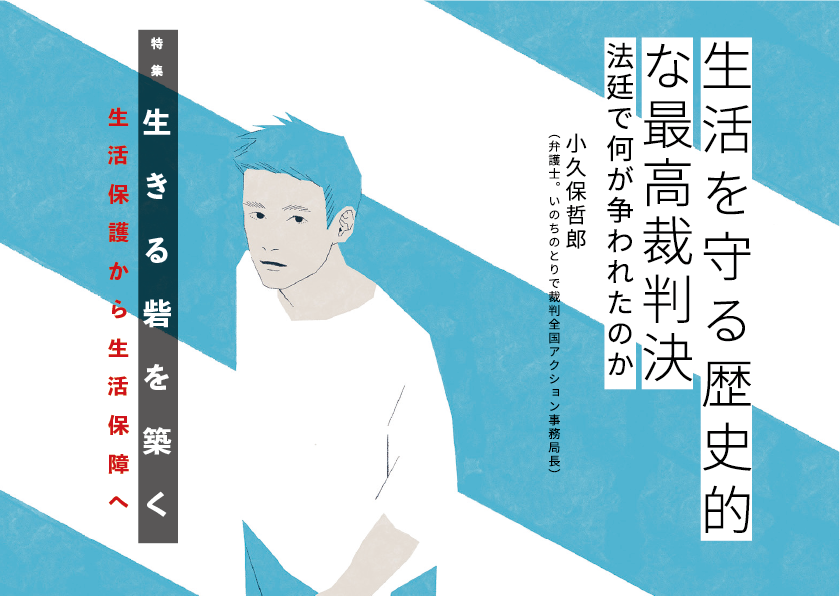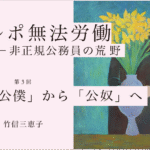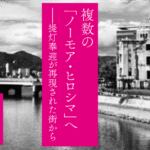1 はじめに――人間の選別と「人種化」
このたびの「いのちのとりで裁判」における議論の焦点の1つは、日本における貧困対策の最後の「とりで」である生活保護制度が「健康で文化的な最低限度の生活」を果たして保障しているのかどうかということであった。
結論的にいえば、もともと「最後のセーフティネット」と呼ぶには低すぎる生活保護制度の生活扶助基準が2013年からさらに段階的に引下げられたことで、制度利用者の生活実態はより厳しいものとなり、それはもはや「節約」の領域にはなく「抑圧」の強制であるというべきものになってしまった。これは制度を通じた暴力である。
生活保護に関するプロジェクトチーム座長を務めていた世耕弘成参議院議員(当時)は、2012年7月の『週刊東洋経済』のインタビューにおいて、生活保護制度の利用者には「フルスペックの人権を認めるべきではない」(https://toyokeizai.net/articles/-/9611?display=b (閲覧日:2025年7月7日))という立場を明確にした。これは二級市民をつくるという発想に他ならない。二級市民の創出は、ある人間集団とその他の人間集団のあいだに優先・劣後関係を創出するということでもある。その優先・劣後関係を創出し、維持するための機能をもつ区別実践(差別実践ともいえる)を私は「人種化」と呼びたい。ここで「差別」ではなく、あえて「人種化」という表現を使用するのは、二級市民化の主張やこれに類する諸言説に、貧困それ自体または貧困の原因を特定の人間集団の生来の属性とみなす理解が内在しているからである。二級市民化を主張する諸言説がこうした理解に基づいているからこそ、貧困を強制された人びとに対し、支援というよりも(ときには「支援」の名を借りて)、監視・管理や排除・放逐を実践していくのである。
「人種が、生得的で本質的な性質に基づく、他と区別される人間集団だとすれば、そのようなものはないというのは、今日研究者の間で合意されていることである」(平野 2022, 3-4)。つまり、人間に優劣をつけるための「人種」は社会的な「でっちあげ」以外に根拠がないのである。私たちが生きている資本主義社会では、資本に奉仕できない者が周縁化されたり、排除・放逐されたりするということが起きている。別の表現をすれば、この社会は放置しておけばお金を稼ぐことがうまい人間とそうでない人間の選別、優先・劣後関係や包摂‐周辺化‐排除の関係を絶えず形成してしまうということである。資本主義社会は、こうした本質的性格を有しているのである。
このたびの保護基準引下げは、前述した「人種化」を伴う100年以上も前の貧困概念への逆行だということを強調しておきたい。この100年以上も前の貧困概念への逆行は、貧困を極めて限定的な理解に閉じ込めてしまうだけでなく、戦後の歴史のなかで次第に標準化してきた人権思想と矛盾するものであることは強調しておきたい。世界中で暫定的に合意されている社会正義の考え方の方向とも全く一致しない。
以上を踏まえて設定したい本稿のキーワードは、「健康で文化的な最低限度の生活」と「差別/人種化」である。これらのキーワードにそくして、貧困対策としての生活保護のこれまでとこれからを考えていきたい。
本稿の全体の流れを説明しておこう。本節に続く第2節において、「貧困」という概念の本質的特徴について簡単に説明する。これを踏まえ、第3節では生活保護基準引下げによって、最低生活保障が動物的生存の保障に限定されてしまったのだということを論じる。これは、保護基準の引下げそれ自体が現代の人権をめぐる理念と相容れないということの説明でもある。第4節においてこの引下げが差別の是認または「人種化」の実践であったこと、第5節において今後の展望について論じていく。