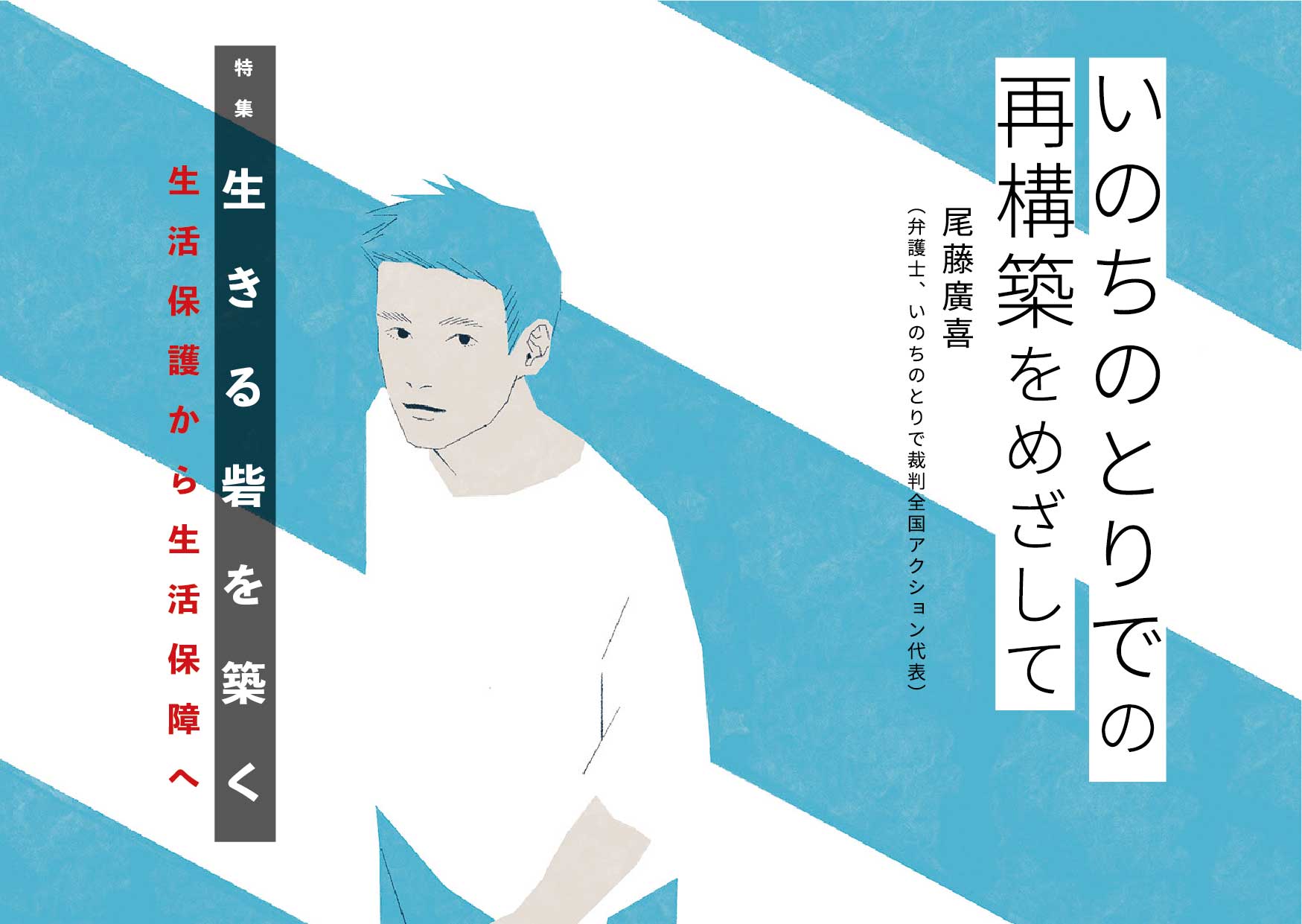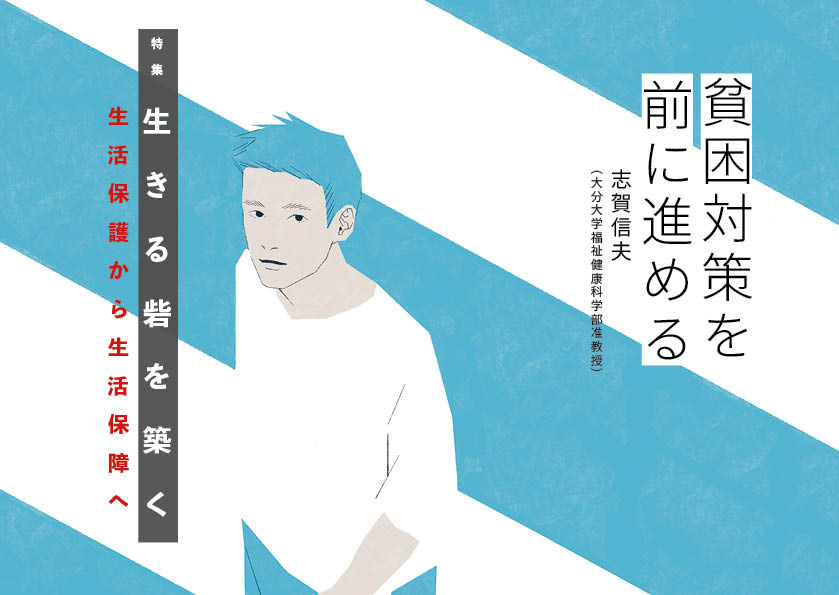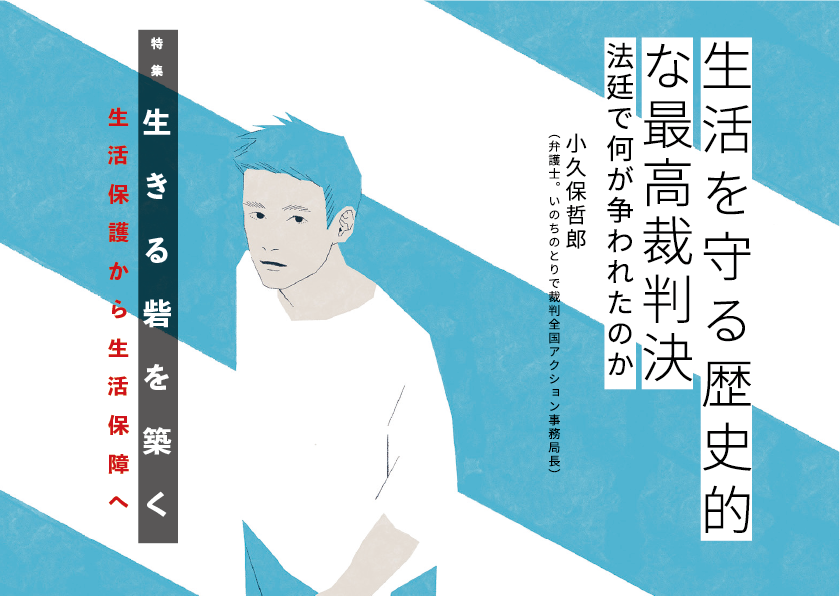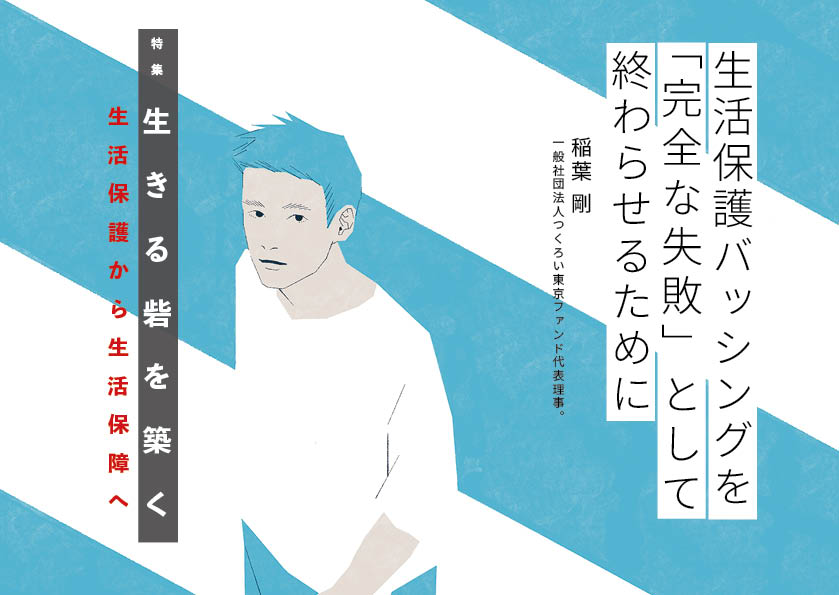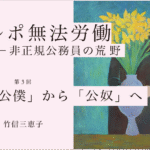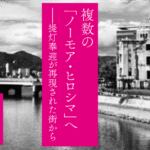歴史に残る最高裁判決
2025年6月27日午後3時、最高裁判所第三小法廷は、「いのちのとりで裁判」(生活保護基準引下げ処分取消し請求訴訟)の大阪地裁分と名古屋地裁分の上告審判決を言い渡した。宇賀克也裁判長は、まず、大阪地裁分の主文から読み上げを始めた。
「主文 一 原判決主文第一項及び第二項のうち、上告人〇〇〇ら及び上告人〇〇らに関する部分を破棄し……」
勝ったと確信した。
判決内容は、原告側の損害賠償請求を認めなかったものの、「厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法」として、2013年の生活保護基準引下げを全員一致で取り消した。原告勝訴の判決だった。
これまで生活保護基準をめぐってその額の違憲・違法性が争われた裁判としては1950年代から60年代にかけて争われた朝日訴訟、2005年から2015年まで老齢加算、母子加算の削減廃止を争った生存権裁判があったが、基準の額自体の生活保護法(以下「法」という。)違反が最高裁で認められたのは、生活保護裁判史上初めてのことであり、まさに歴史的な判決といえる。
判決の後は、ともに判決を聞いた大阪訴訟の原告小寺アイ子さん、小久保哲郎弁護士らと喜びを分け合った。私の隣に座っていた、いつも冷静沈着、緻密な理論派として知られ、後に述べる違法性の判断枠組論を担当した富山の伊藤建弁護士は、「大阪高裁で負けたあと、どんなに苦しかったか」と涙を流して絶句していた。
最高裁の書記官からは、すべての傍聴人が退廷してから原告、弁護団も退廷するように言われていたため、入廷した者と特別傍聴が認められた者は、「いのちのとりで裁判」らしく、全員でひとかたまりとなって最高裁を出ようと話し合い、杖をつきながらゆっくりとしか歩けない小寺さんのペースに合わせて裁判所の正門から出た。
「旗だし」は、全国の裁判所をめぐってきた8つの「逆転勝訴」「司法は生きていた」などの8つの勝訴の旗がすべて集まり、そこに、大阪の亡くなられた原告団長、堰立夫(せきたつお)さんがいつも言われていた「だまってへんでこれからも」の旗が加わった。名古屋弁護団団長の内河恵一弁護士も私も担当した、喜びの爆発した「旗だし」となった。
仕組まれた「引き下げ」
このように、最高裁で厳しく違法性が指摘された2013年から3年間に亘る生活保護基準の引き下げ(以下「2013年引き下げ」という。)は、いったいどのような経過でなされたのだろうか。
仕掛けは計画的だった。
そして、それは「生活保護バッシング」から始まった。