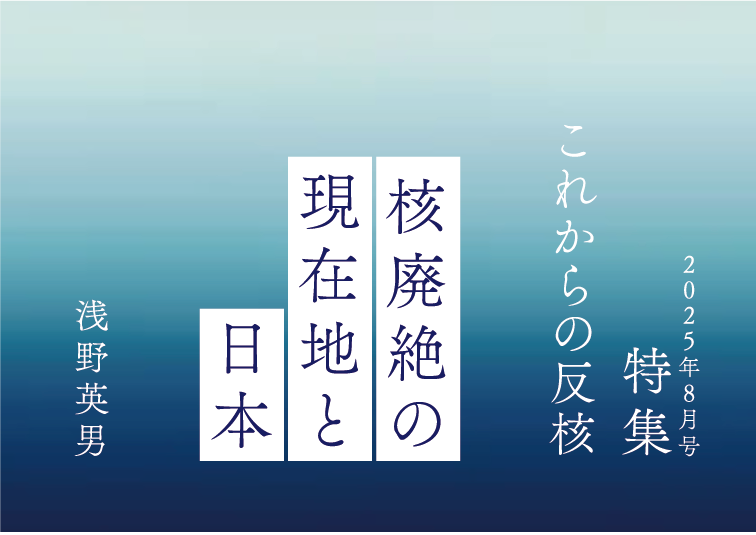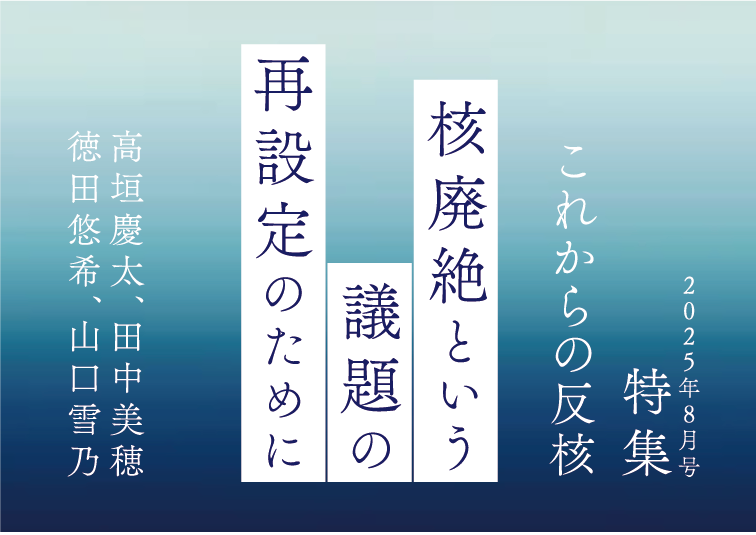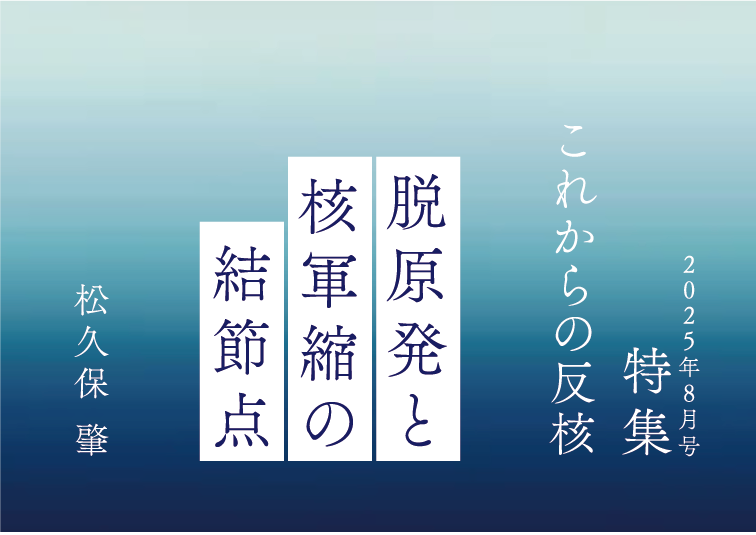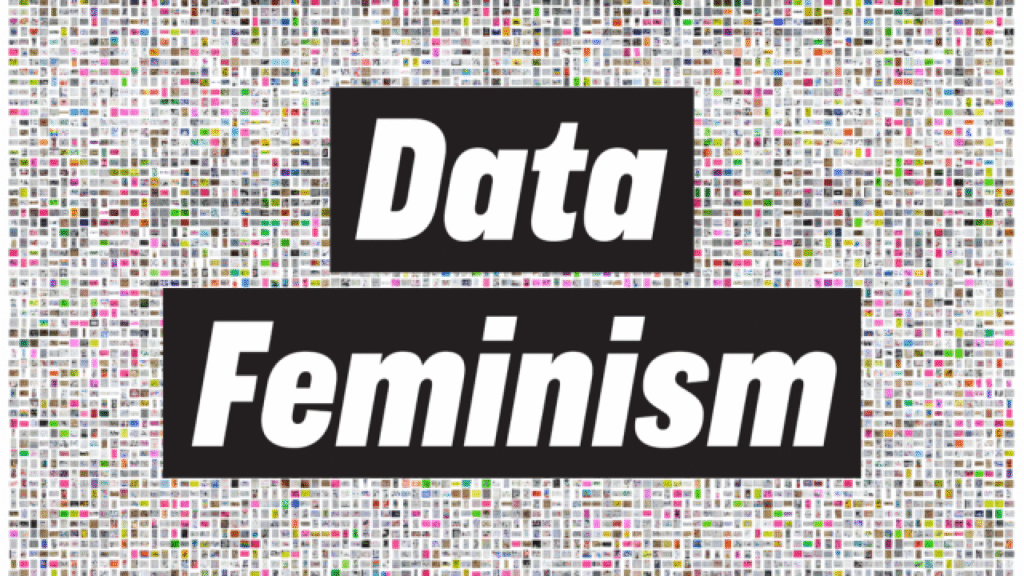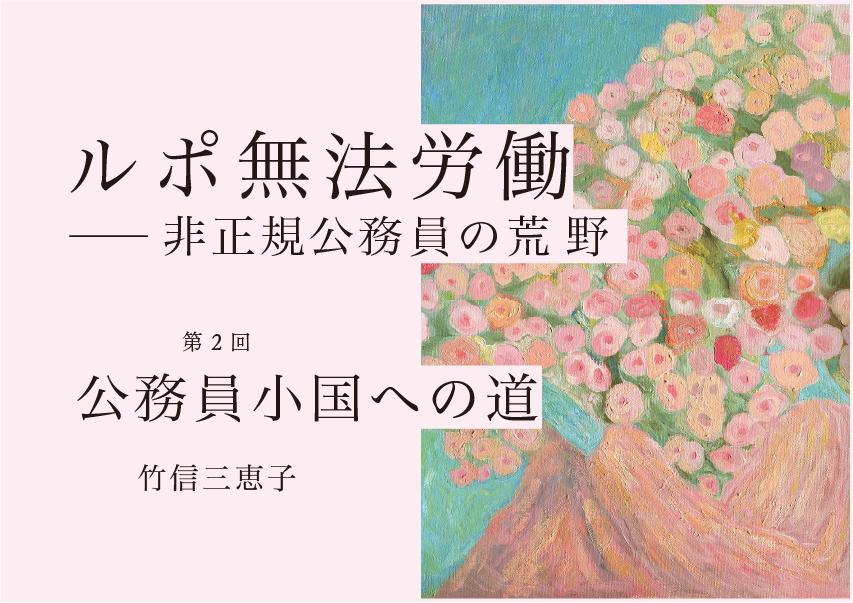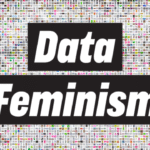【2025年8月号特集】これからの反核
問われる核抑止――核廃絶は「現実的な」選択肢である
本年3月、核兵器禁止条約(TPNW)第3回締約国会議が開催された。今回の締約国会議で焦点の1つとなったのは「核抑止論の問い直し」であった。会議に提出された「安全保障上の懸念に関する協議プロセス」の報告書(注1)は、以下のような点を挙げて、核保有国と同盟国が自らの安全保障にとって必要だとする核抑止論を批判した。
・核兵器が、核保有国が関与する戦争や非核保有国による核保有国への武力攻撃を抑止できなかった事例が存在すること。
・核抑止論では、政治指導者が「合理的」に行動することが想定されている。しかし、現実には、彼ら彼女らは時間的制約を受けながら、不完全かつ誤解している可能性のある情報に基づいて決定を下さなければならない。そこに誤算や誤解、判断ミスが必ずないとは言い切れないこと。
・ 核抑止は人間が設計した機械とプロセスに依存するが、そこから事故や技術的なエラーを完全に排除することはできないこと。
・歴史には、核戦争の手前(ニアミス)を運よく回避できただけの「幸運だった事例」がいくつも存在する。核抑止論者は、こうした運(luck)の存在を無視あるいは過小評価していること。そして、過去の幸運は、将来も幸運であることを保証するわけではないこと。
・特定の危機において核抑止が「成功」したように見えたとしても、それが次の異なる状況下でも機能するという保証にはならないこと。
これらを踏まえて報告書は、核抑止について「有効であるという確証も、有効でないという確証もない。しかし、核抑止が失敗する可能性があることは疑いの余地がない」とした。
むしろ核抑止が失敗する可能性は、核保有国による軍事侵攻や大国間の対立、新たな軍事技術の台頭などによって、かつてなく高まっている。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、「地政学的緊張や不信によって、核戦争のリスクがこの数十年で最高レベルにまで悪化している」と述べている。
このように不確実な状況にある核抑止に対して、私たちが確実に分かっていることがある。それは、核兵器がひとたび使用されれば、壊滅的かつ非人道的な被害が地球規模でもたらされることである。
TPNW第3回締約国会議で採択された政治宣言は、こうした核兵器の人道上の結末を新たな科学的研究が「科学的証拠によって裏付け」ており、しかも「核兵器の影響が、これまで理解されていたよりも深刻で、連鎖的で、長期的で、複雑である」ことを明らかにしていると強調した。
つまり、核抑止は不確実なものであるにもかかわらず、その失敗は一度たりとも許されない。そうであれば、問われるべきは、前述の報告書が指摘するように、「『核兵器が抑止できるか』ではなく、『核兵器が常に抑止できるという確実性はあるか』にある」(強調筆者)といえよう。
そのように考えると、核抑止に依存し続けるのではなく、むしろ核兵器を廃絶することが安全保障上きわめて現実的な選択肢として浮かび上がってくる。目下の国際情勢と核戦争リスクの高まりに照らせば、その実現は急務ですらある。日本政府が立ち上げた「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議も、「すべての国は、核兵器への依存から脱却するために努力し続けなければならない。核抑止が安全保障の最終的な形態であるとこれまで示されたことはなく、またこれからもそうあってはならない」と提言した通りである。そして、米国の「核の傘」に依存する日本にも、その主たる責務があることを忘れてはならない。