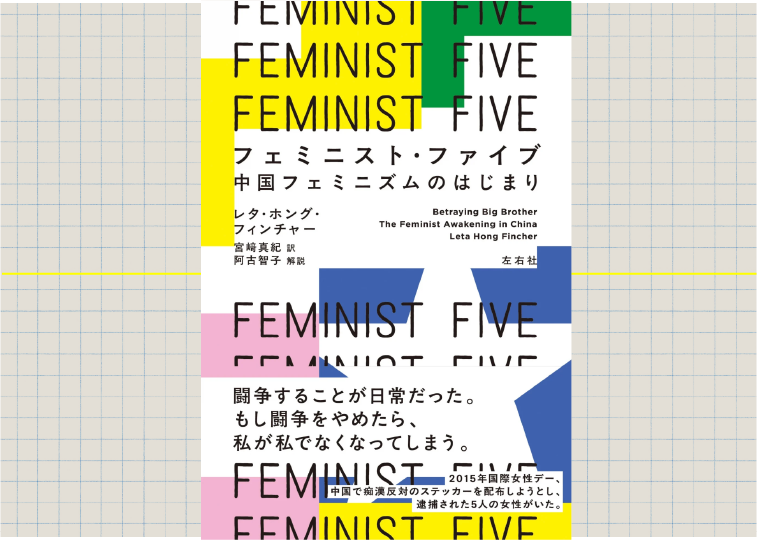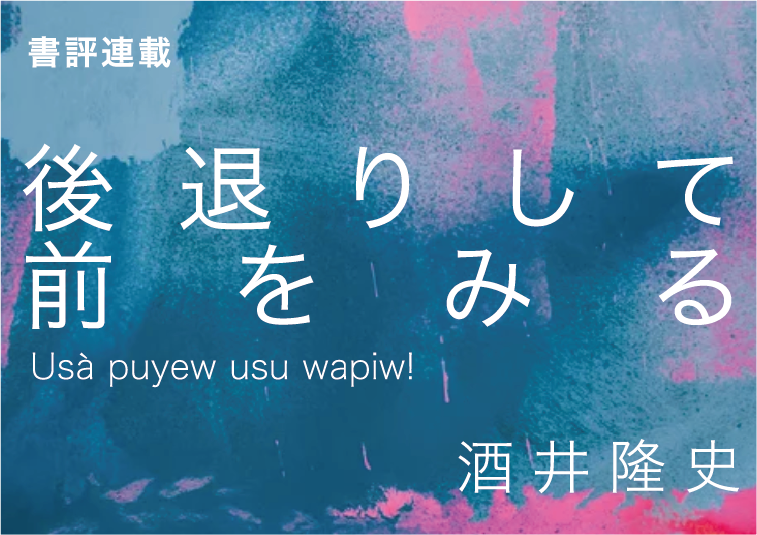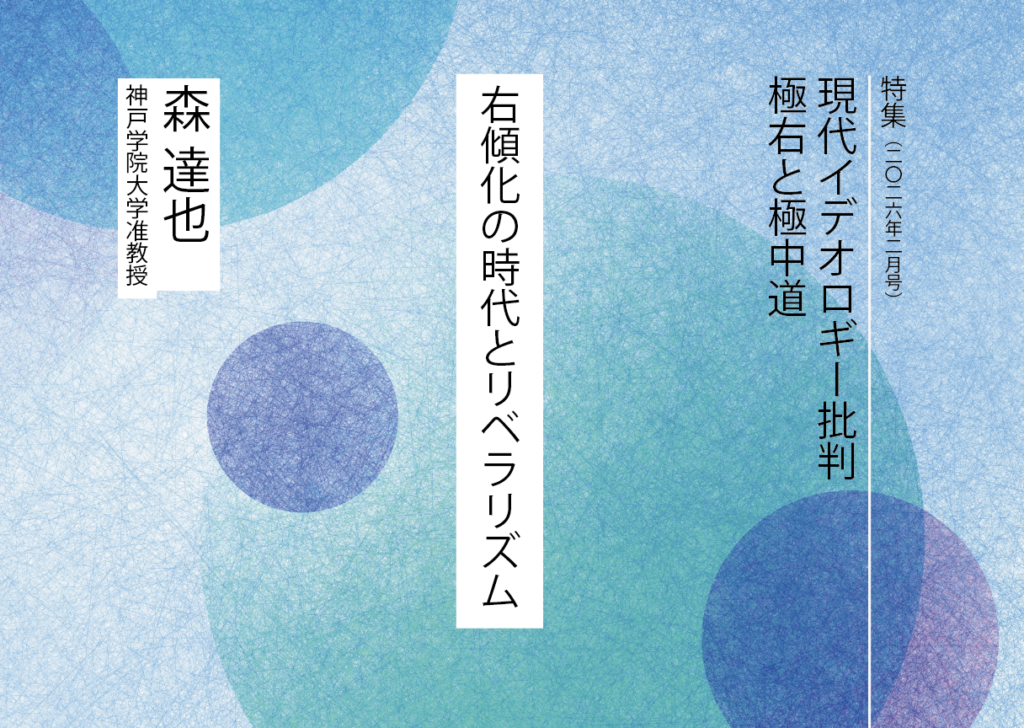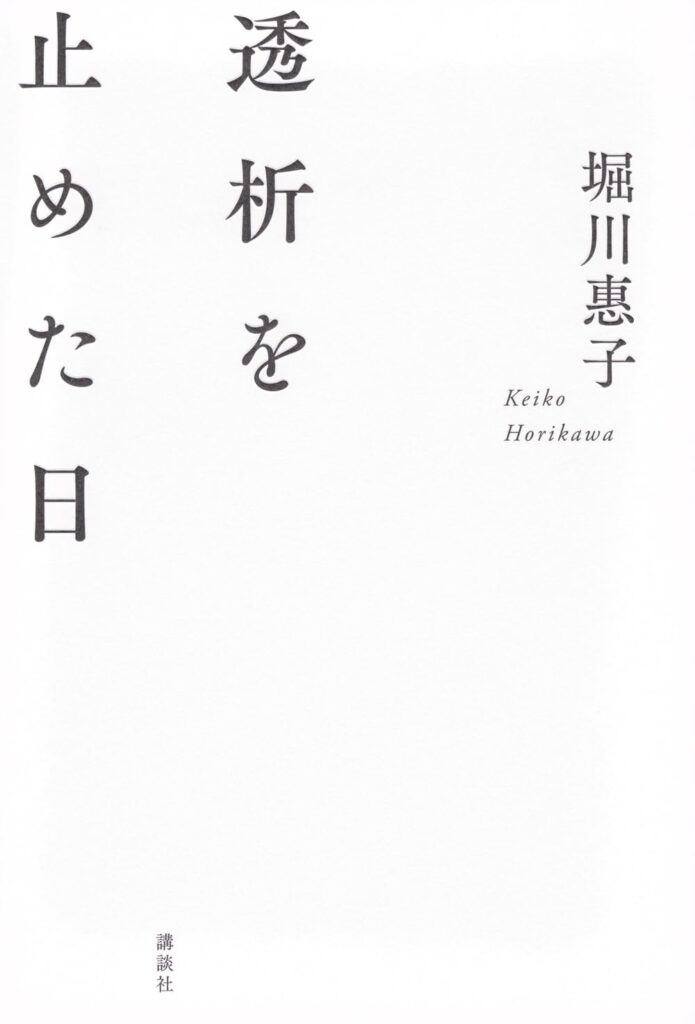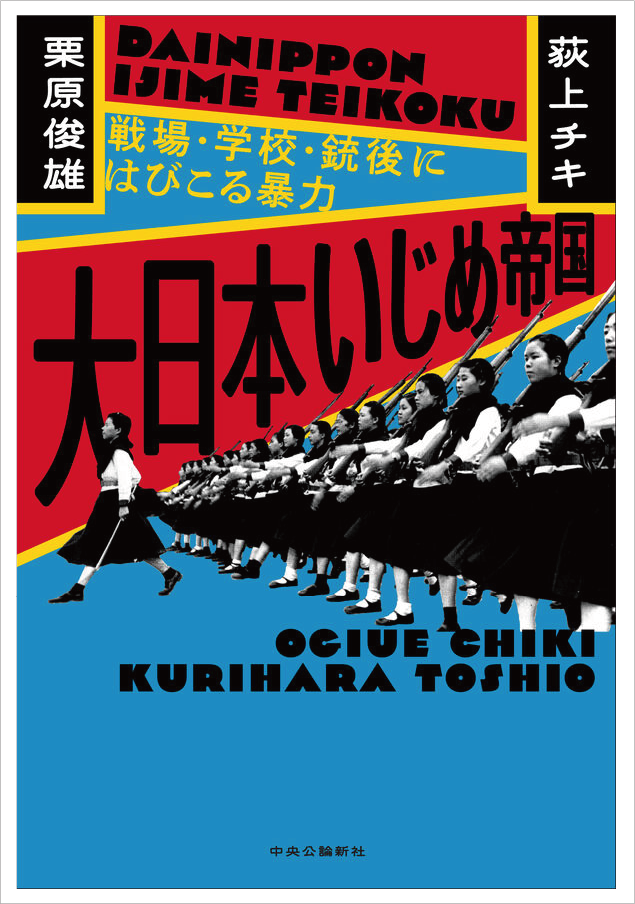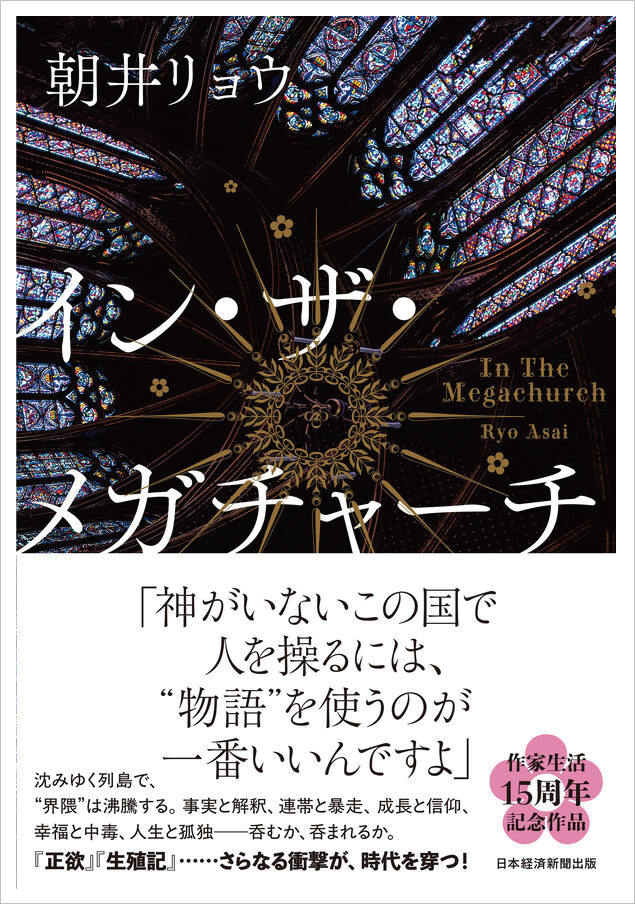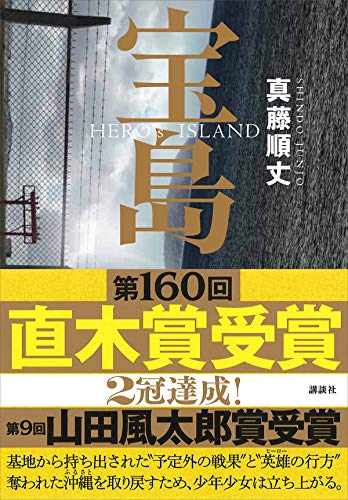10年前のスタンディング
もう10年になる。2015年、国際女性デーの前日の3月7日に、中国でアクティブに活動する行動派フェミニストの5人(以下「フェミニスト・ファイブ」)が不当拘束された事件のことだ。私がこの事件を知ったのは、レイバーネット日本の会員メーリングリストに流れた一報だった。
国際女性デーの日にバスや地下鉄での痴漢行為に反対するステッカーをゲリラ的に配布しようと計画したことが「騒動挑発罪」とされ拘束されたが、世界中のフェミニストからの、そして何よりも中国国内でフェミニスト・ファイブの活動を支え、支援してきた女性弁護士や市民や労働者などの声によって、彼女らは拘留期限いっぱいの37日後に保釈された。この事件の顛末とその後、そして近年の中国におけるフェミニズムや女性の状況と中国共産党の政策を詳細に綴ったのが、レタ・ホング・フィンチャーの『フェミニスト・ファイブ 中国フェミニズムのはじまり』(左右社、以下、本書)である。
日本でも多くのフェミニストらを中心に、5人の釈放を求める国際署名に賛同し、中国大使館前行動が取り組まれた。私も微力ながら、中国の草の根労働運動を支援する立場からいくつかの情報を発信し、4月12日の世界一斉アピール行動日にアジア女性資料センターなどフェミニスト団体が呼びかけた中国大使館前でのアピール・スタンディングにも参加した。
その後、中国フェミニストたちの存在は意識していたものの、中国フェミニズムの情報を系統的に紹介していたウェブサイト「遠山日出也の現代中国女性史研究」や『ハッシュタグだけじゃ始まらない 東アジアのフェミニズム・ムーブメント』(熱田敬子等編著、大月書店、2022年)に収録された先進的な論考や、中国MeTooの盛り上がりなどの報道を読み、中国の草の根労働運動にかかわる情報を翻訳する程度のかかわりだった。
労働運動を支援するフェミニスト
私自身は、1990年代後半にアジアや太平洋地域の草の根労働運動の活動家のネットワークに参加し、厳しい状況の中で活動を続ける草の根労働運動アクティビストやそれを支援する香港などの労働NGOの活動に接した。2001年に世界貿易機関(WTO)への加盟を台湾とともに果たす前後から中国国内で爆発しつつあった国有企業労働者の反民営化のたたかいや、膨大な農民工のうねりを感じつつ、民衆連帯のグローバリゼーションを謳う市民団体ATTAC Japanの結成に加わって現在に至る。
フェミニスト・ファイブの一人である鄭楚然は、逮捕の前年に広州市の大学都市の清掃労働者たちの組織化やストライキを支援していた。私は彼女の書いたシスターフッドにあふれたこの争議の支援レポートを翻訳していたこともあり、逮捕者のなかに彼女の名前があることにすぐに気がついた。本書でもこの時の争議の様子がいきいきと描かれているが(212頁)、残念なことにフェミニスト・ファイブの肖像や活動の様子がわかる写真やポスターなどが一切掲載されていない。この点は前掲の『ハッシュタグだけじゃ始まらない』や鄭楚然の争議支援のフォト・レポートの拙訳を参照してほしい(1)。
支えになったのはシスターフッド
著者は母親が中国系のアメリカのジャーナリストで、本人自身もフェミニストとしてフェミニスト・ファイブや他の中国フェミニストへのインタビューを通じて、警察のガサ入れ、拘束、取り調べ、被疑者の親類縁者にまで広がる保釈後の嫌がらせの実態を明らかにしている。日本でも国家権力や資本による大なり小なりの弾圧には事欠かないので、活動家ならピンとくるだろう(中国の場合は相当厳しいが)。例えば、フェミニスト・ファイブの一人、王曼は釈放後の嫌がらせで慢性的な不眠症になり、PTSDの影響でベッドから出られないほどの精神的にダメージを受けたが、このような苦しい状況から王を救ったのもまたフェミニストの仲間たちだった。「シスターフッドは、私が私自身になり、安心できる安全な場所を提供してくれた」(100頁)。
本書では、中国で活動することの困難さだけでなく、このようなシスターフッドにあふれるエピソードやコメントが随所にみられる。連帯を求めて孤立を恐れない日本の活動家にとっても共感し、勇気づけられる1冊になるだろう。
本書はフェミニスト・ファイブ事件に直接まつわることだけでなく、清末や中国共産党結成当初に活躍した女性革命家たち、また革命中国が切り開いた女性解放の歴史も踏まえたうえで、1995年9月に北京で開催された国連の世界女性会議を契機にして中国で広がったフェミニズム思想やNGO活動、女性ジャーナリストや弁護士の活動などを広く紹介している。毛沢東時代の女性政策の問題点、市場改革に伴う男女間の経済格差の拡大など、そして今日の中国共産党政権による伝統的家父長制が色濃く反映された諸政策にも批判的に言及する。「共産党の正当性を支えてきた急速な経済成長にもはや頼れなくなったいま、習政権下の中国プロパガンダは儒教的性差別要素を復活させ、伝統的な家族観が国家の安定の基盤になるという考えをとくに推し進めようとしている」(227頁)。
運動内における性暴力と女性差別
もうひとつ、本書を活動家にお勧めする理由は、多くのフェミニスト活動家がかつて受けたDVや性暴力の実態や運動内における性差別と性暴力に言及していることだ。本書の著者もまた思春期に性暴力の被害に遭い、それにずっと蓋をしてきたことを本書で告白している(124頁)。
運動内における性暴力については、逮捕されたフェミニスト・ファイブの弁護を買って出た男性弁護士が、逮捕された李麦子の恋人だったテレサに働いた性暴力事件が取り上げられている(105頁)。恋人が拘束された不安を悪用して、この男性弁護士は次第に彼女に性的なコメントや写真を求めた。被害は複数の女性たちに及んでいたこともあり、被害者らはグループを作り、加害弁護士に告発文を送り付けた。弁護士はいったん謝罪したが、なおも被害が続いていることを指摘されると一転、居直った。そして運動の大義を理由に追及を止めさせようとするもの、被害者自身のとらえかたを問題にするものなど、日本の運動シーンでも目にする二次被害、三次被害が相次いだ。しかし「この恥辱を克服する支えになってくれた活動家シスターたちの強い連帯感」(109頁)が被害者たちを救った。
私が支援している三里塚芝山連合空港反対同盟(熱田派)の活動拠点である三里塚闘争連帯労農合宿所でも、1982年に支援の女性に対する支援党派(第四インター)の男性メンバーによる性暴力事件があった。被害女性を支援する女性活動家たちは組織内部の女性差別に対しても追及の範囲を広げ、加害者らは運動と組織から追放された。しかしその過程で組織の家父長制的抑圧が女性たちに大きな傷を残した。現在も続く成田空港反対闘争において、これら女性たちのたたかいの歴史を継承するためにも、本書に記された鄭楚然の言葉を忘れないようにしたい。「人権の旗を振りかざしてヒーローぶっているくせに、女性にハラスメントをし、傷つけておきながら、評判に傷一つつかずに活動を続ける、こういう男たちが大勢いるんだよ」(119頁)。
在日中国人フェミニストたちに励まされて
本書はおおよそ2018年4月ごろまでの中国フェミニズムの動きをカバーしているが、それ以降もフェミニストたちのたたかいは続いている。本書巻末に収録されている阿古智子氏による解説、東京新聞記者の中澤穣氏の『中国共産党vsフェミニズム』(ちくま新書、2024年8月)などでも詳しく知ることができる。
このような政治弾圧は2015年以前からも続いているが、とくに女性アクティビストらを対象とした支援体制を作るべきだという女性弁護士が結成した「中国女性弁護士公益共同ネットワーク」の活躍、そしてフェミニスト・ファイブの事件の4カ月後の2015年7月9日に全国の弁護士ら300人以上の人権弁護士らが一斉に拘束された「709事件」についても詳しく論じている。
女性弁護士の一人、王宇の活躍(187頁)を知ったのは、在日中国人フェミニスト「在日女権連帯会」が昨年末に早稲田大学で上映したドキュメント映画『流氓燕HOOLIGAN SPAROW』を通じてだ。映画の主人公である流氓燕=葉海燕も本書にそのエピソードとともに登場している(192頁)。在日女権連帯会は中国国内のフェミニストへの支援を続けている。今年の渋谷で行なわれた東京ウィメンズマーチ2025では「憤怒超越国境(怒りは国境を超える)」と書かれた大きなバナーをはじめ、色とりどりの手書きプラカードを持参して参加した(2)。在日中国人フェミニストらと一緒に本書の「音読会」を不定期で開催しているが、本書で登場する多くのアクティビストや様々なエピソードと在日中国人フェミニストたちの地道な取り組みがつながったことも、私自身の大きな励みになっている。
女権主義から女工権主義へ
1989年6月4日の天安門事件で弾圧され、香港を拠点に中国の労働者支援を続ける韓東方は、鄭楚然ら若いフェミニストたちが労働者に連帯し、経営者や職場内での凝り固まった性差別意識を打ち破ろうとする姿に心を打たれたという(205頁)。またiPhoneの製造工場の女性労働者によるセクハラ防止を求める書簡が紹介されているが(79頁)、それを掲載したサイト「尖椒部落」は、2018年の中国MeTooや同時期に起こった労働争議の高まりなどを懸念した当局によって同年7月にアカウントが凍結され、2021年には完全閉鎖に追い込まれた(活動内容は前掲書『ハッシュタグだけじゃ始まらない』に詳しい)。だが、22年8月には「尖椒部落」サイトに掲載された女性労働者らのインタビューをまとめた書籍『她的工廠不造夢:十三位深圳女工的打工史』(彼女は工場で夢を見ない 深圳の女性労働者13人の物語)が台湾で出版されるなど、中国の女性労働者たちの声は海を越えて聴こえてくる(3)。鄭楚然のアイデアは今日ますます必要とされている。「もし工場で働く女性たちをフェミニスト意識に目覚めさせる力のある人がいたら、ものすごい結果に結びつくと思う」(214頁)。
世界を変え続けていく
本書でももっともラディカルなアクティビストとして登場するフェミニスト・ファイブの一人、李麦子は、当局による厳しい監視体制の経験を経て、アメリカに移住した。最近、ウェブサイト「低音Voice the voiceless」に10年目の文章を寄せている。
「この10年間を振り返ってみると、私の人生は無駄ではなかったと思う。……20歳のとき、私の目標は世界を変えることだった……いま私が言いたいことは、自分のできることをやりながら、世界を変え続けていく、ということだ(4)」
混とんとした世界情勢を迎えたいま、中国のフェミニストを取り巻く環境は中国国内においても、またアメリカなど海外でも、より一層厳しくなっている。米トランプ政権による一方的な関税引き上げによる「貿易戦争」に対して、中国政府は「奉陪到底」(最後までお付き合いする=徹底抗戦)という強力なスタンスを維持している。しかしそのような強権姿勢はまた、自国の労働者とりわけ農民工や女性労働者らの多大な犠牲の上に実現された「世界の工場」において、労働者の抵抗や自主的な動きに対する徹底した弾圧によって可能となっている。
搾取の帝国と独裁の大国の支配者間の貿易戦争に対するオルタナティブは、「万国の労働者、団結せよ」に象徴される国境を越えた労働者や生産者のたたかいを通じて勝ち取られる、労働時間が圧倒的に短縮され、エコロジカルでまったく新しい生産様式と社会体制を目指す過渡的綱領の一つである。それは、これまで世界中で性差別や性暴力に抗うフェミニズム運動が目指し、獲得してきた地平を土台にした、より一層大胆な社会運動と社会システムのフェミニズム化、つまり「天の半分を支える」女性たちが中心となるシスターフッドに満ちた社会であることは間違いない。彼女たちが失うものは「家父長制」と書かれた暴力の鉄鎖のみであり、獲得するのは「天の半分」どころか、まだ見たこともない新しい世界のすべてである。
1 http://www.chinalaborf.org/report/report14/report140906.html。また本書52頁や213頁で紹介されている鄭楚然らへの支援を訴える労働者たちのフォト・メッセージの拙訳はこちらに掲載している。https://monsoon.doorblog.jp/archives/54360248.html
2 在日女権連帯会のInstagramに活動が紹介されている。https://www.instagram.com/feministchina_jp/
3 同書の前書きの拙訳は私のブログに掲載している。http://attackoto.blog9.fc2.com/blog-entry-540.html
4 http://www.labornetjp.org/news/2025/1742886339533staff01/