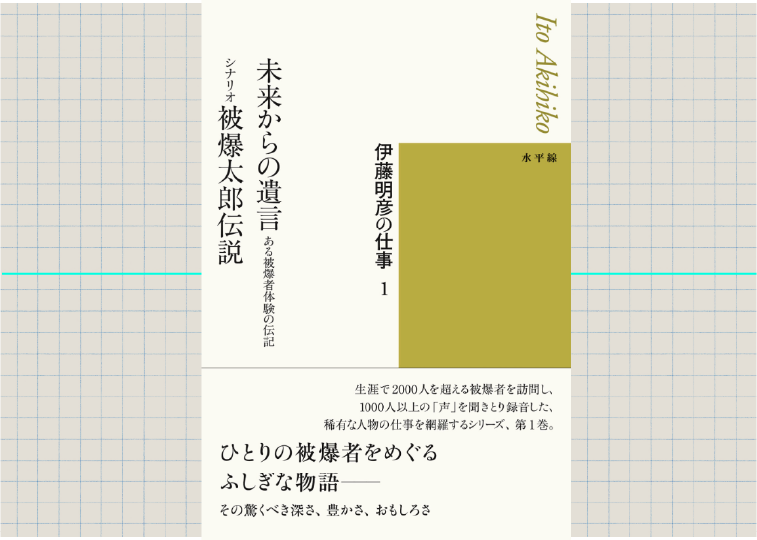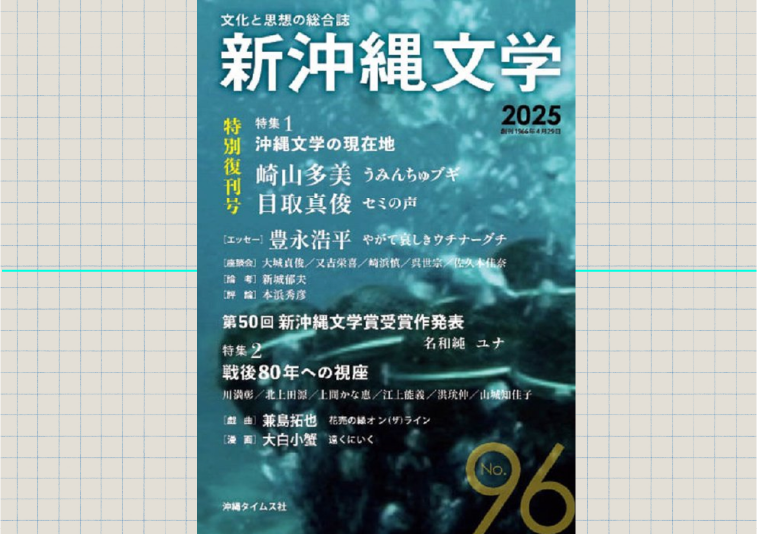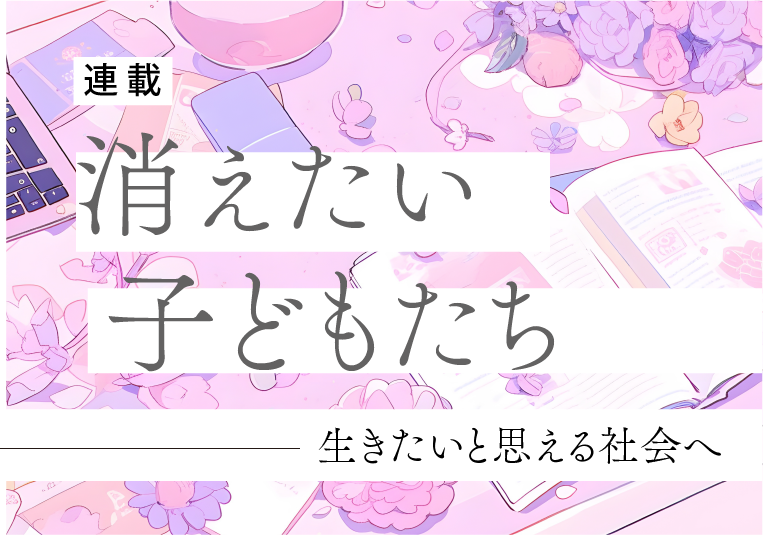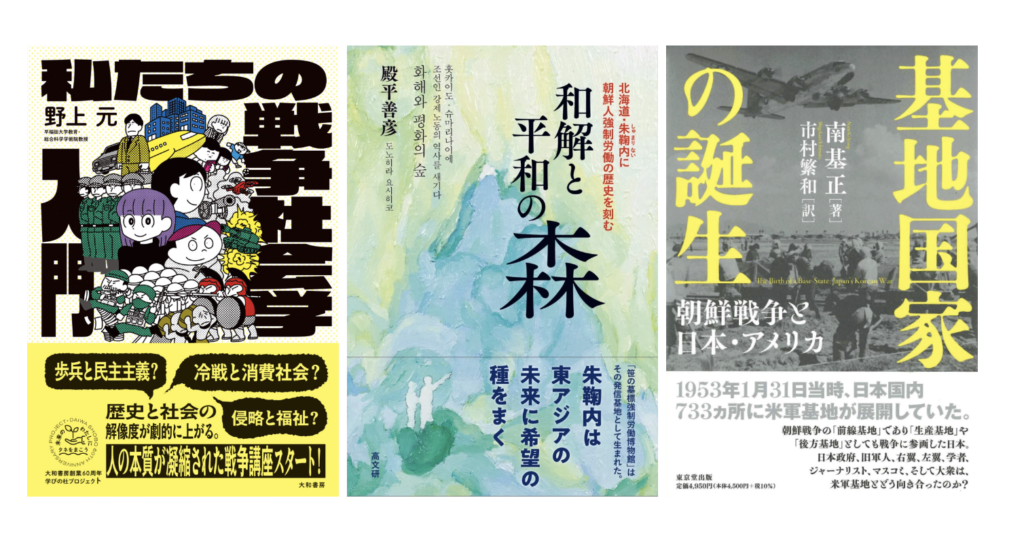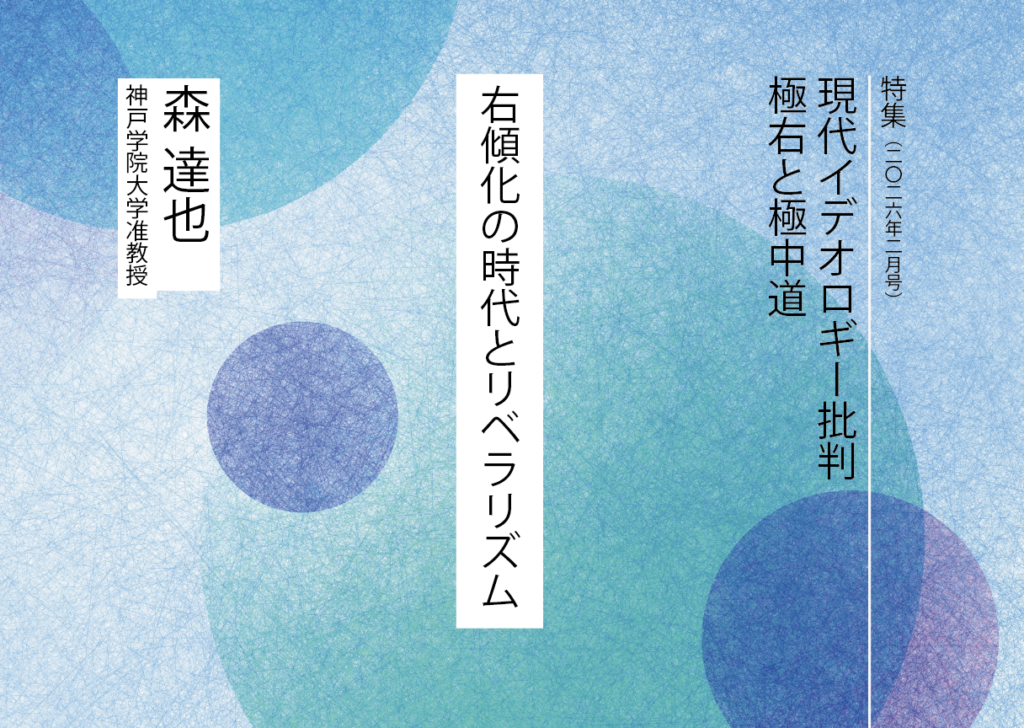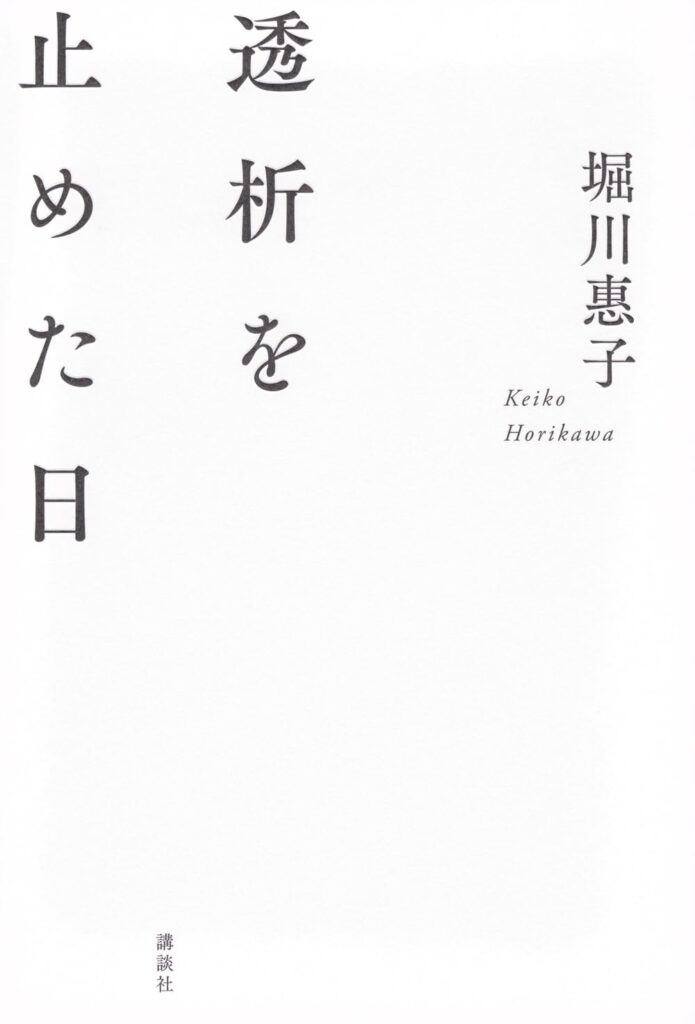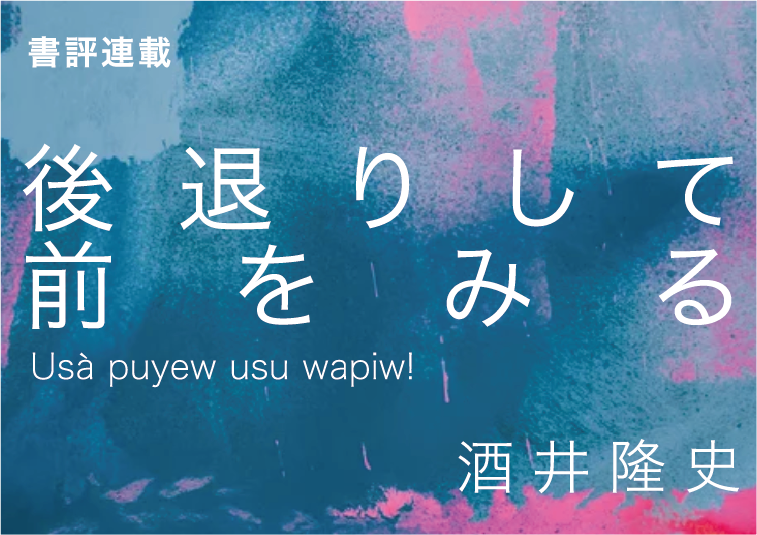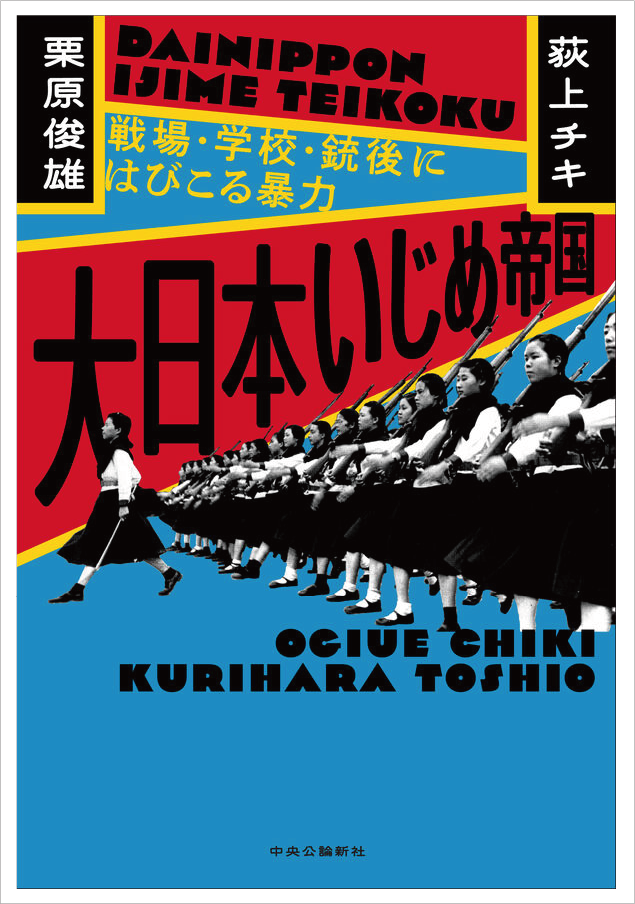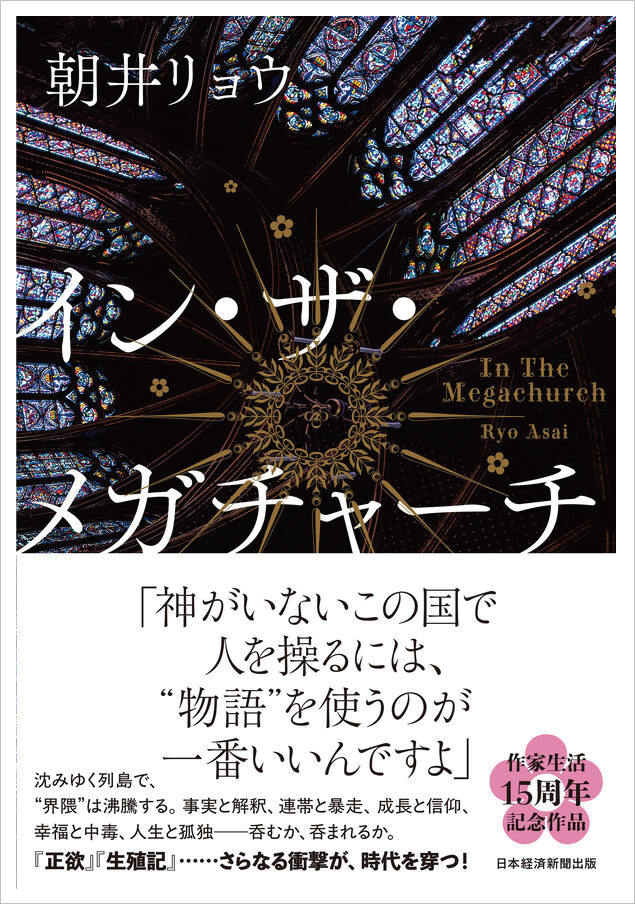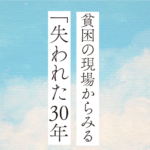伊藤明彦とはだれなのか。本書を評するにあたり、あとがきにあたる西浩孝氏の「編集者から読者へ」を主な参考に、その経歴と人となりをまずたどってみたい。
伊藤明彦は1936年に東京で生まれた。父親の仕事の関係で長崎に転居、長崎に原子爆弾が投下された1945年8月9日には山口に縁故疎開をしていて、直接の被爆はまぬがれている。当時8歳。10日後、母親に連れられて長崎に帰った。おそらく列車で爆心地近くを通過したはずだ。浦上の東南の高台、西山地区に住むが、この地域も被爆後に黒い雨が降り、放射性降下物が落下したともいわれる。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」では、被爆から2週間以内に放射能の影響が考えられる区域に立ち入った人々を「入市被爆者」としている。「入市被爆者」ももちろん被爆者で、相当に被ばくの影響があったと考えられている。
ただ、彼らは原子爆弾の破壊の惨状を目撃したわけではない。多量に放出された初期放射線と熱線と爆風による破壊を体験していない。猛烈な火災から逃げたことも、水を求める人を見捨てたこともなく、たぶん、死骸を踏みぬくといった経験もないだろう。背中一面に刺さったガラス片を竹のピンセットで抜いてもらったわけでもなく、傷口にわいたウジを箸でつまんでもらってもいない。伊藤明彦は後に1000人を超える被爆者からこうした証言を聞き取って録音していくことになる。
1957年制定の旧法「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」であきらかになるまでの12年間、入市被爆はあいまいだった。直接被爆した彼の両親や姉はともかく、長崎にいなかった彼にその自覚はなかった。「私は入市被爆者です。しかし子供時代を含め、長崎ですごしてきた25年間、自分が被爆者かもしれないと考えたことはいちどもありませんでした」というのが、彼の自己認識だった。彼はいわば「遅れてきた被爆者」であった。
長崎のカトリック系の私立海星高校に通い、早稲田大学第一文学部に進学、1960年に長崎放送に記者として就職した。
翌年、浦上四番崩れの生き残りの高齢の女性を取材する。「浦上四番崩れ」とは、キリスト教禁制時代の浦上における潜伏キリシタン弾圧の四度目となる迫害であり、江戸時代の終わりの1868年、浦上のキリスト教信徒が信仰を表明したことをきっかけに約3400名が津和野、萩、福山などの諸藩に流罪となった大規模な弾圧だ。明治を迎えて1873年に帰郷するまで600人以上が厳しい拷問などで殉教したといわれる。苦難を耐え忍び、生きて帰った人々はそれを「旅」と呼んだ。
親に抱かれた幼児として「旅」から生還した浦上四番崩れの最後の生き残りの高齢女性は、彼が取材をしてまもなく亡くなる。ひとつの歴史の終焉に立ち会ったと感じたのだろう。原爆の歴史もいずれ語るものがいなくなるという思いにとらわれ、被爆者の証言を伝えること、その収録と保存を決意して、『被爆を語る』と題したラジオ番組を企画・制作し、初代の担当者となった。1968年11月にその第1回が放送されている。
半年後、佐世保支局への転勤を命じられ、1970年7月に長崎放送を退職。東京の日本電波ニュース社に一時勤務、「被爆者の声を記録する会」を結成した。日本電波ニュース社はまもなく退職し、以降8年ほどの間、警備、皿洗いなどの肉体労働を続けながら、13キロのオープンリール式の録音機を抱え、青森から沖縄まで21都府県の被爆者の約1000人の声を収録した。
安定した生活を投げうって、30代の残りのほとんどを被爆者の声の収録に費やしたのだ。頑ななこだわりと一途さ、常人には考えられない粘り強さがこの人物にはある。2000人以上の被爆者を各県の被爆者団体などのツテでたどり、半分ほどから収録を断られてくじけそうにもなりながら、時には「代受苦(だいじゅく)」という仏教の考え方で自らを励ましもした。自分が苦しみをひきうけることによって、だれかが苦しみからまぬがれている、そんな思いで続けていったのだ。高村光太郎の詩「冬の言葉」の「一生を棒にふって人生に関与せよと。」という一節を胸に刻み、冬枯れの大地に屹立する樹木に自らを重ね、清貧といってもいい日々を耐え抜く。
1000人を超える被爆者の中で、最も彼の心を震わせた被爆者が「吉野さん」だった。被爆者の声の収録がひと段落した頃、「吉野さん」との出会いと突然の別れまで、本人の証言の書きおこしをまじえながらまとめたルポルタージュが、本書に収録の『未来からの遺言──ある被爆者体験の伝記』と題したノンフィクション作品だ(1980年)。以降、彼は多くの本を執筆するが、被爆者の声を収録した経験がそのすべての礎になった。
「吉野さん」と出会ったのは、1971年、東京都の被爆者組織の紹介であった。身長151センチ、体重40キロ、小さなひとだった。被爆当時、10歳。吃音の彼の話の録音テープは5時間半の長さになったという。「吉野さん」は父母、3人の兄と3人の姉がいた末っ子で、1人の姉と彼以外の家族はすべて原爆で失っていた。姉と弟ふたりになり、姉は弟の入院生活を支えるために懸命に働いたが、その姉も22歳の若さで亡くなる。わがままな弟を母のように愛する姉のけなげな姿がひときわ胸をうつ。
天涯孤独の身となった「吉野さん」は苦しい人生を強いられるが、一匹の小さなクモの営みに勇気づけられ、被爆者として社会を変革することが自らの生きがいだと新たな決意を語る。彼の語りは多様なエピソードとその哀切な語り口もあいまって、それだけでひとつの文学作品のようにも感じる。民俗学者、宮本常一の『忘れられた日本人』に収められた「土佐源氏」の古老の語りを思いだした。
彼の話を聞き終わった時、「もう、これから先どれだけの数の被爆者にあっても、これ以上の話にめぐりあうことはないのではないか」と感じたと深い感銘を伊藤も記した。これは憶測だが、彼は「吉野さん」に自らの「代受苦」を生きた人間を見いだしたのではないか。「遅れてきた被爆者」である自分が、長崎にいたら受けた苦しみをひきうけてくれた人々の象徴として吉野さんが現れたように感じたのかもしれない。
ただ、「吉野さん」の物語はそこで終わらない。彼はひとつの謎を抱えていた。そこから謎を探っていく後半の緊迫感は優れたサスペンスやミステリ小説の趣で、謎を抱えたまま奥秩父の山中に姿を消す「吉野さん」の後姿の余韻もひときわ深い。被爆者とはだれか、被爆体験とはなんだったのか、鋭い問いと深い洞察がからみあい、ルポルタージュ文学の白眉、記録文学の傑作になったといっていい。
併せて収録された『シナリオ被爆太郎伝説』(1999年)は、その話をもとに登場人物や設定を変えた映像化のためのシナリオであり、フィクションだ。ここでも「姉さん」の姿がひときわ哀切に語られる。被爆太郎の謎が説き明かされるが、あくまでフィクションであり、謎は謎のまま終わるノンフィクションのほうが優れているようにも思えるが、ぜひ読み比べていただきたい。
「吉野さん」の声の録音テープは、その謎のために、全国の学校などに寄贈された約1000人の「被爆者の声」からは外された。今となってはその生の声の録音を聞くすべはないが、本書の2作で、結局、伊藤明彦はその声を世に伝えたのかもしれない。
伊藤明彦に会ったことがある。おそらく2006年、長崎原爆資料館に勤務していた当時、数人の長崎市職員とともに彼を迎えた。当時、70歳ぐらいだったろう。冷たい目をしていた。不機嫌な顔でこちらを一瞥した。「いやなやつだ」と思った。被爆太郎の謎をあえて暴こうとしない、弱者への深い共感とは裏腹に、彼には、権力に連なる末端の小役人など見下さないではいられない、反権力の怒りと鬱屈したプライドがあったのかもしれない。ただ、それはその仕事を貶めるものではない。むしろ怒りと優しさ、偏狭と寛容の振幅の大きさがこの稀有の人物をつくりだしたとも考えられる。
伊藤明彦は被爆者を特別視して崇めることを批判した。今後、本シリーズで復刊が予定されている「原子野の『ヨブ記』──かつて核戦争があった」でも「被爆者は被爆したにすぎない普通のひとびと」で「被爆者の姿は多様でゆたか」だと喝破している。彼もまた被爆者だ。強さも弱さも歪みもある普通の人間であったとしても否定されはしない。彼の仕事もまた多様で豊かな、ひとりの被爆者の物語りであり、身の上話だが、他の多くの語りと異なるのは、それが優れた文学の域に達していることだ。
伊藤明彦の仕事は、原民喜、大田洋子、林京子などとともに、被爆者によって書かれた一連の「原爆文学」の系譜において読み継がれていくべきだろう。
〈今回紹介した本〉
『未来からの遺言 ある被爆者体験の伝記/シナリオ 被爆太郎伝説』(伊藤明彦の仕事1)
伊藤明彦著、編集室水平線、2024年12月