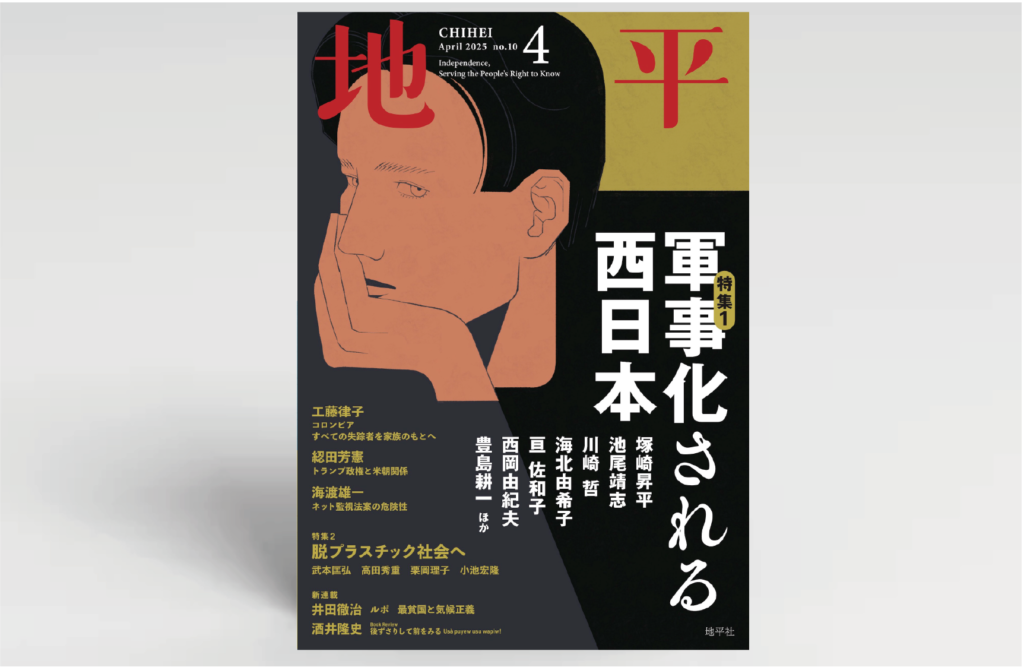法人化の問題点
内閣府に設置された「日本学術会議の在り方に関する有識者懇談会」は昨年12月20日に「最終報告書」として「世界最高のナショナルアカデミーを目指して」を公表した。
報告書は、「独立した立場から政府の方針と一致しない見解も含めて政府等に学術的・科学的助言を行なう機能を十分に果たすためには、政府の機関であることは矛盾を内在している」との理由で学術会議を法人化するとしているが、一方で、独立性の保障どころか、政権や財界が学術会議に介入するための様々な制度を新たに法定する。その根幹は2023年12月の「中間報告」と変わらない(それについては本誌2024年9月号の佐藤学「学術会議への権力介入」と10月号の小森田秋夫「法人化は独立性を高めるのか」参照)。
学術会議は中間報告への懸念を繰り返し表明してきたが無視されつづけてきた。そこで昨年7月29日の懇談会で、学術会議光石会長はこう発言した。
「①大臣任命の監事②大臣任命の評価委員会③『中期目標・中期計画』の法定化④次期会員選考での特別な方法の導入⑤選考助言委員会の設置、この5点は独立した自由な学術の営みを代表するアカデミーの活動を阻害するもので到底受け入れられない。懸念が払拭されなければ重大な決意をする」
だが最終報告でも、字句を多少変えただけで5つの問題は依然残っている。
この最終報告をもとに石破政権は、法人としての新たな学術会議を2026年10月に設立する法案を3月上旬に今国会に提出する。事態は切迫している。憲法第23条「学問の自由」を保障するべく国の機関として設置された学術会議の解体的再編は、戦後憲法体制の柱がまた一つ奪われることを意味する。学術界だけではなく、市民社会も、重大な岐路に立っている。
未来像のまやかし
最終報告に学術会議の未来像についての記述がある。(要旨、太字筆者)
「将来的・最終的には、財政面も含めて自律性も高め、公益法人の形に落ち着くことが学術会議の理想的な在り方である。学術的助言等の活動に対する国民・社会の信頼を積み重ね、財政基盤の多様化を進めながら自律的な運営に至る。その一方で、学術と政治や行政との適切な関係を構築し、国からも一定程度の支援を受ける。ここに至れば、もはや政府任命の監事等が置かれる理由はなく、国にとっても無用のコミットメントをつづける意味はない。そこに着地するまでには、長い努力と実績・信頼の積み重ねが必要である。まずは国が設立する法人として出発し、運営の自律性を少しずつ高めていく。科学者を代表する地位、国に学術的助言を行なう権限、国からの財政的支援などを法律で保障する以上、国民に説明するための仕組みも、法律により制度的に担保される必要がある。」
未熟な学術会議を政権が育てると言わんばかりである。財政的に自律した公益法人をめざし、そこに至るまでは国が金を出す以上、政権が監視・介入する制度が必要だという論理である。
確かに欧米には、1660年設立の英国王立協会など民間法人のアカデミーも多い。その出発点は宗教や国家権力による介入を排除するための学者の共同体であり、その後、社会的信頼を得て発展し、政府に勧告できる公的地位を獲得してきた。そして英国政府は今も王立協会に年225億円の公的資金を供与し、その提言は尊重するが、政府が内部統治に介入する制度はない。
一方、日本では、大学や研究機関の多くは明治以降、国策により作られた。学術会議の前身は1923年に国が設置した学術研究会議で、戦争中は科学者の軍事動員を担った。戦後、そのことを痛苦に反省した科学者たちが話し合い、国の機関として学術会議を設立することを求めた。それは政府と市民社会に学術の公共性を尊重する意識が希薄な中で、「社会経済的な利害からの独立を公財政によって保障する」ためであり、「他方で政治権力、政府からの独立保障のために、職務の独立性を明文で規定し、かつ、会員選考の自律性を確保した」のである。それは「新憲法のもと、戦後日本の国家が学問の自由と科学者コミュニティの独立を民主主義に必須のものとして擁護する志」だったと広渡は指摘する(広渡清吾『社会投企と知的観察』日本評論社)。