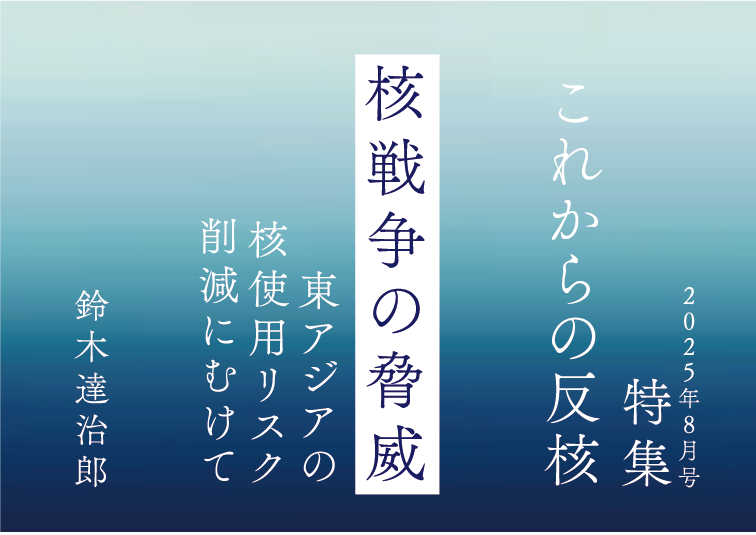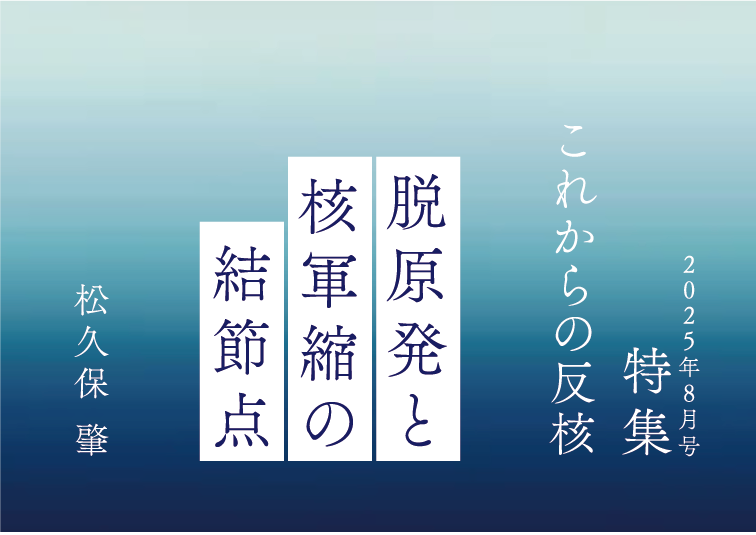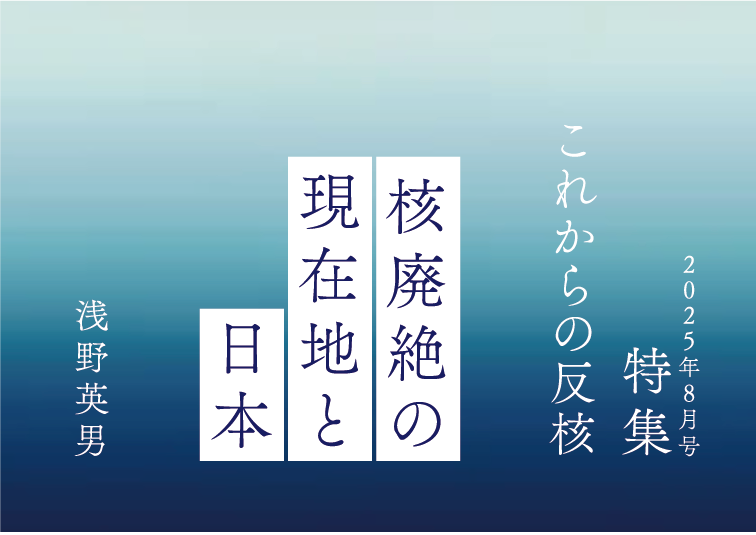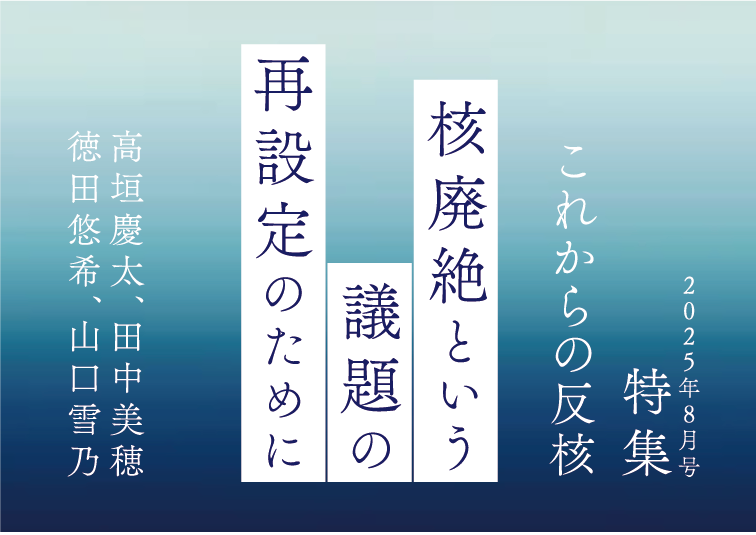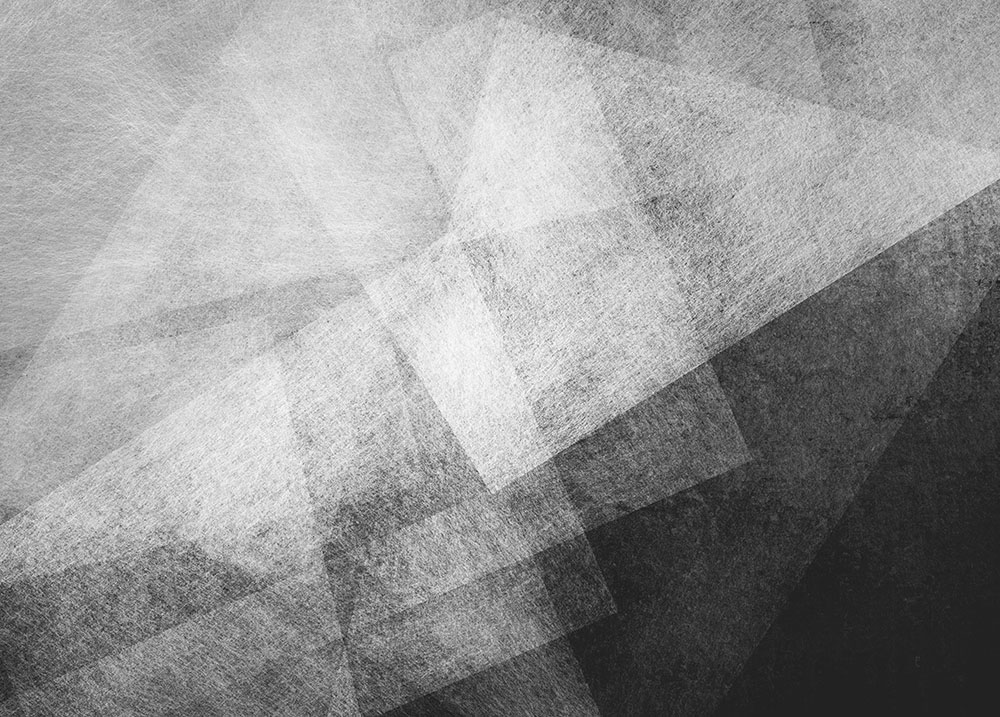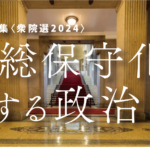ヒバクシャの証言活動への授賞
日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が今年のノーベル平和賞を受賞した。ノルウェー・ノーベル委員会のフリドネス委員長は、10月11日の発表にあたり次のように述べた。
「『ヒバクシャ』として知られる広島と長崎の原子爆弾の生存者たちによる草の根運動は、核兵器のない世界の実現に尽力し、核兵器が二度と使われてはならないことを証言を通じて示してきた」
委員長はさらに「核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道上の結末への認識を高める世界的な運動」によって、核兵器の使用は許されないという「核のタブー」が形成されてきたとした。そして、広島・長崎のヒバクシャの証言がそのような国際規範の確立に大きく貢献したとし、彼らの取り組みをたたえたのである。
なぜ今なのか。ノーベル委員会は「この核兵器使用のタブーが今、圧力の下にある」との憂慮を示している。
核保有国が核兵器を増強・近代化し、新しい国々が核の保有を企て、「現在進行中の戦争においては核兵器の威嚇がなされている」。ノーベル委員会は名指しこそしなかったが、核保有国ロシアがウクライナに対する軍事侵攻の中で核の威嚇を行なっていることへの警告であることは明らかだ。中東では核保有国イスラエルが戦闘を継続、拡大しており、ガザに対する原爆投下の可能性すら語られてきた。
「人類史上、今こそ、核兵器は何かについて思い起こす時だ」とノーベル委員会は訴えている。
実際「終末時計」の針は昨年以来、人類終焉となる午前零時の90秒前を指している。『原子力科学者会報』がこの時計を始めた1947年以来、もっとも零時に近づいているのだ。2022年の核不拡散条約(NPT)再検討会議においては「核兵器使用の脅威は今日、冷戦の絶頂期以来もっとも高い」状態にあるという懸念が最終文書案に記された。
このままでは、また核兵器が使われかねない。それを止めるために今、世界は改めてヒバクシャの声に耳を傾けなければいけない。それが、ノーベル委員会からのメッセージである。
被爆者の皆さんの長年の功績がたたええられたことは誠に喜ばしいことであり、12月10日にオスロで行なわれる式典は、素晴らしい祝福の場となろう。そしてそれは、原爆で命を奪われた多くの人びと、あるいは長く後障害で苦しみながら「核兵器のない世界」を夢見つつその実現を見ることなく亡くなった人びとへの弔いの場ともなろう。だが、そうした被爆者の方々に感謝と敬意を示しつつも、未だ実現できていない核兵器廃絶と平和の達成のために、世界の市民がいま行動を起こすことこそ、何よりも求められている。
ヒバクシャの声こそ抑止力
7年前の2017年、国連で122カ国の賛成により核兵器禁止条約が採択された。同条約成立に向けて尽力してきた核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)は、同年、ノーベル平和賞を受賞した。その受賞理由について、当時のレイスアンデルセン・ノーベル委員会委員長は「あらゆる核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道上の結末への注目を集め、条約を通じて核兵器の禁止を達成するための革新的努力」と語った。
私は2010年以来、日本のNGOピースボートを代表して、ICANの運動に中心的に関わってきた。ICAN全体としては、核兵器の非人道性についてさまざまな啓発活動を行ないながら、各国政府に働きかけ、対人地雷禁止条約などの成功事例も参考にして、核兵器禁止条約の制定に取り組んできた。条約成立後は多くの国に署名・批准を働きかけ、今日締約国は73、署名国も合わせれば98カ国と、実に世界の約半数の国がこの条約に加わるところまで来ている。