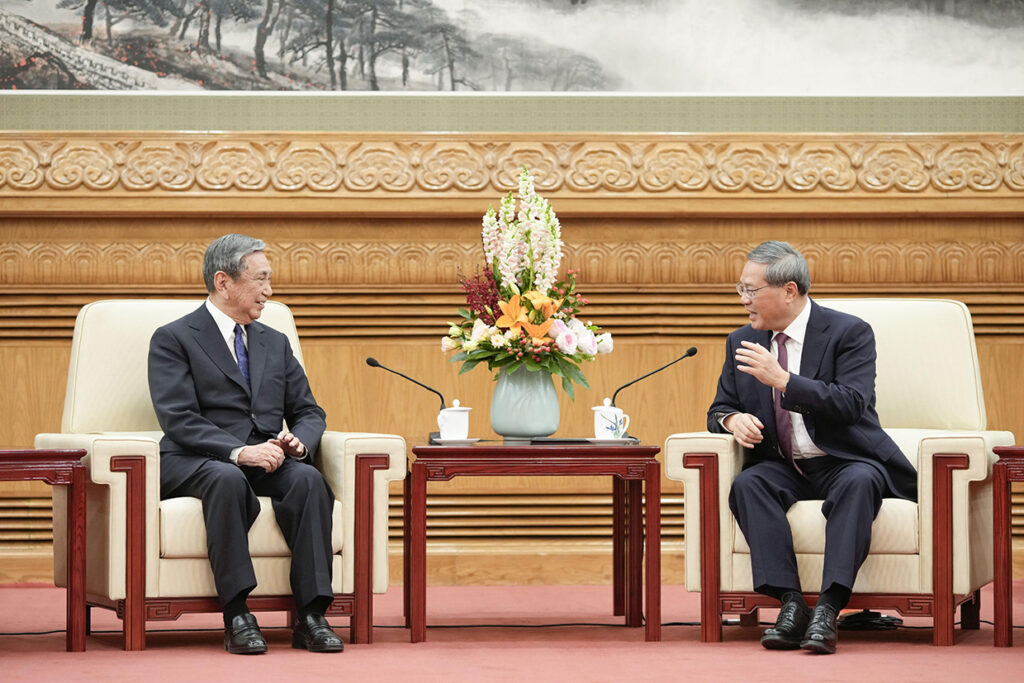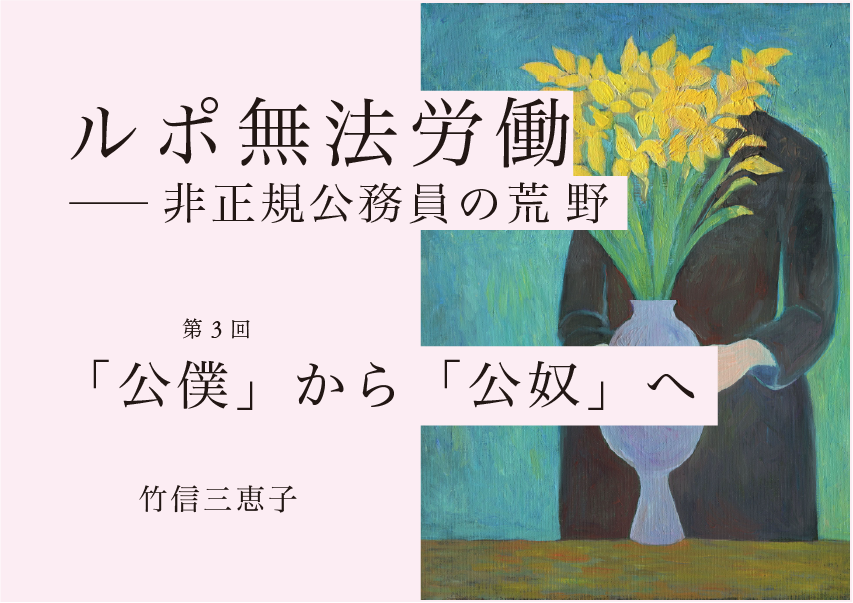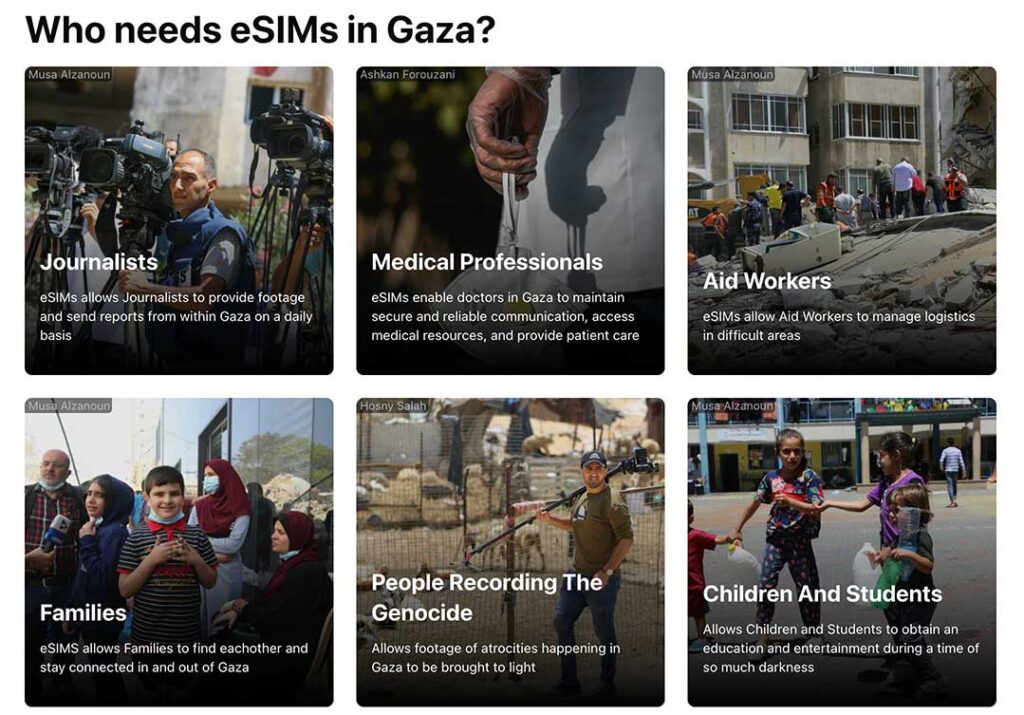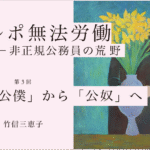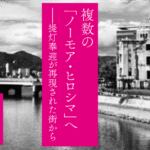国家的プロジェクト
「国際卓越研究大学」の英訳として、文部科学省はUniversity for International Research Excellenceを用いている。今ここにあるものではなく、めざすもの、とのニュアンスである。国際卓越研究大学とは「諸外国のトップレベルの研究大学に伍する研究大学」(公募要領)をつくろうとする国家的プロジェクトである。
その基本的なしくみは、国際卓越研究大学になろうとする大学は「体制強化計画」を作成し、法令に定める要件を満たしていることを示す資料とともに文部科学省に提出する。文部科学省はこれらを審査し、国際卓越研究大学を採択する。採択された大学には、政府が造成した10兆円規模の基金、「大学ファンド」の運用益から助成金が支給される。助成金の額は1校あたり数百億円規模となる。大学はこの助成金および独自に獲得した資金を用いて研究と産学協同等の体制整備をすすめ、「投資と知的価値創造の好循環」をつくりだし、国際卓越研究大学をめざすというものである。
国際的に卓越した研究をめざしている大学は少なくはないだろう。そして、大学が「世界的な研究大学」となるには、さまざまな道筋がありうる。だが、政府は国際卓越研究大学をごく少数に限り、自身が許す体制・方法しか認めていない。そこには、「世界的な研究大学」を形成する以外の別のねらいが潜んでいるとみるべきだろう。
企業による大学支配
2017年10月、東京大学総長(当時)、五神真(ごのかみ・まこと)が財務省の審議会に提出した「産学連携から産学協創へ」という資料には、それまでのように個別の研究室単位ではなく、大学を挙げて産学共同にとりくむことができるようにマネジメント組織を構築する改革案が示されていた。このような体制が必要とされる理由について、資料は「産業界が維持できなくなってきた中・長期のための投資の受け皿を大学につくる」と述べる。この2カ月前、自由民主党の知的財産戦略調査会は「稼げる大学」づくりをめざして、大学ファンドの創設を提言した。二つの流れは政府の科学技術・イノベーション政策の司令塔である総合科学技術・イノベーション会議において合流し、国際卓越研究大学のスキームに結実する。自民党調査会の会長であった甘利明は、後に自身の考える大学改革を遂行してくれる人物として五神の名前を挙げた(「文部科学教育通信」No.471)。
ところで、五神は先の資料の中で、改革後の大学と企業の関係を「産学協創」と呼んでいる。ここでは大学と企業は対等な立場で社会が求める価値を議論することがイメージされていたようである。しかしながら、2023年12月の法改正により、東京大学など5つの国立大学法人には「運営方針会議」と称する、最高意思決定・監督機関がつくられることになった。続いて、運営方針会議は学外委員を過半数とするか、学外委員の賛成を可決の条件とする、事実上の「拒否権」を学外委員に付与することが国際卓越研究大学の要件とされた。国際卓越研究大学に採択されることとひきかえに、最高意思決定権と監督権を学外委員(その多くは企業・経済界の出身者である)が握る体制がつくられつつある。