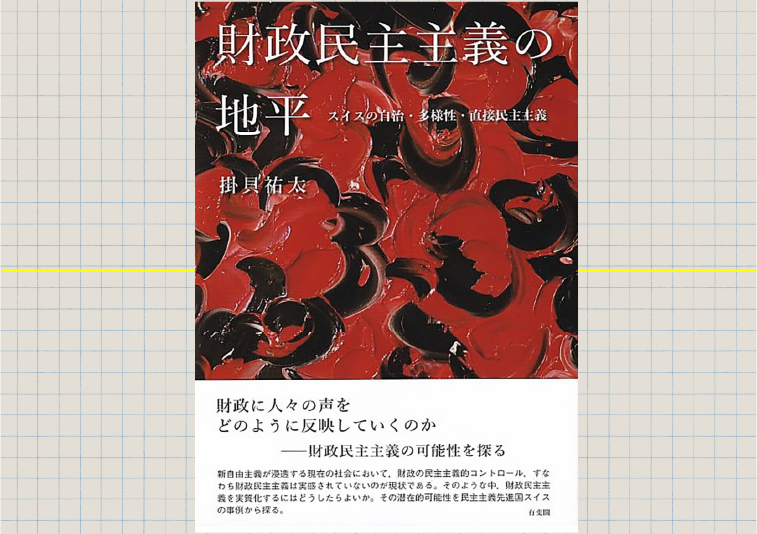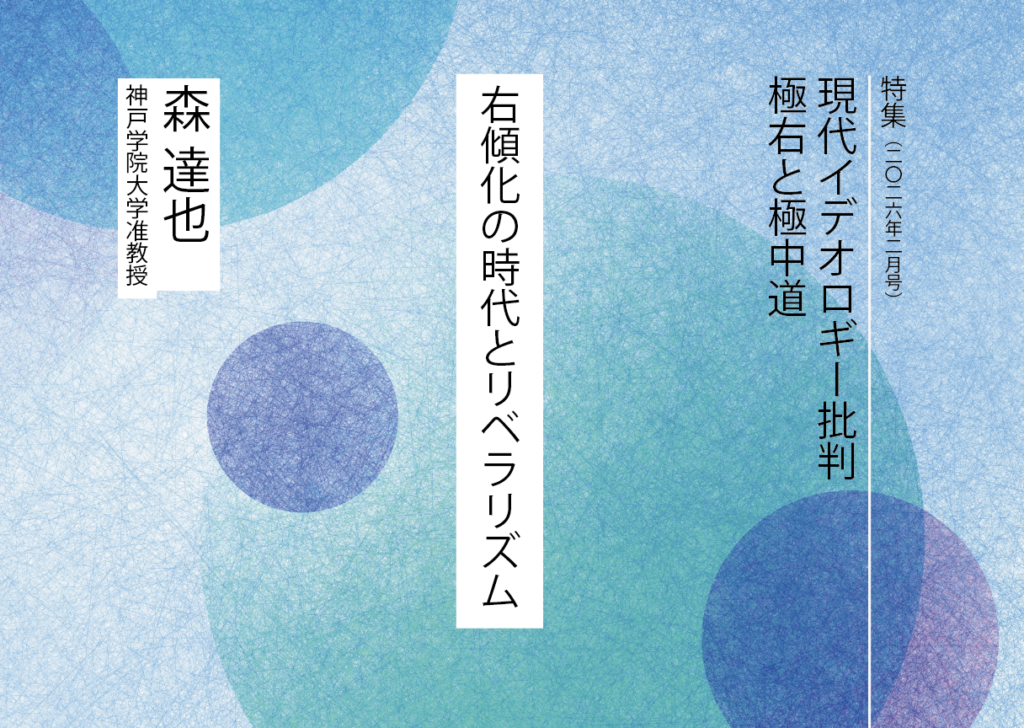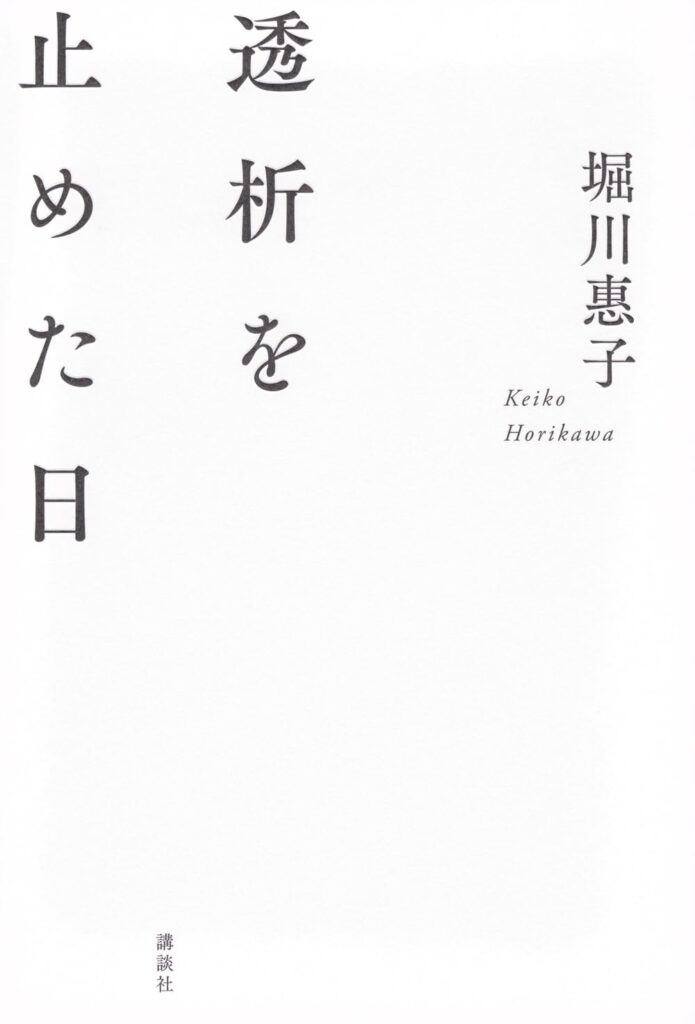戦後80年の節目を前に、さまざまな分野で戦中・戦後の社会を捉えなおす試みが公表されている。本書もそうした成果の一つであり、主に1945年の敗戦からの15年間を対象に、日本のキリスト教界の動きを検証している。
戦後改革で信教の自由が獲得されたが、GHQの占領政策とキリスト教との関係は、当初から問題含みであった。マッカーサーと占領当局はあからさまにキリスト教を優遇し、宣教師の来日や聖書の頒布などを支援した。日本のキリスト教界は物的な恩恵を受けたが、そこには「キリスト教的理想」対「異教徒的野蛮」という植民地主義の継続があり、「精神革命」は起こらなかったと著者は指摘する。
敗戦を境に「変わらなかった」ものへの関心は、他の多くの章にも見られる。教育政策には女性のキリスト教教育者も参与したが、女性への教育機会拡大の訴えは「男女共学化」にすり替えられてしまった。日本のキリスト教界が在日コリアンに関心を示したのは1959年からの帰国事業が最初で、そこでも在日コリアンのキリスト者たちの訴えは届いていなかった。沖縄ではキリスト教会が米軍やアメリカの教会の支援で成り立っており、土地闘争においても住民の側に徹しきれない微妙な立場に置かれていた。
その一方、「剣を取るものは剣で滅びる」というイエスの言葉が沖縄の非暴力闘争のスローガンとなった事実も、本書はもちろん指摘している。歴史を通じて「今」を問う真摯な一冊。(亮)
〈今回紹介した本〉
『戦後日本とキリスト教——敗戦の混乱期から社会制度の確立期まで』
編:富坂キリスト教センター、2025年2月、新教出版社、定価2200円(税込)