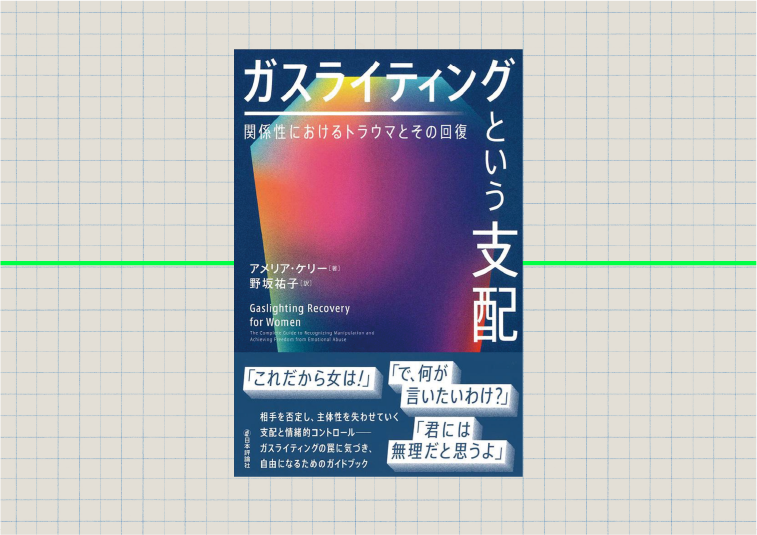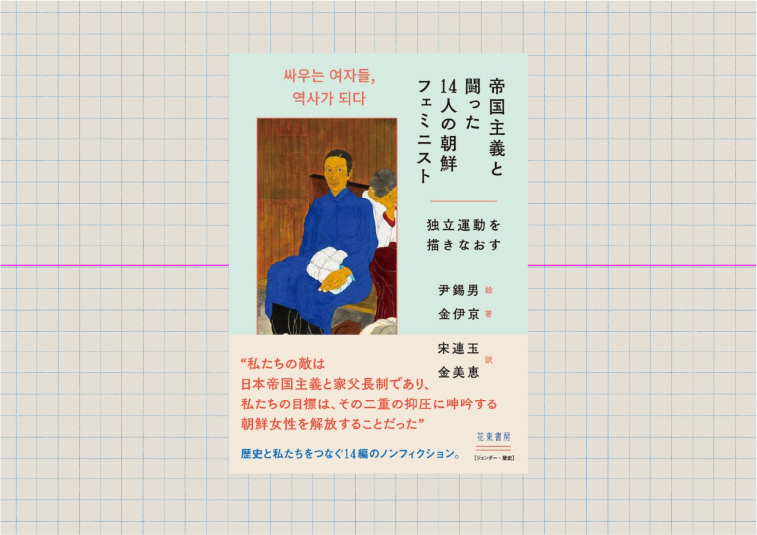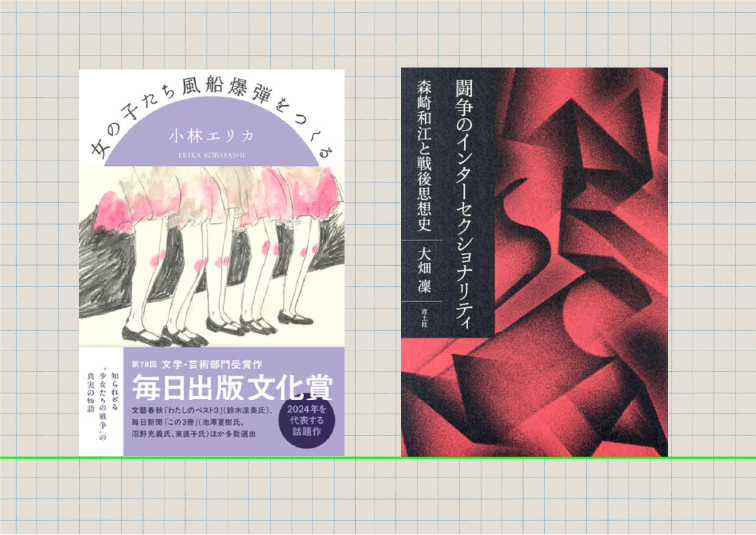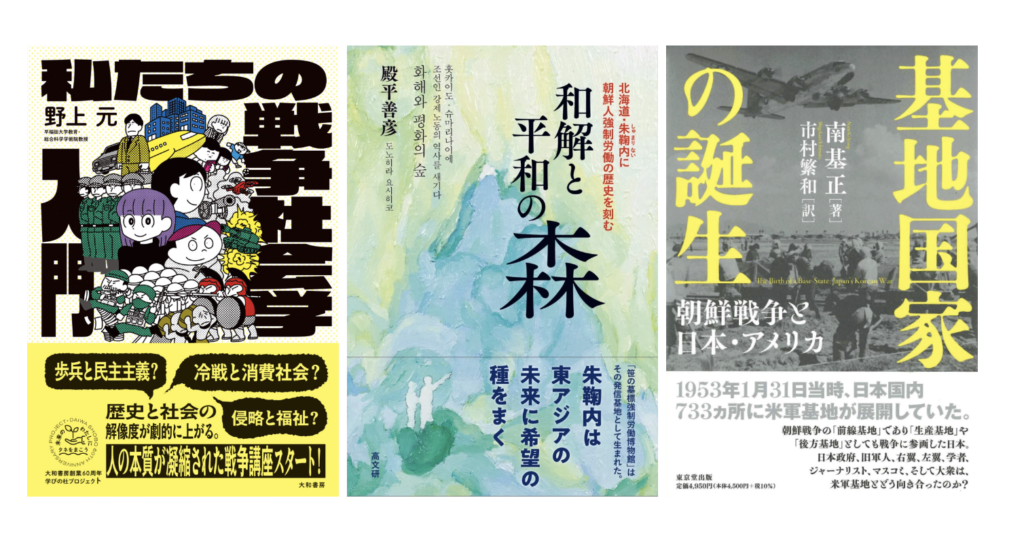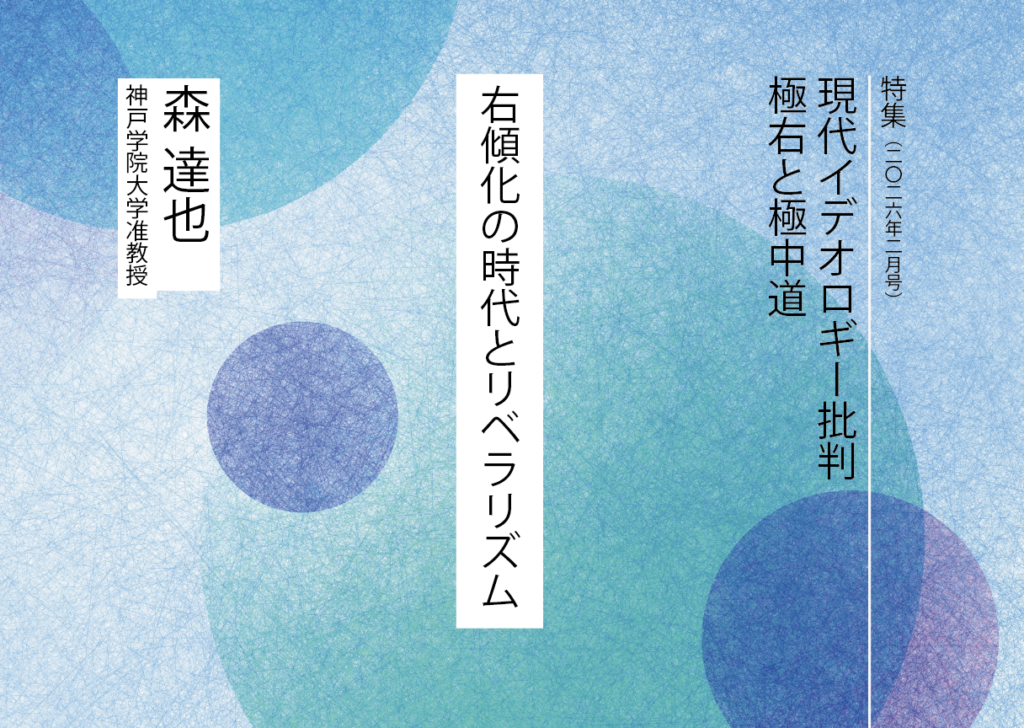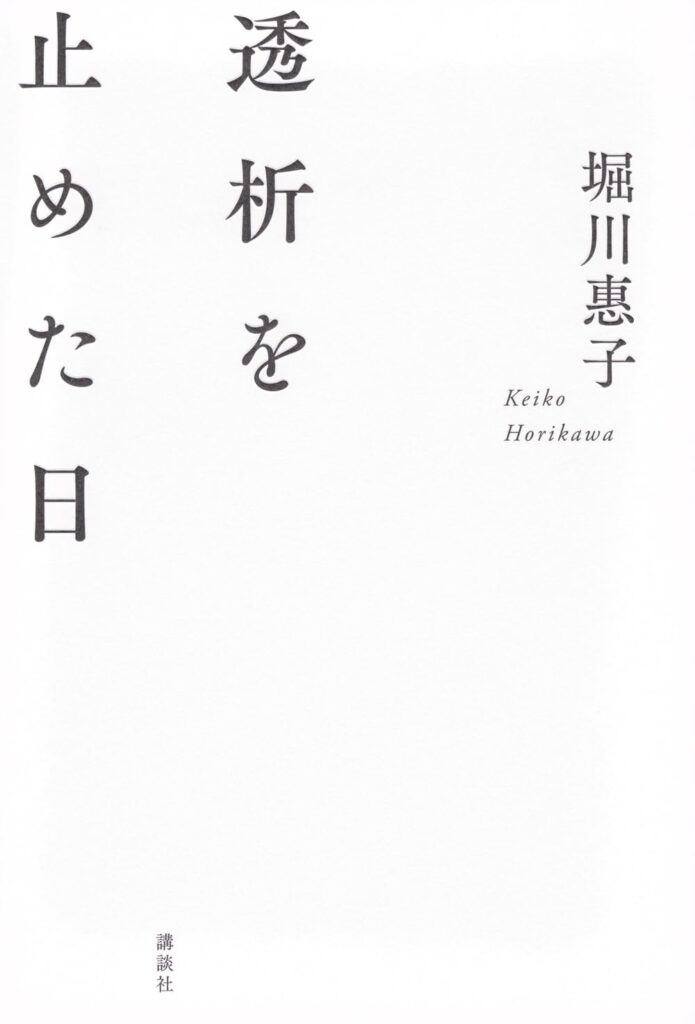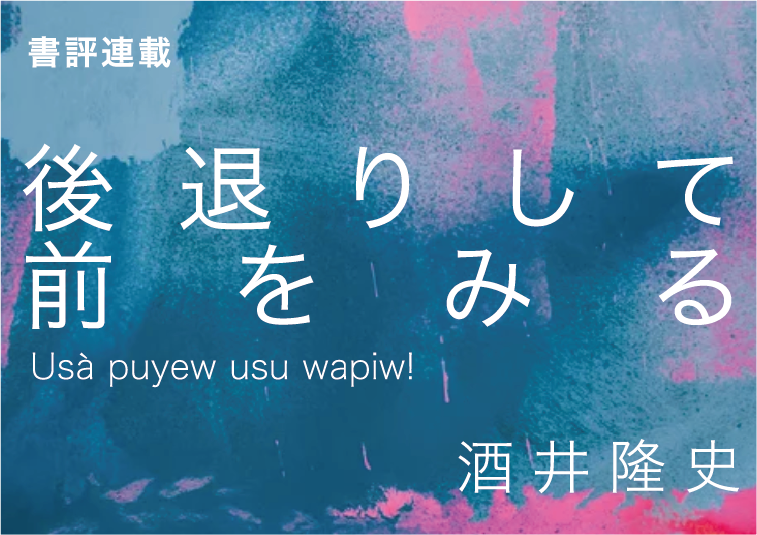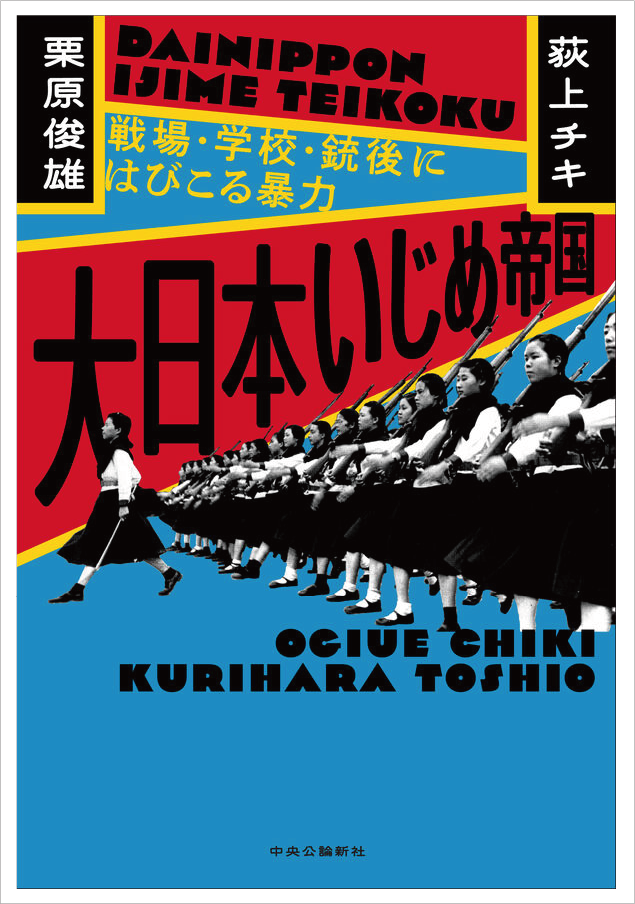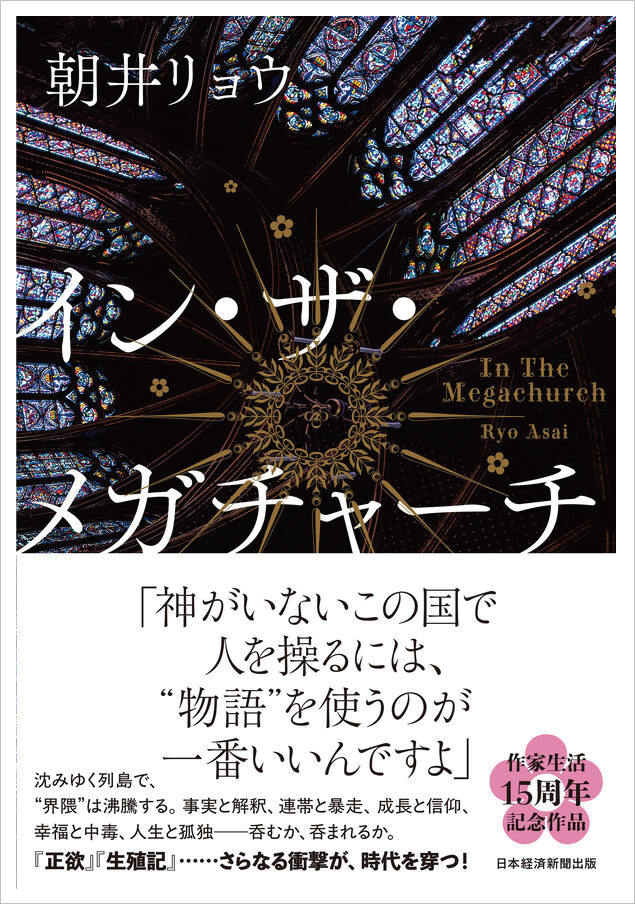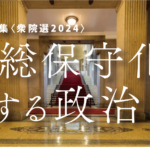「認知が歪んでる。笑」と半笑いで言われた。どっちが、と思ってムッとしたがケンカするほどではない、と思って黙った。あとになって「あれはガスライティングだったんだな」と思った。
スタートアップ界隈で「過去一年間にセクハラ被害を経験した女性起業家が52.4%」(「アイリーニ・マネジメント・スクール」調べ)。という調査が話題になった。女性が事業を立ち上げること、小売店を開くことは、この国ではまだ様々な障害がある。それらを乗り越えて、店頭にたってもリスクは去らない。私は、ふてぶてしさを身に着け、ある程度は自分で身の安全を図ったり、やりかえしたりすることもできるけれど、そもそもそうした防御をしなければいけないこと自体がおかしい。こうした状況から、女性の書店主も、まだ多いとは言い難い。
「ガスライティング」もまた、そうした障壁のひとつだ。『ガスライティングという支配 関係性におけるトラウマとその回復』は、ガスライティングについて実例も用いつつ解説するが、それは全10章のうち第1部の1〜4章であり、5〜10章は実践的な回復の方法について紹介している実践的な本になっている(なお、深刻なPTSDは、医療機関にかかることをお勧めする)。
本書によると「ガスライティングという用語は、心理的な手段によって、相手に『わたしは正気なのか』と自分自身を疑わせるように仕向けること、と定義」されている。正気への疑いを持たせる、という言葉は少し極端な事態を想像させるが、相手の自尊心を損なうほうへ向かわせる行為、と言い換えるとわかりやすいかもしれない。
「忘れたふりをして加害の事実を否認する」「話を聞こえないふりをする」「矮小化する」「情報の価値を下げようとする」「被害者側の記憶は間違っていると無効化しようとする」「女だから○○とステレオタイプ化する」「論点をすり替える」。これらについて、特に女性やマイノリティは経験したことがある、という方は多いのではないだろうか。
「ガスライティングは、そうとわかりやすいかたちで行われるとは限りません。むしろ、こっそりと、気づきにくい方法でなされることがほとんどです」と本書にあるように、はっきりと頭ごなしにどなりつけるようなものではなく、うっすらとした力関係や集団のまとまりを求められる時に用いられやすい。私が体験した冒頭の会話は、左派・リベラルの集まりの中での体験だ。全体としてはその集団の主張に賛成だとしても、細かな異議をあげにくくさせていたり、マイノリティへの配慮が後回しにされがちになっていたりしないだろうか。「とりあえず前に進めたい」という欲望は、そのつもりではなくても、排除のためのガスライティングを容易にひきおこす。被害者として、あるいは加害者として、思い当たることはないだろうか。
今、書店の店頭には様々な多様性やマイノリティ配慮に関する本が並ぶ。それらを読んで学習する人が増え、まだ問題はあれど直接的なセクハラ、パワハラは減少しつつはあるだろう。しかし、いざ、自分の身の回りを見わたすとマイクロアグレッションやガスライティングはまだ横行している印象を否めない。そのことを絶望しているのではなく、これらもまたこうして名指され、書籍となり、知られることで改善していける、ということを信じている。世界はまだまだ変われる。書籍はそのための大事なツールであり、読書は、たとえ一人で読むだけであっても、世界への闘いの最前線である。
●紹介した本
『ガスライティングという支配 関係性におけるトラウマとその回復』
アメリア・ケリー(著)、野坂祐子 (翻訳)、日本評論社 2200円+税