「米国を再び偉大に(Make America Great Again)」を掲げるドナルド・トランプ氏が大統領に返り咲く。2025年1月20日の就任を前に、世界中がトランプ氏の一挙手一投足に注目し、彼がこれまでに口走った政策のどれが実際に実行に移されるのか、不安を抱えながら、数限られる対応策を急いでいる。
日本については、経済面では10~20%と言われる追加関税や貿易黒字の解消、安全保障面では米軍駐留経費や防衛予算の増加などが要求されるのではないかとの予測が連日報じられている。政権1期目における米軍駐留経費の4倍増し請求や鉄鋼・アルミニウムへの追加関税に翻弄された記憶がよみがえってくる。
日本の大きな懸念事項である米中対立の行方についても、よりいっそう先鋭化する可能性が高い。現在急ピッチで政権高官の指名が進むが、その顔ぶれからは、第二次トランプ政権が極めて強硬な姿勢で中国に臨むことが強く予想される。大統領補佐官(国家安全保障担当)に指名されたマイク・ウォルツ下院議員や国務長官に指名されたマルコ・ルビオ上院議員は近年の米連邦議会の超党派での対中強硬姿勢を牽引してきた存在であり、ルビオ氏は中国から入国禁止の制裁を受けている。また、トランプ氏は、中国製品に60%の関税をかけると述べるなど、中国との関係を経済・内政の視点で見る傾向が強いが、通商・産業政策を担う商務長官に指名された実業家ハワード・ラトニック氏も、高関税などを通じて製造業の国内回帰を訴える強硬派であり、トランプ氏の望む政策を忠実に実施していくことになるだろう。
4年間の国際秩序の変化
第一次トランプ政権から今日までの4年間で、国際秩序は大きく変化した。ウクライナとガザで二つの大きな戦争が進行中であり、「民主主義陣営」と「権威主義陣営」の対立はより深刻化し、世界の分断はさらに顕著になっている。日本の位置する東アジアは、覇権争いの最前線として、軍事衝突の危険が現実味をもって語られている。
相対的に米国が力を落とす中、バイデン政権は同盟国との連携強化を安保政策の前面に出し、日米、米韓、米豪といった各同盟関係の強化はもちろんのこと、QUAD(日米豪印)、AUKUS(米英豪)、日米韓、日米比といった同盟・準同盟的な多国間枠組みを多数構築して制度化し、それをインド太平洋地域に張り巡らせて中国を囲い込む政策を進めてきた。
しかし、対する中国は、その経済力を後ろ盾に各国への影響力をさらに高め、また、中露の協力は進み、露朝も軍事協力を深めて北朝鮮がウクライナ戦争に派兵するまでになっており、地域の緊張は激化する一方である。
他方、この4年間のもう一つの大きな変化として、グローバルサウスといわれる新興国・発展途上国のグループが力をつけ、発言力を増している点も挙げられる。例えば、新興国を含むG20が先進国のみからなるG7に劣らぬ存在感を示すようになったし、中露印・ブラジル・南アフリカからなるBRICSが加盟国を増やし、パートナー国制度の創設を決定して地理的・経済的に大幅に拡大した。これらグローバルサウス諸国には、米中覇権争いで中立的立場をとる国々が多く、例えばASEAN(東南アジア諸国連合)の多くの国々は「米中どちらのサイドも取らない」と明確に意思表明している。ASEANでの政府関係者・有識者相手の世論調査において「米中対立下でASEANはどう対応すべきか」との質問に「米中いずれかを選ばざるをえない」と答えたのはわずかに8.0%であった。つづく「米中いずれかを選ばねばならないとしたら、いずれを選ぶか」との問いでは、2020年以来毎年行なわれるこの調査において、本年初めて中国を選ぶ回答者が過半を超えた(中国50.5%、49.5%。ISEAS – Yusof Ishak Institute、2024年)。
インドがグローバルサウスのリーダーとなるべく「グローバルサウスの声サミット」を主導して100カ国以上が参加し、また、トルコや南アフリカがウクライナやガザの戦争で独自の動きを見せるなど、グローバルサウスの存在感は日増しに高まっている。
トランプ氏のいない4年の間に、世界は多極化(Multipolar)の時代に入ったのである。


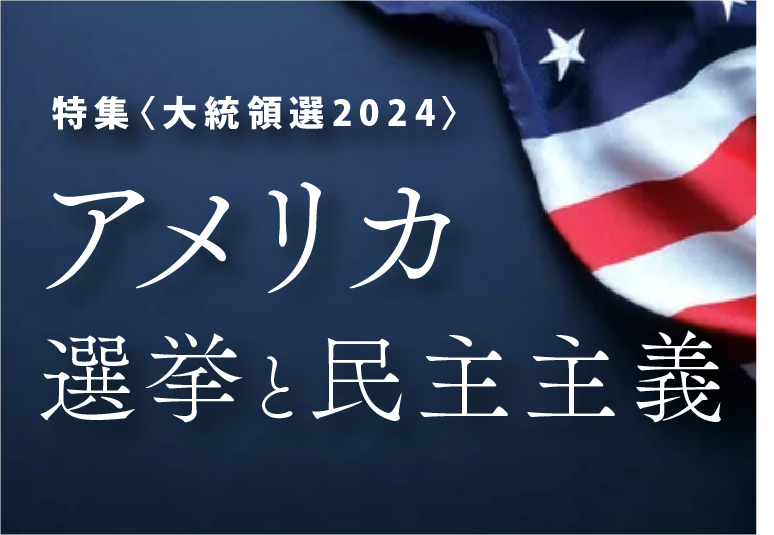










-768x1024.jpeg)



