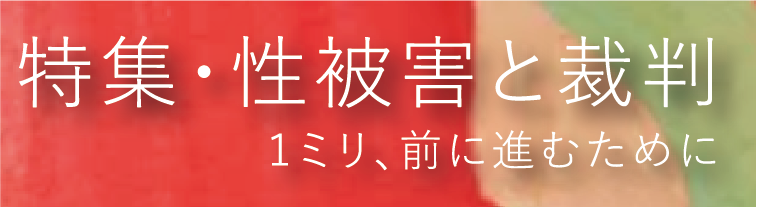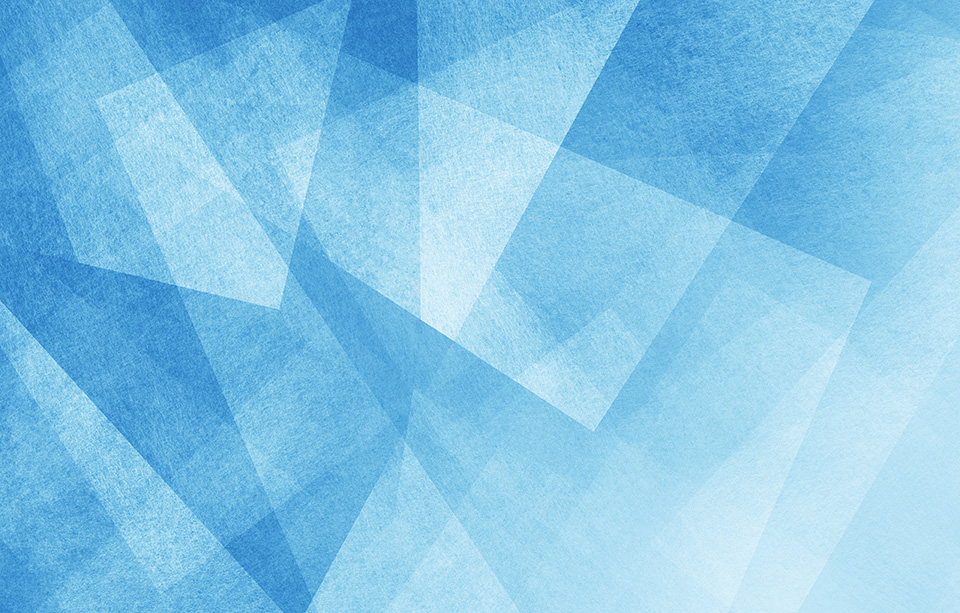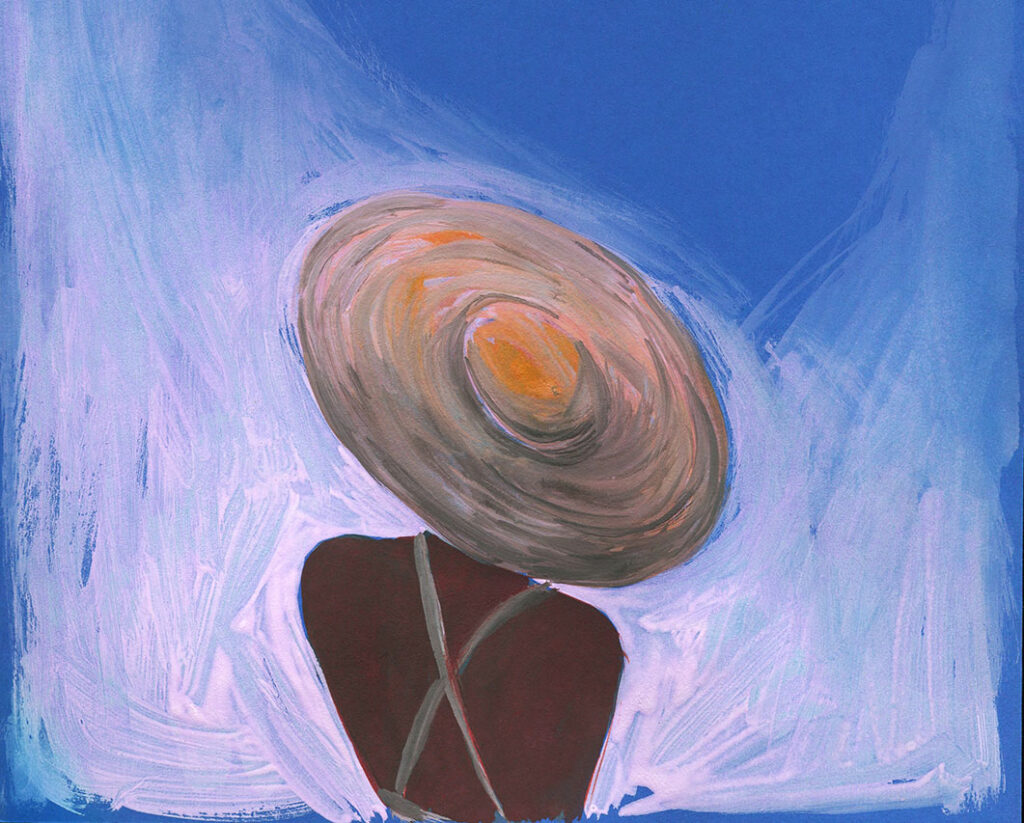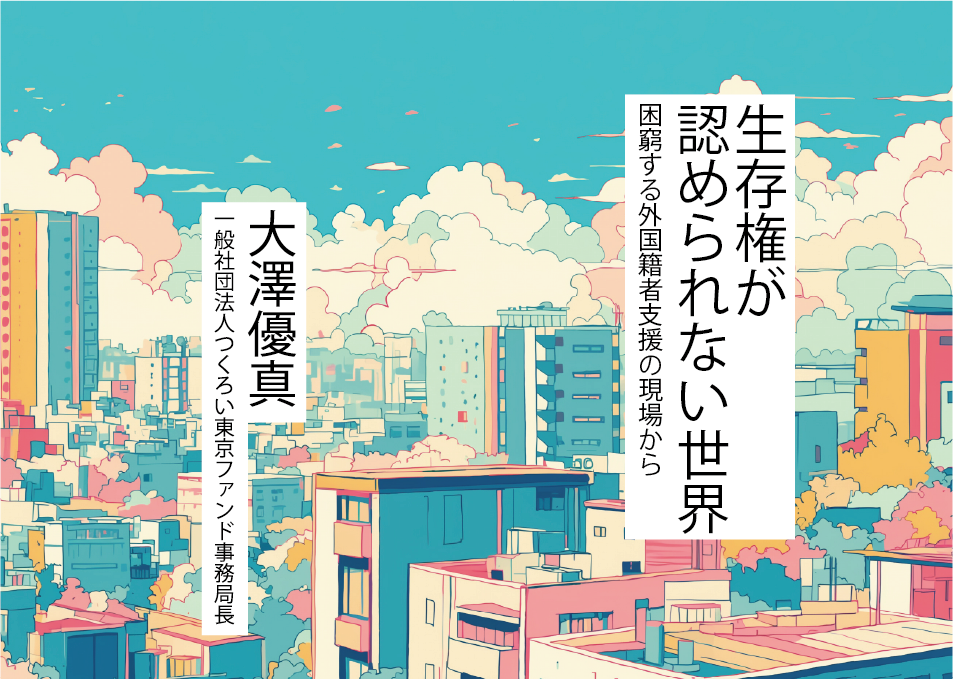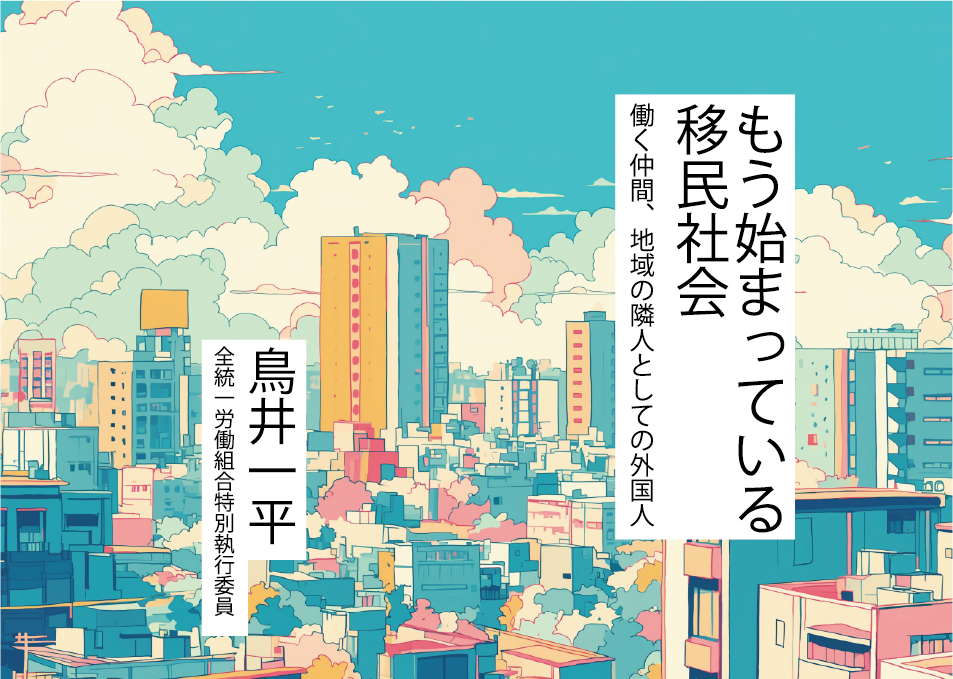西廣陽子(にしひろ・ようこ)
弁護士。成蹊大学大学院法務研究科修了。東京弁護士会犯罪被害者支援委員会委員、東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会委員。ジャーナリスト伊藤詩織さんの性被害に関する民事訴訟で代理人を務めた。
聞き手:小川たまか(おがわ・たまか)
1980年生まれ。ライター。著者に『「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。』(タバブックス)『告発と呼ばれるものの周辺で』(亜紀書房)など。
日本では2008年に被害者参加制度が始まり、これによって犯罪被害者や遺族らが刑事訴訟に参加できることとなった。この制度は主に犯罪被害者やその遺族からなる、全国犯罪被害者の会(2000年設立)がその権利を訴えて勝ち取ったものといえる。
犯罪被害者支援の経緯を辿れば、三菱重工ビル爆破事件をきっかけとして1980年に犯罪被害給付金が設けられたものの、警察庁が「犯罪被害者対策」に乗り出したのは地下鉄サリン事件以降。さらに犯罪被害者等基本法が成立したのは2004年のことだ。
警察の捜査や司法の中で、長らく被害者の権利やケアは後回しにされる状況があった。それは性犯罪の被害者も例外ではなく、むしろ「特殊な被害」とタブー視されてきたことで被害者の姿がさらに見えづらく、他の犯罪被害者や遺族と連帯しづらい状況もあったと考えられる。
フジテレビ・中居正広問題など、近年になり著名人の性暴力事件が報道される中で、被害者側の弁護士が大きな役割を果たすことが日本でも徐々に知られはじめるようになった。しかし、刑事事件などで弁護士が加害者側(容疑者側)についているというイメージを持っている人も少なくなく、性犯罪被害に遭った際、すぐに弁護士に相談しようと考えられる人ばかりではないだろう。
実際には、民事訴訟だけではなく刑事事件においても、被害者が弁護士の介入によって法的支援を得ることは重要である。全国の性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでも、弁護士との連携による法的支援を行なうことがある。
しかし過渡期であるための課題は山積している。たとえば性暴力やDVの被害者から相談を受けるのは女性弁護士が多い。被害者に女性が多いこともあるが、被害者よりも加害者側につくほうが利益を得やすい状況があることと無関係とは言えない。性暴力は権力勾配を利用して行なわれることが多いため、社会的地位のある立場の男性から若い女性に対して、という構図になりやすい。両者のどちらが経済的に有利かは明らかだ。10年ほど前に筆者はある女性弁護士から「弱者の側につくと自分も(経済的に)弱者になっていく構造がある」と聞いた。性暴力とその支援の現場の取材を続けるうちに、この話をより深刻に受け止めている。
弁護士による性暴力の被害者の支援と課題について、西廣陽子弁護士に聞いた。