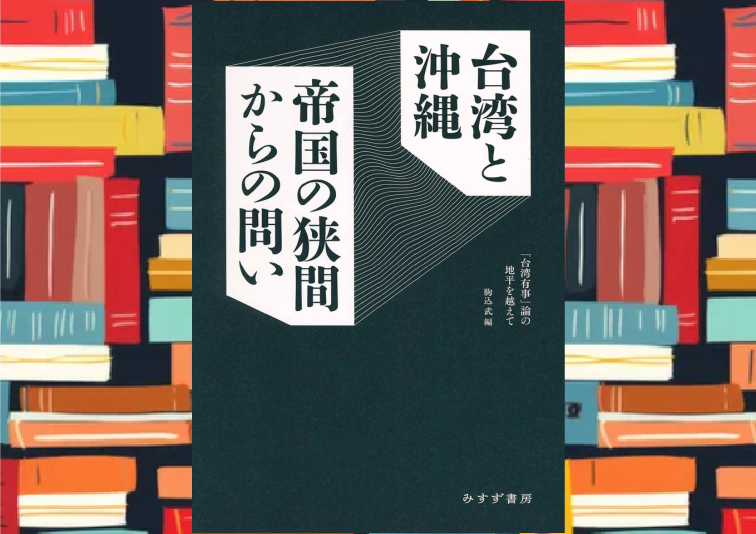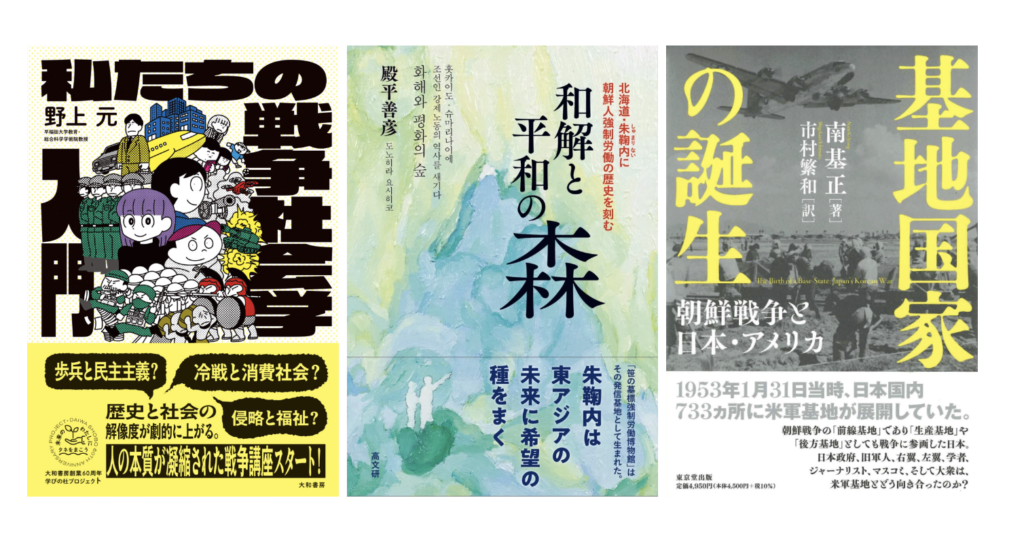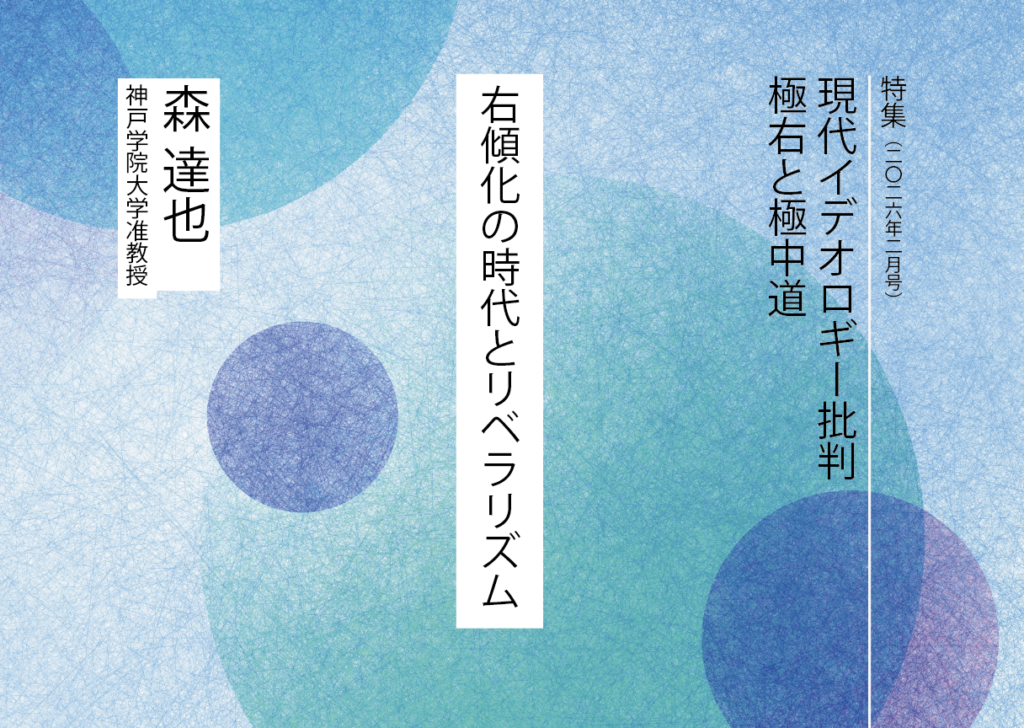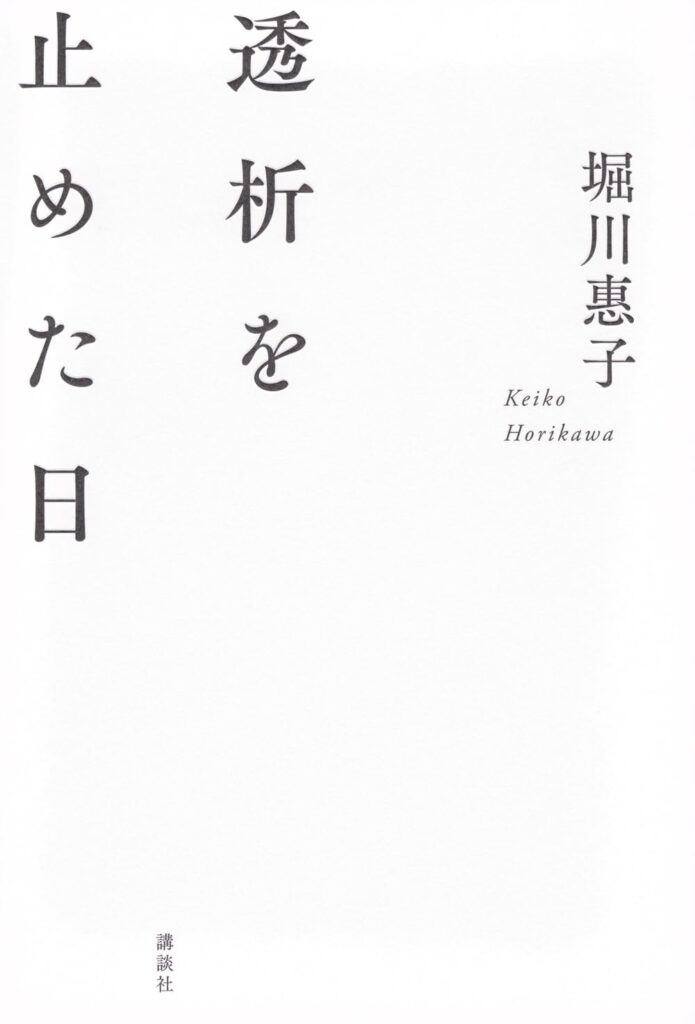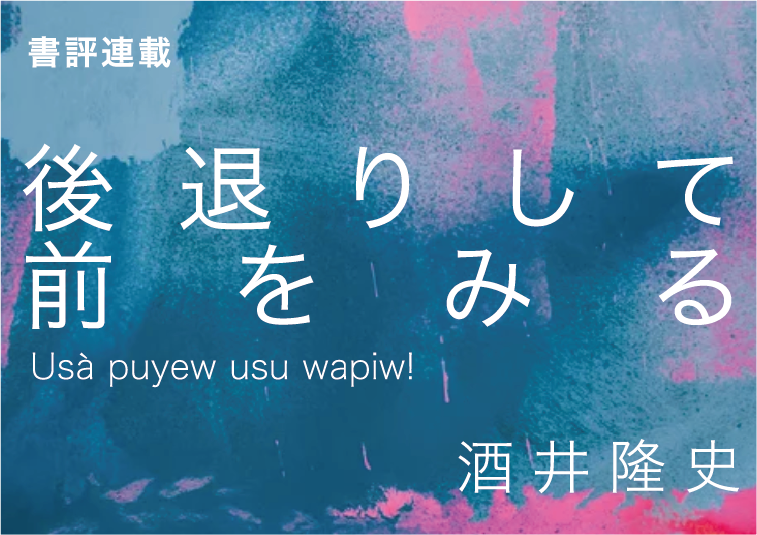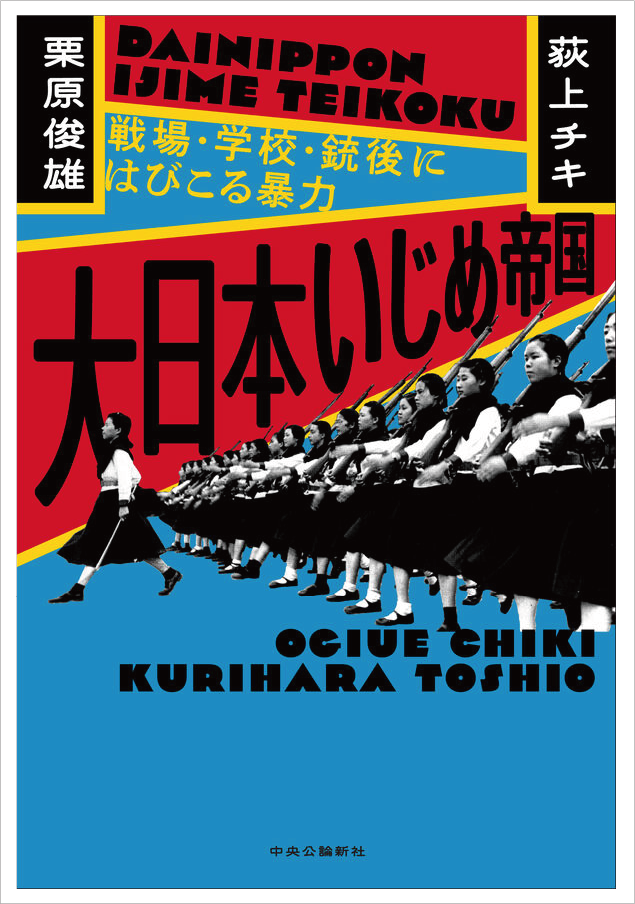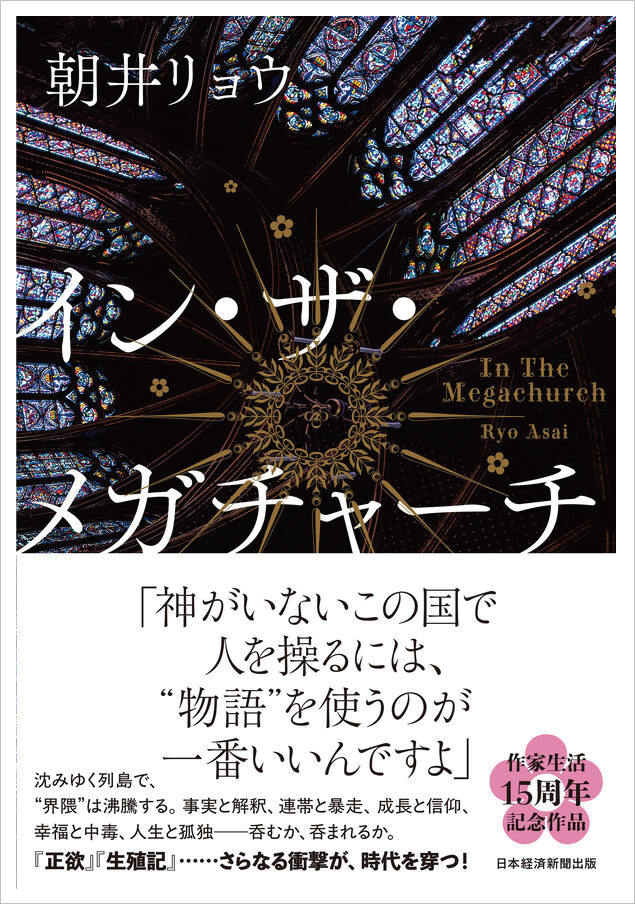1 複数の「対話」の扉を開く
米国の次期大統領が決まり、米中対立のさらなる悪化が懸念されている。焦点とされる台湾への中国の軍事的圧力も、連日のように報じられている。日本では「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事」(安倍晋三元首相の2021年12月の発言)との説明が、今後ますます正当化されるだろう。すでに琉球弧の島々には、「島嶼防衛」の名の下に自衛隊基地が次々と建設され、中国本土を直接攻撃できるミサイルの配備が進められようとしている。
しかし、大国の目線と一体化した思考からは、肝心の台湾や沖縄の人々がどんな思いでこの状況を見つめているのかといった関心は、すっぽりと抜け落ちてしまう。もっとも渦中にある当事者の意志を無視したままでは、大国の狭間で何度も犠牲に供された二つの地域に、またも苦しみを押しつけることになるのではないか。本書は、そのような危機感を抱いた編者の駒込武が、2023年7月に京都で主催したシンポジウム「台湾と沖縄 黒潮により連結される島々の自己決定権」を契機として編まれた。
企画の主旨は、台湾と沖縄のそれぞれで苦境に抗う闘いをつづけている当事者の声に、まずは耳を傾けることにあった。そこで、台湾の民主化運動で長く発言してきた政治学者・歴史家の呉叡人、石垣島で自衛隊基地の是非を問う住民投票をめぐる訴訟に取り組んできた宮良麻奈美が招かれ、さらに台湾出身で日本留学中の張彩薇が加わって登壇し、発言している。既存の政治や運動が主導する台湾・沖縄間の交流にはないような対話の機会を生み出している点で、この取り合わせが企画の成功を決めたように思う。
留学生という不安定な立場の張はもちろんのこと、闘争現場の当事者である呉や宮良にしても、台湾や沖縄ではむしろ周縁的な立場にある。呉叡人は、一般に台湾独立論の理論家と見なされるが、彼が唱える「独立」と台湾の将来像は、台湾政治の主流を占める親米反共路線とは大きく異なる。宮良が闘っている石垣島の軍事化は自衛隊が進めているため、米軍の新基地建設には反対する沖縄県知事や県政与党からの批判も、鈍くなりがちだ。それだけに、石垣市独自の政治文化である自治基本条例を否定する保守市政に対して、苦しい闘いを強いられている。
三人の発言によって、私たちは既成の台湾・沖縄像が無効となるだけでなく、複数の台湾、複数の沖縄が(日本本土と同様に)内部で格闘している状況を目の当たりにし、だからこそ、では誰の声を聞き、誰と対話するか、そのためにいかに真剣に知るか、試されていると言えよう。
では、本書はどのような対話を作り出し、またいかなる質の対話への誘いとなっているだろうか。